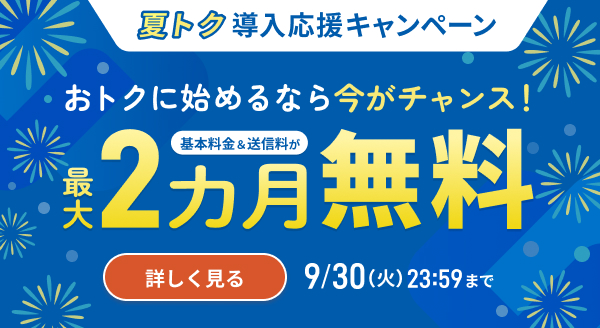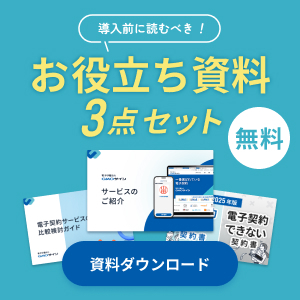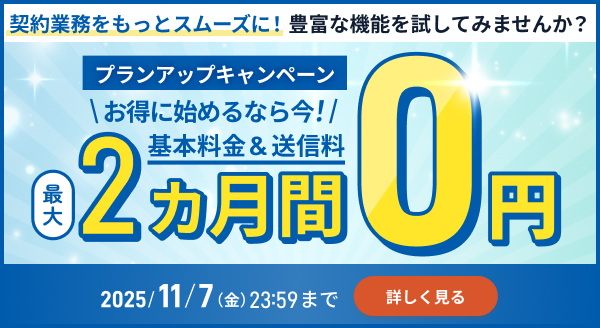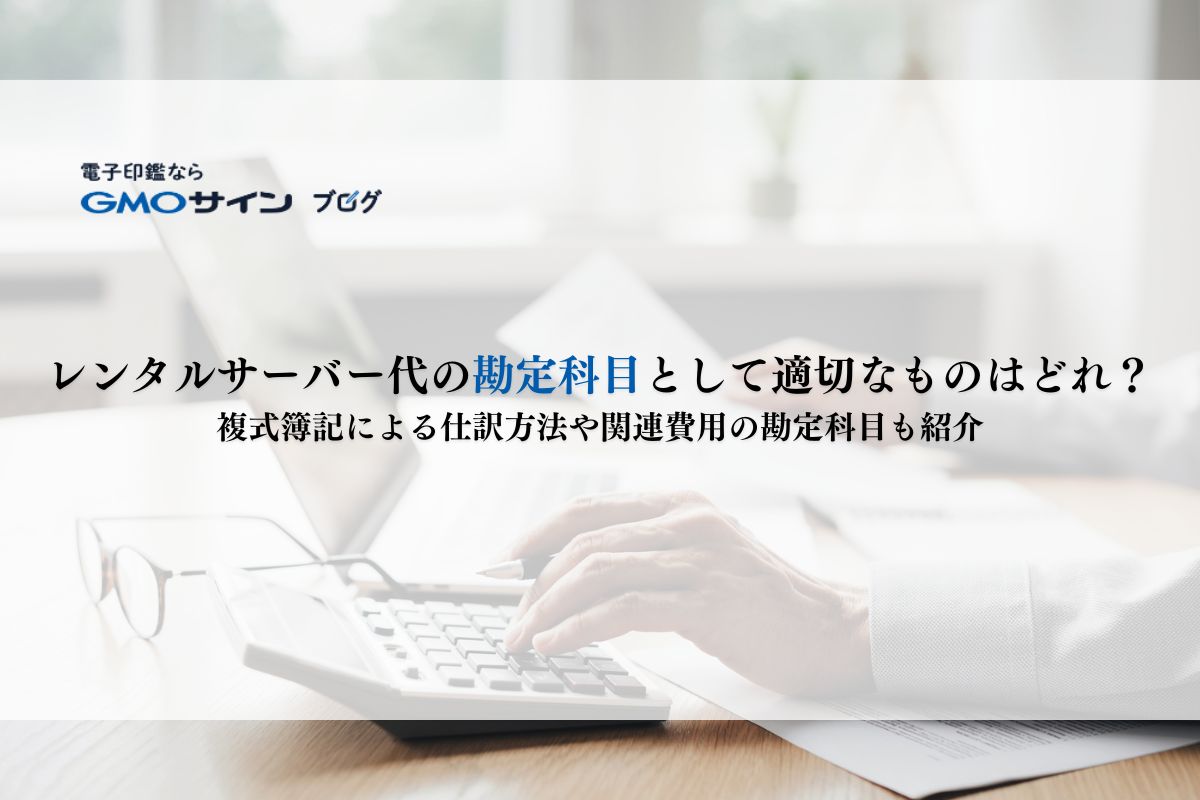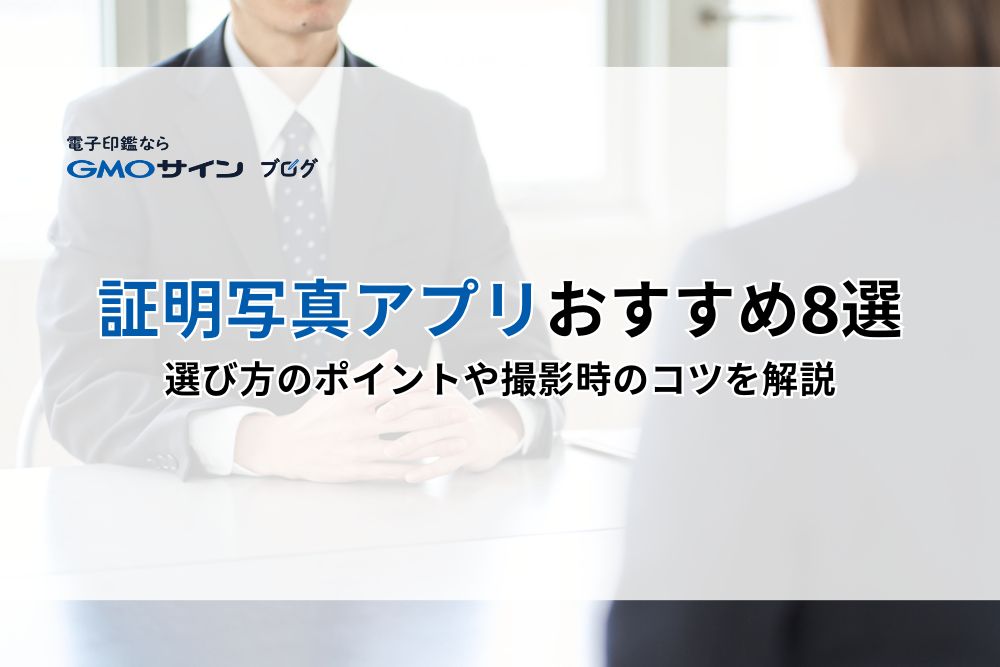一括償却資産の仕分け方は?節税に役立つ少額減価償却資産もわかりやすく解説

法人の仕訳においては、項目ごとに条件が決められています。たとえばオフィス内で使う設備に関しては、取得価額や使用可能期間によって、いくつかの仕訳項目から適切なものを選ばなければいけません。
そうした設備費用に関する仕訳項目の一つには減価償却資産以外にも一括償却資産があり、節税対策で採用している企業も多いです。この記事では、一括償却資産の概要や仕訳するメリットやデメリット、具体的な仕訳方法などについて分かりやすく解説します。
減価償却資産とは
減価償却資産とは、経年劣化する資産を指します。具体的には、建物や設備、車両などが対象となります。
また資産の経年劣化とは、年月が経つにつれて資産の価値が目減りするという考え方です。そのため、経年劣化しない土地や骨とう品などは減価償却資産としては分類されません。
一括償却資産とは
減価償却資産は、法人が取得した価額10万円以上の資産が対象となります。資産の種類や数によって償却期間が異なりますので、会計処理における負担が大きくなってしまいます。
そこで使われるのが一括償却資産です。一括償却資産とは、償却資産における会計処理を簡素化できる勘定項目です。
一括償却資産の対象となる資産は「10万円以上20万円未満」のもの
一括償却資産の対象となるのは、取得価額が10万円以上で20万円未満の資産です。基準は価格ですので、同じ種類の資産でも購入した金額によって対象にならないケースがある点に気をつけましょう。
一括償却資産の償却期間は「3年均等償却」
一括償却資産の償却期間は3年であり、この期間内で均等に償却します。たとえば取得価額が15万円のパソコンの場合、一般的な減価償却ではパソコンの耐用年数は4年なので、通常なら取得価額を4年間にわたって償却処理を行います。
しかし、一括償却資産を利用すれば、15万円を3年間にわたって均等に償却するため、購入した年度の3年間で毎年5万円ずつの償却を行います。次に、このように償却するメリットについてご紹介します。
一括償却資産のメリット
償却資産の仕訳方法には様々な種類がありますが、その中でも一括償却資産を採用することには以下のようなメリットがあります。
- 短期間で経費計上できる
- 会計処理の簡素化による業務効率化
- 償却資産税の対象外となる
- 月割りする必要がなくなる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
短期間で経費計上できる
一括償却資産では、取得価額を3年間という期間で全額を経費計上します。一般的な減価償却では、償却期間が3年よりも長くなってしまう資産は数多くあります。しかし、一括償却資産ではかかった経費を3年間で償却し切れるので、資金繰りの改善に役立ちます。
会計処理の簡素化による業務効率化
一括償却資産を採用すれば、条件を満たす資産の減価償却はすべて3年間で均等に償却できます。そのため、資産ごとに異なる法定耐用年数を調べた上で適切に償却するための会計処理が必要だったところを一括償却資産にすることで会計業務が簡素化できるのです。
償却資産税の対象外となる
一般的な償却資産は、償却資産税の課税対象となります。しかし、同じ資産でも仕訳方法を変えて一括償却資産にすれば、償却資産税の課税対象外となりますので節税効果が期待できます。
月割りする必要がなくなる
一般的な減価償却資産は、年の途中で取得した資産だと初年に1年分償却することはできません。取得した月によって、月割りしてから計算する必要があります。たとえば4月1日から決算期がスタートする企業では、10月に購入した資産は期末までの6カ月分しか初年度の償却ができないのです。
一括償却資産のデメリット
多くのメリットが期待できる一括償却資産ですが、以下のようなデメリットもあります。
- 除却処理できない
- 損金算入明細書を提出しなければならない
それぞれ詳しく解説します。
除却処理できない
除却処理とは、計上した資産を除却することで、その時点で残っている価額を消滅させる方法です。資産は耐用年数を過ぎると価値が大幅に減少して、減価償却もできなくなります。しかし、残存する価値に対して税金が発生してしまうため、節税目的で除却処理が行われるのです。
損金算入明細書を提出しなければならない
一括償却資産処理を選択した場合には、確定申告を行う必要があります。また損金算入明細書を提出する義務が発生する点にも要注意です。
一括償却資産の確定申告について
一括償却資産で会計処理をした場合、確定申告の義務が生じます。そこで、確定申告における必要な作業について解説します。
資産のリストアップ
一括償却資産の損金算入明細書では、一括償却資産をどの年から事業のために使いはじめたのかリストアップします。このリストは、使いはじめた年が早い順に記載しなければいけません。
取得価額の合計を年度ごとに行う
一括償却資産の確定申告では、同一の年度に取得した資産の合計取得価額を算出した上で、それらを3年に均等償却するという計算方法を適用します。そのため、本来の減価償却よりもスムーズに計算できます。
当期の月数
一括償却資産の確定申告で、記録のために資産ごとに当期間中の使用月数も記載しなければいけません。
損金算入額
当期間中に経理処理をした損金算入額を計算し、その合計額も確定申告の用紙に記載します。
前期からの繰越額
確定申告においては、当期の損金算入だけでなく、前期からの繰越額に関しても記入する箇所があります。そのため当期分の損金算入に不足額が生じている場合には、前期からの繰越額によって補うことが可能です。
一括償却資産と混同しやすい償却資産
会計処理で便利な償却資産には、一括償却資産の他にも少額減価償却資産があります。そこで、少額減価償却資産について詳しく解説します。
少額減価償却資産とは取得金額が「30万円以内」のもの
少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満で経年劣化する資産です。中小企業では、多くの資産を全額即時償却できる点が魅力です。
対象となる企業
少額減価償却資産を適用して減価償却方法を利用できる企業は、常時雇用している従業員が500人以下で、青色申告をしている中小企業者または農業協同組合です。
償却できる資産の限度額
少額減価償却資産は、全額を即時償却できるという大きな特徴がありますが、償却可能な上限は300万円までと設定されています。そのため、複数の資産を同じ年に少額減価償却しようと考えている場合には、上限を意識して減価償却方法を工夫する必要があるでしょう。
(参考:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁)
一括償却資産を仕訳する方法
一括償却資産を仕訳する際には、以下のような方法があります。
- 決算調整方式
- 申告調整方式
それぞれ詳しく解説します。
決算調整方式
一括償却資産では、取得した償却資産を3年間にわたって均等に償却します。先述の15万円のパソコンを購入して一括償却する例ならば、1年間に5万円ずつを3年間にわたって償却することになります。
この場合、帳簿では借方に一括償却資産と取得価額の15万円を計上します。また貸方には現金で15万円と計上します。そして決算期には、借方には減価償却費として年度分の5万円、貸方には一括償却資産として5万円を計上します。
申告調整方式
取得時には事務用品や消耗品として仕訳していた資産を確定申告では一括償却資産として計上して一括償却したい場合には、申告調整方式を用います。
資産を取得したときの仕訳では、借方には事務用品や消耗品などの科目と合わせて取得価額が記載されているでしょう。また貸方には現金で同じ金額が仕訳されているはずです。
一括償却資産以外に節税できる費用や資産
一括償却資産や少額減価償却資産以外にも節税できる費用や資産がありますので、ご紹介します。
資産と計上されなければ課税されない
たとえば修繕費などは、計上した場合には資産としては計上しません。また資産として計上されなかった科目に関しては、基本的に償却資産税はかかりません。
二重課税のリスクがあるものも対象外
土地や建物のように固定資産税がかかるものは、償却資産税の対象外となります。なぜなら、二重課税のリスクがあるからです。同じ理由から、自動車も自動車税がかかるため、償却資産税は課税されません。
無形の固定資産も対象外
ソフトウェアや特許など無形の資産は、償却資産税の対象外となっています。
一括償却資産に関するよくある質問
20万円以下の資産は一括償却できる?
取得価額が「10万円以上20万円未満」の減価償却資産は、一括償却資産として選択すれば取得年度含め3年間で均等に償却できます。
一方、10万円未満はその年度に全額経費処理し、20万円ちょうどは一括償却資産の対象外です。
30万円一括償却資産の延長はいつまで?
青色申告者が取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産について一括償却を選べる特例は、平成18年4月1日から令和8年3月31日までの取得分が対象です。
一括償却資産とは?
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産で、取得年度から3事業年度にわたり均等償却するものをいいます。事業の用に供した年度から(取得価額合計×当期月数/36)を毎期必要経費に計上可能です。
一括償却資産が終わった4年目以降はどうしたらよい?
一括償却資産は3年で取得価額を全額償却し、帳簿価額はゼロになります。4年目以降はさらに減価償却することはできず、引き続き使用する場合はそのまま帳簿に残し、廃棄・売却などした際に処分損益を計上します。
自社にあった会計処理でうまく節税に役立てましょう
本記事でご紹介した一括償却資産は、節税や会計処理の簡素化に役立つ便利な資産です。しかし、企業の業種などによっては活用できないケースも考えられるでしょう。
そこで本記事では、少額減価償却資産などで節税する方法をお伝えしましたので、自社にあったやり方で経営に役立ててください。