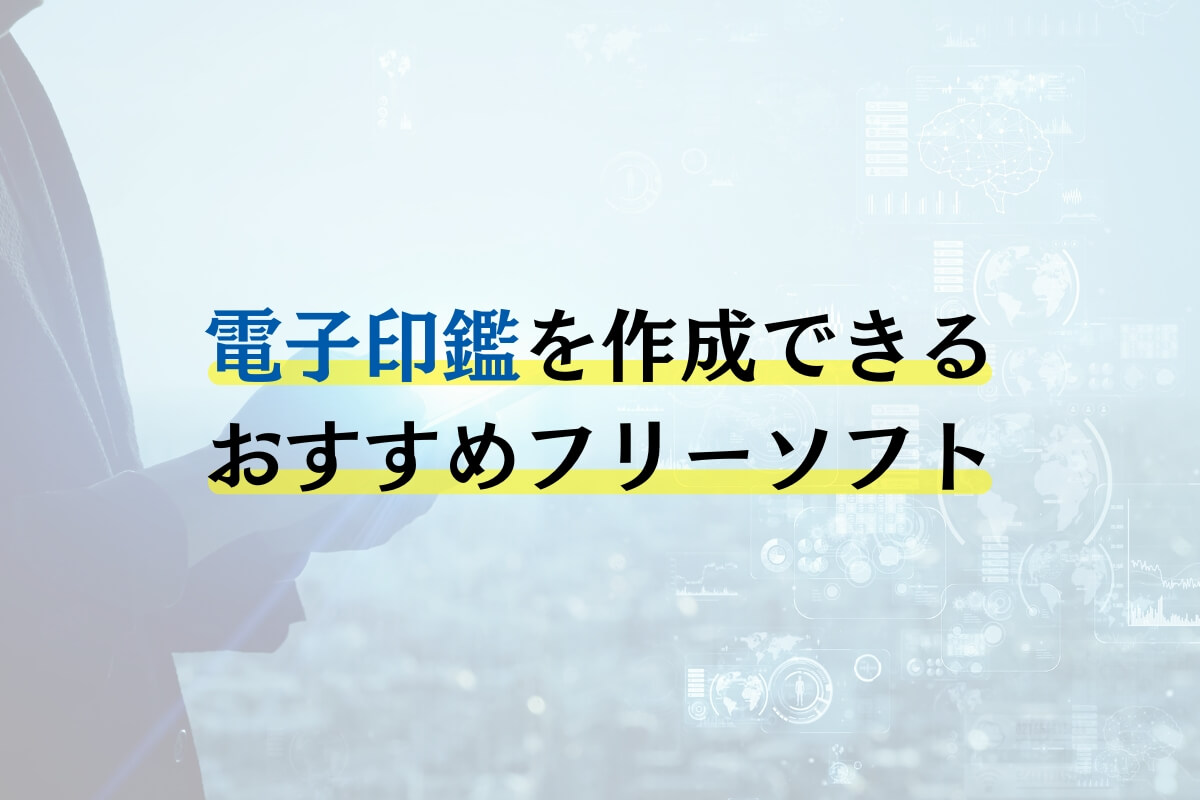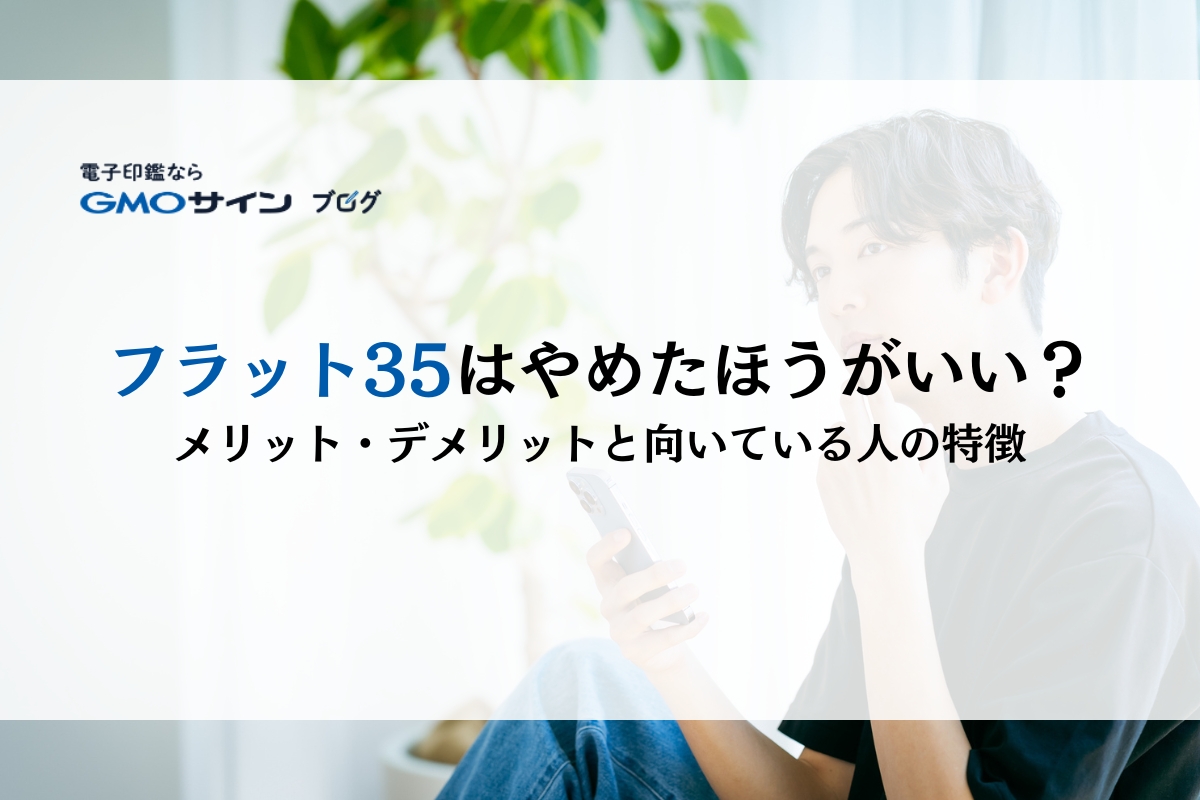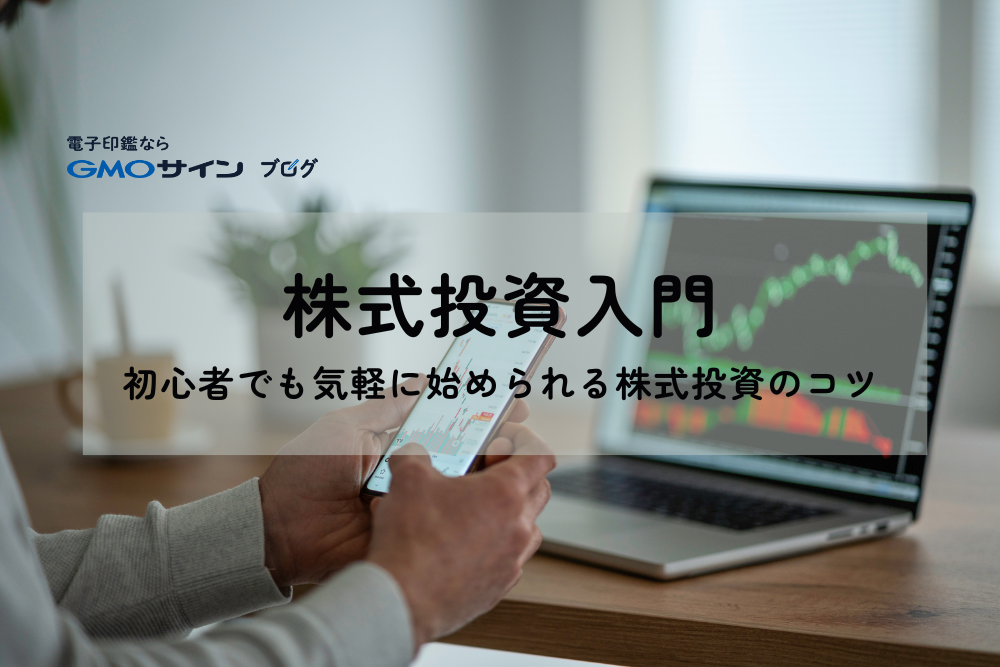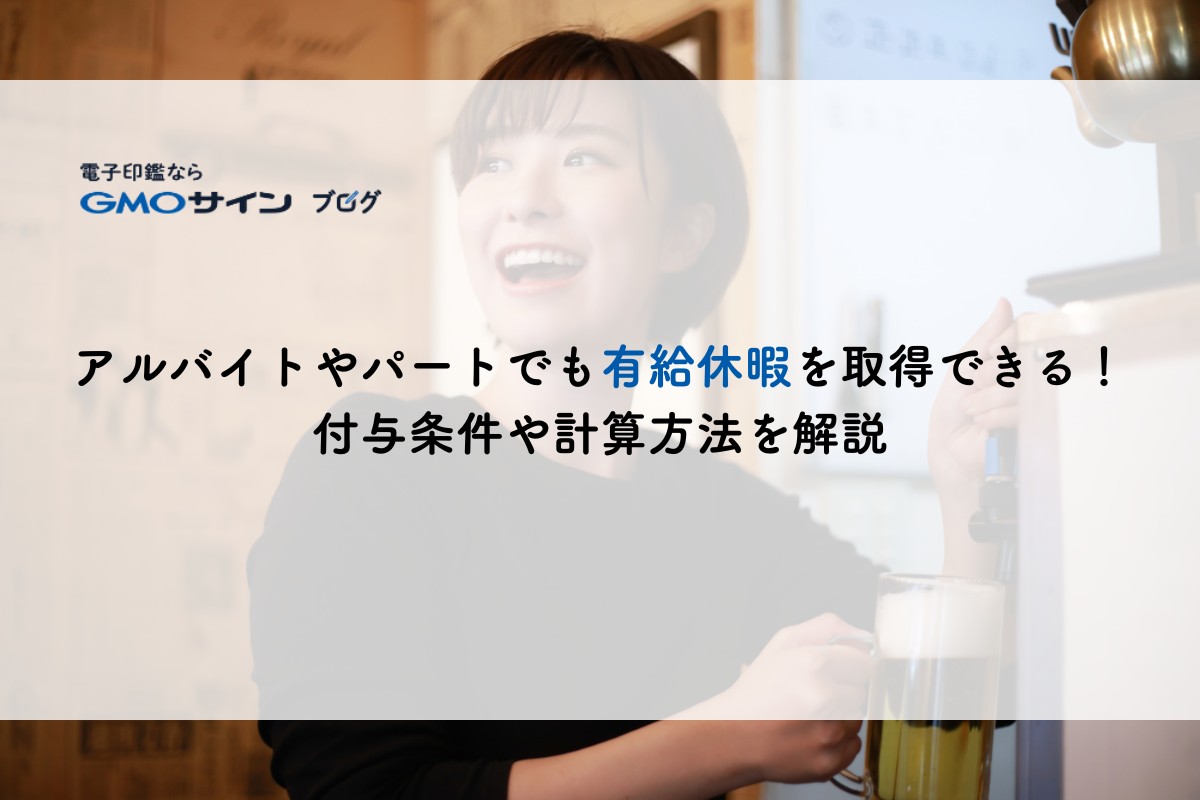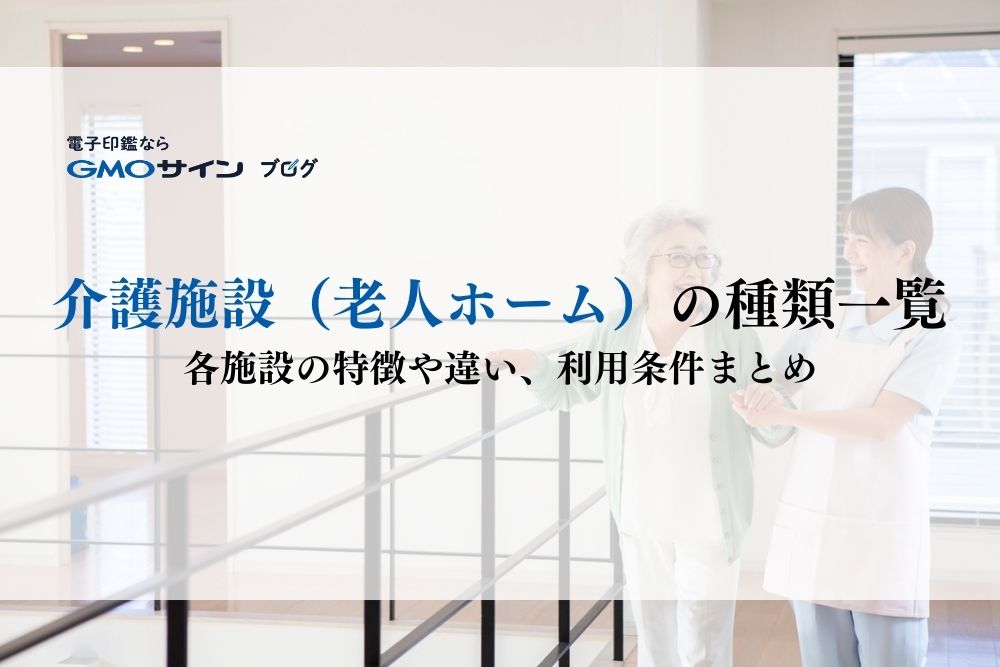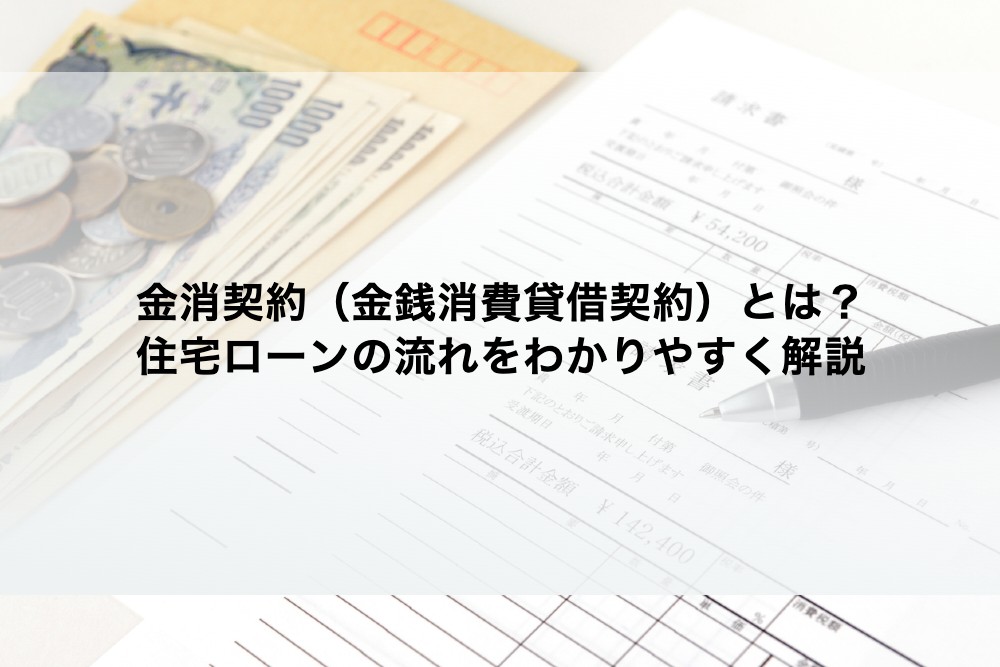産業処理廃棄物処理委託契約書の書き方は?
産業廃棄物の処理を依頼する際には契約書の作成が義務なの?
盛り込むべき必須項目を知りたい!
産業廃棄物の適正処理は事業者の重要な責任です。この責任を果たすために必要なのが、処理業者との間で交わす「産業廃棄物処理委託契約書」です。
産業廃棄物処理委託契約を行う際は要件を満たした契約書を作成することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令にて定められています。正しい契約書を作成し、産業廃棄物処理に関するリスクを最小限に抑えましょう。
また、産業廃棄物処理委託契約書の取り交わしについては、紙の契約書よりも電子契約のほうが、業務効率とコストの両面においてメリットがあります。
- 印刷や郵送にかかる業務時間を削減できる
- データとしてクラウド上に保存できるため保管場所を取らず、問い合わせがあった場合の検索もかんたん
- 紙の契約書の場合は必要な収入印紙代が不要(電磁的取引であり、課税文書に該当しないため)
『電子印鑑GMOサイン』は、複数の契約書や添付書類を一緒に送信できる封筒機能があるため、産業廃棄物処理契約書の取り交わしに適しています。取引先ごとにフォルダ管理も可能なので、契約書と添付書類をまとめて保存することも可能です。
月に5通までの電子契約が可能なお試しフリープランを使えば、無料で始められます。電子契約の導入を検討されている方はお気軽にお試しください。
産業廃棄物処理委託契約書に盛り込むべき必須項目
産業廃棄物処理委託契約書に記載する項目は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で明確に定められています。以下の項目を記載しない場合、契約書が法的に有効と認められない恐れがあるので、必ずご確認ください。
委託する産業廃棄物の種類と量
産業廃棄物処理委託契約書において最も基本となるのが、委託する廃棄物の種類と数量です。廃棄物処理法では、これらを明確に記載することが義務付けられています。
廃棄物の種類は、廃プラスチック類、金属くず、汚泥など、法律で定められた20種類から該当するものを選択します。
| 番号 | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 石炭火力発電所で発生する石炭がら、焼却残灰、灰カス、炉清掃物など。 |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水処理や製品製造工程などから排出される泥状の物。 |
| 3 | 廃油 | 鉱物性廃油、動植物性油、溶剤、タールピッチ、潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの。 |
| 4 | 廃酸 | あらゆる酸性の廃液、写真定着廃液、廃硫酸など。 |
| 5 | 廃アルカリ | あらゆるアルカリ性の廃液、写真現像廃液、廃ソーダ、金属石鹸液等。 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 廃合成樹脂建材、廃発泡スチロール等梱包材、廃タイヤ、合成ゴムくず、固形状、液状のすべての合成高分子化合物。 |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムのみ(車などのタイヤは廃プラスチック類に分類)。 |
| 8 | 金属くず | 鉄骨・鉄筋くず、金属加工くず、廃容器缶くず等。 |
| 9 | ガラスくずおよび陶磁器くず | ガラスくず、陶器くず、コンクリートくず(工作物の新築・改築除去によって生じたものを除く)、耐火れんがくず、石膏ボード、石綿含廃棄物等。 |
| 10 | 鉱さい | 電気炉等の鉱さい、高炉等の残さい、不良石炭、不良鉱石など。 |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築・改築・除去から発生するコンクリート破片や煉瓦破片。 |
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物処理施設から発生するばいじんであって、集塵装置において捕集されたもの。 |
| 13 | 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、製本業、パルプ・紙、紙加工品製造業、新聞業(印刷を伴う物に限る)、出版業(印刷を伴う物に限る)、印刷物加工業から生じた紙くず。 |
| 14 | 木くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生じた木くず・木製家具等。 |
| 15 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去によるものに限る)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くず、PCBがしみ込んだ天然繊維くず(業種限定なし)。 |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品・医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 |
| 17 | 動物系固形不要物 | とさつ場でとさつし又は解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥にかかる固形状の不要物。 |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される動物のふん尿。 |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農場から排出される動物の死体。 |
| 20 | 13号廃棄物 | 以上の産業廃棄物を処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物。コンクリート固形物など。) |
廃棄物の性状や荷姿に関する情報も重要です。液状か固形か、どのような容器に入れるのかなど、取り扱い上の注意点を記載しておいてください。
また、処理委託する量についても、排出頻度や一回あたりの排出量を具体的に記載します。曖昧な表現は避け、年間総量や月間排出量などの形で数値化して記載しておくとよいでしょう。
処理の方法、場所、期間
産業廃棄物の処理方法や場所、期間についても具体的な取り決めが必要です。
処理場所については、運搬を委託する場合は運搬の最終目的地の所在地を記載します。一方、処分委託の場合は処分施設の所在地や処理方法、施設の処理能力を明記する必要があります。
中間処理を委託するケースでは、その産業廃棄物の最終処分場所の所在地や方法、施設の処理能力も忘れずに記載しましょう。
委託料金と支払い方法
廃棄物処理法の施行規則では、委託者が受託者に支払う料金を委託契約書に記載することが求められています。料金体系は廃棄物の種類や量、処理方法によって異なるため、具体的に記載することが重要です。
- 重量あたりの単価なのか
- 容積あたりの単価なのか
- 一回の収集あたりの固定料金なのか
- 追加料金が発生する条件
このように料金の算出基準や追加料金が発生する場合の条件を明確にしておきましょう。支払い方法については、支払いのタイミングや支払い手段を明記します。請求書の発行方法や支払い期限なども具体的に定めておくと安心です。
契約の有効期間と更新
委託契約の有効期間は、一般的には1年間という期間が多いですが、事業の特性に応じて適切な期間を設定して記載しましょう。
契約更新の方法についても明記が必要です。自動更新とするのか、都度更新の手続きを行うのかを決めておきます。自動更新を選択する場合は、更新を希望しないときの通知期限(例:契約期間満了日の1カ月前までに書面で通知)についても、あらかじめ規定しておくと安心です。
再委託の禁止または条件
産業廃棄物処理における再委託は、適正処理の責任の所在を曖昧にするリスクがあるため、厳しく規制されています。そのため、契約書には再委託の禁止または条件について明確に記載する必要があります。
原則として、排出事業者の書面による承諾なしに処理業者が第三者に処理を再委託することは禁止されています。ただし、例外的に承諾を得て再委託を行う場合には、再委託先の業者名、所在地、許可番号などの情報を契約書に記載する必要があります。再委託先が適切な許可を持っていることの確認方法や、再委託に関する責任の所在も明確にしておくと安心でしょう。
また、災害などの緊急時における一時的な再委託の取り扱いについても、定めておくことをおすすめします。予期せぬ状況で処理が滞ることを防ぐため、どのような条件で緊急的な再委託が認められるのかを事前に合意しておくことが重要です。
契約解除に関する事項
通常解除の場合の通知期間(例:解除の1カ月前までに書面で通知)を定めることにくわえて、契約違反・不正行為・破産など、即時解除となる条件も具体的に記載しておきます。
損害賠償に関する規定も必要です。契約解除によって生じた損害の賠償責任の範囲や、免責事由(不可抗力による場合など)を明確にしておきましょう。
その他に書くべき事項
上記の項目のほかに記載すべき項目としては、以下のものが挙げられます。
- 当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物かどうか
- 積替え又は保管を行う場合には、その場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
- 安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替保管場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 法令の遵守
- 反社会的勢力排除条項
- 機密保持条項
法定記載事項にくわえて「反社会的勢力の排除条項」や「機密保持条項」といった実務上重要な項目を追加することで、より安全に取引ができます。さらにくわしい内容を知りたい方は、産業廃棄物処分委託契約書の手引きもご覧ください。
これらの項目を適切に盛り込むことで、法的に安全かつ実務的に機能する契約書を作成しましょう。
産業廃棄物処理委託契約書のテンプレート
産業廃棄物処理委託契約書を作成する際には、法令で定められた必須記載事項をすべて網羅することが重要です。
一から作成するのは難しいため、テンプレートの活用がおすすめです。ただし、テンプレートを利用する際は、そのまま使用するのではなく、自社の状況にあわせてカスタマイズすることが大切です。
以下の産業廃棄物処理委託契約書は「収集運搬と処分の両方を同一の業者に委託する場合」を想定した場合のテンプレートです。
依頼業者が異なる場合は、全国産業廃棄物連合会の公式サイトに掲載されている「様式1:産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書」および「様式2:産業廃棄物処分委託基本契約書」をご利用ください。
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
排出事業者:_______________(以下「甲」という。)と、
収集運搬及び処分業者:________________(以下「乙」という。)は、
甲の事業場:_________________から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市:______________ 許可都道府県・政令市:_______________
許可の有効期限 :______________ 許可の有効期限 :_______________
事業範囲 :______________ 事業範囲 :_______________
許可の条件 :______________ 許可の条件 :_______________
許可番号 :______________ 許可番号 :_______________
〔特管〕
許可都道府県・政令市:______________ 許可都道府県・政令市:_______________
許可の有効期限 :______________ 許可の有効期限 :_______________
事業範囲 :______________ 事業範囲 :_______________
許可の条件 :______________ 許可の条件 :_______________
許可番号 :______________ 許可番号 :_______________
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市:______________ 許可都道府県・政令市:_______________
許可の有効期限 :______________ 許可の有効期限 :_______________
事業区分 :______________ 事業区分 :_______________
産業廃棄物の種類 :______________ 産業廃棄物の種類 :_______________
許可の条件 :______________ 許可の条件 :_______________
許可番号 :______________ 許可番号 :_______________
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
種類 : ____________________________________________________________________
数量 : ____________________________________________________________________
単価 : ____________________________________________________________________
◎処分に関する種類、数量及び委託単価
種類 : ____________________________________________________________________
数量 : ____________________________________________________________________
単価 : ____________________________________________________________________
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸 入 廃 棄 物: 無
② 輸 入 廃 棄 物: 有 ________________________________________________________
4.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :_______________________________________________
所在地 :_______________________________________________
処分の方法 :_______________________________________________
施設の処理能力:_______________________________________________
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。スクロールできます
最終処分先の番号 事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力 引用:公益社団法人 全国産業廃棄物連合会 産業廃棄物処分委託契約書の手引き
6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:_____________________________________
積替保管施設の所在地:_________________________________________________________
積替保管施設の保管上限:_______________________________________________________
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類 :___________________________________________
提示する時期又は回数:___________________________________________
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第 1 項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第 1 項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成_____年_____月_____日から平成_____年_____月_____日までの_____年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成____年_____月_____日から平成_____年_____月_____日までとする。この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成_______年_____月_____日
甲 ___________________________
乙 ____________________________
産業廃棄物処理委託契約書は義務? 事業者が知っておくべき重要性
産業廃棄物処理委託契約書は事業者と処理業者それぞれの責任範囲と役割を明確化し、適正な処理を担保するために、作成が義務付けられている契約書です。この章では、産業廃棄物処理委託契約書に関する概要と重要性を解説します。
収集運搬委託契約書と処分委託契約書から構成される
産業廃棄物処理委託契約書は、大きく分けて「収集運搬委託契約書」と「処分委託契約書」の2種類で構成されています。これは廃棄物処理法において、収集運搬と処分が別々の業務として区分されているためです。
収集運搬委託契約書には、運搬の最終目的地や、積替保管を行う場合はその所在地と保管上限などの情報が含まれます。一方、処分委託契約書には、処分の場所・方法・処理能力、最終処分の場所・方法・処理能力、さらに搬入業者の情報などを記載する必要があります。
両契約書には共通する項目もあり、法令の遵守、委託内容の詳細、適正処理に必要な情報の提供といった基本事項が記載されます。くわえて、排出事業者と受託者の責任範囲、再委託の禁止、委託業務終了報告なども明記しなければなりません。
産業廃棄物処理委託契約書が必要な理由
なぜ産業廃棄物処理委託契約書の作成は義務付けられているのでしょうか? その根本には「排出事業者責任」という考え方があります。
廃棄物処理法では、産業廃棄物は事業者が自ら処理することを原則としています。しかし現実には、専門の処理業者に委託するケースがほとんどです。そこで問題となるのが、委託後の責任の所在です。
契約書では、どのような種類・量の廃棄物をどのように処理するのかを明確にし、その処理過程における責任の範囲を文書化します。これにより、不適切な処理が行われた場合の責任の所在が明らかになるのです。
また、産業廃棄物処理委託契約書には、廃棄物の性状や注意事項など、適正処理に必要な情報を委託業者に正確に伝達する役割もあります。安全かつ適正な処理を行うためにも、書面で正確に伝えることが重要です。
契約書を作成しない場合のリスク
産業廃棄物処理委託契約書を作成せずに廃棄物処理を委託した場合の、最も直接的なリスクは法的罰則です。
廃棄物処理法では、委託基準に違反して処理を委託した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。許可のない業者に委託するなど特に悪質な場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則が課されるリスクもあります。(参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
また、契約書がないことで廃棄物の処理過程が不透明になり、不法投棄などの不適正処理につながるリスクも高まります。もし委託先が不法投棄を行った場合、排出事業者にも責任が及ぶ可能性があるでしょう。環境問題への取り組みが企業価値に直結する現代では、コンプライアンス違反による社会的信用の失墜にもつながりかねません。
適正な契約書を作成することは、企業の社会的責任を果たすうえでも欠かせないことなのです。
産業廃棄物処理委託契約を結ぶ際の5つの注意点
産業廃棄物処理委託契約書を作成する際は以下のポイントを押さえることで、法令違反を防ぎ、安心して廃棄物処理を委託できます。
二者契約であること
産業廃棄物の処理を委託する際は、排出事業者が収集運搬業者および処分業者とそれぞれ直接契約を締結する「二者契約」が原則です。
これは、廃棄物処理法に基づくもので、収集運搬と処分が法律上別個の業務とされ、それぞれに対して適切な許可を有する業者との契約が求められるためです。処理過程での問題発生時に責任の所在を明確にするために、二者契約の原則を遵守しましょう。
書面で契約すること
産業廃棄物処理委託契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、書面での締結が義務付けられています。口頭やメールによる合意では、法的要件を満たさないため注意が必要です。
なお、2005年に施行された「e-文書法」により、必要な要件を満たす電子契約書も法的に有効とされています。紙の契約書と電子契約書のいずれも、適切に作成されていれば問題ありません。
また契約内容に変更が生じた場合にも、必ず書面で取り交わす必要があります。処理量の増加や廃棄物の種類の追加、処分方法の変更などが発生した場合には、その都度書面による変更手続きを行ってください。
必要な項目を盛り込むこと
産業廃棄物処理委託契約書には、廃棄物処理法で定められた必要項目をすべて記載しなければなりません。法令で規定された項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なっていたりする場合は処理委託基準違反となり、厳しい罰則の対象になります。
特に留意すべき事項として、石綿含有産業廃棄物がある場合はその旨を必ず明記してください。また、積替えや保管を行う際には、事業所の所在地や保管可能量の上限なども併せて記載する必要があります。
くわえて適正処理に必要な情報(廃棄物の性状や荷姿、保管状況での変化可能性など)や契約解除時の未処理廃棄物の取り扱いに関する事項も含める必要があります。
契約書に許可証等の写しが添付されていること
産業廃棄物処理委託契約書には、委託先業者の許可証の写しを必ず添付しなければなりません。この添付書類は契約書の有効性を保証する重要な要素であり、法令で義務付けられています。
添付すべき書類には、契約内容に該当する許可証や再生利用認定証等の写しが挙げられます。たとえば収集運搬を委託する場合は収集運搬業の許可証、処分を委託する場合は処分業の許可証が必要です。両方を委託する場合はそれぞれの許可証の写しを添付しなければなりません。
また、許可証には有効期限があるため、更新時には新しい許可証の写しを再度添付する必要があります。これを怠ると、知らないうちに無許可業者に委託してしまうリスクが生じます。排出事業者としての責任を果たし、適正な産業廃棄物処理を確保するためにも、許可証等の写しの添付は必須事項として認識しておきましょう。
5年間保存すること
産業廃棄物処理委託契約書は、契約終了の日から5年間保存することが法律で義務付けられています。この保存義務を怠ると、排出事業者は委託基準違反として罰則を受ける可能性があります。保存期間中に立入検査や行政からの問い合わせがあった場合、すぐに契約書を提示できる状態にしておきましょう。
電子契約の場合も同様に5年間の保存義務があります。クラウドサービスを利用している場合は、サービス終了やデータ消失のリスクが考えられるため、定期的なバックアップを取ることをおすすめします。
契約書の保存は法的要件であるだけでなく、廃棄物処理に関する紛争やトラブルが発生した際の証明や行政からの問い合わせがあった際の適正処理の証明にも役立つものです。しっかりと重要性を認識し、適切な保存を行いましょう。
産業廃棄物処理委託契約書の取り交わしは電子契約でも可能
産業廃棄物処理委託契約書は書面での発行が義務付けられていますが、従来の紙媒体だけでなく電子契約での締結も法律で認められています。廃棄物処理法に規定された「書面による契約」には、電子契約も含まれるのです。
また、保管の面でもメリットがあります。産業廃棄物処理委託契約書は5年間の保存義務があるため、紙の契約書では保管スペースの確保が必要です。電子契約であればデータとしてクラウド上に保存できるため、物理的なスペースが必要ありません。検索機能を使えば、問い合わせがあった場合に探す手間も省けるでしょう。
事業者によっては、契約にかかるコストにおいても大きな削減効果が期待できます。印刷費や郵送費、保管コストはもちろんのこと、紙の契約書では貼付けが必要な印紙税が、電子契約なら不要です。
電子契約書は電磁的取引であり、税法上の課税文書に該当しないため、印紙税がかからないのです。業務効率化とコストカットの両面でおすすめできるので、産業廃棄物処理契約を作成する際は電子契約の導入をご検討ください。
『電子印鑑GMOサイン』は、複数の契約書や添付書類を一緒に送信できる封筒機能があるため、契約書に添付すべき許可証の写しなどをまとめて送ることが可能です。また、取引先ごとにフォルダ管理が可能なので、保存方法にも困ることがありません。
月に5通までの電子契約が可能なお試しフリープランも用意しています。無料で導入できるので、電子契約の導入を検討されている方はお気軽にお試しください。
産業廃棄物処理委託契約に関するよくある質問
産業廃棄物契約とは何?
産業廃棄物契約とは、事業者が自社の廃棄物処理を外部の専門業者に委託する際に締結する約束のことです。この契約は「収集運搬委託契約書」と「処分委託契約書」の2種類から構成されます。
廃棄物処理法では、どのような種類・量の廃棄物を排出し、どう処理するかを明確にしたうえで、許可を持つ業者と書面で契約することが義務付けられています。
契約書には廃棄物の種類や数量、処理方法など法定事項を漏れなく記載し、業者の許可証のコピーも添付しなければなりません。
産業廃棄物処理委託契約は必須?
事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、必ず書面による契約を交わすよう廃棄物処理法で定められています。この規定に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
事業活動を安全に継続するためにも、この契約は必ず締結しましょう。
産業廃棄物の契約書は義務?誰が作成する?
産業廃棄物処理委託契約書の作成は、法律上「排出事業者」の義務となっています。
実務上は処理業者が契約書のひな形を用意してくれるケースも多いですが、最終的な責任は排出事業者にあることを忘れてはいけません。
内容に抜け漏れがないか、法定記載事項が網羅されているか、必ず確認が必要です。
産廃契約は現場ごとに必要?
工事現場など場所が変わる場合や、廃棄物の種類・処理方法が異なる場合には、新たな契約や契約内容の変更が必要となることもあります。
特に注意すべきは、契約書に記載された「廃棄物の種類」や「運搬の最終目的地」「処分方法」などが変わる場合です。こうした情報に変更が生じたときは、口頭ではなく書面による変更手続きが求められます。
現場ごとに廃棄物の性状が大きく異なるケースでは、それぞれの現場に適した契約内容を検討する必要があるでしょう。
産業廃棄物処理委託契約書に印紙はいくら分必要?
産業廃棄物処理委託契約書は、印紙税法に基づく課税対象となるため、適切な印紙を貼付する必要があります。
具体的な金額は契約の形態によって異なります。収集・運搬契約書は印紙税法の課税物件表「第1号の4文書」に該当し、処分契約書は「第2号文書」に分類されます。また、収集・運搬と処分を一体化した契約書の場合は「第1号の4文書」として扱われます。
印紙の金額は契約金額によって変動するため、事前に確認が不可欠です。
【第1号の4文書(収集・運搬委託契約書) 印紙税額】
スクロールできます
契約金額 印紙税額 1万円未満 非課税 10万円以下 200円 50万円以下 400円 100万円以下 1,000円 500万円以下 2,000円 1,000万円以下 10,000円 5,000万円以下 20,000円 1億円以下 60,000円 5億円以下 100,000円 10億円以下 200,000円 50億円以下 400,000円 50億円を超えるもの 600,000円 契約金額の記載のないもの 200円 解約の場合 不要 参考:国税庁 【第2号文書(処分委託契約書) 印紙税額】
スクロールできます
契約金額 印紙税額 1万円未満 非課税 100万円以下 200円 200万円以下 4000円 300万円以下 1,000円 500万円以下 2,000円 1,000万円以下 10,000円 5,000万円以下 20,000円 1億円以下 60,000円 5億円以下 100,000円 10億円以下 200,000円 50億円以下 400,000円 50億円を超えるもの 600,000円 契約金額の記載のないもの 200円 解約の場合 不要 参考:国税庁
印紙の貼り忘れは追徴課税のリスクも伴うため、契約締結時には必ず確認しましょう。また、契約期間が長期にわたる場合や金額が大きい場合は、かなりの印紙税負担になることもあります。
産業廃棄物処理委託契約書とあわせて作成すべき書類はある?
産業廃棄物処理委託契約書を作成する際は、いくつかの重要書類をあわせて準備する必要があります。
まず必須なのが処理業者の「許可証の写し」です。また、廃棄物を引き渡す際には、排出事業者が「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を発行する必要があります。このマニフェストは、廃棄物の収集・運搬・処分の各段階を記録し、適正な処理を確認するための重要な管理ツールです。
さらに、適正処理のために必要な情報として、廃棄物の性状や取扱上の注意点をまとめた資料も用意するとよいでしょう。特に有害物質を含む廃棄物の場合は詳細な情報が不可欠ですので、忘れずに用意してください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを記録・追跡するための書類で、排出事業者が作成し、処理業者に交付します。1990年に制度が導入され、1998年にはすべての産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務化されました。
マニフェストには、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。
- 交付年月日・交付番号
- 排出事業者の氏名・住所・電話番号
- 排出事業場の名称・住所
- 産業廃棄物の種類・数量・荷姿
- 有害物質の有無(該当する場合)
- 処分方法
- 運搬業者および処分業者の名称・住所
処理業者は処理完了後にマニフェストを返送し、排出事業者は適正な処理が行われたことを確認します。マニフェストは5年間の保管が義務付けられており、記載漏れや虚偽記載には罰則が科されることがあります。
産業廃棄物処理契約は電子契約での締結が便利
産業廃棄物処理契約書について、記載すべき事項とひな形、注意事項を解説しました。産業廃棄物処理契約書の作成は法律で義務付けられているため、適切な項目を含んだ正しい契約書を作成しましょう。
産業廃棄物処理契約は書面で契約内容を残す必要がありますが、紙の契約書だけでなく電子契約書でも可能です。電子契約であれば、オンライン上ですぐに取引先へ送信できるため、印刷や郵送といった契約業務を効率化できます。
特に大きなメリットがコスト削減効果です。紙の契約書では、印刷費や郵送費、保管コストが発生しますが、電子契約ではこれらを大幅に削減できます。また、紙の契約書では必要な印紙税が電子契約なら不要です。
『電子印鑑GMOサイン』は、複数の契約書や添付書類を一緒に送信できる封筒機能があるため、産業廃棄物処理契約書の取り交わしに適しています。取引先ごとにフォルダ管理も可能なので、契約書と添付書類をまとめて保存することも可能です。350万社以上の導入実績があり、国内シェアNo.1(※)を獲得しているため、安心してご利用いただけます。
GMOサインでは、月に5通までの電子契約が可能なお試しフリープランも用意しています。無料で導入できるので、電子契約の導入を検討されている方はお気軽にお試しください。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)