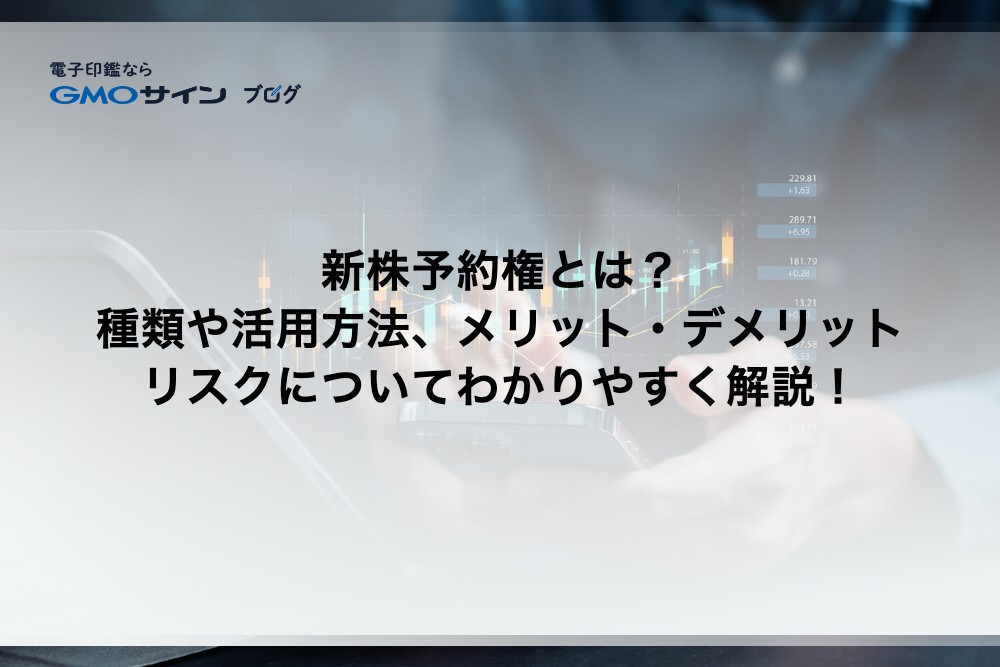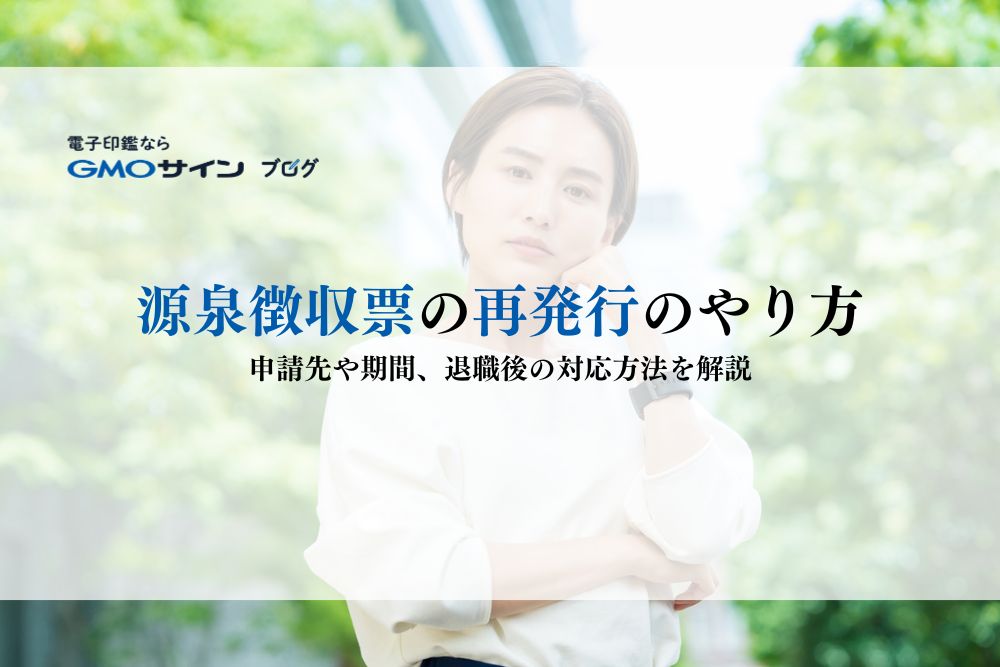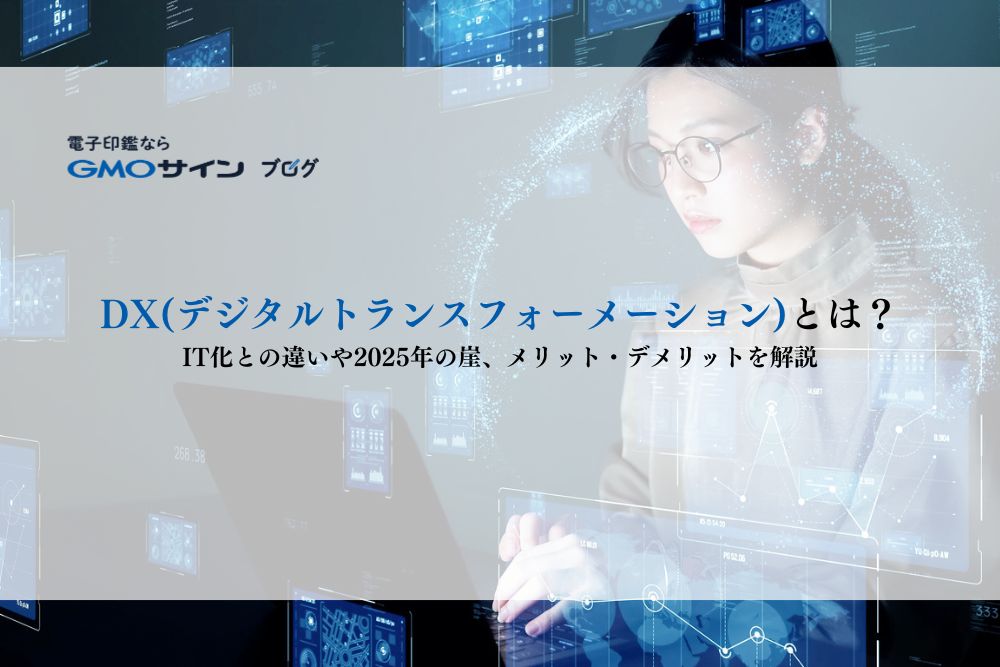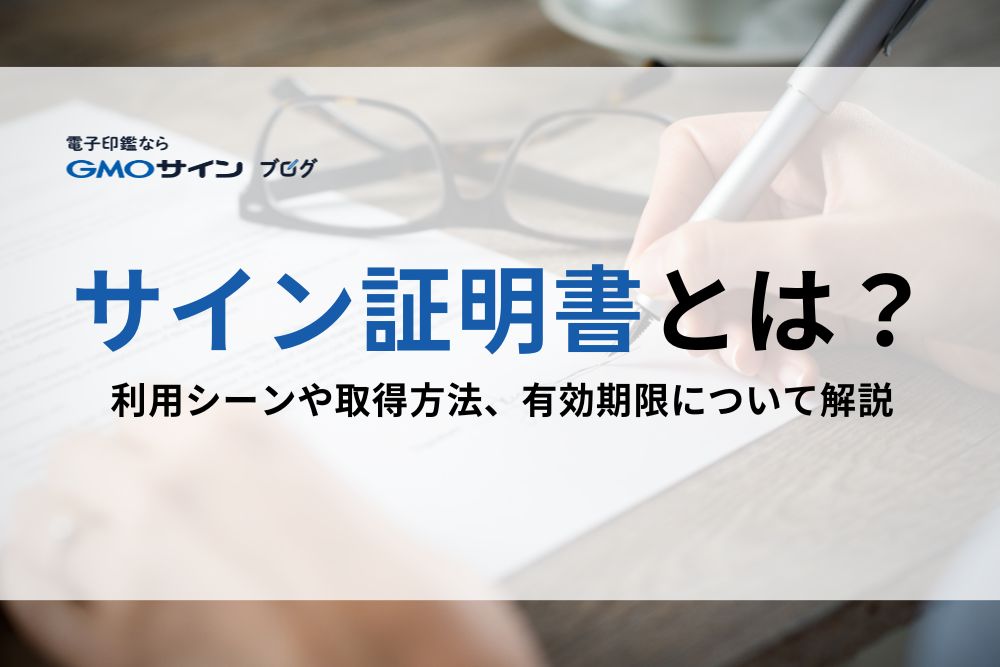与信とは、企業が取引先に対して信用を与えることです。商品やサービスを先に提供し、代金を後日回収する後払いを許容する仕組みになります。
業務効率化の観点から、都度回収せずに後日回収できる与信取引は、取引先の増加とともに増えるでしょう。
一方で、「与信審査はどのようにすればよいか?」「与信管理をどう進めたらいいかわからない」などの疑問や悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。与信取引を行うにあたり、与信審査と与信管理の正しい手続きと理解が必要です。
本記事では、与信の基本的な概要や与信審査の具体的な手順、与信管理の詳細な内容までを詳しく解説します。この記事を読むことで、与信取引に必要な知識が深まり、適切な与信審査や与信管理に取り組めます。
与信とは?
与信とは、企業が取引先を「信用できる」と判断し、後払い取引を可能にする仕組みです。具体的には、商品やサービスを先に提供した後で代金を回収する方法を指します。
与信による取引は、3つの重要な役割を担います。
- 取引の効率化
- リスク管理
- 信頼関係の構築
例えば、与信取引を導入することで、随時回収する必要がなくなり、業務の効率化が可能です。
また、リスク管理では、取引先の信用評価を通じて支払い能力を見極める手段となり、貸し倒れリスクや未回収リスクを事前に察知し、防止策を講じられます。
与信審査と与信管理
与信取引にあたって、与信審査と与信管理を理解しておくことが重要です。ここではそれぞれの概要について説明します。
与信審査とは?
与信審査とは、取引先ごとに審査結果に基づいて信用力を評価し、取引上限金額である与信限度額や取引条件を決定する手続きです。取引先に関する情報などから調査する主な内容は以下の通りです
- 取引先の財務状況
- 支払い遅延など過去の取引履歴
- 業界の先行き
あらゆる情報から総合的に審査判断した結果に基づいて与信限度額を正しく決定します。適切な取引条件の設定と取引リスクをコントロールするために与信審査は欠かせません。
与信管理とは?
与信管理とは、与信審査の結果をもとに決められた与信限度額の範囲での取引や取引条件どおりの運用を管理します。また、取引先の状況を継続的に確認し、回収リスクの管理が必要です。
例えば、審査結果で決めた与信限度額以上の取引を行った場合、取引先の支払い能力を超過する恐れが生じ、リスクが高まります。また、取引先の業績が悪化した場合には、取引条件変更や与信限度額の見直しが必要となるでしょう。
このように管理することで、取引後の問題を防ぎ、安定した取引関係を続けられます。
さらに与信管理では、定期的な取引条件の見直しを必要とします。日々の企業活動により財務状況や業界動向が変化するため、現状に応じて対応することが重要です。
与信審査の方法と流れ
与信審査の方法には情報収集と分析・評価があります。与信審査の結果をもとに、取引条件を決定する流れです。ここでは具体的な審査内容と流れ、および留意点について解説します。
情報収集による最新の情報で判断
最新の情報を収集することが与信審査における最初のステップです。取引先の正確な状況を把握するために、外部情報と内部情報を組み合わせて判断します。
以下に外部情報の種類をまとめました。
| 外部情報の種類 | 情報取得先 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| 取引先の決算書 | ・取引先依頼 ・取引先ホームページ | ・取引先の財務状況 |
| 調査レポート | ・調査会社(東京商工リサーチや帝国データバンク) | ・取引先の経営状況 ・取引先の信用力に関わる外部評価 |
| 商業登記簿謄本 | ・法務局・オンライン登記システム | ・取引先の役員人事などの運営状況 |
次に内部情報の種類について見ていきましょう。
| 内部情報の種類 | 情報取得先 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| 営業担当者へのヒアリング | 現在または過去の営業担当者 | ・取引先の近況や信頼性 |
| 過去の取引歴 | 社内の取引記録 | ・支払い遅延の有無 ・取引額の推移 |
外部情報と内部情報を組み合わせた活用は、取引先の現状や信用力を多角的に評価できます。例えば、決算書から財務内容を確認し、取引履歴から支払い遅延がないことを確認できれば、取引先の財務の健全性を高く評価できます。
データや人間性などからの分析・評価
収集した情報をもとに、データと人的要素から定量分析と定性分析から評価します。
定量分析は、外部情報から得た売上高や利益率などの財務データを用いた指標を業界平均などと比較して評価します。取引先の安全性や収益性、競争力などを把握可能です。
定性分析は、経営者の人間性や経営力、業界の動向といった数値化できない要素を評価します。例えば、経営者の実績や判断力、業界内での評判が審査のポイントです。
審査結果による取引内容の決定
審査結果に基づいて、以下のような内容を決めます。
- 与信限度額の設定
- 取引条件の設定
- 必要に応じた担保や保証
与信限度額は取引先の信用力に応じて取引の上限額を設定します。信用力が高いほど、回収リスクも低いため、高い金額の設定が可能です。
取引条件の設定は取引先へ支払条件や納期、支払い方法を明確に伝えます。信用力の高い先には支払期日に余裕をもたせることが可能です。取引先との条件交渉において、お互いがWin-Winになるように柔軟な対応を取れます。
信用力の低い取引先には、取引リスクを軽減するために必要に応じて担保や保証を求める場合があります。不動産や取引先が別の取引先に販売した債権を担保としたり、第三者から保証を取り入れたりするといいでしょう。
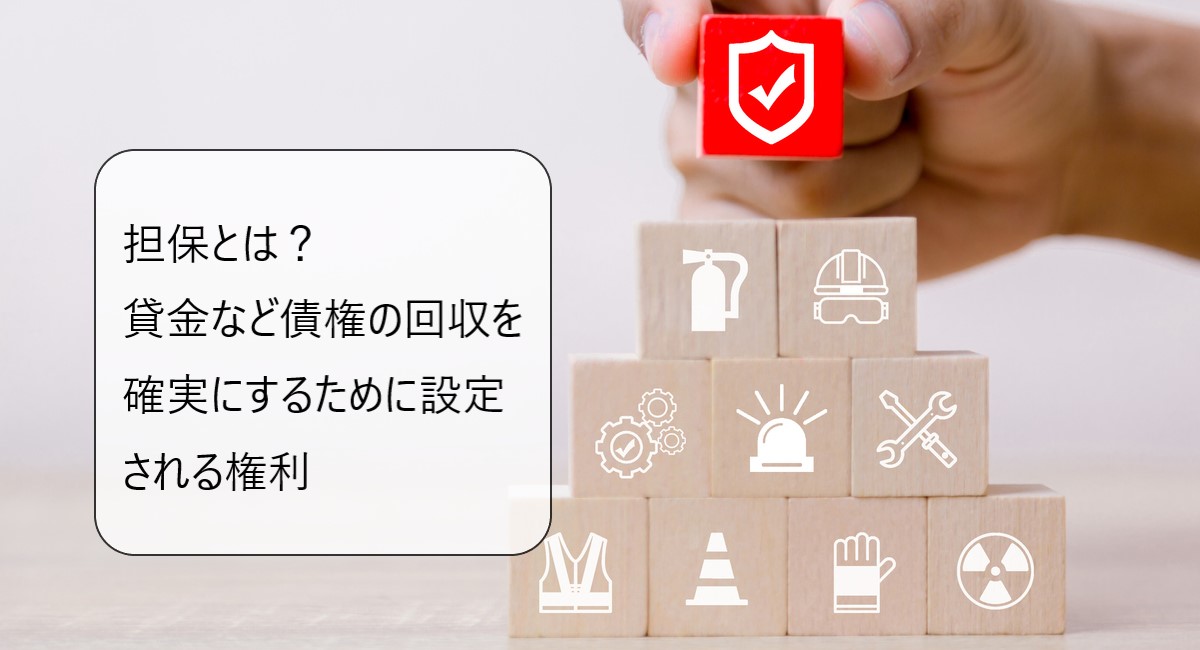
与信審査の留意点
与信審査を行う際には、以下のポイントに注意する必要があります。
- リスク回避
- 透明性の確保
- 定期的な見直し
与信審査ではリスク回避を念頭に置く必要があります。取引先の信用力を客観的かつ慎重に評価し、貸し倒れや未回収リスクを最小限に抑えた取引を維持することが重要です。
審査基準を明確にして審査に透明性を確保する必要があります。担当者の属人的な判断を排除して公平性を保ちましょう。
定期的な見直しで取引の安定性を維持します。取引先の状況や市場環境の変化を迅速に察知することで、現状に合った信用力を基にした取引が可能です。
与信管理の重要性
与信管理は、与信審査による結果をもとに取引先の信用力を評価したあと、取引を進めるうえで欠かせません。与信管理により3つの重要な効果が発揮されます。
- 連鎖倒産を防止する
- 資金繰りの逼迫を回避する
- 貸倒れによる減益を防ぐ
与信管理を怠ると上記の効果が発揮されず、大きなリスクを招く可能性があります。与信管理を適切に行うことで、企業は経済的な安定性を確保し、健全な取引関係の維持が可能です。
ここでは与信管理がもたらす3つの重要な効果を解説します。
連鎖倒産を防止する
適切な与信管理を行えば、取引先の状況変化をいち早く察知して対策でき、連鎖倒産の防止につながります。
連鎖倒産は倒産した企業と取引していた企業も資金繰りが悪化して倒産してしまうことです。連鎖倒産の多くの原因は、倒産先から代金を回収できなかったためです。
また、複数の取引先との取引バランスを保った与信管理は、1社に対する売上依存度を下げ連鎖倒産の防止策として効果的でしょう。
資金繰りの逼迫を回避する
適切な与信管理により、取引先からの代金回収が遅延し自社の資金繰りが逼迫するといった事態を回避できます。
最新の情報で取引先の支払い能力を把握し、回収が遅れるリスクを事前に軽減することが可能です。
与信管理により取引先の支払い遅延の兆候を見逃さず、早期に取引条件を見直せます。自社の資金繰りへの影響を最小限に抑えられるでしょう。
貸倒れによる減益を防ぐ
取引先が支払い不能に陥って発生する貸倒れによる影響を防げます。与信管理が適切に機能していることで、取引先の信用状態から察知して最悪の事態の場合への準備が可能です。
取引先に対する定期的な見直しから信用状態が悪化していることに気づき、取引縮小や取引条件の変更に動いて貸倒れを防げます。
与信管理を怠ると、貸倒れが予期せぬ形で発生し、自社の財務状況や経営に悪影響を与えかねません。信用状態の悪化を早く把握した貸倒れリスクの回避が、減益を防ぐことにつながるでしょう。
与信管理の方法
適切な与信管理の実施は、取引先からの回収リスクを最小限に抑えた健全で安定した取引の維持につながります。
主な与信管理の方法は以下の通りです。
- 与信限度額の運用
- モニタリングの実施
- 取引先の分散
ここでは、具体的な与信管理の方法を解説します。
与信限度額の運用
与信限度額は取引先の信用度に応じて設定された取引額の上限です。与信限度額を適切に管理することで、取引先の支払い能力以上になる取引を抑制できます。
支払い能力以上の取引は、取引先の資金繰りを逼迫させ、自社が回収できないリスクが高まります。
与信限度額を適切に運用するために必要な取り組みは以下の2つです。
- 与信限度額の適切な設定
- 定期的に与信限度額を見直す
与信審査で判断した信用力や確認した財務状況をもとに、今後の取引見通しを含めて与信限度額を設定します。与信限度額の範囲内で取引することで、回収リスクの軽減が可能です。
取引先の業績や市場環境の変化に応じて、与信限度額の調整が必要になります。
与信審査の見直しによる結果が良くなっていれば、与信限度額を引き上げます。一方で、悪化していれば、引き下げすることで取引量の縮小に方向転換が可能です。
モニタリングの実施
与信限度額を設定したあとの運用のなかでモニタリングの実施が重要になります。主なモニタリングは以下の通りです。
- 取引先の財務データの確認
- 支払い状況のチェック
- 外部情報の活用
取引先の財務データの確認で決算書の確認は重要ですが、定期的な業況確認資料を確認することも必要です。決算書以外の提出を受けることが難しい場合は、ホームページの開示有無や営業担当にヒアリングする手段があります。
日常の取引で支払い状況や取引条件の遵守状況を確認することで、取引先の変化を早期に見つけられます。支払日の入金タイミングをチェックすることも有効です。
昼間の入金は自社に振り込まれる入金を待って行っている可能性があり、資金繰りに余裕があるかどうか見分けられます(※支払時間帯は目安の一つに過ぎず、必ず通帳残高推移や資金繰り表とあわせて判断すべきです)。
取引先の分散
取引先の分散は、複数の取引先と取引することで、1社に依存しすぎるリスクを減らす方法です。分散の主な方法は下記の通りです。
- 取引先の多様化
- 依存度の見直し
- 業界や地域の分散
複数の取引先と取引することで、状況が急変した取引先があっても自社全体に与える影響を低く抑えられます。
取引をすすめるにつれて、売上や仕入れが一定割合以上を占める取引先に対して、依存度を下げる戦略を取ることが重要です。
特定の業界や地域に偏らず、幅広いジャンルの取引先を確保することで、業界動向や経済状況の変動によるリスクを軽減できます。
与信審査と与信管理を適切に実施しよう
与信とは、取引先ごとに信用を与えることです。与信により円滑で効率的な取引が可能になります。
与信取引するうえで、与信審査と与信管理は重要です。与信審査では情報収集と分析・評価が必要になります。与信管理は取引をすすめる際に欠かせません。
与信管理によりもたらされる以下の効果は重要です。
- 連鎖倒産を防止する
- 資金繰りの逼迫を回避する
- 貸倒れによる減益を防ぐ
正しい審査と管理の徹底が取引のリスクを管理するために欠かせない手続きになります。適切な運用がリスクを抑えた安定した経営につながるでしょう。