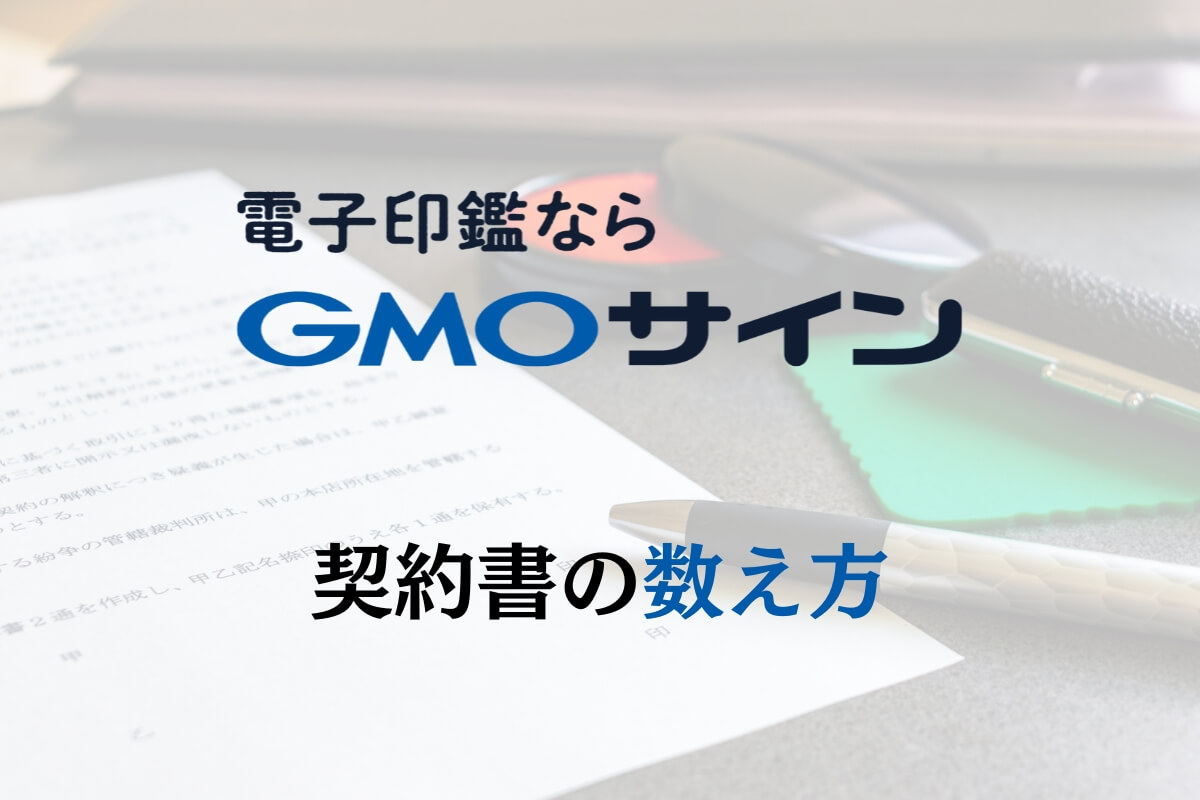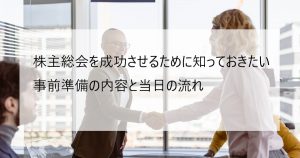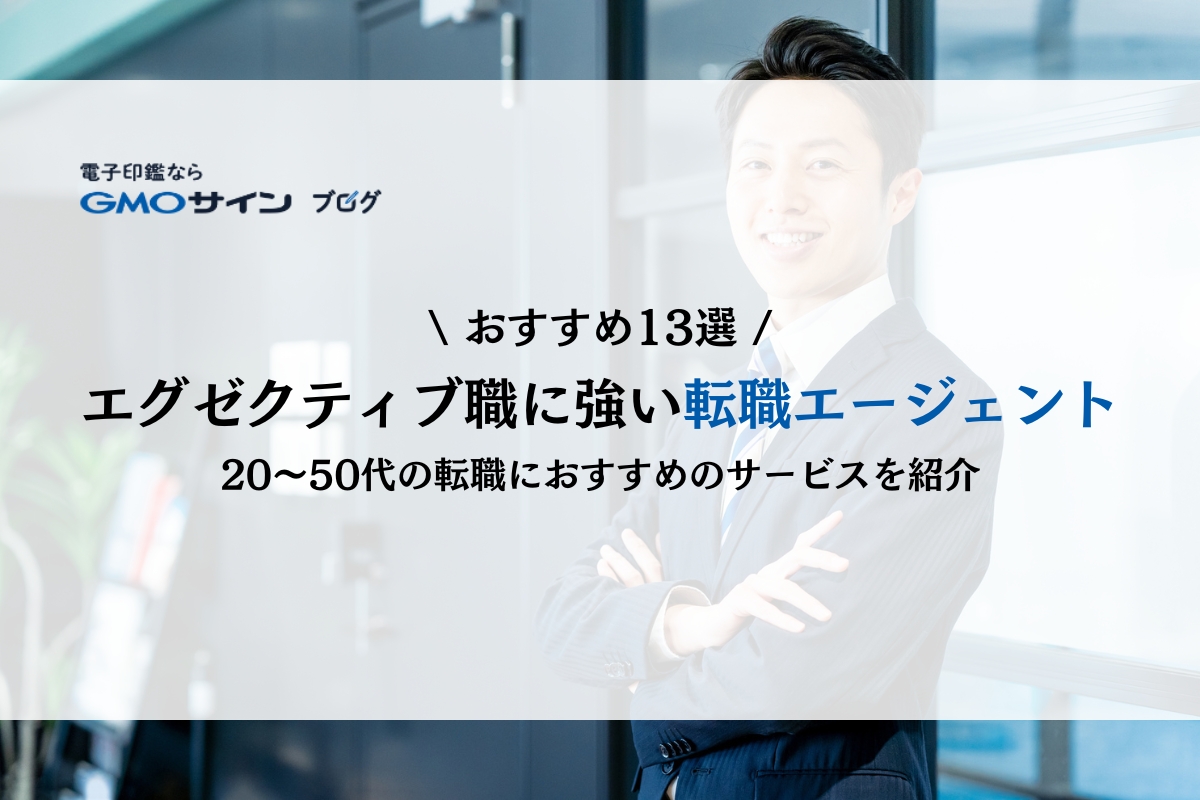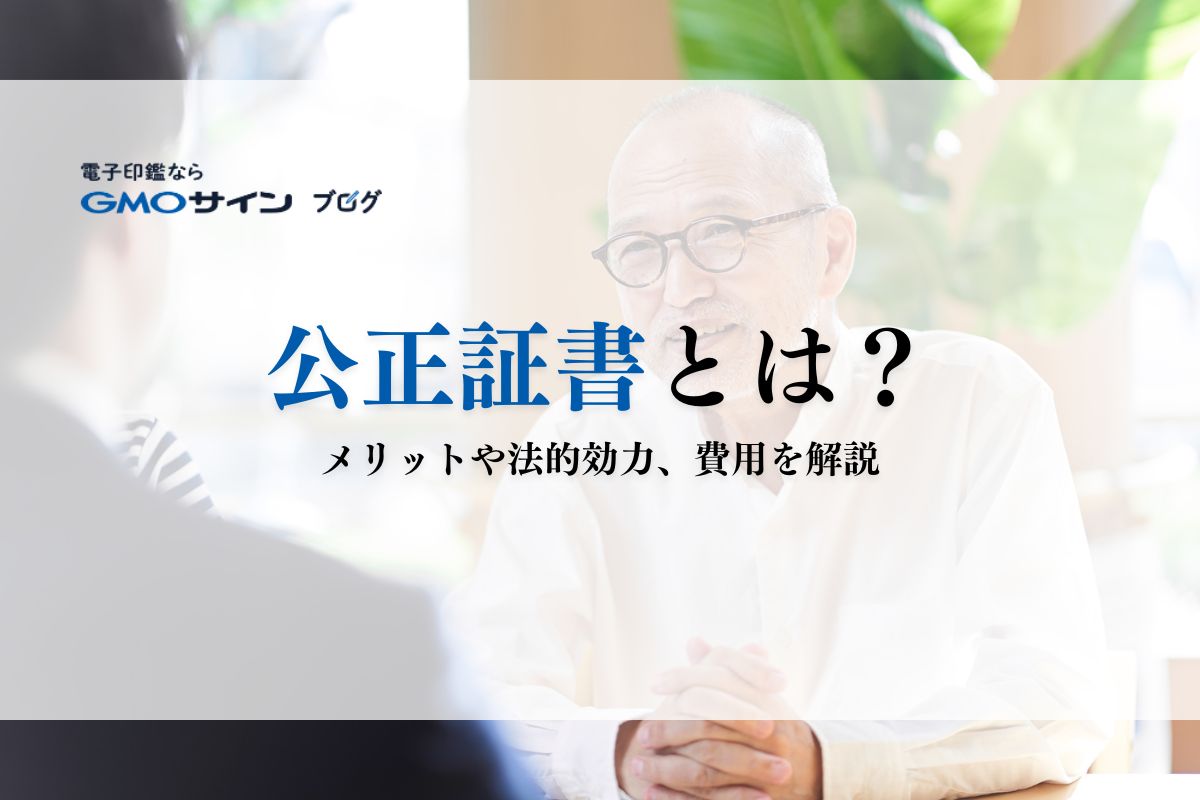商号とは、事業活動を行うにあたって使用される会社名のことで、公的な文書や契約書で用いられます。企業にとって重要な役割を果たしますが、商号の定義や他の用語との違いなどについて把握しきれていない方もいるでしょう。
この記事では、商号の意味や屋号・商標との違い、決定時に注意すべき会社法の内容などをわかりやすく解説していきます。商号についてかんたんに把握したい方や失敗しない決定方法を知りたい方は参考にしてみてください。
商号とは
商号とは、会社が事業活動を行うにあたって使用される名称、いわゆる会社名を表します。事業を行うにあたって、契約書に記載され、顧客からも会社の顔として認識される大切な名称です。
商号は法律によって規定されており、法人の場合は法人登記の際に同時に商号も登録します。以降はその商号をもとに自社の活動を行うことになるため、名称については慎重に決めなければなりません。
屋号との違い
個人事業主には商号の登記義務がなく任意なため、屋号を用いる場合が多いと前述しました。屋号は法的拘束力がなく、個人が事業を行う場合の一般的名称として、自由に利用できます。
しかし、商号と違って法的拘束力もないため、似通った名称が利用されるなどのトラブルが発生する場合もあります。その場合でも、一方的に権利を主張することができず、対応が難しい点はデメリットといえるでしょう。
屋号を付けること自体も任意なため、個人事業主は屋号なしで事業を進めても問題はありません。
商号を決める際の注意点
商号を決める場合にはいくつか法的に定められた要件があり、これを満たしていなければ商号として受理されません。商号については会社法の第6条・第7条・第8条に命名についての注意点が記載されています。
(商号)
引用:会社法|e-Gov法令検索
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
こちらの内容をもとに、改めて以下で注意点をまとめています。
会社種類は明示する
会社の商号には会社の種類を明示しなければなりません。会社の種類は株式・合名・合資・合同のいずれかになります。入れる場合は商号内のどの部分でも問題はありません。
しかし、他の種類の会社だと誤認されかねない文字は用いてはならないとされています。つまり、会社の種類に該当する株式や合名などの文字は、種類を表す箇所以外では用いるべきではないということです。
誤認の可能性がある文字や名称は使えない
取引先や会社名を目にする一般消費者が会社名を誤認するのを防ぐために、誤認の可能性がある文字や名称は使ってはいけません。また、不正の目的で他の会社と誤認される商号を意図的に使用した場合、相手方は営業上の利益を侵害されたとして、侵害の停止や予防の請求ができます。
同一所在地で同一商号は禁止
同一所在地で既に他人が登記した商号が存在している場合、後から登記申請を行う法人や個人事業主が同一の商号を登記することはできません。これは事業主体が同一であるとの誤認を防ぐためでもあります。
ただし、同一商号でも所在地が異なる場合は使用が認められています。集合住宅や複数の会社が入っているビルについても、部屋番号が違えば別の所在地とみなされて同一商号の利用が可能です。
また、前株と後株の違いがある場合は別の商号とみなされるため、同一所在地でも登記は認められます。これに対して、同じ文字で読み方が異なる場合は、同一商号とみなされて同一所在地では登記できないため注意しましょう。
公序良俗に反してはいけない
これは当然の話ではありますが、商号に差別的表現や、大多数に不快感を与えるような文言を入れることも禁止です。また、資格名を表す商号、歴史上の人物名からなる商号をつけることもほとんどの場合は却下されます。
商標権侵害を問われないか注意
商品やサービスに対して使用する商標に与えられる商標権の効力は、対象の商品だけではなく、類似している範囲にも及びます。この類似している範囲には、会社の商号も含まれているため注意が必要です。
つまり、商標権が登録されている商品やサービスと登記した商号が類似していると判断された場合、商標権侵害を問われる恐れがあります。商標権侵害と認定されてしまえば、商号の変更を余儀なくされ、最悪の場合は商標権者への損害賠償責任を負うケースも考えられます。
商号を考えた後は、その名称が商標権侵害を問われる危険性がないかを調査しなければなりません。商標権については、インターネット検索により特許情報を確認できるため、必ず確認して侵害のリスクを防ぎましょう。
商号は他人に貸すことが可能
自社に付けた商号は、他人に貸し出すこともできます。商号を貸す側のブランドや知名度が高い場合は、借りた側の事業がうまくいくメリットがあるため、この手法はよく用いられており名板貸しとも呼ばれています。
しかし、この名板貸しはたびたびトラブルを引き起こしています。紛らわしい名前の会社によって商号を貸したと勘違いされた、第三者が貸した側の会社と契約していると勘違いしていたなど、責任の所在に関する問題が後を絶ちません。
商号の譲渡も可能
商号は貸し出すだけではなく、譲渡することも可能です。ただし、商号の譲渡にはいくつかの条件があり、事業譲渡や合併などの営業とともに譲渡する場合と、廃業や解散・精算など営業を廃止する場合に限られるので注意が必要です。
商号を譲渡する側は、同一の市町村において競業避止義務を負うことになり、同一の営業を行うことが禁止されます。
ただし、競業避止義務は特約を定めることが認められており、期間短縮などの条件緩和や最長30年まで期間を延長するといった措置も可能になっています。また、商号を譲り受けた側(譲受人)が商号を続けて利用する場合、譲渡人の事業で生じた債務を弁済する責任、いわゆる商号続用責任を負うことになります。
これは譲り受けた商号を使って営業する以上、譲受人側を信頼した譲渡人を保護する目的で存在する規定です。譲受人に対する請求権は、商号の譲渡日以降2年間に渡って有効であることを覚えておきましょう。
商号についてのよくある質問
会社名や商標との違いは?
商号は法的に登記される会社の名称のことで、契約書や登記簿など公的な文書で使用されます。会社名は、企業を呼称する際に使用する一般的な名称のことです。日常的なビジネスシーンで広く利用されます。
商標は、特定の商品やサービスを識別するための標識です。特許庁に出願・登録することで、他者によって同一の商標が利用されることを禁止できます。
商号の変更を行う際は、どのような書類や手続きが求められる?
商号の変更を行う際に必要な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 印鑑届書(商号の変更にあわせて、印鑑の更新を法務局に届け出る場合)
- 代表取締役の印鑑証明書(商号の変更にあわせて、印鑑の更新を法務局に届け出る場合)
株式会社が商号を変える場合、定款の内容を変更するために株主総会で特別決議を行う必要があります。その後、法務局に登記申請書や株主総会の記事録などを提出しましょう。
商号変更登記を怠ると、会社法第976条に則って代表者が100万円以下の罰則を受ける可能性があります。また、登録が完了した後は、税務署への届け出や取引先への連絡なども忘れずに行うことが大切です。
商号を選ぶ際に注目すべきポイントは?
商号を選ぶ際は、法的な制限への考慮はもちろんのこと、事業内容を反映させたわかりやすい名称を選択することが大切です。商号が長過ぎると取引先や顧客の記憶に残りづらくなってしまうので、簡潔な名称を付けましょう。
また、現代ではWebから集客することが多いため、考えた商号でドメインを取得できるのか確認しておくことも重要なポイントです。他者に取得されている場合はドメインを買い取ることも可能ですが、設立時に余計な費用が発生しないように、事前に商号を調整しておきましょう。
商号は目的をもって決めるべき
商号が取引先や顧客に与える印象は、とても大きなものになります。いわゆる会社の顔として重大な役割を果たすため、権利の侵害や法的にリスクのある商号にはせず、安全かつ明確な方針に基づいて慎重に決定しましょう。
商号を決める場合は、地域の名称を入れたり事業内容を入れたりと、自社で取り組んでいる内容やゆかりのあるものを名称に用いることをおすすめします。また、仕事に対する取り組みの姿勢がわかるようなインパクトのある言葉や、座右の銘としている言葉を取り入れるのもよいでしょう。