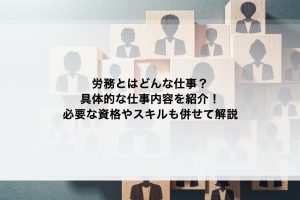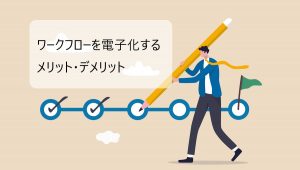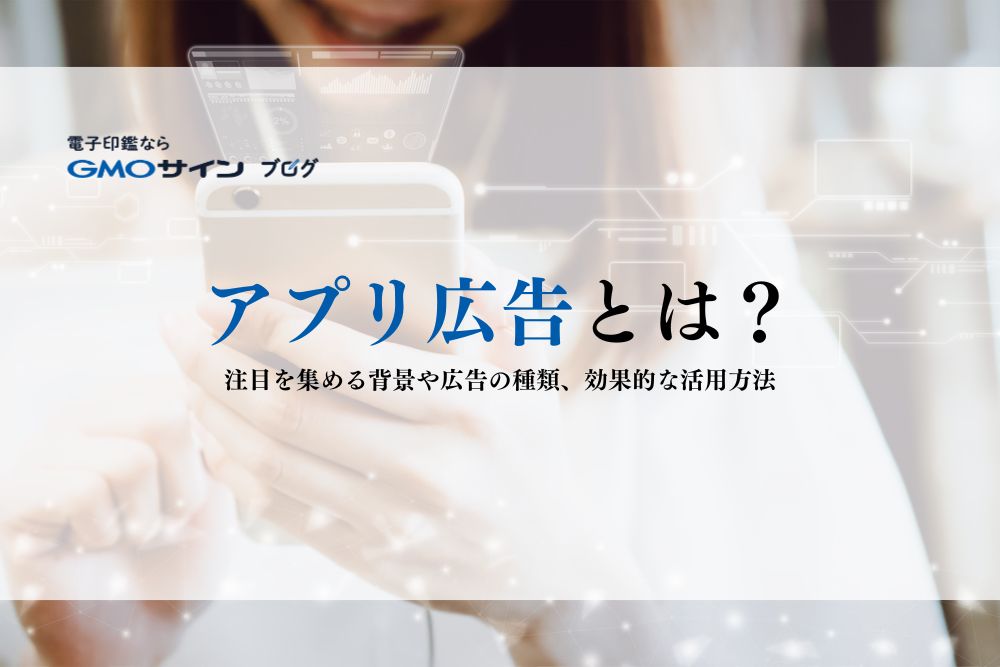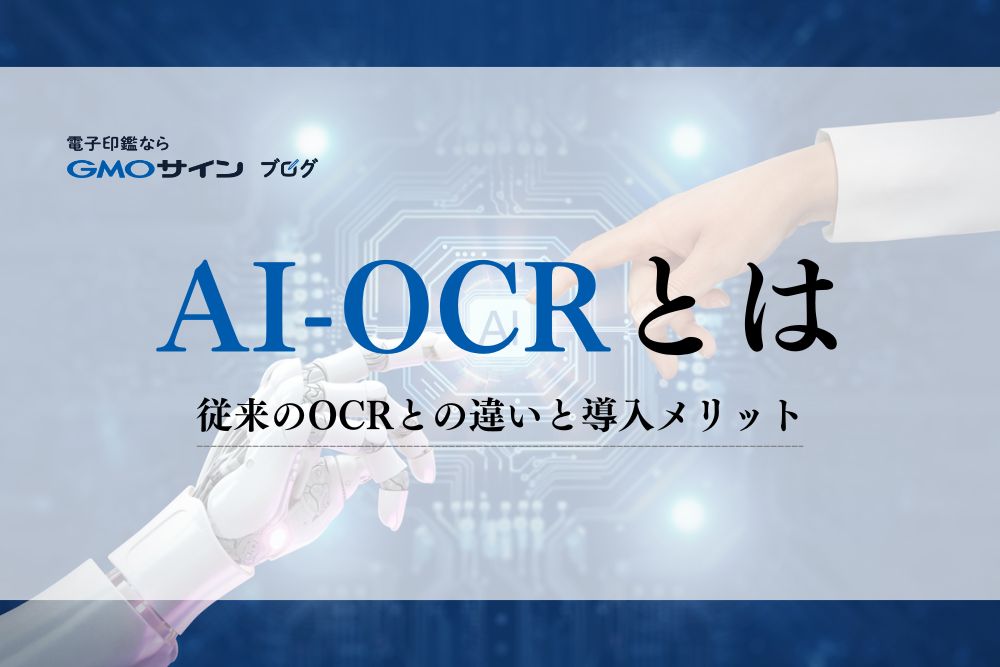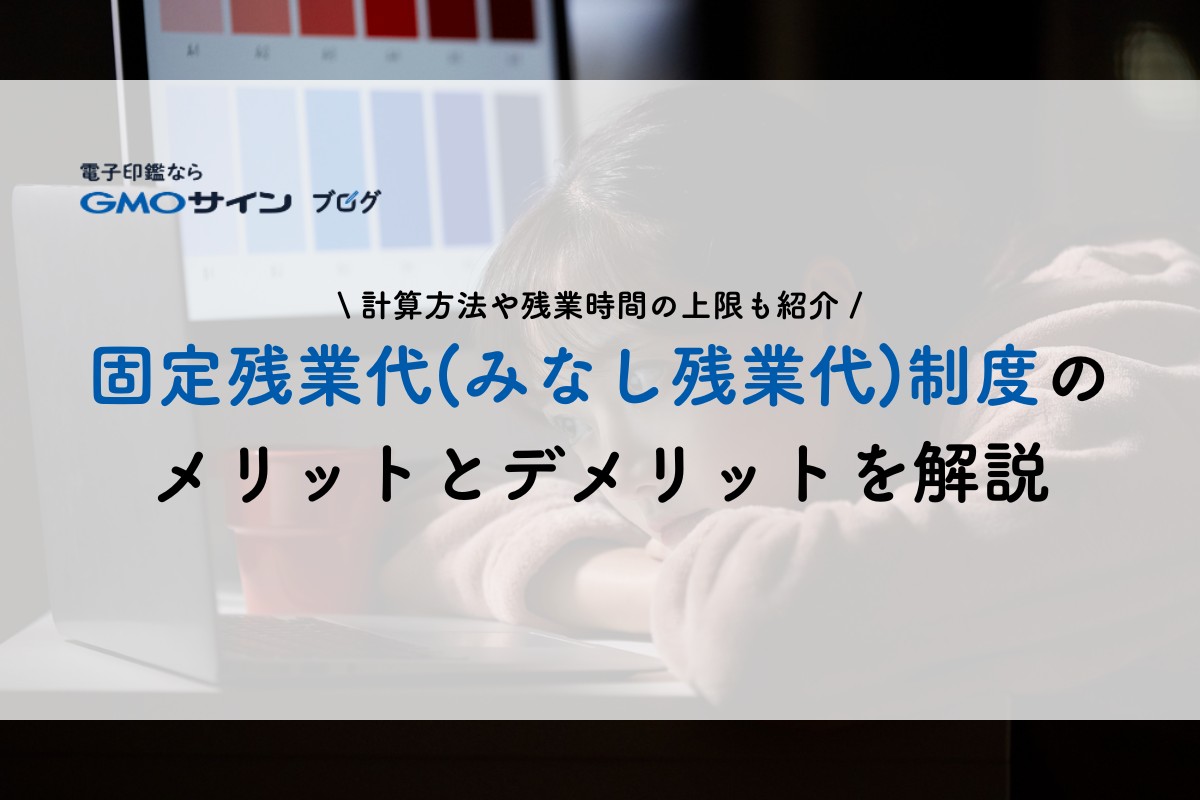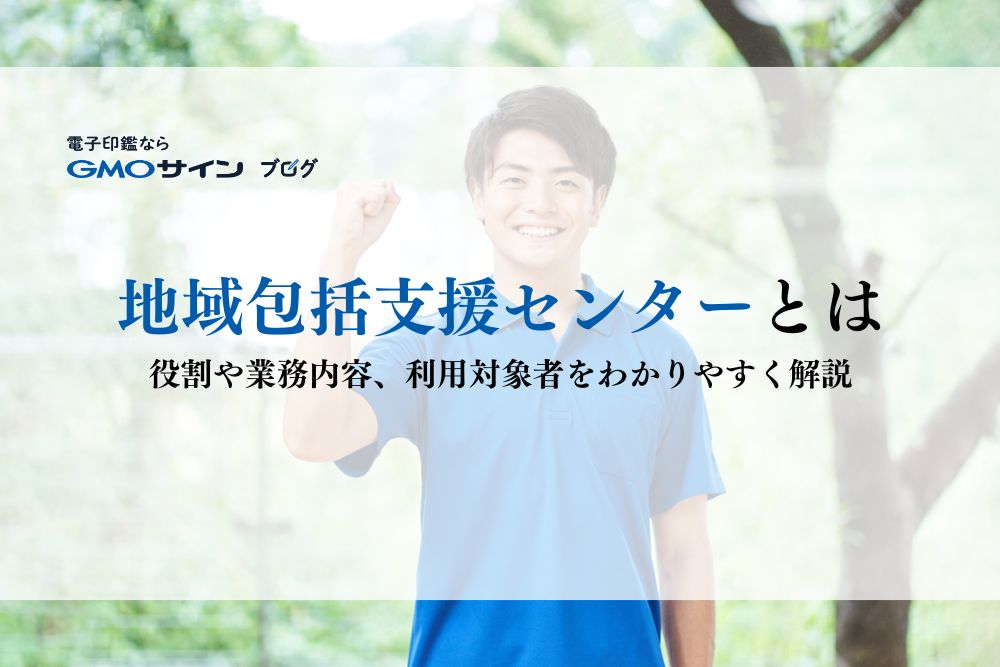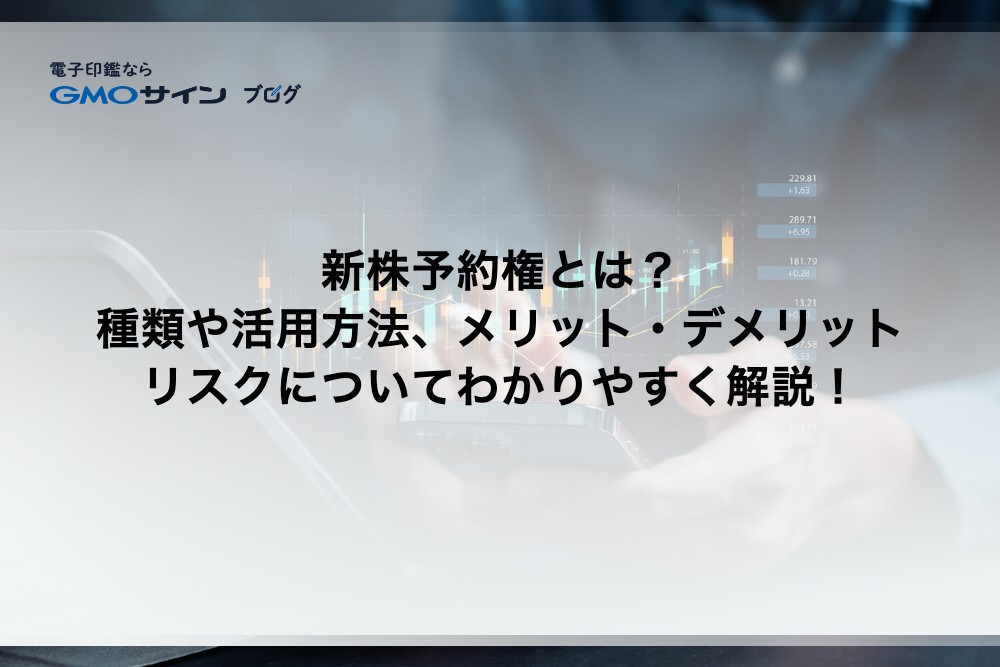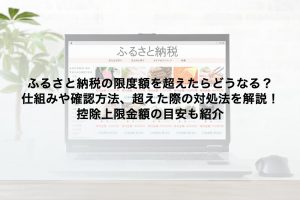\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /
\\ 期間限定キャンペーン実施中 //
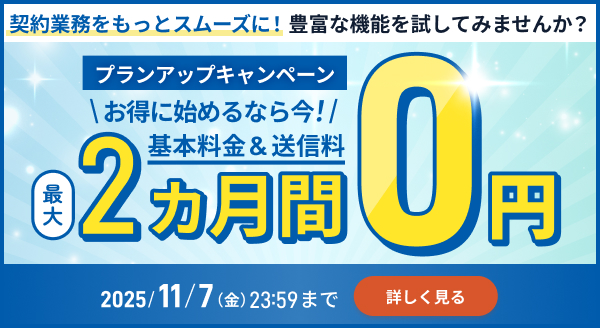
【予告】GMOサイン10周年特別セミナー


就業時間と労働時間は、私たちの働き方に深くかかわる重要な概念です。しかし、これらの違いを正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。これらの時間は、働き方や給与計算、法的な労働環境の理解に直接影響を及ぼすポイントです。
当記事では、就業時間と労働時間の具体的な定義と、それらがどのように計算されるかについて詳しく解説を行っています。ぜひ参考にしてください。
就業時間と労働時間は、どちらも働く時間に関連した概念ですが、意味は異なります。これらの違いを理解するために、まずそれぞれの定義から見ていきましょう。
就業時間は、従業員が勤務地に出勤し、勤務を開始する時間から終了する時間までの総合的な時間を指します。
出勤時にタイムカードを押してから退勤時にタイムカードを押すまでの時間と考えるとわかりやすいでしょう。従って、就業時間には休憩時間も含まれます。
労働時間は、従業員が雇用主の指揮監督下にあり、仕事を行う時間を指します。休憩時間は含まれません。労働基準法においては、一般的に1日8時間、1週40時間を超える労働は法律で制限されています。
第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
出典:労働基準法|e-Gov法令検索
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法の規定では、法定労働時間を超える場合、超過分については時間外労働とみなされ、割増賃金が発生します。22時から翌朝5時までの深夜労働や法定休日の労働も同様です。
また、労働基準法第35条においては、1週につき1日または、4週を通じて4日以上の休日を設けることが義務付けられています。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
出典:労働基準法|e-Gov法令検索
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働時間については、労使間における労働契約や労働協約などにより所定労働時間を定めることが認められています。
就業規則とは、会社における労働条件や職務遂行上の秩序などについて定めた規則のことです。労働基準法第89条に基づき、一定規模以上の事業場では、就業規則の作成が義務付けられています。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
出典:労働基準法|e-Gov法令検索
就業規則には、労働時間や就業時間、休憩時間、休日など、労働者の働く時間に関する規定を含めることが一般的です。これらの規定は、労働基準法や労使間の協定などに基づいて定められます。
具体的には、以下のような項目が就業規則に盛り込まれることが多いです。
一日の勤務開始時間と終了時間、および休憩時間を明記します。就業時間の延長や短縮に関する規定を設ける場合も少なくありません。
従業員が勤務すべき労働時間について明記します。また、時間外労働の手続き、割増賃金など時間外労働についての規定も同様に明記が必要です。
会社における休日や年次有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇など、休日や休暇に関する規定を明記します。
22時から翌5時までの深夜労働や休日労働についての規定を設け、これらに対する割増賃金を明記することがあります。
何が労働時間に含まれるかは、労働法の領域でしばしば議論となっています。以下に、特定の状況における労働時間の考え方についていくつかの例を挙げます。
労働者が仕事を始める前や終えた後に行う一部の準備作業や終了作業は、労働時間に含まれることが多いです。たとえば、工場で作業を行う前に必要な保護具の着用や、飲食店で開店前の準備や閉店後の清掃などが該当します。
ただし、これらの活動が労働時間に含まれるかどうかは、その活動が労働者の主要な業務を可能にするもので、その業務の一部とみなされるかどうかによります。
労働者が働く準備が整えたうえで、使用者の指示を待っている待機時間も労働時間に含まれることがあります。救急医療スタッフが緊急呼び出しを待つ時間や、タクシードライバーが乗客を待つ時間などが該当するでしょう。
ただし、待機時間が労働時間に含まれるかどうかは具体的な状況によります。
労働者が仕事のために移動する時間も労働時間に含まれることがあります。たとえば、営業担当者が顧客訪問のために移動する時間や、出張のための移動時間などが該当します。通勤時間は原則として労働時間には含まれません。
ここまで挙げた例は一般的な原則に過ぎず、具体的な状況や労働協約や就業規則により、適用されるルールは変わる可能性があります。
これらの規定は、労働者と事業主間の関係を明確にし、公正な労働環境を維持するために非常に重要です。
フレックスタイム制は、コアタイム(必須出勤時間)とフレキシブルタイム(出退勤が自由な時間)を設定する制度です。この制度では、労働者はフレキシブルタイム内で自分の働きたい時間を自由に選択できます。そのため、就業時間と労働時間の考え方は従来の働き方と異なることに注意が必要です。
たとえば、フレキシブルタイムが午前7時から午前10時、午後3時から午後8時で、コアタイムが午前10時から午後3時と設定された場合を考えてみましょう。
この場合、就業時間はフレキシブルタイムとコアタイムを合わせた時間、つまり午前7時から午後8時までとなります。一方、労働時間は実際に労働者が働いた時間です。たとえば、労働者が午前8時に出勤し、午後4時に退勤した場合(うち休憩1時間)、その労働時間は7時間となります。
フレックスタイム制では、労働者は自身のライフスタイルに併せて働く時間を調整できるため、ワークライフバランスの向上に寄与します。しかし、この制度を採用する場合、事業主は労働時間の管理を適切に行い、過労や法定労働時間の超過などを防ぐことが必要です。
フレックスタイム制を導入する場合、就業規則にその詳細を明記し、労使協定とともに労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
事業主は就業規則を定める際には、労働基準監督署長への届け出が必要です。また、労働者に対してもこれを周知する義務があります。以下に、就業規則の設定と届け出に関する一般的な手順を示します。
就業規則には、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇など、労働条件と職場の規律に関する事項を含めなければなりません。作成過程においては、従業員の意見を反映させるために彼らと協議することが望ましいです。
10人以上の労働者を常時雇用する事業場では、就業規則の作成または改定について、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数代表の意見を聴かなければなりません。
就業規則が完成したら、事業主はこれを労働基準監督署長に届け出ます。この届け出は、就業規則の設定・変更後すぐに行わなければなりません。届け出には、就業規則と労働者代表の意見聴取に関する書類を添付する必要があります。
事業主は、就業規則を労働者に周知する義務があります。これは、労働者が就業規則の内容を理解し、適切に行動できるようにするためです。周知の方法としては、就業規則を職場の見やすい場所に掲示したり、コピーを配布したりする方法などが存在します。
賃金の計算は、労働者の働いた時間に基づいて行われ、時間外労働や深夜労働に対する割増賃金の計算も含まれます。以下に、いくつかのケースについて具体的な計算方法を示しますが、これは基本的な考え方であり、具体的な計算方法は就業規則や労使間の協定によります。
就業時間が1日9時間(休憩時間1時間含む)であった場合、労働時間は8時間となります。そのうえで、労働者が法定労働時間の8時間を超えて1時間働いた場合、その1時間が時間外労働となります。
この場合には、超過した時間に対して25%で計算した割増賃金の支払いが必要です。
22時から翌1時まで働いた場合には、3時間の深夜労働になります。深夜労働に対しては、25%で計算した割増賃金の支払いが必要です。また、深夜労働が時間外労働にも該当する場合には、両者をあわせた割増率での賃金の支払いが必要となります。
時間外労働の割増率が25%、深夜労働が25%のため、両者が重複する深夜時間外労働に対しては、50%で計算した割増賃金の支払いが必要となるわけです。
法定休日に8時間労働した場合、すべての労働時間が休日労働となります。休日労働に対する割増賃金は基本賃金の35%となります。休日労働と時間外労働は重複しませんが、深夜労働とは重複します。
そのため、深夜休日労働の場合には、合計である60%で計算した割増賃金の支払いが必要です。
このケースでは、時間外労働、深夜労働、休日労働の複合的な要素を含むことがあります。たとえば、休前日の深夜時間外労働と休日の深夜労働を考えてみましょう。土曜日の22時から翌日の日曜日の2時までの4時間勤務したとします(土曜日が休前日で日曜日を法定休日とします)。
この場合、土曜日の22時から24時までの2時間は時間外労働であり、かつ深夜労働となります。従って、基本賃金に対して時間外労働と深夜労働の割増賃金がそれぞれ発生します。
具体的には、時間外労働に対する割増賃金(25%)と深夜労働に対する割増賃金(25%)を合算した基本賃金の50%が割増賃金です。日曜日の0時から2時までの2時間は、休日労働であり、かつ深夜労働となります。この場合には、すでに述べたように基本賃金に対して休日労働と深夜労働の割増賃金がそれぞれ発生する点に注意です。
具体的には、休日労働に対する割増賃金(35%)と深夜労働に対する割増賃金(25%)を合算した基本賃金の60%が割増賃金となります。
就業時間とは、従業員が会社の指示のもとで労働する時間のことを指します。一般的には「始業時刻から終業時刻までの時間」として定義されており、労働基準法によって1日8時間、週40時間を超えないように定められています。この時間には休憩時間は含まれません。
就業時間が9時から17時と設定されている場合、単純計算では8時間となりますが、実際の勤務時間はこれより短くなります。なぜなら、労働基準法では、6時間を超える労働に対して少なくとも45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えることが義務付けられているからです。
したがって、9時から17時までの就業時間の場合、通常1時間の休憩時間が設けられ、実質的な労働時間は7時間となることが一般的です。
就業時間が「会社が定めた勤務すべき時間帯」を表すのに対し、就労時間は「実際に労働した時間」を指します。
たとえば、就業時間が9時から17時までと定められていても、残業で19時まで働いた場合、就労時間は実働10時間(休憩除く)となるのです。
就業時間と労働時間の違いと、それぞれの計算方法を解説してきました。これらの概念は、労働者の権利を守り、労働環境を改善するために不可欠なものです。
また、事業主はこれらの時間を適切に管理し、法令遵守を図ることが求められます。具体的な状況や法的な疑問がある場合は、社労士など労働関係法令の専門家に相談しましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。