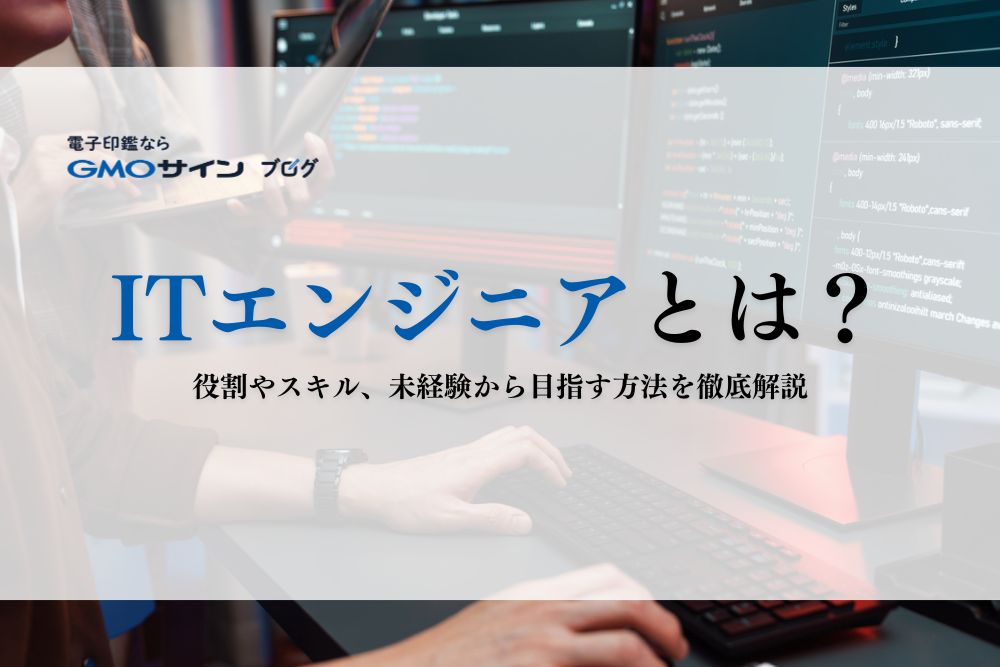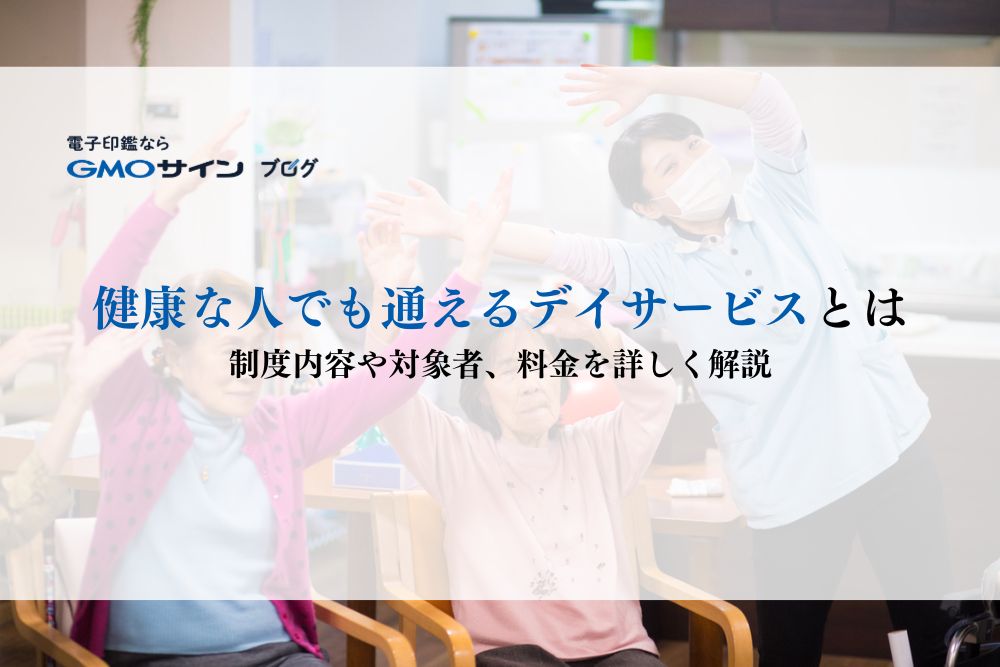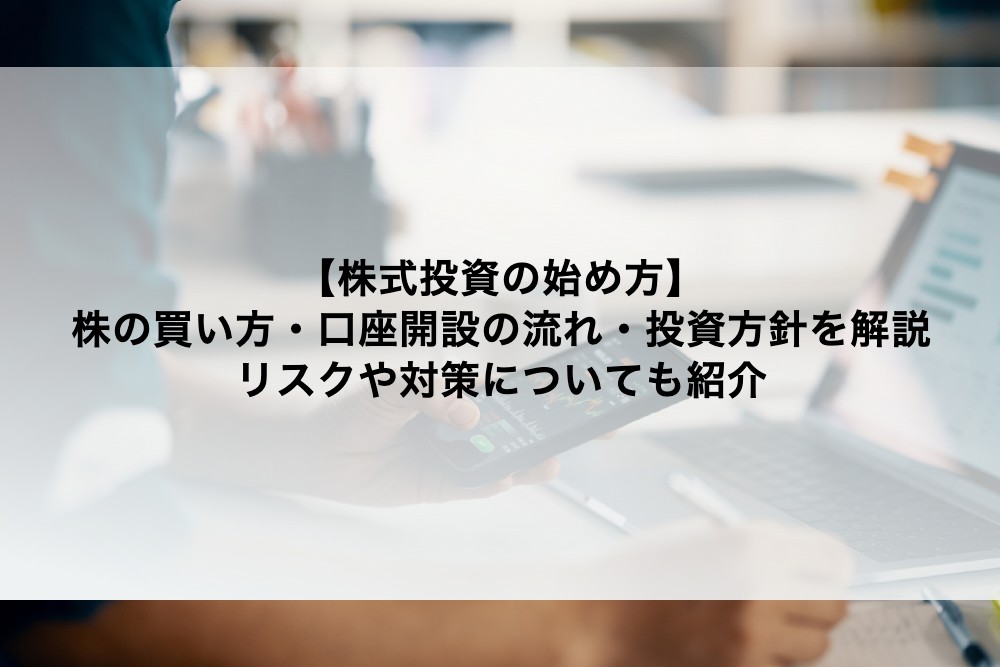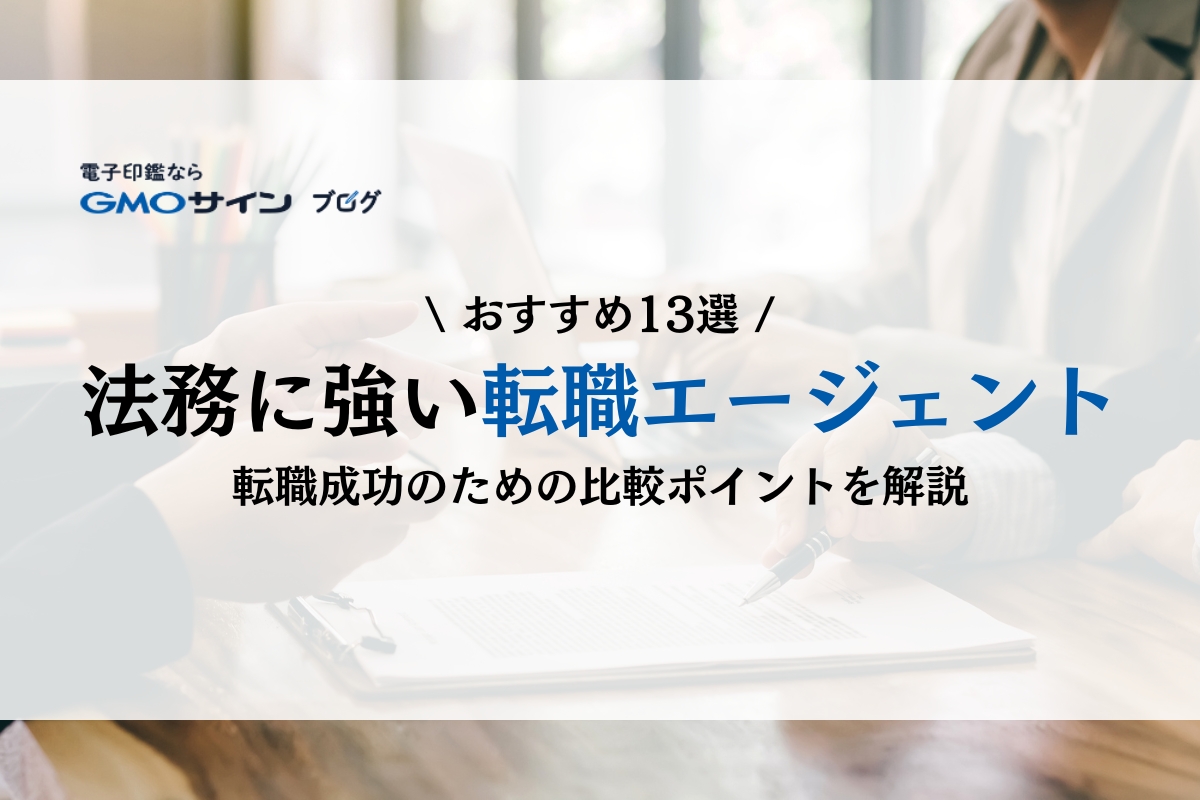製造物責任法とは通称PL法と呼ばれており、製造物の欠陥から消費者の身体や財産などに損害が生じた場合において、事業者に対して賠償を求めるための法律となっています。製造物を作る事業者にとっては重要な法律ですが、製造業者以外にも対象となる事業者が存在します。
そこで本記事では、製造物責任法の概要や適用されるための要件、対象となる事業者について詳しく解説します。
製造物責任法(PL法)とは
製造物責任法とは、Product(製造物)とLiability(責任)から通称「PL法」と呼ばれる法律であり、製造物の欠陥によって身体や財産などに損害が生じた場合において、事業者に賠償を求めることを定めています。
通常、損害賠償請求する場合には、損害の原因となった者の有責性や過失などを証明しなければなりません。
製造物責任法が適用されるための要件
製造物責任法では、第3条で事業者に損害賠償するための要件として以下のように定めています。
(製造物責任)
第三条
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(参考:e-Gov法令検索)
この条文から、製造物責任法を適用するための要件として以下の2つが求められています。
- 製造物に該当すること
- 欠陥が認められること
それぞれの要件について詳しく解説します。
製造物に該当すること
製造物責任法第2条第1項では、製造物とは「製造又は加工された動産」と規定しています。通説によって具体化すると、製造物は以下の3つの要素を満たすものだと考えられています。
有体物である
有体物とは、実際に触れられる実体があるものを指します。そのため、電気やプログラム、サービスなどは製造物責任法の対象となりません。
製造または加工されている
製造とは、製品の設計段階から完成するまでの行為全般のことです。また加工とは、動産の本質を維持しつつ、手を加えることで新しい価値を付与することとされています。
動産である
動産とは、パソコンや電化製品など手で動かせるようなものを指します。
欠陥が認められること
製造物責任法第2条第2項では、欠陥とは「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と規定しています。具体的には、以下の3つの類型に分かれます。
設計上の欠陥
設計段階で安全性を欠いていたことから、製造物に生じた欠陥
製造上の欠陥
製造過程におけるミスや材料の取り違えなどによって、仕様通りに作られなかったことから生じた欠陥
指示・警告上の欠陥
製造物を使用する上でリスクを回避するために必要な情報を与えなかったことから、安全性を欠いてしまうこと
製造物責任法によって責任を負う者とは
製造物責任法が適用されて賠償責任を負う者としては、製造物を作った事業者が挙げられますが、ほかにも以下のような者が対象となりえます。
輸入業者
海外の企業が作った製造物で損害が発生した場合には、欠陥品を国内に持ち込んだことから輸入業者は責任を負うことになります。
表示製造業者
実際には作っていなくても、製造業者として企業名などを表示した表示製造業者も責任を負います。たとえば、製造物に自社のブランドを表示した事業者などが対象です。
免責事由
製造物責任法第4条では、製造物に欠陥があった場合でも製造物責任が否定される免責事由として、以下の2つが定められています。
- 開発危険の抗弁
- 部品製造業者の抗弁
それぞれ詳しく解説します。
開発危険の抗弁
開発危険の抗弁とは以下の仕組みを指します。
製品の欠陥について、会社が製品を引き渡した時点の科学や技術の知識ではその欠陥を認識できなかった場合に、製造物責任が免除される。
つまり、当時の科学レベルでは予測できなかった問題については、会社は責任を負わなくてよいということです。
しかし、この抗弁における「科学または技術に関する知見」とは世界最先端レベルを意味しており、また立証責任は製造者にありますので、この抗弁で免責されるケースは現実的にはほぼ不可能といえます。
部品製造業者の抗弁
部品製造業者の抗弁は以下のような仕組みのことです。
部品に欠陥があっても、その欠陥が完成品メーカーの設計や指示に従った結果として生じたものであり、かつ部品メーカーに過失がなかったことを証明できれば、部品メーカーは責任を免れることができる。
つまり、指示通りに作っただけで落ち度がなかった場合は責任を問われません。
実際には製造物に使っている原材料や部品の製造業者は下請けなどであるケースが多く、基本的に完成した製造物を作った事業者の指示で納品しています。
また納入する原材料や部品がどのように使われているかは、守秘義務などの理由から知らされていない場合もあります。このような理由から、この抗弁権が認められているのです。
製造物責任法への具体的な対策
製造物責任法では、製造物に欠陥が生じたことを立証されるだけで、事業者は責任を負うことになります。
そこで、事業主ができる具体的な対策をご紹介します。
製造過程を随時チェックする
製造ラインが完成して生産体制が安定してきたころは、設備が新しく材料も問題なく運ばれているため、スムーズに製造物を生産できているでしょう。しかし、時間の経過につれて設備が劣化したり材料の種類が変わったりするなどの理由から、生産体制に変化が生じる場合があります。
このような変化に対応するためには、製造ラインに支障が生じていないか随時チェックする必要があります。製造物には欠陥を一切生じさせてはいけませんので、些細な点でも必ず確認しましょう。
欠陥発生時の対応を周知しておく
どれだけ気をつけていても、製造物に欠陥が生じる事態は考えられます。そのような場合に備えて、すべての従業員に対応の研修やマニュアルの配布などを行うとよいでしょう。
実際に製造物に欠陥が見られた場合には、即座に回収したりメディアへの対策を講じたりするケースが多いです。できれば専門の部署を作っておき、万が一の事態に備えておきましょう。
説明書に注意喚起などを記載する
製造物には、使い方などを記載した説明書が添付されています。説明書には適切な使用法だけでなく、誤った使い方に対する注意喚起や警告文などを記載しておきましょう。
製造物責任法に関するよくある質問
製造物責任法が対象外のものは何?
製造物責任法は、会社などが作ったり輸入したりして売っている製品が対象です。無料でもらった試供品や、個人が趣味で作った物は対象外です。
また、お店で普通に売っているだけの人や、設計だけした人も基本的には対象になりません。製品そのものだけが壊れた場合も対象外です。
製造物責任法のトラブルにはどう対応すればよい?
製品によって誰かが被害を受けてしまったら、被害拡大防止のため、被害者の救済を最優先にします。次に、何が起きたのか素早く事実確認と原因究明を行いましょう。
また、製品の不具合の情報収集と分析の体制を整え、必要に応じて製品回収(リコール)や修理などの対策を実施します。苦情対応の手引きの作成や関係者との情報共有も大切です。
製造物責任法の時効は何年?
製造物責任法では、損害賠償を求める場合、被害にあったことと相手を知ってから3年以内(けがや死亡の場合は5年以内)に請求しなければなりません。
また、製品が引き渡されてから10年が経つと、基本的に請求できなくなります。
(参考:製造物責任法第5条|e-Gov法令検索)
事業者は製造物責任法を意識する必要があります
製造物責任法では、製造物を作る事業者や関連業者に対する責任が厳格に定められています。そのため、あらゆる事業者は製造物責任法を意識した社内体制の構築や、欠陥発生時の対応の共有などが求められているのです。