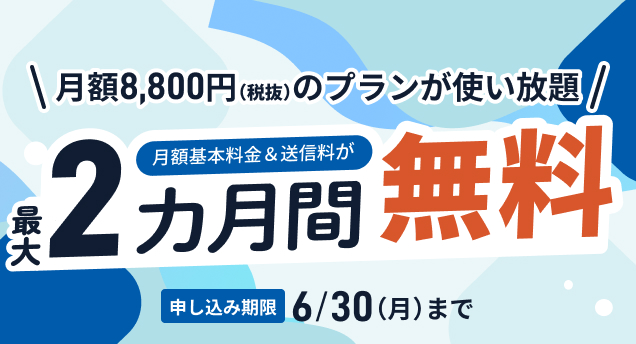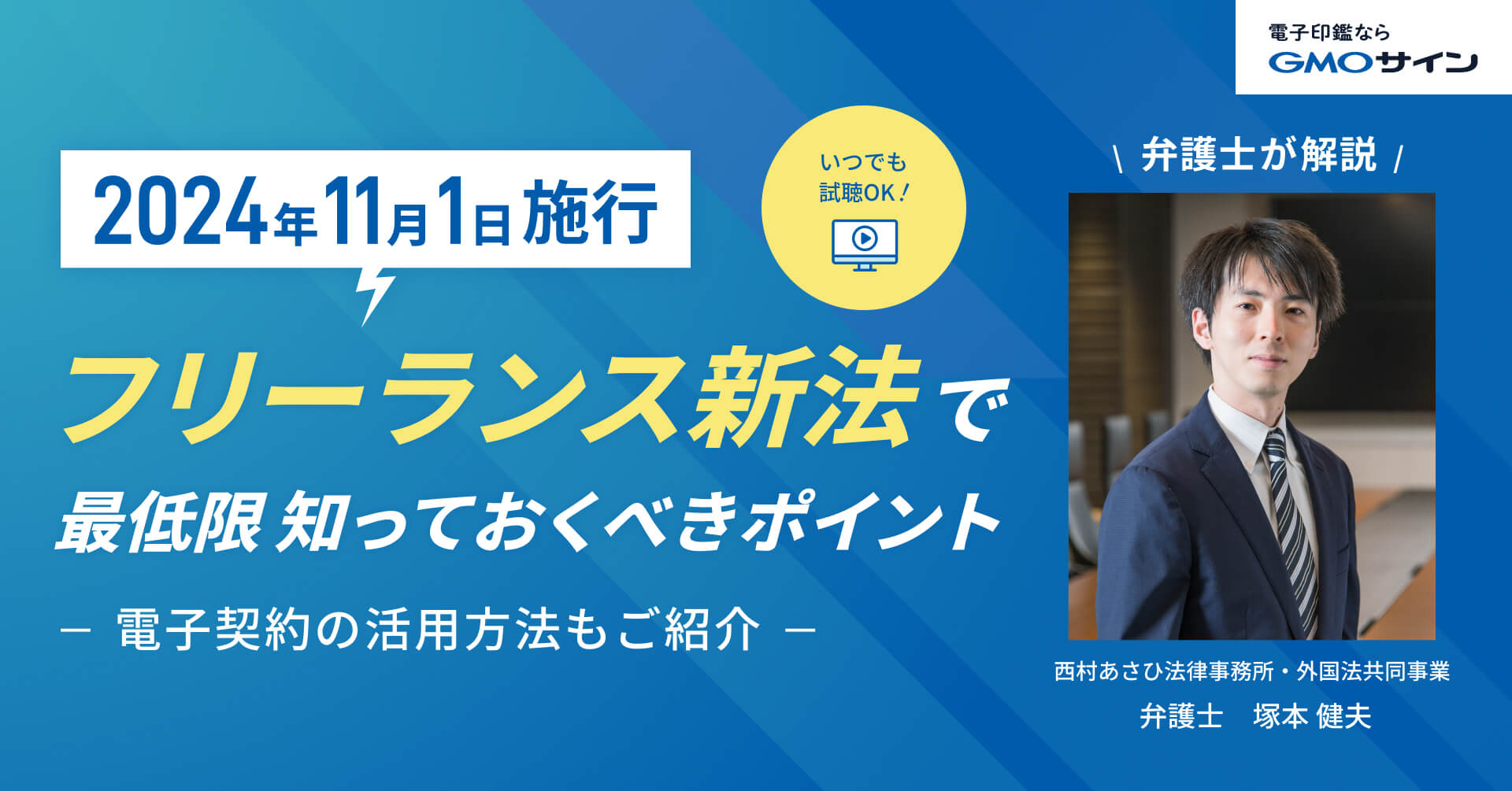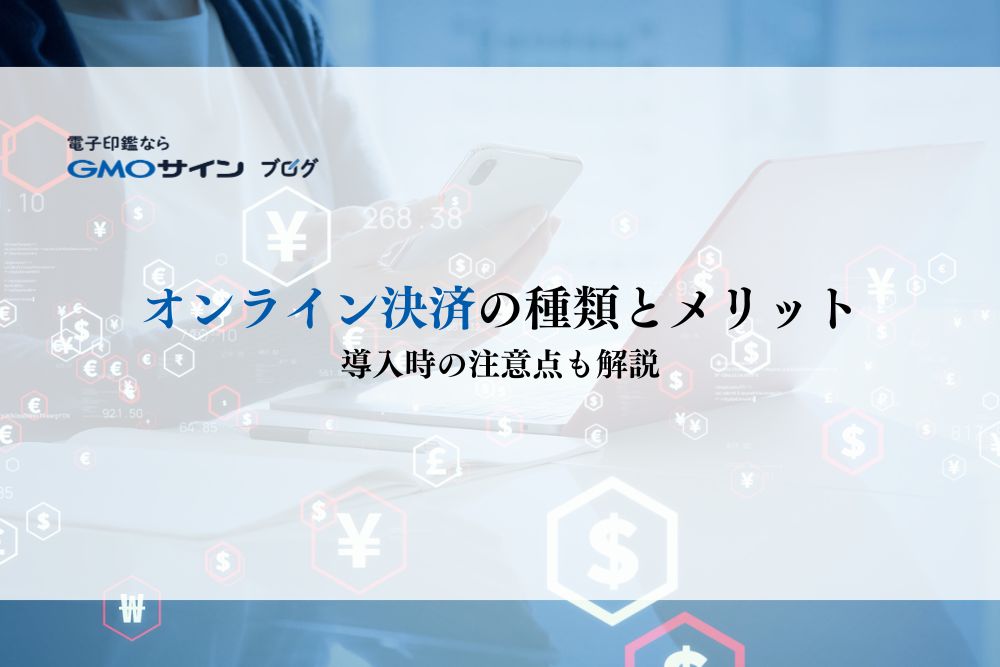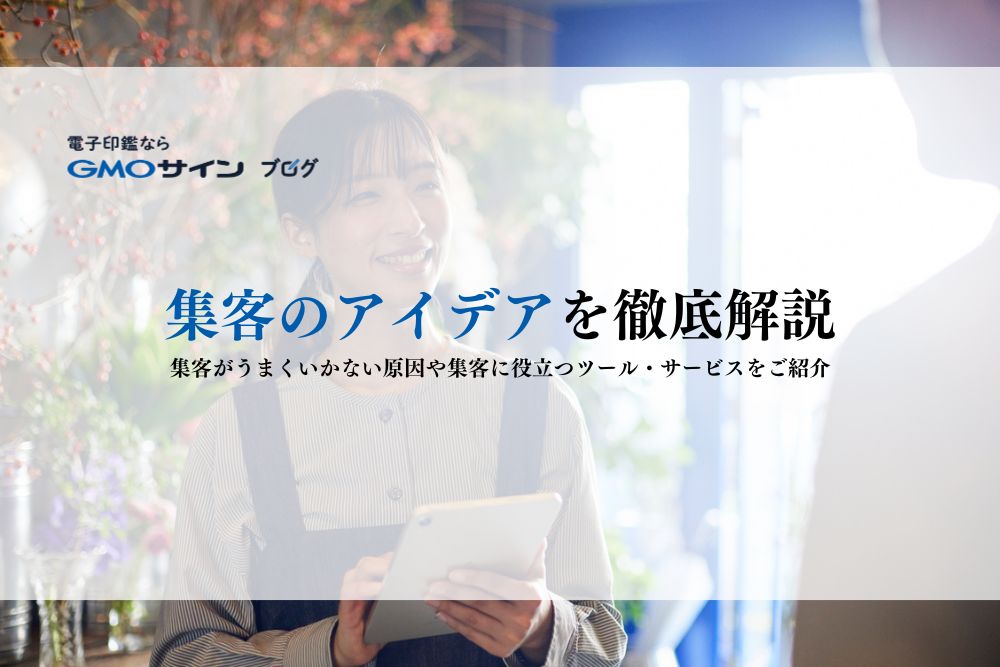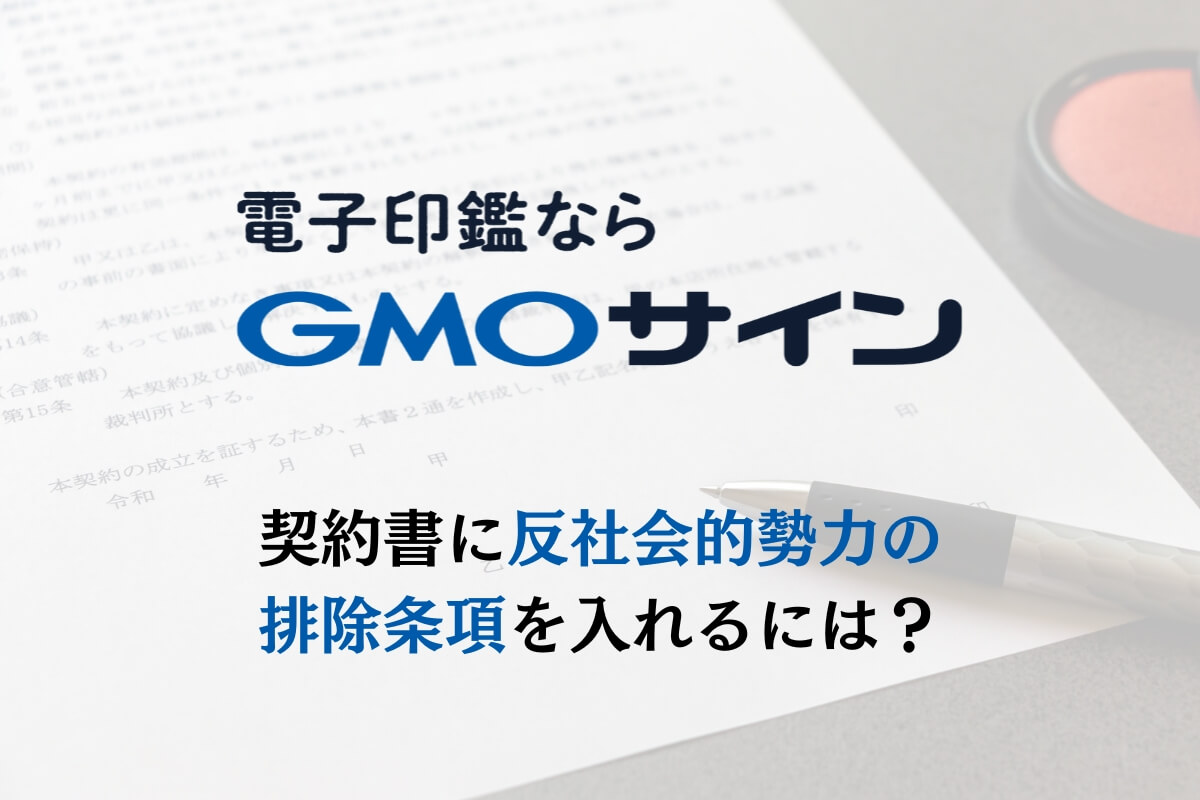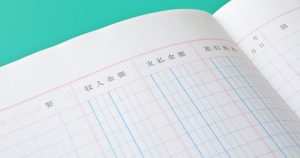「下請」(したうけ)とは、引き受けた仕事をさらに別のものが引き受けて行うこと指す言葉です。たとえば、自社製品の部品の製造委託や自社で請け負った仕事を外部の会社に委託する場合です。このような取引を公正に行うために設けられた法律が「下請法」で、委託側である親事業者には多くの義務や禁止行為が定められています。
\ フリーランス新法について弁護士の塚本健夫先生が詳しく解説 /
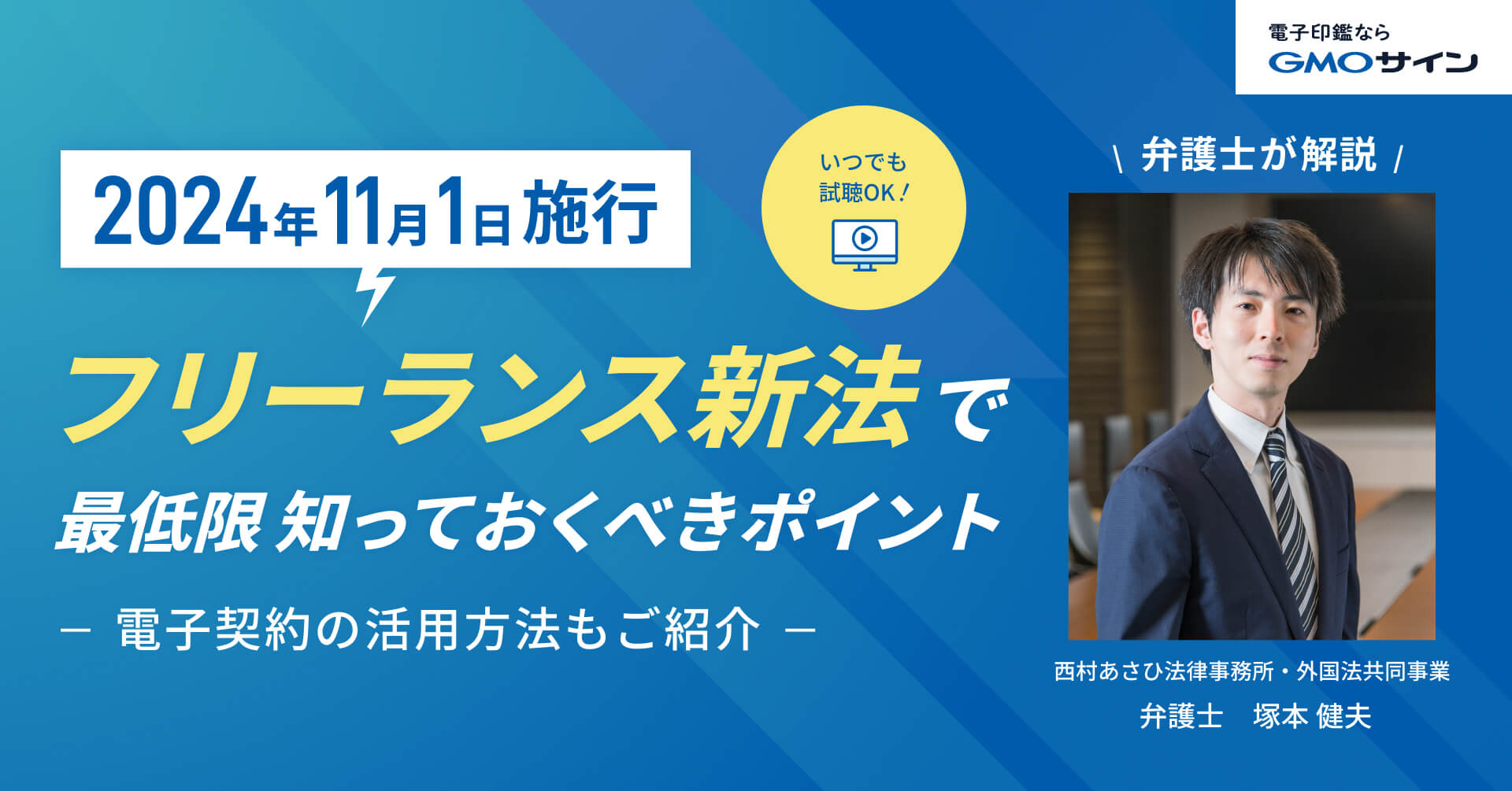
2024年11月1日から施行の新法について、制度背景や具体的な内容をポイントにまとめてわかりやすく解説します。類似の「独禁法」や「下請法」との違いと法対応への留意点、各義務項目と通知の仕方についてもご紹介。さらに電子契約を利用することでかなう契約締結と業務効率化についてもご案内いたします。
- フリーランスに業務を委託する事業者
- フリーランスとして働いている方
- 下請法や独占禁止法との違いを知りたい方
※本動画は2024年11月7日に開催されたセミナーのアーカイブ動画です。予めご了承ください。
目次
下請法とは
「下請法」(したうけほう)は、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律で、正規な名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。下請法における「下請」とは、規模が大きな企業が規模の小さな企業や個人に仕事の全部、または一部を委託することを意味します。仕事を発注する事業者を「親事業者」、仕事を引き受ける事業者を下請事業者と呼びますが、発注側である親事業者と受注側である下請事業者との関係性は、親会社と子会社の関係に似て下請事業者が弱い立場になりがちです。そのため下請法は、中小企業や個人事業主を守るために存在する法律といえます。
下請法に関連が深い法律に「独占禁止法」(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)があります。下請法は独占禁止法を補完する法律として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制するために作られた法律です。
下請法の対象となる事業者
下請法に対象となるのは、取引の内容と、親事業者と下請事業者のそれぞれの資本金によって分かれて定められています。
対象となる4つの取引
スクロールできます
| 製造委託 | 事業者が業務として物品の販売を行っている場合、物品もしくはその半製品、部品、附属品等の製造を、他の事業者に委託することが「製造委託」です。
たとえば、自動車メーカーが部品メーカーに発注する場合などが当てはまります。 |
| 情報成果物作成委託 | 事業者が業務として情報成果物の提供を行っている場合に、情報成果物の作成行為の全部または一部をほかの事業者に委託することが「情報成果物作成委託」です。
ソフトウェアなどのプログラム開発や、設計図やデザイン、文章作成、撮影などが当てはまります。 |
| 役務提供委託(サービス提供委託) | 事業者が事業として行っている顧客へのサービス提供の全部、または一部をほかの事業者に委託することが「役務提供委託」です。
たとえば、ビルメンテナンス業者が依頼された業務を外部に委託する場合が当てはまります。 |
| 修理委託 | 事業者が事業として行っている修理業務の全部、または一部をほかの事業者に委託することを「修理委託」といいます。
たとえば、自動車ディーラーが車の修理を外部に委託する場合が当てはまります。 |
このように、下請法の対象は、すでに存在している商品や市場で販売されていて誰しもが買うことのできる商品を購入するといった取引ではなく、親事業者が事業として行っているものの製造などを委託したり、親事業者が受注した業務を外部に委託したりといった取引です。たとえば、既存製品をそのまま購入した場合は対象外ですが、既存製品のラベルを変更したり、サイズを変更したりという場合は対象となります。(なお、建設業法に規定されている建設業を営む事業者が請け負う建設工事も製造委託ですが、下請法でなく建設業法の規制を受けるため、下請法の適用外となります。)
下請法の対象となる取引の例
- 自動車メーカーが自動車部品を部品メーカーに発注する。
- 出版社が雑誌に載せる原稿の執筆を依頼する。
- ビルメンテナンス業者が請け負った業務を外部に委託する。
- システム会社が請け負ったプログラム開発の一部を外部に委託する。
下請法の対象とならない取引の例
- 自社のWEBサイトのデザインや文言執筆を外部に委託する。
- 外部から受注した機械製造を行うため、規格品のボルトやネジを購入する。
- 弁護士や会計士への業務依頼
- 修理会社が自社で使用している物品の修理を外注する。
下請法の対象となる取引の種類と、資本金の関係
下請法は、先に挙げた4つの取引を2つのグループに分け、それぞれ親事業者と下請事業者の資本金によって、下請法が適用されるかどうかを決めています(資本金区分)。
1.物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
該当する取引が「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」のうちプログラム作成に関係する取引、「役務提供委託」のうち運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係る取引がこれに該当します。これらの取引を行う場合に、親事業者と下請事業者の資本金が以下の場合、下請法の対象となります。
- 資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人事業者に委託するとき
- 資本金1000万円超~3億円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人または個人事業者に委託するとき
2.情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
該当する取引が「情報成果物作成委託」(プログラムの作成を除く)、「役務提供委託」(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合に該当します。
- 資本金5000万円超の法人が、資本金5000万円以下の法人または個人事業者に委託するとき
- 資本金1000万円超~5000万円以下の法人が、資本金1000万円以下の法人または個人事業者に委託するとき
資本金区分について、まとめると次のようになります。
スクロールできます
| 親事業者 | 下請事業者 |
製造委託
| 3億円超の法人 | 3億円以下の法人・個人 |
修理委託
プログラム作成運送・倉庫における保管情報処理 | 1000万円超〜3億円以下 | 1000万円以下の法人・個人 |
スクロールできます
| 親事業者 | 下請事業者 |
情報成果物作成委託
(プログラム作成を除く)
| 5000万円超の法人 | 5000万円以下の法人・個人 |
役務提供委託
(運送・倉庫における保管・情報処理を除く) | 1000万円超〜5000万円以下 | 1000万円以下の法人・個人 |
注)情報処理とは、電子計算機を用いて、計算、検索等の作業を行うことで、プログラムの作成に該当しないものをいいます。例えば、受託計算サービス、情報処理システムの運用(データ入出力、稼動管理、障害管 理、資源管理、セキュリティ管理等)などです。
情報サービス・ソフトウェア産業における 下請適正取引等の推進のためのガイドライン(経済産業省)
下請法で定められた親事業者の義務
下請法では親事業者に対して4つの義務が課しています。それぞれ下請事業者を守るための大切な義務です。
スクロールできます
| 書面の交付義務 | 親事業者が下請事業者に発注する際、「3条書面」と呼ばれる書類を下請事業者に対して交付する義務があります。3条書面に記載しなくてはならない内容も細かく定められているため、注意が必要です。 |
|---|
| 支払期日を定める義務 | 親事業者は、下請事業者との合意のもと、下請代金の支払期日を決定します。支払期日は「物品などを受領した日」から最長60日(2ヶ月)以内で、できる限り短い期間内に定める必要があります。また、起算日は物品の受領、すなわち下請業者が納品した日から数えます。親事業者の検収や検査、締め日は関係ありません。 |
|---|
| 書類の作成・保存義務 | 親事業者は、下請事業者に対して委託した業務内容や下請代金の額などを記載した書類(5条書面)を作成し、2年間保存する必要があります。 |
|---|
| 遅延利息の支払義務 | 親事業者が下請事業者に対して、支払期限までに支払わなかった場合、遅延利息を支払う義務があります。物品を受領した日から起算して60日を経過した日から、実際に支払われる日までの期間について、その日数に応じて未払い金額に年利14.6%を乗じた額の遅延利息を支払います。 |
|---|
下請法で定められた親事業者の禁止行為
親事業者には以下の禁止事項が課せられています。これは、仮に下請事業者の了解を得ていたとしても、親事業者に違法性の認識がなかったとしても、これらの禁止事項に該当する場合は下請法違反となりまるので注意が必要です。
スクロールできます
| 1.受領拒否の禁止 | 親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず納品物の受領を拒むと下請法違反となります。 |
|---|
| 2.下請代金の支払い遅延の禁止 | 物品などを受領した日から60日以内に定めた支払期限までに下請代金を残額支払わない場合、下請法違反となります。受領日から起算するため、親事業者の検収・検査の有無は関係ありません。
なお、受領日から60日後に振り込もうとした場合、その当日が銀行の休業日になる場合があります。この場合に限り、銀行の翌営業日まで支払いを順延できますが、その最長期間は2日以内と定められています。そのため、年末年始やゴールデンウィーク等のような連休が重なるタイミングでうっかり支払期限を過ぎてしまい下請法違反となる場合があるため、注意が必要です。 |
|---|
| 3.下請代金の減額 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金を減額すると、下請法違反となります。発注後に消費税額が上がったから、他の部品の価格が高騰したから、競合他社が大安売りを始めたからというような理由で下請代金の値引きを要請することは下請法違反の行為です。 |
|---|
| 4.返品の禁止 | 納品された物品に不具合があるなど、明らかに下請事業者に責任がある場合、受領後速やかに返品することは問題ありませんが、それ以外の場合、受領後の返品は下請法違反となります。 |
|---|
| 5.買いたたきの禁止 | 親事業者が下請代金の額を決定する場合、一般的に支払われる額よりも著しく低い額を定めることは、「買いたたき」として下請法違反となります。 |
|---|
| 6.購入・利用制限の禁止 | 正当な理由なく、親事業者の指定する製品や材料を下請事業者に購入させたり、サービスに加入させたりすることは、下請法違反となります。 |
|---|
| 7.報復措置の禁止 | 下請事業者が、親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会、または中小企業庁に知らせたことを理由に、取引量を減らしたり、停止したり、そのほか不利益な扱いをしたりすると下請法違反となります。 |
|---|
| 8.有償支給原材料等、対価の早期決済禁止 | 下請事業者に委託した業務について、親事業者が下請事業者に必要な材料や部品などを有償提供している場合、下請事業者に責任がないにもかかわらず、材料費などの支払日を下請業務の支払期日よりも早い時期に支払わせることは、下請法違反となります。 |
|---|
| 9.割引困難な手形の交付の禁止 | 下請事業者に対して下請代金を手形で支払う場合、支払期限までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形(繊維製品においては90日、その他については120日を超える手形)を交付すると、下請法違反となります。 |
|---|
| 10.不当な経済上の利益提供要請の禁止 | 下請事業者に対して、自己の利益のために金銭や役務、その他経済上の利益を提供させ、下請事業者の利益を不当に害すると、下請法違反となります。 |
|---|
| 11.不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注の取り消しや発注内容の変更、または受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すると、下請法違反となります。 |
|---|
下請法に違反した場合の罰則
親事業者が下請法に違反した場合「勧告」「指導」「罰金」といった対応が取られます。勧告を受けた場合、公正取引委員会のWEBサイト上で「下請法勧告一覧」として企業名や違反内容、勧告概要などが公表され、社会的信頼の失墜に繫がります。また、親事業者の義務に関する違反などでは50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
下請法については、公正取引委員会や中小企業庁が力を入れて取り締まりを行っています。自社が親事業者となる取引がないか、ある場合は下請法を遵守しているか、定期的に確認を行いましょう。また、自社が下請事業者の場合で、親事業者から下請法に違反する行為を受けたときは、声を上げることも重要です。中小企業庁から定期的に送付されている「下請事業者との取引に関する調査」での申告や、中小企業庁が行なっている「下請かけこみ寺」に相談するとよいでしょう。
下請法は下請事業者を守るための法律、親事業者は徹底した遵守を
下請法、はいわゆる下請取引において、立場の弱い下請事業者を守るための法律です。親事業者に対して義務や禁止事項を細かく規定されており、これを遵守しなければ、たとえ無自覚で違反行為と認識が無かったとしても、違法な行為として罰則が科されます。
もし、下請事業者をないがしろにしたという違反事実を公開された場合、大きな信頼失墜に直結します。自社が親事業者となる取引があるかどうか、下請法に違反していないか、これまでの下請取引をきちんと確認し、問題があれば早急に改善しましょう。
\ フリーランス新法について弁護士の塚本健夫先生が詳しく解説 /
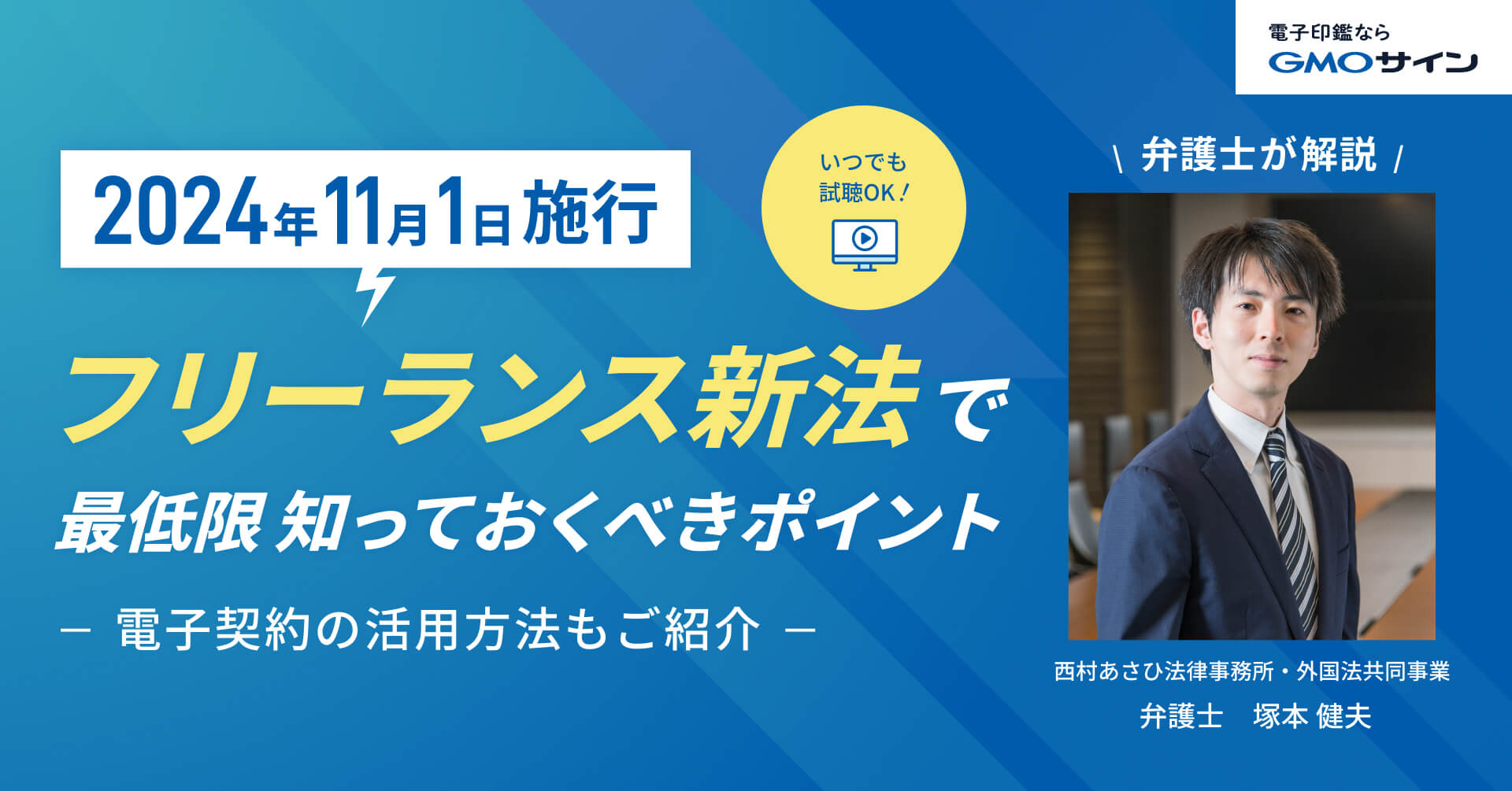
2024年11月1日から施行の新法について、制度背景や具体的な内容をポイントにまとめてわかりやすく解説します。類似の「独禁法」や「下請法」との違いと法対応への留意点、各義務項目と通知の仕方についてもご紹介。さらに電子契約を利用することでかなう契約締結と業務効率化についてもご案内いたします。
- フリーランスに業務を委託する事業者
- フリーランスとして働いている方
- 下請法や独占禁止法との違いを知りたい方
※本動画は2024年11月7日に開催されたセミナーのアーカイブ動画です。予めご了承ください。