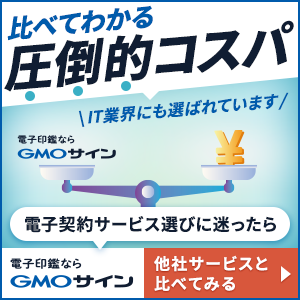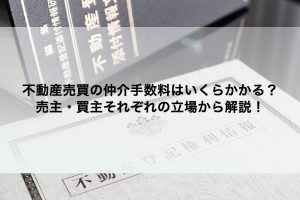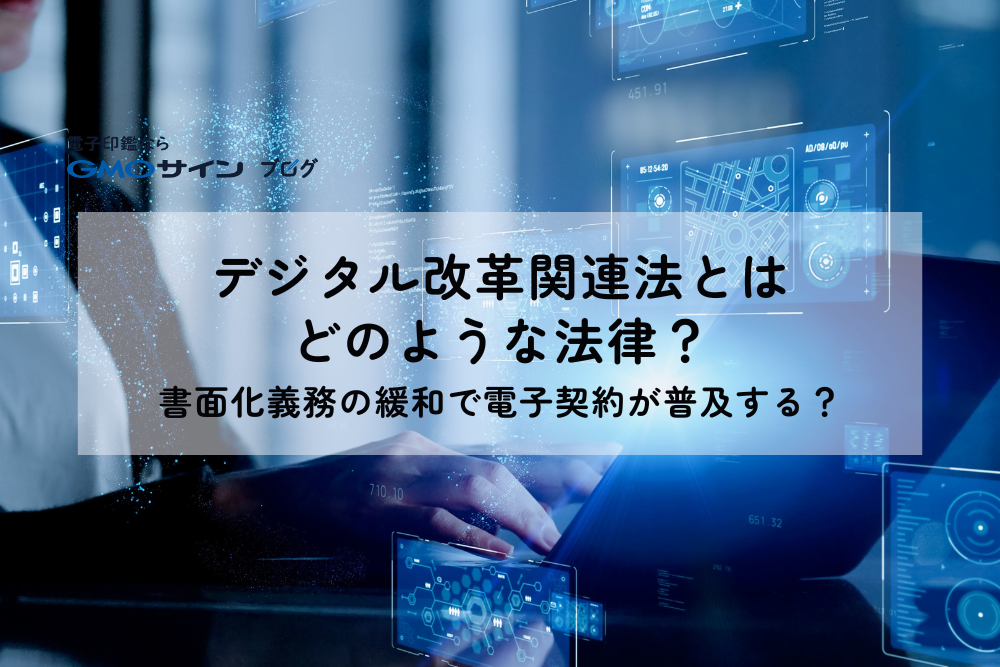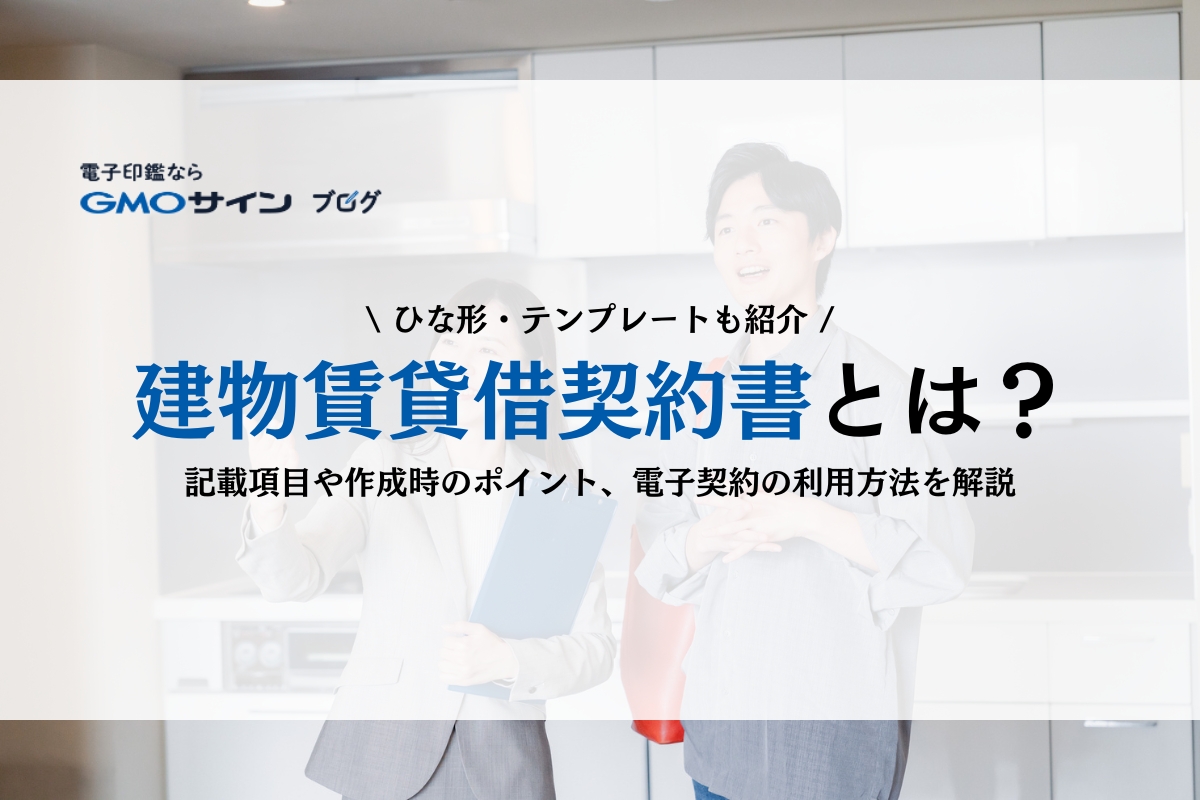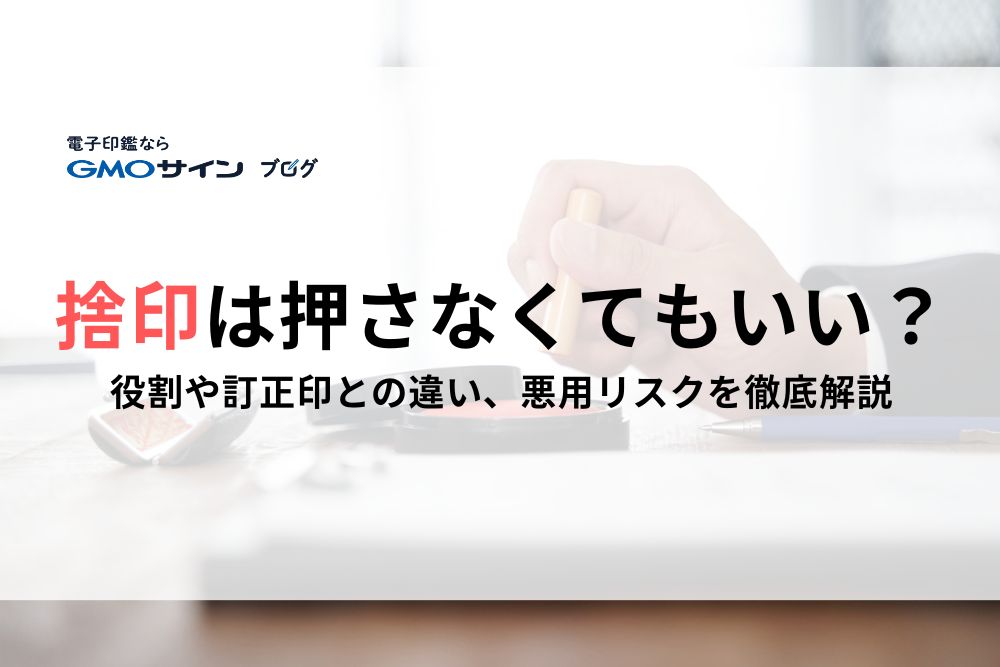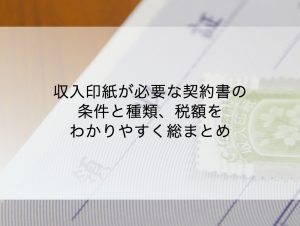少しでも家計を楽にしたい、自分の学費を稼ぎたいなどの理由で扶養されている方がパートを掛け持ちする場合、社会保険や税金がどうなるかご存知でしょうか?
本記事では、パートを掛け持ちした場合の社会保険や税金はどうなるのか、パートを掛け持ちすることのメリットやデメリットとあわせて紹介します。現在、収入が少なくパートの掛け持ちを検討されている方はぜひ、参考にしてください。
パートの掛け持ちは可能
パートの掛け持ちは、基本的には可能です。ただし、就業規則に副業や掛け持ちを禁止する規定がある場合は、その限りではありません。また、就業規則で禁止されていない場合でも、掛け持ちをしたい場合は双方の就業先に対して、ほかでも働くことを話しておいた方がよいでしょう。
後述する社会保険、税金関連の出勤調整について相談もしやすくなり、後のトラブル防止にもつながります。

扶養とは?
扶養とは、1人で生計を立てることが難しい者(被扶養者)に対し、おもに収入を得ている者(扶養者)が経済的な支援をすることを意味します。
たとえば、世帯のなかで夫が扶養者として生活費を稼ぐ場合は、妻と親族が被扶養者となります。反対に、妻が扶養者として生活費を稼ぐ場合は、夫と親族が被扶養者です。パートを掛け持ちすることで一定の収入を超えてしまうと、世帯の扶養から外れることになります。
具体的には次の4つの要件すべてに該当する者を指します。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない。または白色申告者の事業専従者ではない
また、上記とは別に、世帯の納税者に次の要件をすべて満たす配偶者がいる場合、その配偶者は被扶養者(扶養される者)となります。
- 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は除く)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が58万円以下(令和6年分以前は48万円以下)である(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない。または白色申告者の事業専従者でない
(参考:国税庁 No.1180 扶養控除、No.1191 配偶者控除)
【収入別】扶養から外れた場合の社会保険や税金
被扶養者は、パートの掛け持ちにより一定の収入を得ると扶養から外れます。ただ、扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、扶養を外れる収入はそれぞれ異なっています。
ここでは、実際にいくら収入を得ると扶養から外れるのかについて解説します。なお、以下で説明する年収は、130万円の壁以外交通費は含みません。
93万円の壁
被扶養者の年収が93万円を超えると、住民税の支払いが発生する可能性があります。住民税における所得割・均等割という2種類の税金のうち、一定以上の所得がある人が負担する均等割が適用されるためです。
ただし、年収から給与所得控除額の65万円を差し引いた額が58万円以内であれば、扶養からは外れません。
各道府県の道府県庁所在地や埼玉県の川越市、熊谷市、神奈川県の伊勢原市、海老名市など2級地の均等割非課税限度額は41万5,000円~42万円。そして、それ以外の3級地は38万円です。
たとえば3級地に住んでいる場合、年収から給与所得控除の65万円を引いた金額(所得)が39万円以上だった場合は、個人住民税の均等割分である5,600円が課税されます。
(参考)
松戸市 パート(給与)収入が103万円(所得48万円)以内でも税金がかかるの?
東京都 主税局 個人住民税
花巻市 個人住民税の非課税限度額とは
106万円の壁
厳密には月収8万8,000円以上、年収にして105万6,000円以上になると、社会保険への加入義務が生じます。ただし、パートの社会保険への加入要件は年収だけではありません。次の要件すべてを満たしている場合に対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 従業員数が51人以上の企業で働いている
- 月収が8万8千円以上
- 2カ月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない(休学中・定時制・通信制は加入対象)
(参考:厚生労働省 社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について)
また、パートの場合、1社で106万円を超えた場合のみ適用されます。掛け持ちをしていて、1社は90万円でもう1社が17万円のあわせて107万円の場合、社会保険への加入は対象外です。
なお、年収106万円で支払う社会保険料の目安は15万円前後となります。
123万円の壁(旧103万円の壁)
令和7年の税制改正により、税法上の扶養のボーダーラインとされていた「103万円の壁」が見直され、123万円の壁に引き上げられました。
これにより、令和7年度中の被扶養者の年収が123万円超の場合、配偶者控除や扶養控除が受けられません。
この「123万円」という給与収入の基準は、扶養親族等の合計所得金額の要件である58万円と、給与所得控除の65万円を合計した金額を指します。
なお、この123万円の壁は扶養控除の範囲を示すものであり、所得税が発生する「160万円の壁」とは別です。160万円の壁については、後ほど解説します。
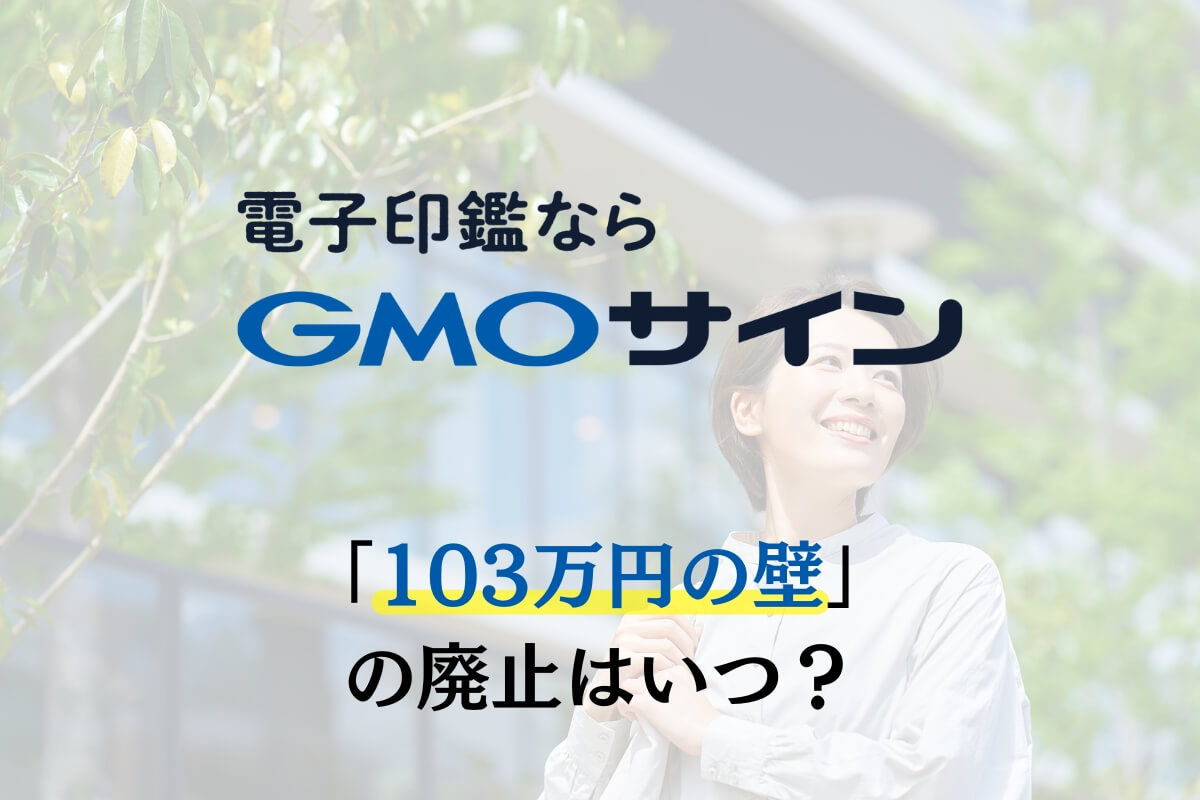
130万円の壁
被扶養者の年収が130万円を超えると、学生も含め106万円の壁のような要件はなく、自ら社会保険へ加入しなければなりません。そして、親もしくは配偶者の社会保険の扶養から外れます。
先ほど解説した106万円の壁であれば、パートを掛け持ちしている場合、1社からの収入が106万円より少ない場合は、社会保険の加入対象にはなりませんでした。
しかし、130万円の壁ではパートの年収合計で見るため、1社で130万円を超えなくても、合計で130万円を超えれば社会保険の加入対象となります。年収130万円で支払う社会保険料の目安は20万円前後です。
なお、2024年11月6日現在、繁忙期や人手不足など雇用側の都合、もしくは収入を上げたい労働者側の都合で130万円を超えて働きたい場合、政府の救援策があります。詳しくは厚生労働省の「年収の壁突破・総合相談窓口」にお問い合わせください。
160万円の壁(本人)
令和7年の税制改正により、これまで所得税の課税ラインとされていた「103万円の壁」が見直され、最大160万円まで所得税がかからない仕組みに変更されました。
- (旧)103万円の壁:基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円まで非課税
- (新)160万円の壁:基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円まで非課税
この基礎控除額は、年収に応じて段階的に設定されており、200万円以下では最大95万円が適用されますが、200万円を超えると控除額が徐々に縮小します。
新たな基礎控除額は、次のようになります。
| 基礎控除 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年まで | 令和7・8年 | 令和9年以降 | ||
| 本人の 合計所得(年収) 金額 | 132万円以下 (200.4万円未満) | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超336万円以下(200.4万円超 475.2万円未満) | 88万円 | 58万円 | ||
| 336万円超489万円以下 (475.2万円超 665.5万円未満) | 68万円 | |||
| 489万円超655万円以下 (665.5万円超 850万円未満) | 63万円 | |||
| 655万円超2,350万円以下 (850万円超 2,545万円未満) | 58万円 | |||
さらに今回の改正では、19歳以上23歳未満の扶養親族に対して「特定親族特別控除」が導入されました。
これにより、扶養控除の上限が従来の年収103万円から150万円に引き上げられ、年収150万円までであれば従来どおり最大63万円の控除が適用されます。
さらに、年収150万円を超えても188万円までは控除額が段階的に減るものの、一定の控除を受けることが可能です。
そのため、対象年齢の扶養親族を持つ家庭では、160万円の非課税枠と特定親族特別控除の両方を確認し、制度を活用することがポイントです。
160万円の壁(配偶者)
160万円の壁は、被扶養者のなかでも配偶者のみに関わるもので、160万とは配偶者特別控除の満額上限となる金額です。
かつては「150万円の壁」とされていましたが、令和7年度の税制改正で給与所得控除が上がったことにより、160万円の壁となりました。
配偶者は、年収123万円までは配偶者控除、123万円を超えると配偶者特別控除が適用されます。そして配偶者特別控除を満額で受けられる年収が160万円です。
被扶養者である配偶者の年収が160万円を超えると、扶養者の控除額が段階的に減額され、201.6万円を超えると扶養者の控除額は0円になります。なお、配偶者控除・配偶者特別控除の場合、扶養者の年収が1,220万円を超えると、配偶者の収入に関わらず控除対象外となるので注意が必要です。
自身のパート収入と扶養者の年収別控除額は次のようになります。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
| 配偶者の 合計所得金額 | 58万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
\\ こちらの記事もおすすめ //
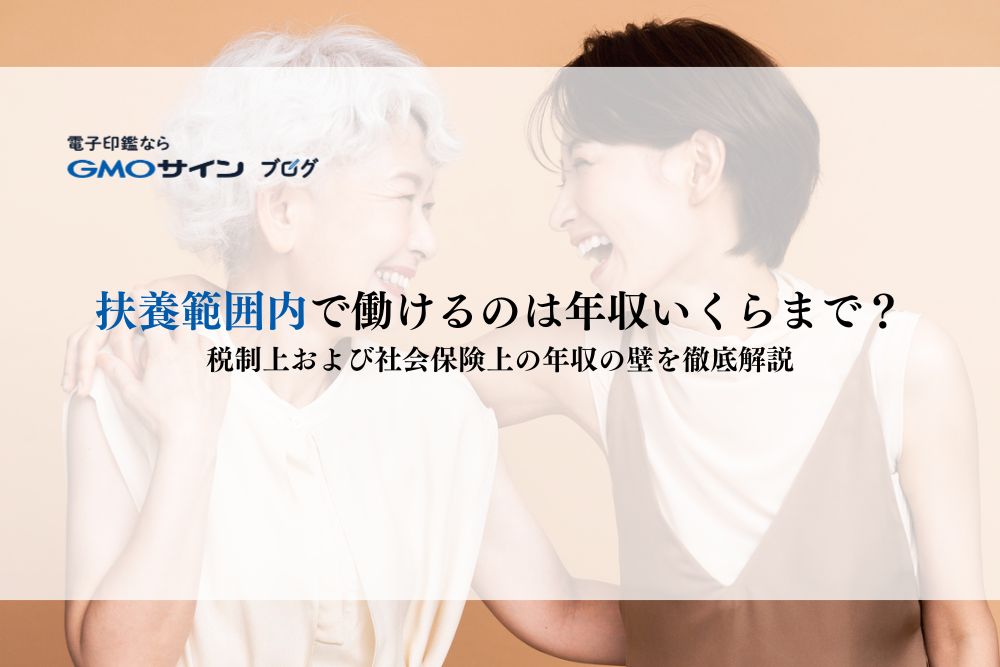
パートを掛け持ちして働くメリットとデメリット
ここまで、パートを掛け持ちした場合の収入により、社会保険や税金がどうなるのかについて見てきました。そのうえで、パートを掛け持ちして働き、年収の壁を超えてしまう場合のメリットとデメリットを解説します。
パートを掛け持ちして働くことのメリット
パートを掛け持ちして働くことで得られるメリットとしては、さまざまな職種を経験できる、収入源を増やせるなどが挙げられます。特に複数の収入源を持っていれば、万が一、1つの勤め先でトラブルが起きても、収入源が途絶えるリスクを抑えられます。
また、年収の壁を超えてしまう場合のメリットとしては、社会保険に入ることで将来的な年金額が増える可能性がある点が挙げられます。会社の厚生年金に加入すれば、基礎年金に厚生年金がプラスされるので、扶養の範囲内で受け取る場合よりも、多くの年金を受け取れるのは大きなメリットです。
さらに、健康保険にも加入すれば、傷病手当金や、出産手当金も受け取れます。そのほかに、当然ながら収入が上がるのもメリットの一つです。
パートを掛け持ちして働くことのデメリット
パートを掛け持ちして働くことのデメリットには、スケジュール調整が難しくなる点が挙げられます。複数の会社で働くことになるため、シフトが重ならないよう自分で徹底した調整が必要です。
また、単純に身体的な負担が増大してしまうリスクもあります。業務内容にもよるものの、複数の仕事に従事することになるため、1つの会社で働くよりも心身の負担増加には注意が必要です。
そのほか、掛け持ちでパートをした場合、確定申告を行う必要が生じます。年収が20万円以下であれば、年末調整のみで確定申告は不要になりますが、それ以上の収入がある場合は確定申告が必須です。
さらに、扶養から外れることで、扶養者の税負担や扶養手当の減少につながり、結果的に世帯全体の収入が減ってしまう可能性がある点も大きなデメリットといえるでしょう。
パートの掛け持ちは年収を考慮したうえで検討する
1つのパートだけでは思ったように収入を得られない場合、掛け持ちして働きたいと思う方は多いのではないでしょうか。
パートの掛け持ちができれば収入が増えるのはもちろん、何かしらの理由で1つの会社で働けなくなっても、急に収入がゼロになる心配もありません。家計や学校の授業料の足しとして働いている場合、無収入にならないのは大きなメリットといえるでしょう。
ただし、いくつか注意しなければならない点もあります。特に重視すべきは、社会保険料や税金の壁です。一定の収入を超えてしまうと世帯の扶養から外れてしまい、以前よりも長時間働いたにも関わらず、収入が減ってしまうケースも少なくありません。
また、より大きな問題として、扶養から外れてしまうと、扶養者の保険料や税負担が増大してしまうことが挙げられます。扶養者控除がなくなる、会社からの扶養手当がなくなるなど、場合によっては年間で数十万円の減少となってしまう可能性もあります。そのため、本人の収入は上がっても、世帯収入は減少するといったことにもなりかねません。