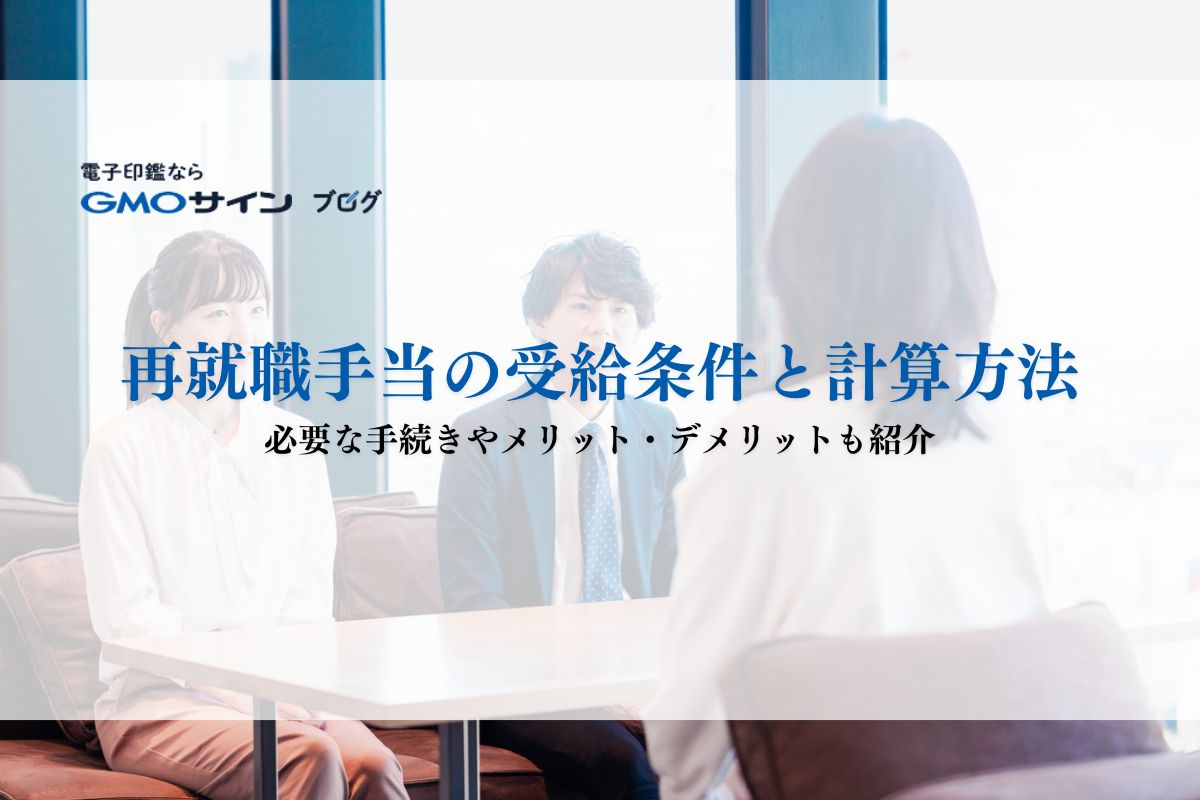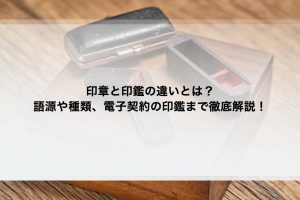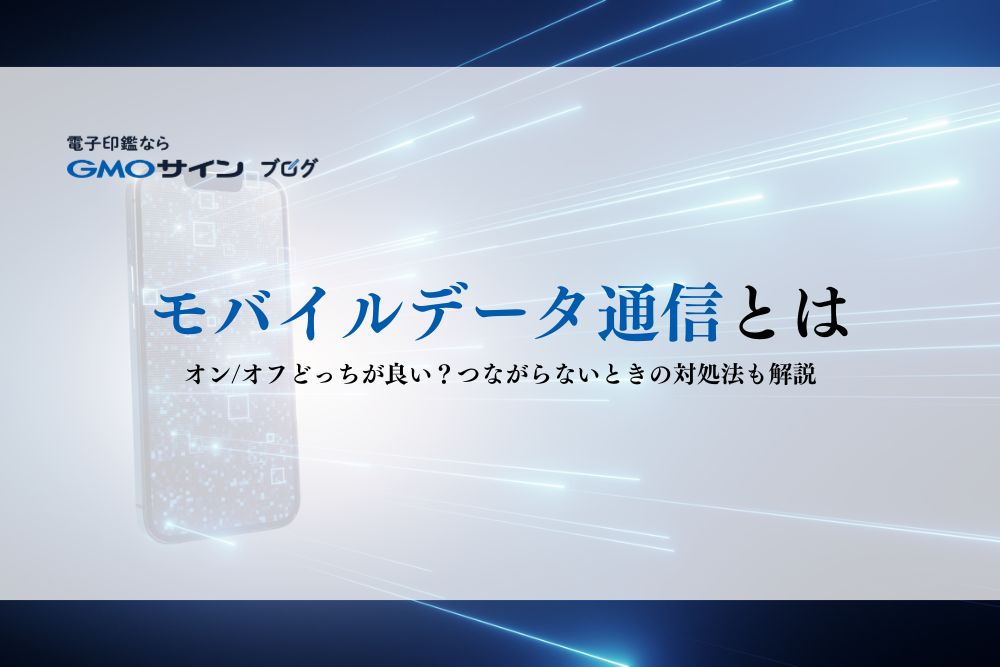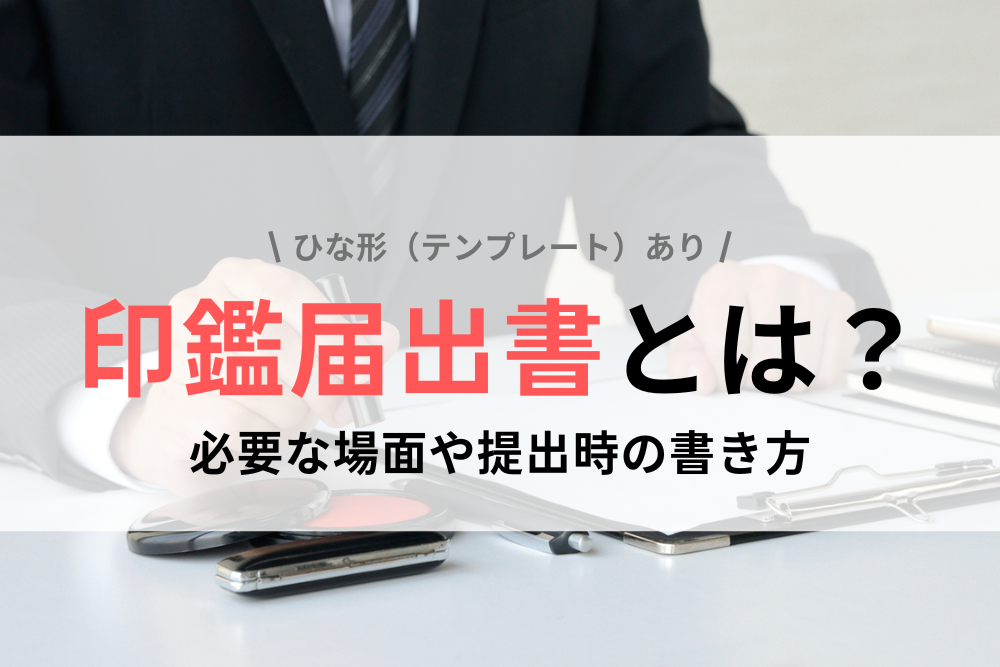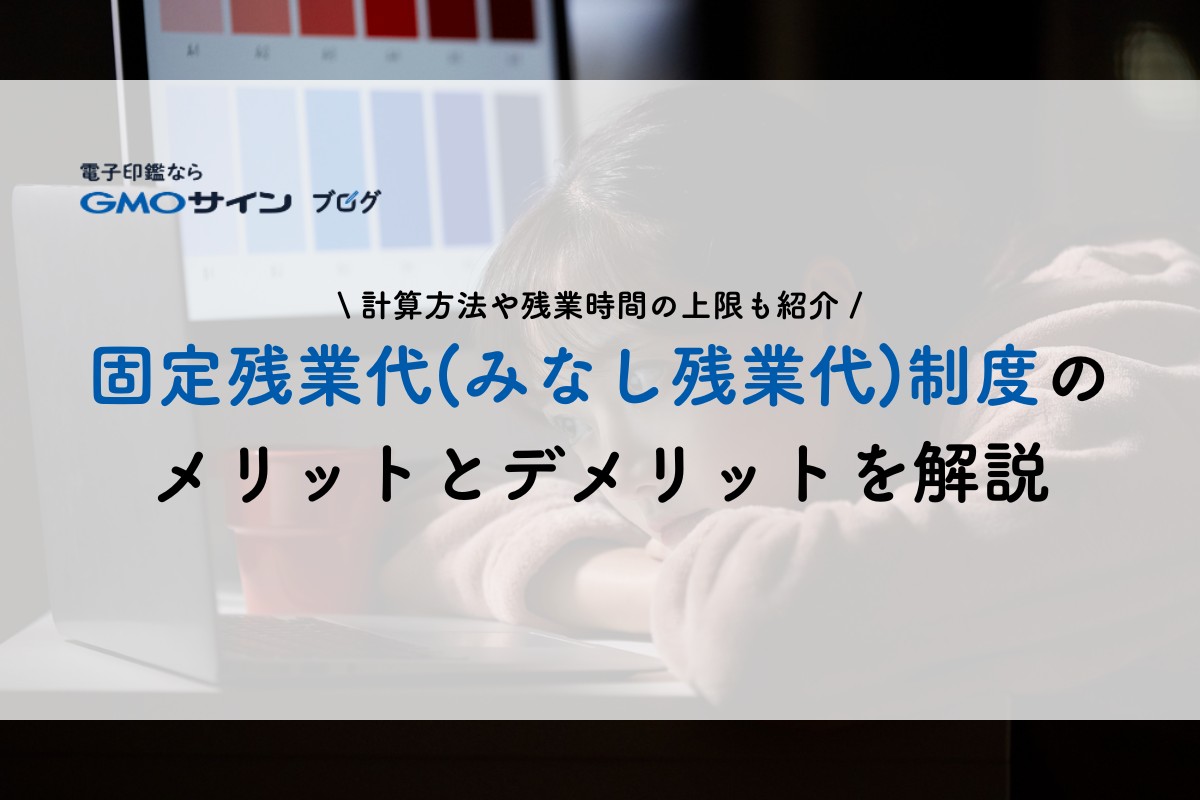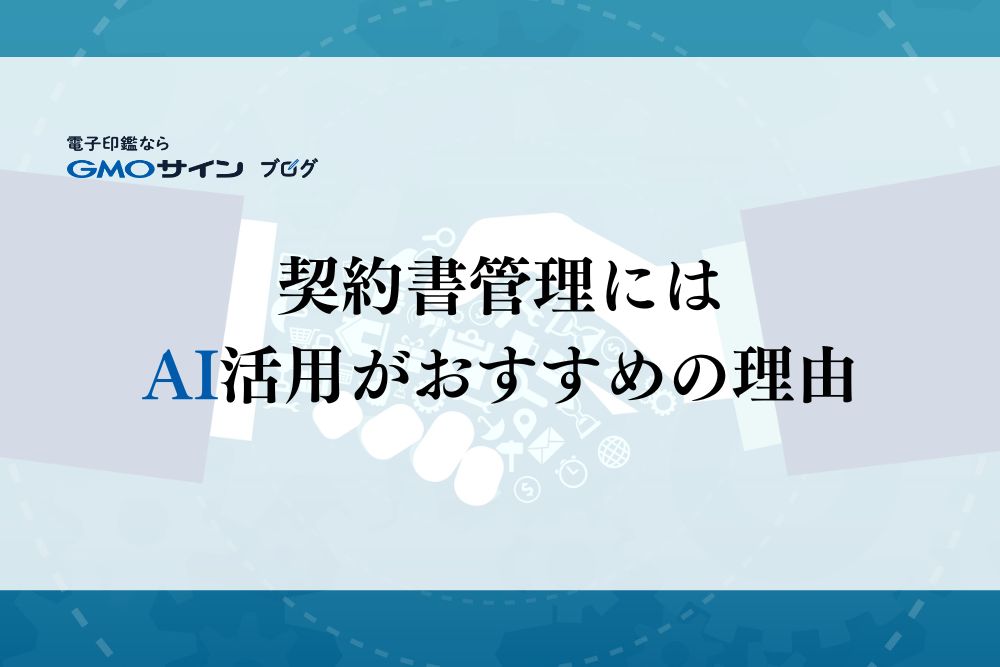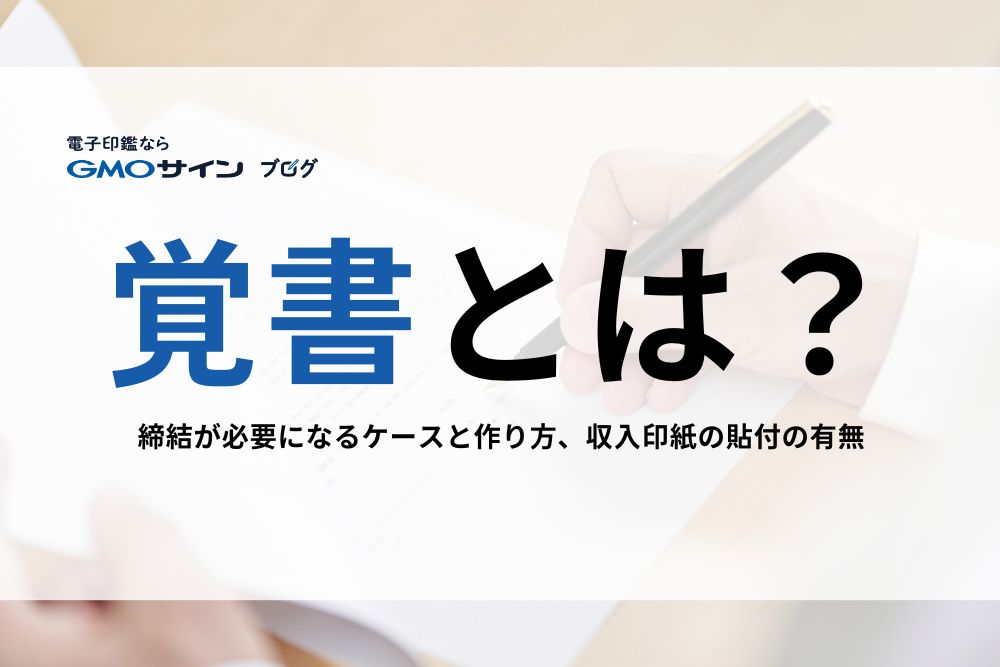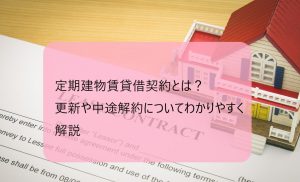近年ハラスメントの一種として知られているマタハラは、従業員のモチベーションダウンや職場の雰囲気の悪化などのマイナスの影響を与えかねない重大な懸念事項です。どのような職場でも起こりうるため、事業主はマタハラへの対策を考える必要があります。
そこで本記事では、マタハラの内容や事業主がとるべき対策などについて詳しく解説します。
マタハラとは
マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略称であり、おもに女性が妊娠を理由として受ける嫌がらせを指します。具体的には、妊娠や出産、または育児休暇などの休暇を希望したことを理由として、上司や同僚から理不尽な嫌がらせを受けるケースが多いです。
マタハラに類似する用語
マタハラとよく似た用語として、パタハラ(パタニティ・ハラスメント)という言葉があります。パタハラとは、父性という意味のパタニティとハラスメントから成る造語です。
パタハラはマタハラと同じく、出産・育児に関することがら、たとえば育児休暇制度の利用などを理由として職場内で嫌がらせを受けることを指します。パタハラはおおむねマタハラの男性バージョンと言ってよいでしょう。
マタハラ・パタハラに関する注意点
マタハラやパタハラは、職場内で起こるハラスメント行為の一種です。しかし、これらの造語はあくまで妊娠から出産、育児までの期間で行われる嫌がらせを説明するために作られたものであるため、国が作る正式な法令や文書には使用されません。
国が発表する公の文章や法令には、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」という言葉を使用しています。しかし、定義などはマタハラおよびパタハラと同じであり、妊娠や育児休暇などの利用と嫌がらせに因果関係が生じるものが該当します。
つまり、自分自身がマタハラ・パタハラと思い込んでいても、第三者からはマタハラやパタハラに該当しないと判断されるケースもあるので注意が必要です。
マタハラの分類
マタハラの嫌がらせの内容はさまざまですが、大きく分類すると以下の2つのタイプに分けられます。
- 状態に関する嫌がらせ
- 制度などを利用することに対する嫌がらせ
それぞれ詳しく解説します。
状態に関する嫌がらせ
状態に関する嫌がらせとは、女性の従業員が妊娠または出産する際に、その従業員に対して不利益になるような取扱いを示唆する言動をとり、就業環境を脅かすことです。妊娠や出産以外にも、以下の3つの状態に陥った際に行われた場合にもこの嫌がらせに該当します。
- 妊娠または出産に関すること(つわりなど)が原因で、労務の提供ができなくなったり、労働能率が下がったりしてしまった時
- 産後休業をとったり、就業制限の規定によって産後の就業ができなくなったりした時
- 危険有害業務や坑内業務の就業制限の規定によって、業務ができなくなった時
これらの状態に関する嫌がらせの具体例には、職場に妊娠を報告した際に「妊娠したら仕事をやめてほしい」「忙しい時期に妊娠するなんてありえない」など言葉を浴びせられたり、「妊娠中はまともに仕事ができない」と決めつけて雑用ばかりさせられたりすることなどが挙げられます。
制度などを利用することに対する嫌がらせ
現代日本では、育児休暇をはじめとした妊娠や出産、育児に関するさまざまな制度が存在します。制度などを利用することに対する嫌がらせとは、従業員がこれらの制度を利用しようとした際に、その利用を妨害するなど該当する従業員に対して不利益な取扱いを行い、就業環境を脅かすことです。
たとえば、産前の検診を受けるために休暇を申請した女性が休暇を拒否されて、勤務時間外への受診を強要されたり、育児休暇を申請した際に「育児休暇を取得するならそのまま退職してもらう」と脅したりすることがこの嫌がらせに該当します。
事業主に求められる対策
事業主に求められる対策について、「厚生労働省の指針を守る」ことと「不利益取扱いの禁止」の2つの視点から解説します。
厚生労働省の指針を守る
厚生労働省は事業主に対して、以下の2つの法律からマタハラなどの「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」を防止する措置を行うことを義務付けています。
男女雇用機会均等法第11条の2
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条の二
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、 出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定に よる休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により 当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するため に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(参考:厚生労働省)
育児・介護休業法第25条
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第二十五条
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(参考:e-Gov法令検索)
不利益取扱いの禁止
事業主が「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」を防止する措置を行う上で意識しなければならないのが、妊娠・出産などを理由とした該当する従業員への不利益となる行為です。厚生労働省は、男女雇用機会均等法第9条第3項でこのような不利益取扱いを禁止しています。
<男女雇用機会均等法第9条第3項(抄)>
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関 する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不 利益な取扱いをしてはならない。
(参考:厚生労働省)
不利益取扱いに該当する行為は、以下のように例示されています。
- 解雇すること。
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
- 降格させること。
- 就業環境を害すること。
- 不利益な自宅待機を命ずること。
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
- 不利益な配置の変更を行うこと。
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
(参考:厚生労働省)
事業主がマタハラを防止するために行うべき4つの措置
事業主が職場内でのマタハラを防止するためには、以下の4つの措置を講ずる必要があります。
マタハラ防止の周知
マタハラを防止する事業主の方針を周囲に啓発することが必要です。最初に、従業員に対してどのような行動・発言がマタハラに該当するのかを周知します。特に、妊娠や出産に対して否定的な言動がマタハラに直結することを強調することが大切です。
また妊娠や出産などに該当する従業員が、気軽に制度利用ができる旨も周知させることも忘れないようにしましょう。さらに該当する従業員に対してマタハラにあたる行為を行った場合には、厳正に対処する事項を就業規則などに規定しておき、管理監督権限を持つ従業員を中心にすべての従業員に知らせる必要があります。
相談窓口の設置
マタハラを受けた被害者が相談できる窓口を設置する方法もおすすめです。相談窓口には、適切な知識を持った従業員を配置して、相談内容や状況に応じて速やかに適切な対応がとれるように配慮しておく必要があります。
また相談者の相談内容がマタハラに該当するか微妙であったとしても、その状況を放置せずに相談に対して真摯に対応する姿勢が求められます。さらに相談窓口は対面だけでなく、電話やメールなど複数のルートを用意するなど相談しやすい環境づくりを心がけておくことも大切です。
発生時の対応
マタハラが発生した場合には、迅速な対応が求められます。その場合には速やかに事実確認を行い、事実が確認できたら被害者には配慮の措置、加害者には罰則に則った措置を適正に行う必要があります。
職場内の制度を整備する
職場内に存在するマタハラの原因を解消することも必要です。たとえば、育児休暇などを申請しにくいような雰囲気が充満している場合は、まずはその空気を変える必要があります。具体的には、上司が率先して育児に関する制度を利用したり、制度を利用しても不利益を受けることがない実績を作るとよいでしょう。
また妊娠・出産に関する制度だけに注視してしまうと、その制度を利用しない従業員から反発が来る可能性がありますので、ほかの制度も整備してすべての従業員が働きやすい取り組みも行えば、効率的に職場の空気を変えていけるでしょう。これらの措置を行う際には、相談者やマタハラの加害者双方のプライバシーを保護することも大切です。
また事実関係の確認の際に協力してくれた方に対しても、不利益な状況にならないような配慮も忘れずに行いましょう。
実際に行われたマタハラへの対策
実際の企業で行われたマタハラへの対策を3つご紹介しますので、参考にしてください。
パンフレットの作成
マタハラが行われた場合の対処方針や内容を詳細に記したパンフレットを職場で配り、マタハラに関する情報の周知を行う方法は、多くの企業で行われています。
どのような行為がマタハラに該当するのか、マタハラを行った場合はどのような処分が下るのかをわかりやすく記載しておくとより効果的です。
管理職向けの制度周知パンフレットの作成
会社で用意している育児休暇などの制度を管理職がしっかりと把握すれば、ほかの従業員も制度を利用しやすい環境を作れます。また男性の管理職に対して妊娠・出産中の女性の取扱いに関するポイントを示せば、適切な対応がとれるように促すことが期待できます。
相談から対応までの流れをフローチャートで示す
マタハラの相談から対応までの流れを一目でわかるようにまとめておけば、マタハラの被害で悩んでいる方が安心して相談できるようになります。この方法では、相談することによってプライバシーが害されることがないことを明記しておくとより効果的です。
マタハラに関するよくある質問
なぜマタハラが起こるの?
マタハラのおもな原因は、「女性は家のことをするべき」という昔の考え方や、妊娠や育児について職場の理解が足りないことです。また、忙しい職場では、誰かが休むと仕事が増えるため、不満が出やすくなります。こうした理由が重なって、マタハラが起きています。
マタハラは男性にも関係がある?
マタハラは女性だけでなく、男性にも関係があります。男性が育児休業や時短勤務を希望したとき、上司や同僚からいやなことを言われる場合があります。
これを「パタハラ(パタニティハラスメント)」といいます。男性も育児に参加しやすい職場にするため、マタハラやパタハラについての理解が大切です。
マタハラの対策には、すべての従業員の協力が必要
マタハラの防止には、事業主を中心としてすべての従業員が一丸となって取り組むことが大切です。そのためにはマタハラに関する情報共有を積極的に行い、妊娠・出産に関係するすべての人が働きやすい環境を作るようにしましょう。