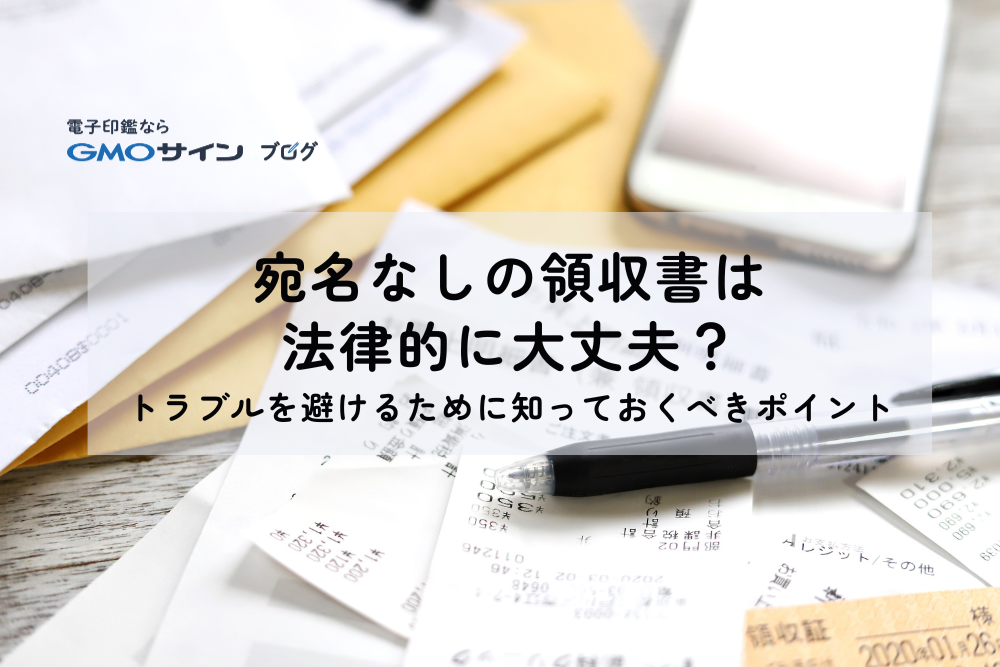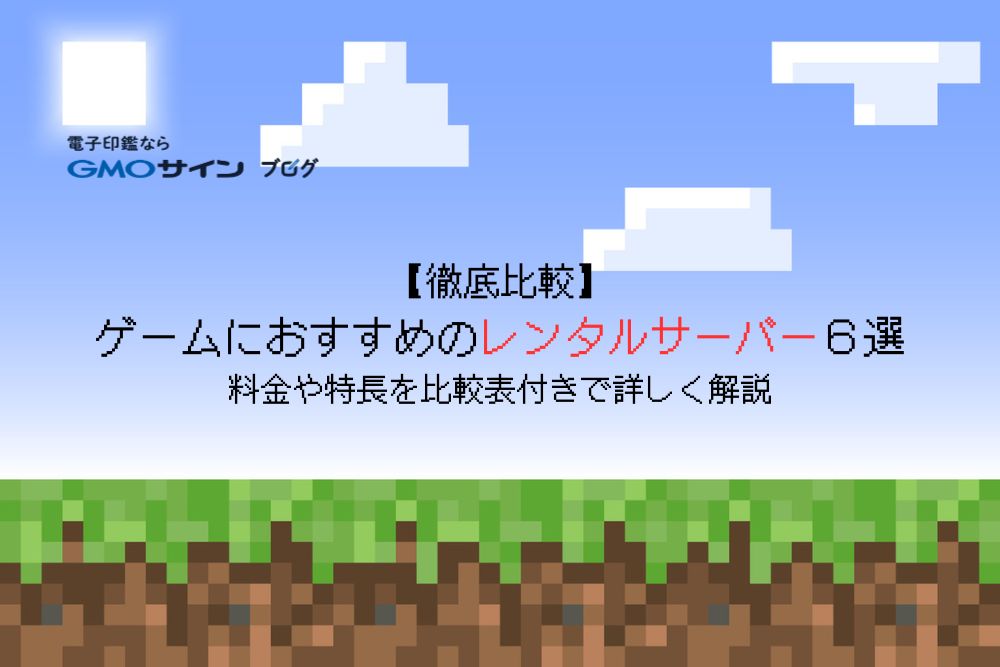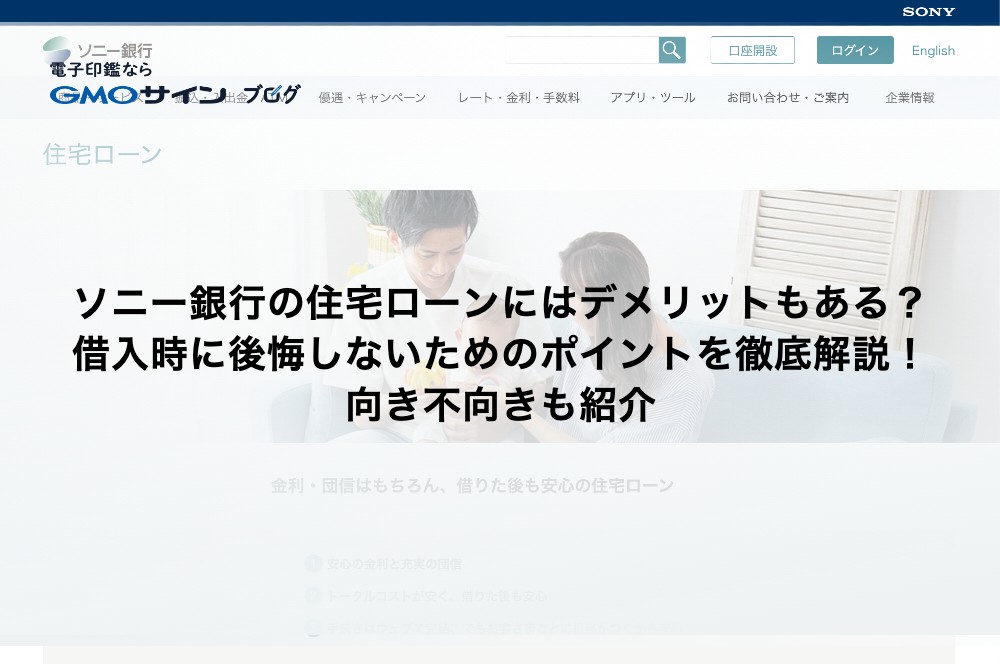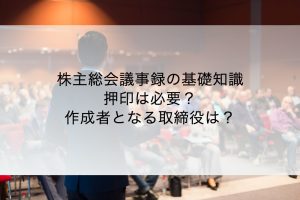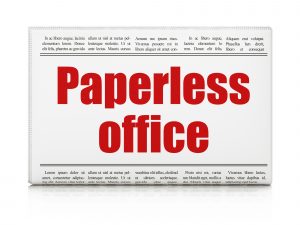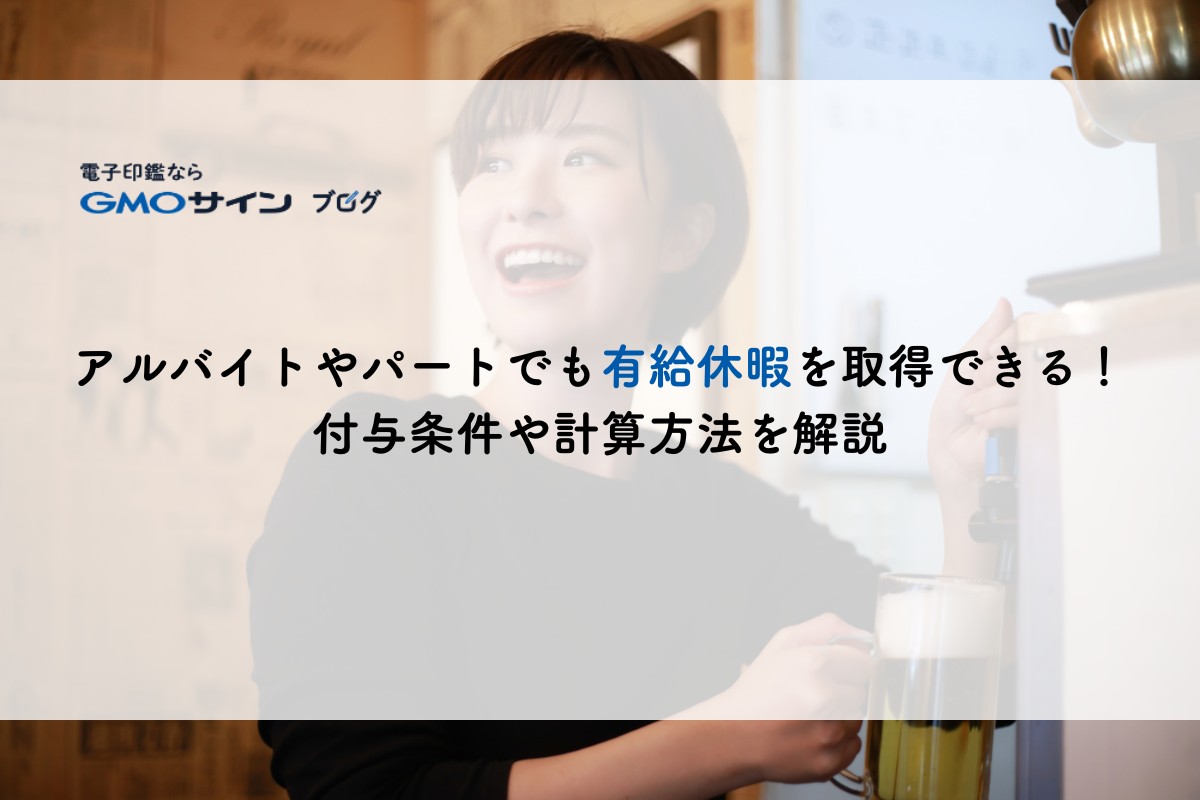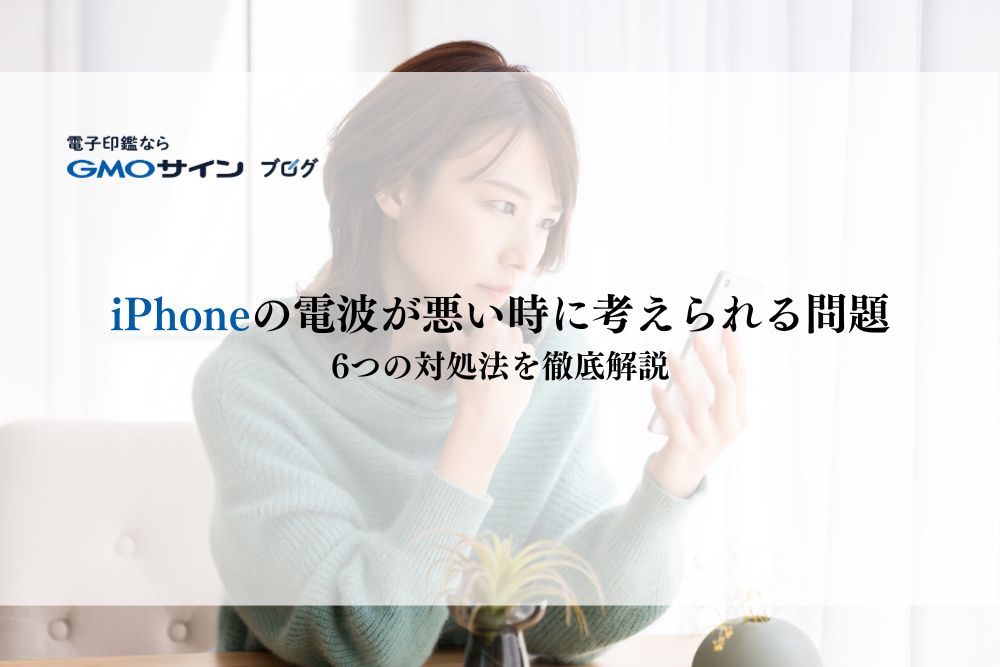業務改善などのビジネス上の課題解決のために、コンサルタントを利用するケースは少なくありません。
コンサルティング契約にはさまざまなものがあるため、たとえばコンサルティング契約書と印紙税との関係など、契約に際しどのような点に注意すべきか詳しくはわからないという方もいるのではないでしょうか。
今後、コンサルティング会社と契約を交わすことになったときに困ることがないよう、この記事ではコンサルティング契約書と印紙税や収入印紙について解説します。ぜひ参考にしてください。
収入印紙に関するリスクを回避したい方は『電子印鑑GMOサイン』などを使った電子契約での取り交わしを検討してみてはいかがでしょうか。
コンサルティング契約の形態
コンサルティング契約を交わすにあたって、その内容によって契約の分類は変わってきます。一般的なコンサルティング契約をいわゆる典型契約で分類すると、請負契約と準委任契約の2種類に分類できます。
前者であれば基本的に課税文書扱いになり、収入印紙を貼らなければなりません。後者の場合は非課税文書扱いになるケースが多いので、収入印紙を貼付する必要はないことになります。
請負契約の契約書は2号文書に該当する
締結するコンサルティング契約が準委任契約の場合であれば、その契約書は基本的に非課税文書となりますので、収入印紙の貼付は必要ありません。
他方、請負契約としてコンサルティング契約を交わす場合には、請負に関する契約書として2号文書にあたり、収入印紙の貼付が必要となります。
成果物の作成を約束したコンサルティング契約は請負契約となり、その際に交わす契約書は課税文書のうち2号文書に該当することになります。2号文書の場合、貼付しなければならない収入印紙の額すなわち印紙税額は契約金額によって異なります。具体的な金額は、以下の表をご覧ください。
| 印紙税額(1通または1冊につき) | |
|---|---|
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
なお、請負契約に該当した場合でも、印紙が必要なのは紙の契約書のみです。電子契約であれば課税文書ではなく電磁的取引に該当するため、収入印紙の貼り付けは不要です。
収入印紙に関するリスクを回避したい方は『「GMOサイン』などを使った電子契約での取り交わしを検討してみてください。
成果報酬型の請負契約だと7号文書に該当する可能性
2号文書に該当するのは、契約書の中で金額の記載のあるものです。しかし、コンサルティング契約書の中には金銭の記載のないものもあります。
たとえば、請負契約の形態を取っているけれども、成果報酬の支払い方法を取っているようなケースです。この場合、具体的な金額の記載はなされないでしょう。コスト削減を依頼するようなケースが例として考えられます。
もし成果報酬型のような金銭の記載のない請負契約の場合、その契約期間が3カ月を超える場合には課税文書のうち7号文書に該当します。
知的財産権の譲渡を契約内容に含むコンサルティング契約書は1号文書
コンサルタントが提供する成果物に関し、知的財産権の譲渡を契約内容とする場合、その契約書は1号文書扱いになるので注意が必要です。そのため、請負契約を交わし知的財産権の譲渡を内容とするコンサルティング契約書は1号文書かつ2号文書という形になります。
1号文書かつ2号文書の場合、印紙税はどうなるのかというと、原則は1号文書扱いになります。ただし、請負の契約金額が知的財産権の譲渡対価を上回った場合には2号文書にあたることになります。
1号文書扱いとなったコンサルティング契約書に貼付する収入印紙の額は以下のとおりです。
| 印紙税額(1通または1冊につき) | |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
準委任契約型のコンサルティング契約書であれば非課税文書扱い
準委任契約という形態でコンサルティング契約を交わしたのであれば、その契約書は非課税文書扱いになります。よって印紙税を納税する必要は基本的にありません。
準委任契約とは、委任者が受任者に対して法律行為ではない事務を委託する契約のことです。コンサルティング契約の場合、作業や知識、ノウハウ、情報の提供に特化されている場合には準委任契約に分類されます。
たとえば、自社で講演を企画し、講師としてコンサルタントを招いたとします。この場合、契約形態が準委任契約であるとコンサルティング契約書に明記されていないと請負契約と指摘される可能性があるため、「今回の契約は準委任契約である」旨を契約書の条項に盛り込んでおくと安心でしょう。
知的財産権の譲渡を伴うなら準委任契約でも課税文書
コンサルタントに特定の作業を依頼しただけであれば、基本的には準委任契約で非課税文書扱いになります。
しかし、その作業によって知的財産権が発生し、委任者に譲渡するかたちになっているのであれば、そのコンサルティング契約書は1号文書扱いになります。よって課税文書に該当し、印紙税の納税義務が発生します。
たとえばコンサルティング契約の内容として、プログラミングのコーディング作業が含まれていたとします。そのプログラムを委任者に提供することが知的財産権の譲渡にあたり、その契約書は1号文書扱いになると考えられます。
請負契約と準委任契約の違いについて解説
前述のように、締結するコンサルティング契約が請負契約になるか、準委任契約になるかで印紙税の納付義務が発生するかどうかが変わってきます。
請負契約と準委任契約にはどのような違いがあるのでしょうか。両者の違いについてかんたんに見ていきましょう。
基本的な契約内容・目的の違い
請負契約と準委任契約は、その内容・目的が異なります。かんたんに言えば、請負契約は結果重視であるのに対し、準委任契約は過程重視です。請負契約の場合、それまでの過程がどうであれ求められた業務が完遂されなければなりません。
一方、準委任契約の場合、仕事の過程が重視されますので、過程において過失がなければ基本的に責任は問われないことになります。
業務責任の違い
受注者・受任者の業務に関する責任の種類も異なります。請負契約の場合、仕事を完成させなければなりませんので、仕事が終わらなかったり仕事に何かしらの不備があったりした場合には業務の責任を問われます。
一方、準委任契約の場合、仕事の過程に関する責任がありますので、善管注意義務を怠ると責任を問われます。
報告義務の違い
報告義務の有無も両者の相違点の一つです。報告義務は、請負契約にはなく、準委任契約にはあります。請負契約の場合、契約内容に盛り込むことで報告義務を課すことができます。
成果物の有無
成果物が発生するかどうかも異なる部分です。請負契約では原則として成果物が発生するのに対し、準委任契約では発生しません。もちろん例外はあり、請負契約であっても成果物が発生しないケースはあります。
業務実施における費用負担の違い
業務実施にあたって、費用が発生することがあります。この費用を誰が負担するのかも請負契約と準委任契約とでは異なります。
請負契約の場合、仕事を完成するにあたって発生した費用は基本的には受注者が負担しなければなりません。一方、準委任契約の場合は原則として委任者が業務実施にあたって発生する費用をすべて負担します。
再委託の可否
受注者・受任者による再委託ができるかどうかも異なります。請負契約の場合は基本的に再委託が可能です。請負契約は仕事の完成が目的であって、誰が完成させたかについては法律上規定がありません。
再委託を禁止する場合は、契約内容に盛り込めば可能となります。一方、準委任契約の場合、契約当事者の信頼関係の下で成り立っているので、原則として受任者自身が業務を担当しなければなりません。
再委託先の責任
再委託した場合、何か問題が起きた場合に誰が責任を負うかも違いがあります。請負契約の場合、再委託先が何かミスしても受注者(請負人)がその責任を負わなければなりません。
一方、準委任契約では再委託は原則として禁止されていますが、特約があれば可能となります。この場合、受任者が原則として責任を負いますが、代理権が付与されているケースでは一定の範囲で再委託先が責任を負うこともあります。
契約解除権の違い
請負契約でも準委任契約でもいつでも契約解除は可能です。
ただし、請負契約の場合は仕事が完成するまでの間はいつでも損害を賠償して契約を解除することができるのに対し、準委任契約の場合は一定の場合に損害賠償責任を負うことがあるものの、必ずしも損害賠償責任を負うわけではないという点で若干の違いがあります。
印紙の有無
請負契約の場合、その契約書は基本的に課税文書となるため、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。一方、準委任契約の場合、その契約書は課税文書とされていないため、基本的には収入印紙を貼り付ける必要はありません。
コンサルティング契約書と収入印紙に関するよくある質問
コンサルティング契約書に印紙は必要?
コンサルティング契約書に収入印紙が必要かどうかは、その契約の具体的な内容や形態によって異なります。
準委任契約の場合は不要で、請負契約の場合は契約金額に応じた印紙が必要です。
契約書に「コンサルティング契約」と書かれていても、その実質的な内容が「仕事の完成を約束するもの(請負)」なのか、「事務処理の委託(準委任)」なのかによって、印紙の必要性が変わるため、心配な場合は弁護士に相談しましょう。
収入印紙に関するリスクを回避したい方は、『GMOサイン』などを使った電子契約での取り交わしを検討してみてはいかがでしょうか。
印紙税がかからない契約書はある?
印紙税がかからない契約書はあります。印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」に該当する契約書や領収書などに対して課される税金です。逆に言えば、課税文書に該当しない契約書には印紙税はかかりません。
具体的に印紙税がかからない契約書(非課税文書)には、以下のようなものがあります。
- 印紙税法で課税対象として列挙されていない文書
- 契約金額が一定額未満の文書
- 特定の法律で非課税とされている文書
- 電子契約
特に電子契約であれば、紙の契約書では貼り付けが必要な印紙が不要になります。収入印紙に関するコストやリスクを抑えたい方、『GMOサイン』などを使った電子契約での取り交わしをおすすめします。
契約書に収入印紙を貼らなかったらどうなる?
収入印紙が貼られていなくても、契約の当事者間で合意した内容が無効になるわけではありません。しかし、過怠税等の金銭的なペナルティが発生します。
まとめ
コンサルティング契約書に収入印紙の貼付が必要になるかどうかは、その契約が請負契約なのか準委任契約なのかにより決まってきます。そのため、具体的な契約内容から判断し、印紙税の課税対象になるかどうかをよく見極めることが欠かせません。
コンサルティング契約書の作成にあたっては、収入印紙の貼り忘れがないよう、貼付の要否をしっかりと確認するように心がけるようにしましょう。
「GMOサイン」は、はじめて電子契約を行う方にもわかりやすい操作画面が特徴で、国内の導入社数は350万社(※)を超えています。月に5通までの電子契約が無料でできるお試しフリープランもご利用いただけるので、お気軽にご利用ください。
※ 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)