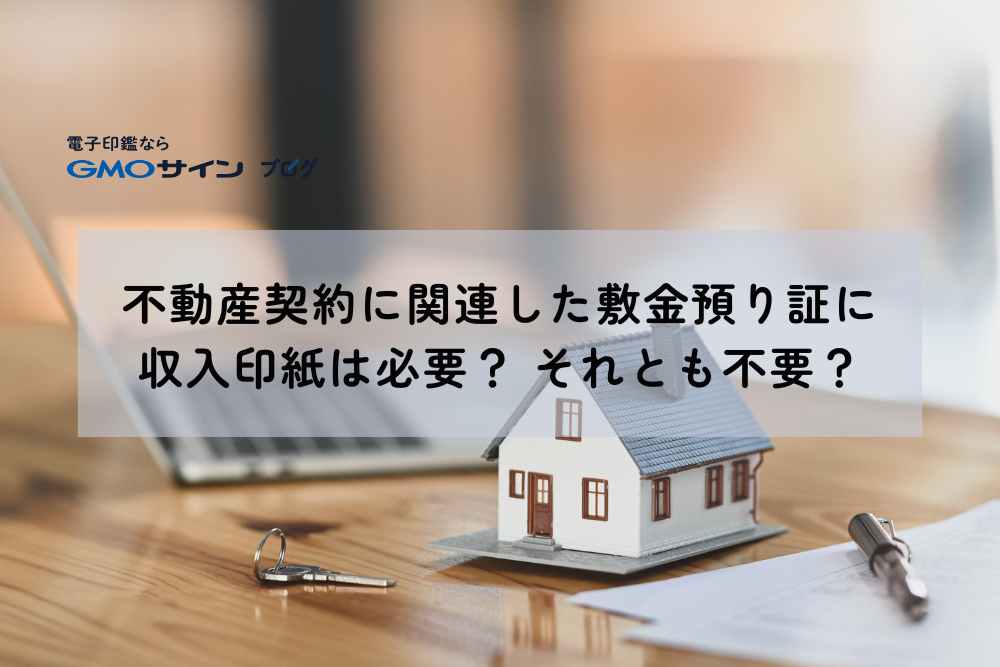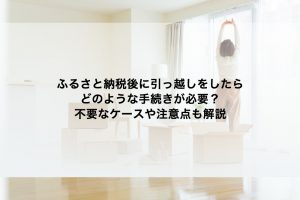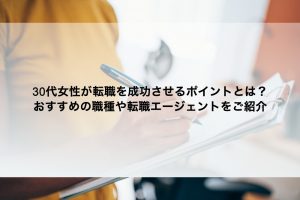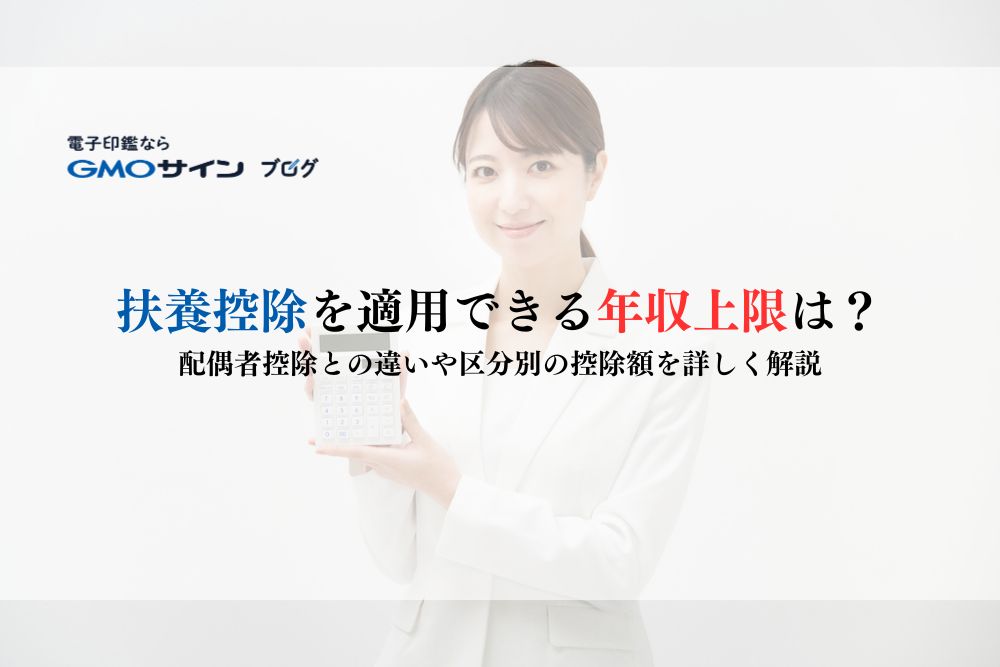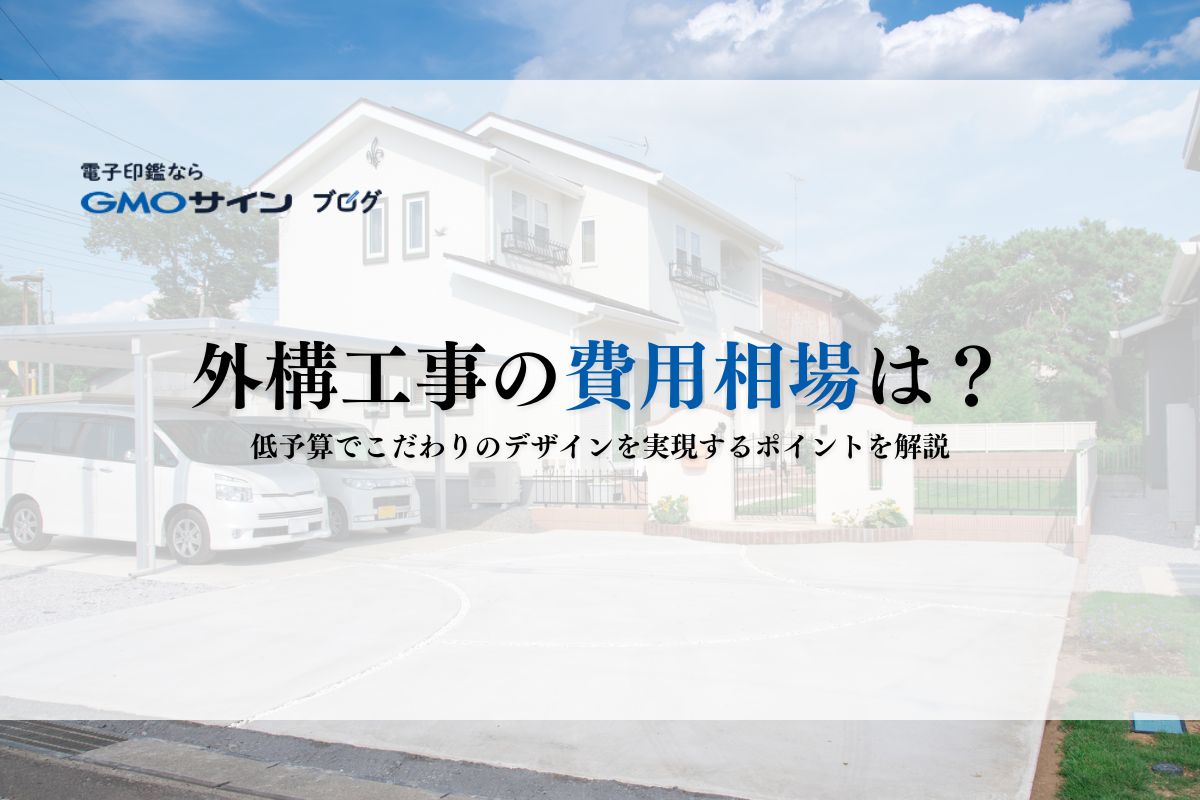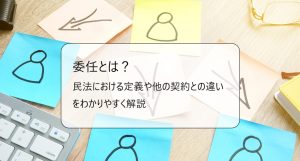2020年4月に施行された改正民法によって、危険負担に関する条項について変更がくわえられました。解釈に対して争点があった条項が変更・明文化されているので、詳細を把握しておくことが大切です。
この記事では、民法改正後の危険負担の事項のポイントや売主側と買主側のそれぞれが確認しておきたい点などを解説していきます。「改正されたことは知っているものの、具体的にどのような点に注意すべきなのか分からない」という方は、内容を参考にしてみてください。
危険負担とは
売買契約のように、ある2つの債務が対価となる契約(双務契約)が成立した後に問題となるのが危険負担です。危険負担とは、債務者の責任が発生しない理由で本来引き渡すはずであった目的物が滅失・毀損などに陥り、後発的に履行不可能となってしまった際に、契約当事者のうち、どちらがそのリスクを負担するかという問題です。
たとえば、ハンドメイドのガラス製品を取り扱っているお店があるとします。そのお店に、1つ50万円のガラスの花瓶(目的物)の注文が入り、売主は花瓶を作成しました。
花瓶は引き渡しの際に代金を受け取るという契約となっているとします。しかし、完成した花瓶が地震の被害で引渡し前に割れてしまい、売主の花瓶を注文者に引き渡す債務が履行不可能となってしまいました。
この時点で、売主の債務は消滅してしまっています。しかし、この状態でも注文した側(買主)は、代金を支払わなければならないのかという疑問が生じるのではないでしょうか。このような場合に、危険負担が問題となります。
従来の危険負担の問題に関する2つの主機
危険負担の問題に対する考え方には、以下の2つがあります。
- 債権者主義
- 債務者主義
1つ目は、債権者主義という考え方です。債権者主義とは、一方の債務が後発的に不履行になった場合でも、もう一方の債務は消滅しないという考え方です。
ガラスの花瓶の例では、花瓶が地震で割れてしまったために、買主(債権者)は目的の花瓶が手に入ることはありません。しかし、売主側の危険を負担して、債権者である買主が花瓶の代金の支払いをしなければならないという考え方になります。
2つ目は、債務者主義という考え方です。債務者主義とは、債権者主義においては消滅しなかったもう一方の債務も消滅するという考え方です。
ガラスの花瓶の例では、買主はガラスの花瓶が手に入らなくなってしまったため、代金の支払い義務も同時に消滅するという考え方となります。この場合は、売主(債務者)が危険を負担します。
民法改正後の危険負担に関する事項のポイント
2020年4月に施行された改正民法により、危険負担に関する事項がいくつか変更されました。
改正された事項は、危険負担に関する従来の判例や解釈について明文化した点と、従来の解釈に対して争点があった条項を変更・明文化した点の2つに大きく分けられます。
前者の場合は、今までの解釈などを単にわかりやすく示しただけであるため、実務的には大きな影響はありません。つまり、この点においては改正前の民法に関する知識がしっかりと備わっていれば問題がないということです。
一方、後者のほうは実務で取り扱う場合にこれまでとは異なる運用方法になる点もあります。改正された点についてしっかりと把握しておくことが大切です。改正前と比較して抑えておきたいポイントは3つあります。
債権者主義の廃止
旧民法の534条と535条では、片方の債務が後発的に不履行になった場合でも、もう一方の債務は消滅しないという考え方である債権者主義を採用していました。しかし、目的物の引渡し前にもかかわらず、債権者が危険を負担するという点に関しては、以前より有識者たちから多くの批判の声が上がっていました。
買主がガラスの花瓶を手に入れていないにもかかわらず、ガラスの花瓶が壊れてしまうリスクを負うのは不公平ではないかと考えたわけです。債権者主義の考え方では、ガラスの花瓶が手元に届いても届かなくても、料金の支払い義務が発生するため、不公平に感じてしまうのも頷けます。
そのため、実務においては当事者間の契約で、代金の支払い時期や引き渡し時期などの基準時点を定める方法が取られていました。定められた時期以降に危険が売主から買主に移るという考え方です。これは民法で定められている運用方法ではなく、目的物の引き渡しがあってはじめて買主に危険が移転するとしています。
こうした実務での運用方法と民法の解釈に差があることをふまえて、改正民法では争点になっていた債権者主義自体を廃止することになったのです。
また、債権者主義の廃止に伴って、特定物の取扱いも変更となりました。特定物とは、売買などに取り扱われる目的物として、具体的な個として特定されたもののことです。
たとえば、魚屋で鮭を買おうとした時、鮭を1匹くださいと言えばそれは不特定物となります。しかし、並んでいる鮭の中から欲しい個体を指さして「この鮭を1匹ください」と対象を指定した場合は、その鮭は特定物として扱われます。
旧民法では、この特定物の引渡しに関わる危険も債権者が負担するように示されていました。しかし、そうなると買主は目的物(鮭)が手に入る前に何らかの理由で目的物が消失したとしても、その目的物にかかる料金を支払う必要が出てきてしまいます。
こうした状況を受けて改正された民法では、特定物の引き渡しに関する危険負担を債務者が担うことになりました。目的物が手に入る前に消失した場合は、売主に対してその商品の代金を支払う必要がなくなるというわけです。
反対給付債務の履行拒否権
このポイントでは、一方の債務がいずれの責任によることなく履行不可能になってしまった場合の考え方について明示されています。つまり、ガラスの花瓶が売主の手に渡る前に、どちらの責任でもない地震によって消滅した場合、買主(債権者)側が花瓶の料金を支払う必要があるのかどうかということです。
改正された民法では、この点について以下のように明示されています。
(債務者の危険負担等)
引用;民法|e-Gov法令検索
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
つまり、買主(債権者)側の料金を支払わなければならないという債務は当然になくなることはないが、代金の支払いは拒否可能であると決められたわけです。しかし、当然にその債務がなくなるわけではありません。代金の支払いという債務を消滅させたい場合は、解除権を行使して契約自体を解除する必要があります。
危険の移転時期
旧民法では、目的物の滅失によって発生する責任(危険)の移転が契約締結後のどの時点で発生するのかが明示されていませんでした。つまり、契約を結んだ双方の責任がなく目的物(商品など)が滅失した際に、どのタイミングで発生したものであれば買主が追完請求権などの権利を行使できるのかが曖昧だったのです。
しかし、今回の改正では、危険の移転が生じる時期が引き渡し時であると明示されたため、曖昧だった故に発生したトラブルを防ぐことができるようになりました。
(目的物の滅失等についての危険の移転)
引用;民法|e-Gov法令検索
第五百六十七条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
契約書などに記載された危険負担に関する条項でチェックしたいポイント
売主と買主の間で売買契約を結ぶ場合、危険負担に関する項目が契約書に定められることがほとんどです。民法の改正に伴い、変更点がいくつか生じているため、売主側・買主側それぞれの視点でチェックしたいポイントをまとめました。
売主側がチェックしたいポイント
売主側に有利な契約を結ぶのであれば、従来どおりの債権者主義を採用したいところです。しかし、民法改正後もそうした姿勢を取ってしまうと、買主側から忌避されてしまい、契約自体が結べなくなるといった事案が発生する可能性が高まります。
そのため、一方的に買主側に有利な契約を提示する際には、さまざまなリスクをふまえて慎重に行う必要があります。お互いに快適な契約を結ぶためには、基本的には改正後のルールに則り、目的物が買主の手に渡った時点を持って危険の移転が行われるとしたほうがよいでしょう。
買主側がチェックしておきたいポイント
買主側がまずチェックしたいポイントは、債権者主義が採用された内容になっていないかどうかです。この記載に気づかないで契約をしてしまうと、買主側が不利になってしまうので注意が必要です。
買主側が納品後に目的物を検収する場合、引き渡し時点に危険の移転を設定してしまうと検収前に危険が買主に移ってしまいます。そのため、検収で目的物の損傷が見つかっても、買主が危険を負担しなければならないという事態に陥ってしまいます。こうした事態を避けるためにも、検収の完了時にしておいたほうが安心です。
危険負担に関するよくある質問
危険負担と債務不履行の違いは?
危険負担とは、契約の目的物が事故や災害など債務者の責めに帰さない事由によって滅失・損傷した場合、その損失をどちらが負担するのか定めたルールのことです。
一方で債務不履行は、契約当事者が契約内容どおりの義務を履行しないことを指しており、品質が不十分な場合や納期の遅延などが該当します。故意の債務不履行が発生した場合は、損害賠償請求や契約解除の対象となる可能性があるので注意が必要です。
危険負担と不可抗力の違いは?
不可抗力は、予見や回避が不能な外的事情によって契約が履行できない状態のことです。天災事変や戦争などが原因で契約が履行できない場合は、債務不履行の責任を負う必要がなくなります。
不可抗力によって債務が消失した場合、反対債務をどのように処理するのかという問題が発生するでしょう。この問題のことを危険負担と呼び、契約によって定められたルールに則って処理を行います。
危険負担に関連する法令や制度は何がある?
危険負担に関連する法令や制度は、おもに民法にて定められています。たとえば、民法第536条では、当事者双方の責任ではない事由によって履行が不可能になった場合は、債権者が反対給付の履行を拒むことができると記載されています。
また、民法第567条では、目的物の滅失で発生する責任(危険)の移転が生じる時期が、引き渡し時であると明示されています。危険負担に関連したトラブルを防ぐためには、このような法令について把握しておくことが大切です。
まとめ
従来の民法では曖昧だった点や争点になっていた点がありました。しかし、改正後にはしっかりと解決方法が明文化され、きちんと双方が納得できる形になっています。
契約を結ぶ両者が互いに納得した状態で契約を結べば、何かあった場合でも大きなトラブルへの発展を回避することが可能です。双方の利益を守るためにも、改正された危険負担に関する内容についてしっかりと知識をアップデートしておくようにしましょう。