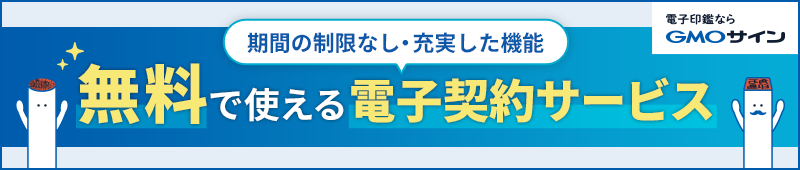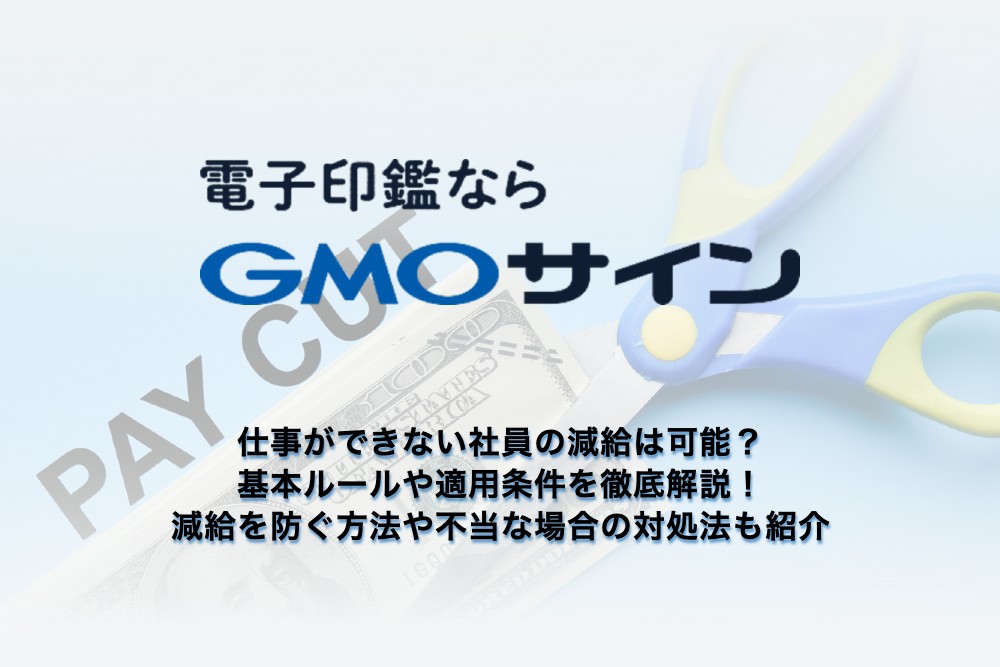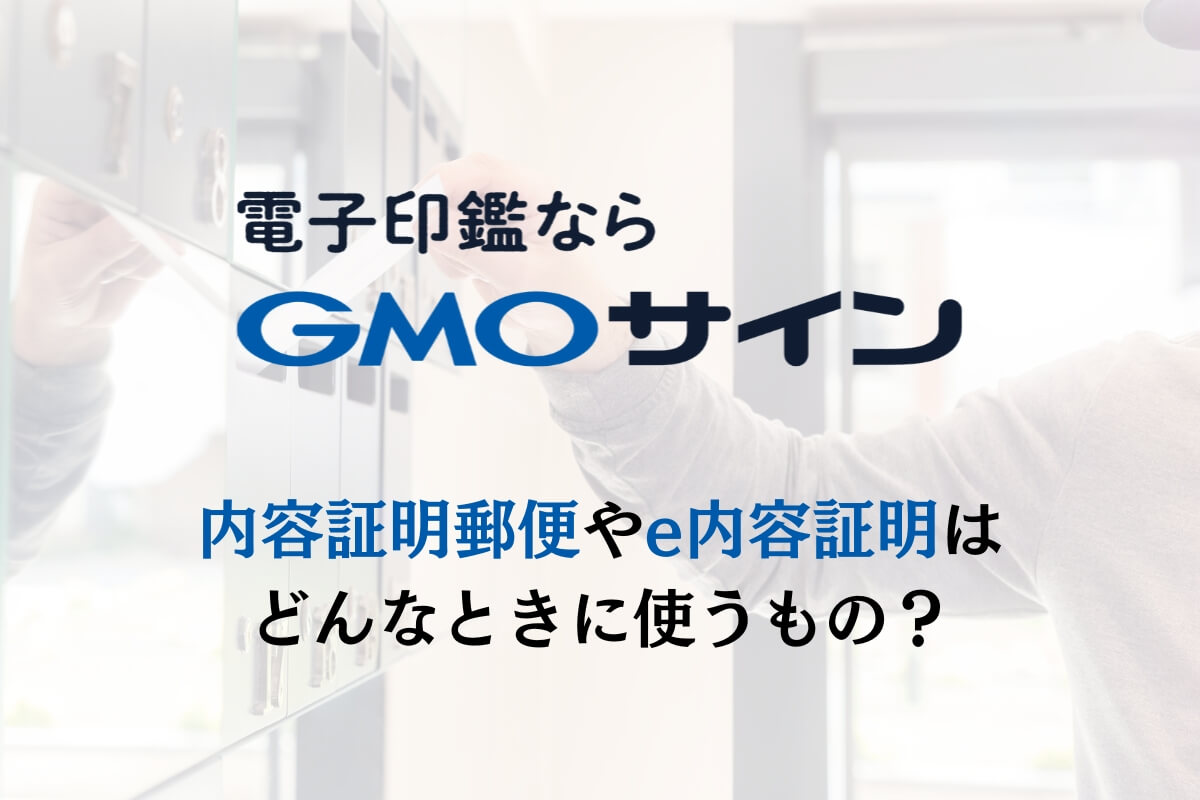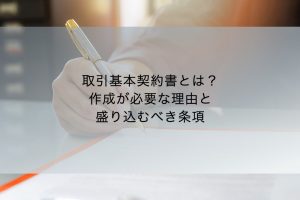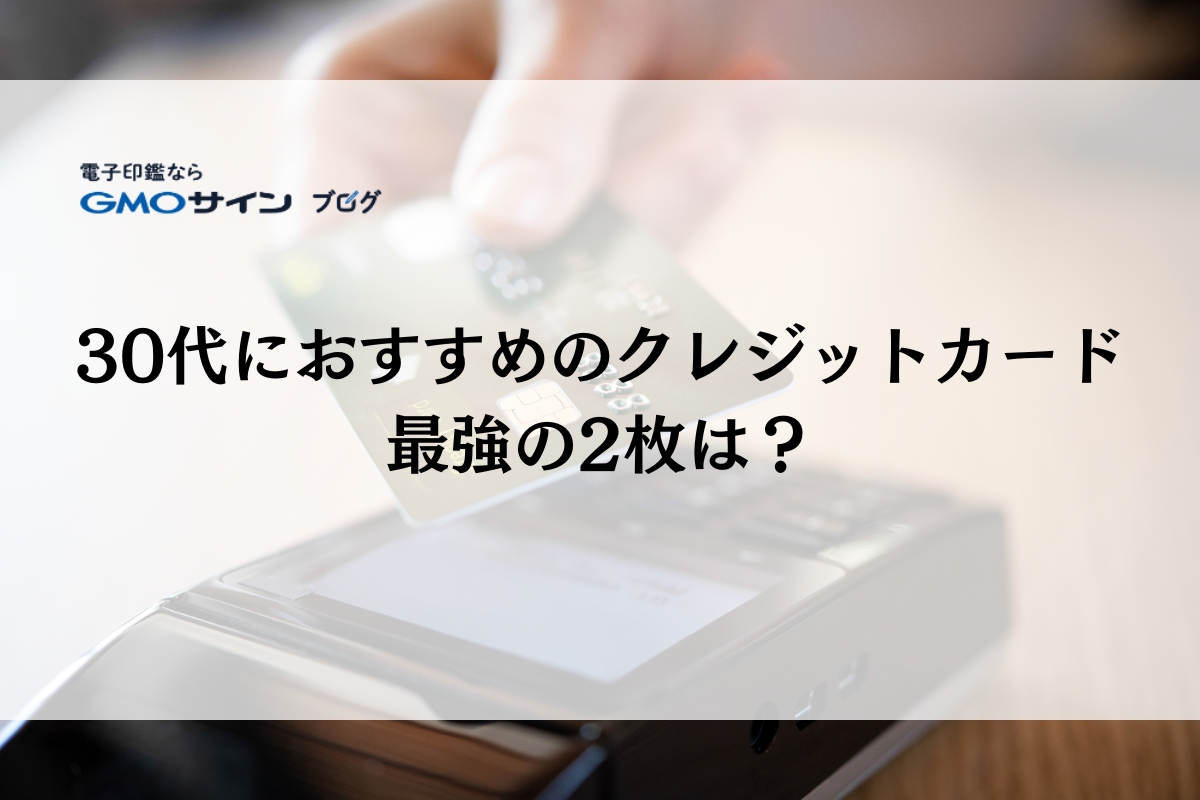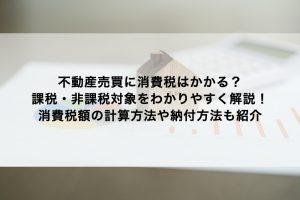近年、働き方改革の一環で、副業・兼業を推進する企業が増加傾向にあります。副業を検討している方のなかには、「副業を開始する際に、開業届を税務署に提出するべきか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
開業届を出すことでさまざまなメリットがありますが、同時にデメリットもあるため、慎重に検討するべきです。
この記事では、副業を予定している方へ向けて、開業届のメリット・デメリットを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
開業届とは?
開業届とは、新たに事業を開始した個人事業主が税務署に提出する書類のことです。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業届には、氏名・生年月日・マイナンバー・住所・職業・屋号などを記入します。
特に難しい項目はありませんが、職業の記入時には注意が必要です。職業欄には、自営業・フリーランスといった漠然とした表現ではなく、文筆業・イラストレーター・モデル・司会業・洋菓子販売業など、具体的な事業内容をイメージできる文言を記入しましょう。
なお開業届は、事業を開始してから1カ月以内に提出することが義務付けられています(提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、これらの日の翌日が期限)。
(参考:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
開業届の提出方法
開業届の提出方法には、以下の3種類があります。
- 税務署に持参して提出する
- 税務署に郵送する
- e-Taxのシステムを用いてオンラインで提出する
税務署の開庁時間は平日の8時30分から17時までですが、閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)や早朝・夜間であっても、時間外収受箱に投函することで手続きができます。なおe-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付が不要で、メンテナンス時間を除き24時間利用可能です。
(参考:国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
開業届を出し忘れても罰則は科されない
個人事業主は、起業から1カ月以内に所轄税務署に開業届を提出する義務があります。ただし罰則規定がないため、開業届を出さずに事業をはじめても刑事罰が科されることはありません。
開業届を税務署に提出することには、メリットとデメリットがあります。税制上の優遇措置などのメリットが得られるため、一定の売上が見込まれる場合は、開業届の提出がおすすめです。
一方、健康保険組合によっては開業届を出すことで扶養から外れたり、失業保険を給付できなくなったりする可能性があります。デメリットがメリットを上回る場合は、開業届を提出しないことも検討しましょう。
開業届を税務署に出すメリット
以下、開業届を税務署に提出することで得られるメリットを紹介します。
青色申告特別控除を受けられる
最大のメリットは、特別控除が受けられることです。開業届および青色申告承認申請書を税務署に提出したうえで、複式簿記で帳簿を作成・保存し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限までに提出すれば、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられます。
控除される金額および条件は以下のとおりです。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を作成する |
| 65万円 | 55万円の控除を受けるための条件を満たしたうえで、電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳について、優良な電子帳簿の要件を満たして、電子データとして保存すること)またはe-Taxによる電子申告を実施する |
青色申告では、課税所得額が減らせるため大きな節税効果が得られます。一定の売上が見込まれる場合は、開業届および青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
家族に支払った給与を経費として計上できる
青色申告者は、生計を一にしている家族・親族(15歳以上)に事業を手伝ってもらっていて、労務の対価として給与(青色事業専従者給与)を支払っている場合、支払った金額を必要経費に算入できます。必要経費として計上すれば、課税所得額が減らせるため、節税効果を得ることが可能です。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。無制限に必要経費に算入できるわけではなく、届出書に記載された金額の範囲内、かつ専従者の労務の対価として適正な金額でなければ認められないことにもご留意ください。
また青色事業専従者として給与の支払いを受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(参考:国税庁 No.2070 青色申告制度)
最大3年間赤字の繰越しが可能
青色申告者は、事業所得に損失(赤字)があり、損益通算しても控除しきれない金額(純損失の金額)が生じた場合、損失額を翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除できます。(参考:国税庁 No.2070 青色申告制度)
たとえば初年度に100万円の赤字となり、2年目に30万円の黒字・3年目に70万円の黒字が出た場合、2年目・3年目は初年度の赤字によって黒字を相殺できるため、課税所得額をゼロにすることが可能です。
なお前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しの代わりに損失が生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けられます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度であり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。掛金を支払えば、退職・廃業時に、共済金を受け取ることが可能です。
個人事業主の場合、税務署に開業届を提出したうえで事業所得を得て確定申告していなければ、小規模企業共済に加入できません。いつか訪れる廃業を見据えて、開業届を出したうえで小規模企業共済に加入し、掛金を支払うこともご検討ください。
くわえて廃業時に受け取れる共済金に関しても、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制面でメリットが受けられます。(参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済制度 制度の概要)
保育所の利用申し込み時に就労証明書の代わりになる
保育所(保育園)の利用を申し込む際には、就労証明書を提出する必要があります。個人事業主は、会社員などと異なり雇用主から証明書を発行してもらえませんが、確定申告書の控えや営業許可証の写し(飲食業・食品加工業など許認可が必要な業種・業態の場合)、開業届の控えなどで代用可能です。
ただし事業を開始した直後(初年度)の場合は、まだ確定申告を終えていないため、確定申告書の控えを提出できません。また許認可が不要な業種・業態(文筆業・イラストレーターなど)の場合は、営業許可証の写しも提出できないでしょう。このようなケースでは、税務署に開業届を出して控えを保存しておけば、代用可能です。
屋号名義の口座を開設できる
個人事業主は、本名の名義の口座(プライベート用の口座)を事業で利用しているケースもあるでしょう。ただしプライベートによる利用なのか、ビジネスにおける利用なのかを判別することが困難で、経理処理が困難になるためおすすめしません。
また屋号(ペンネームやビジネスネーム)で事業を営んでいて、振込先口座の名義が個人名の場合、取引先が「正しい口座なのだろうか」「振り込んでも大丈夫だろうか」と不安を感じることがあるかもしれません。
そのため、屋号で事業を営むのであれば、本名名義の口座ではなく、屋号名義の(または個人名と屋号を組み合わせた名義の)ビジネス口座を開設することも検討しましょう。
開業届を税務署に出すデメリット
開業届を提出すれば、さまざまなメリットが得られますが、デメリットもあります。開業届を提出することで考えられるデメリットを紹介します。
健康保険上の扶養から外れる場合がある
配偶者(夫または妻)の健康保険上の扶養に入っている方は、開業届を提出するかどうかを慎重に判断しましょう。
健康保険組合によっては、開業届を提出している場合は扶養から外れるケースがあります。扶養から外れてしまうと、国民健康保険に加入し、自分自身で保険料を納めなければいけません。
(参考:企業の窓口マガジン 個人事業主で開業届を出していないとどうなる?提出するメリットとデメリットを紹介)
失業保険の給付を受けられない可能性がある
失業保険は、会社などを退職してから次の職場に就職するまでの失業期間の生活を支援するための制度です。
開業届を税務署に提出すると、失業者ではなく個人事業主として扱われるため、失業保険の給付を受けられなくなる可能性があります。失業保険を満額受給したい場合は、失業保険の受給期間が満了してから事業を開始し、税務署に開業届を提出しましょう。
ただし再就職手当に関しては、再就職だけではなく、事業を開始することでも受給できる場合があります。以下のような要件を満たす場合は、税務署に開業届を提出することをおすすめします。
- 雇用保険の被保険者となる者を雇用して雇用保険の適用事業主となること
- 1年を超えて安定的に継続できる事業であること
なお要件は上記のほかにも存在するため、詳しくはハローワークへお問い合わせください。
(参考:北海道労働局 北海道ハローワーク 雇用保険の受給に関すること )
副業収入20万円以下であれば開業届を出さない方がいい場合もある
繰り返しにはなりますが、開業届を提出すれば、税制上の優遇措置(青色申告特別控除など)を受けられます。また開業届の控えは、保育所の利用を申し込む際に提出する就労証明書としても利用可能です。さらに屋号名義の口座を開設する際にも金融機関から提出を求められるため、本格的に事業をはじめて一定の売上が見込まれる場合は、税務署に開業届を出しておきましょう。
一定の売上とは、確定申告が必要とされる、副業収入が20万円を超えるかどうかを目安に判断するとよいでしょう。(参考:国税庁 確定申告が必要な方)
メリットとデメリットを正しく把握し、メリットがデメリットを上回る場合は開業届を提出し、デメリットが大きい場合は提出しないことも検討しましょう。
開業届は出さないほうがいい?メリット・デメリットをふまえて判断を
事業を営む方は、事業を開始してから1カ月以内に税務署に開業届を提出する義務があります。ただし、罰則規定はないため、提出しなくても刑事罰を科される心配はありません。
開業届および青色申告承認申請書を提出し、複式簿記で帳簿を作成・保存しておけば、税制上の優遇措置(青色申告特別控除、最大3年間の赤字の繰越しなど)を受けることが可能です。
また開業届の控えは、保育所の利用を申し込む際に就労証明書として使用できます。さらに、屋号名義の口座を開設する際に金融機関から控えの提出を求められるため、本格的に事業を営むのであれば、税務署に開業届を提出しておくべきです。
一方で開業届を出すと、健康保険組合によっては扶養から外れる場合があるといったデメリットもあります。失業保険を受給できなくなる可能性もあるため、提出するタイミングを慎重に見極めましょう。メリット・デメリットを比較したうえで、開業届を提出するかどうかを判断してください。