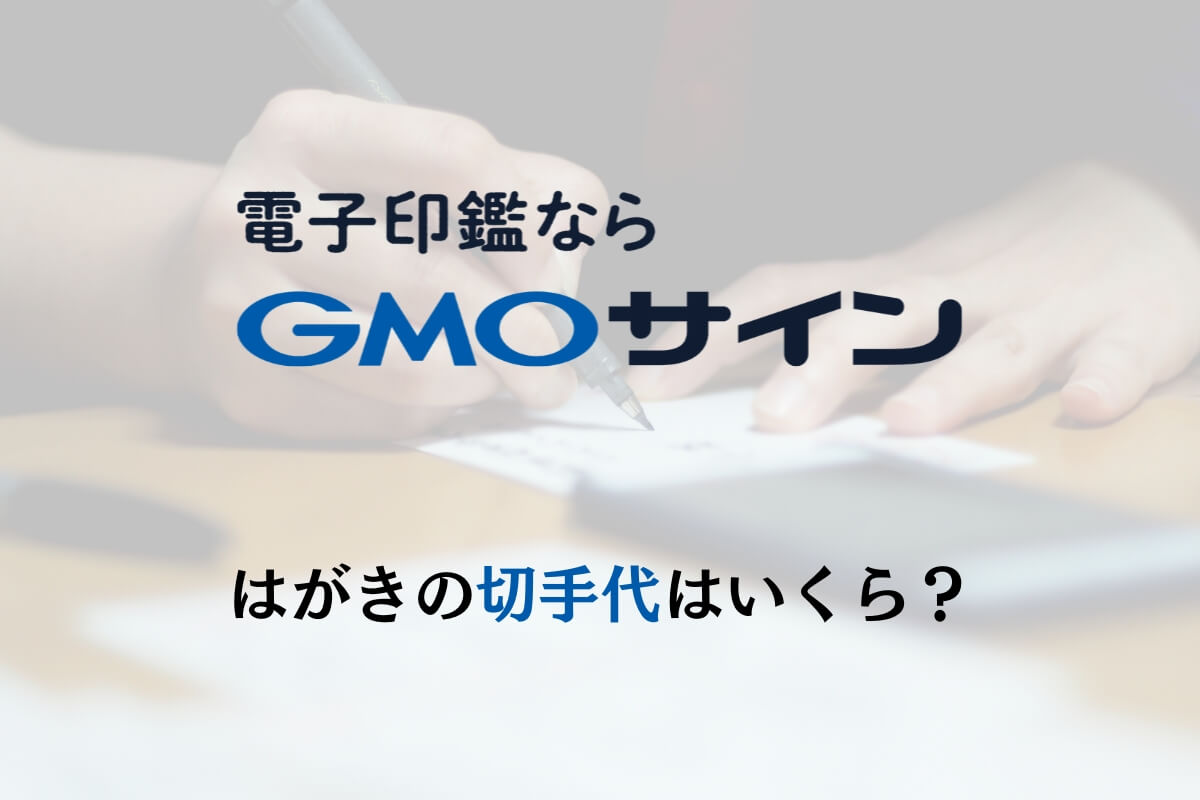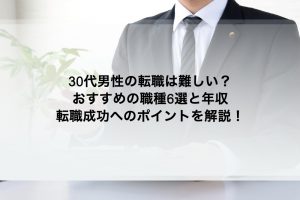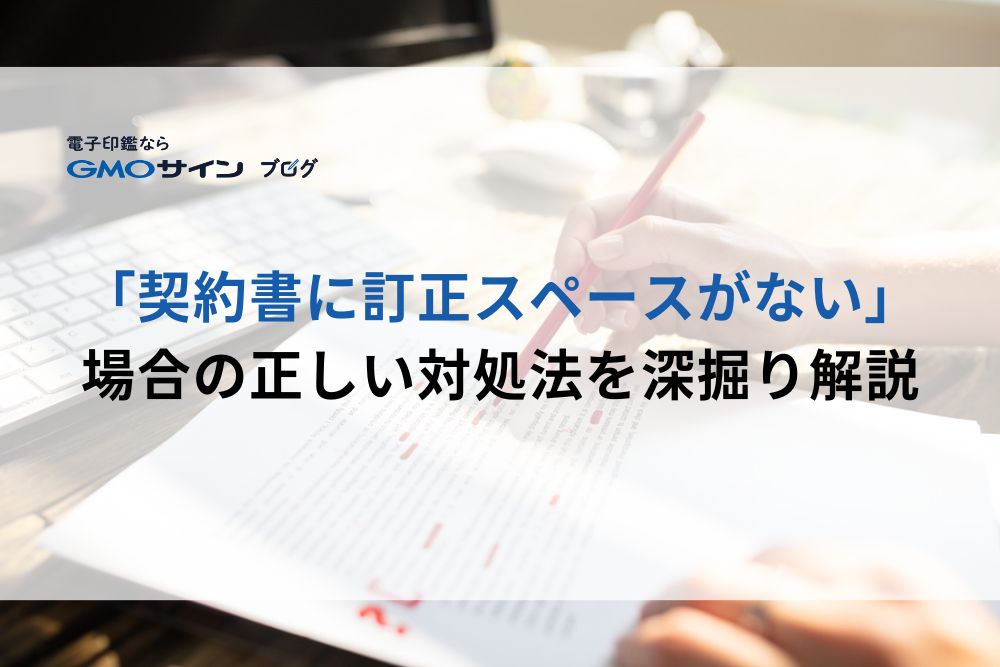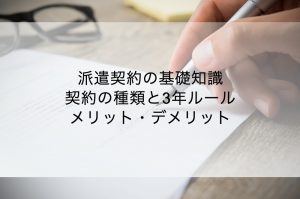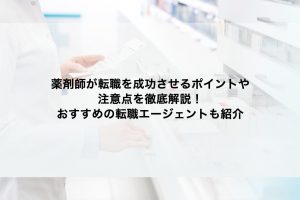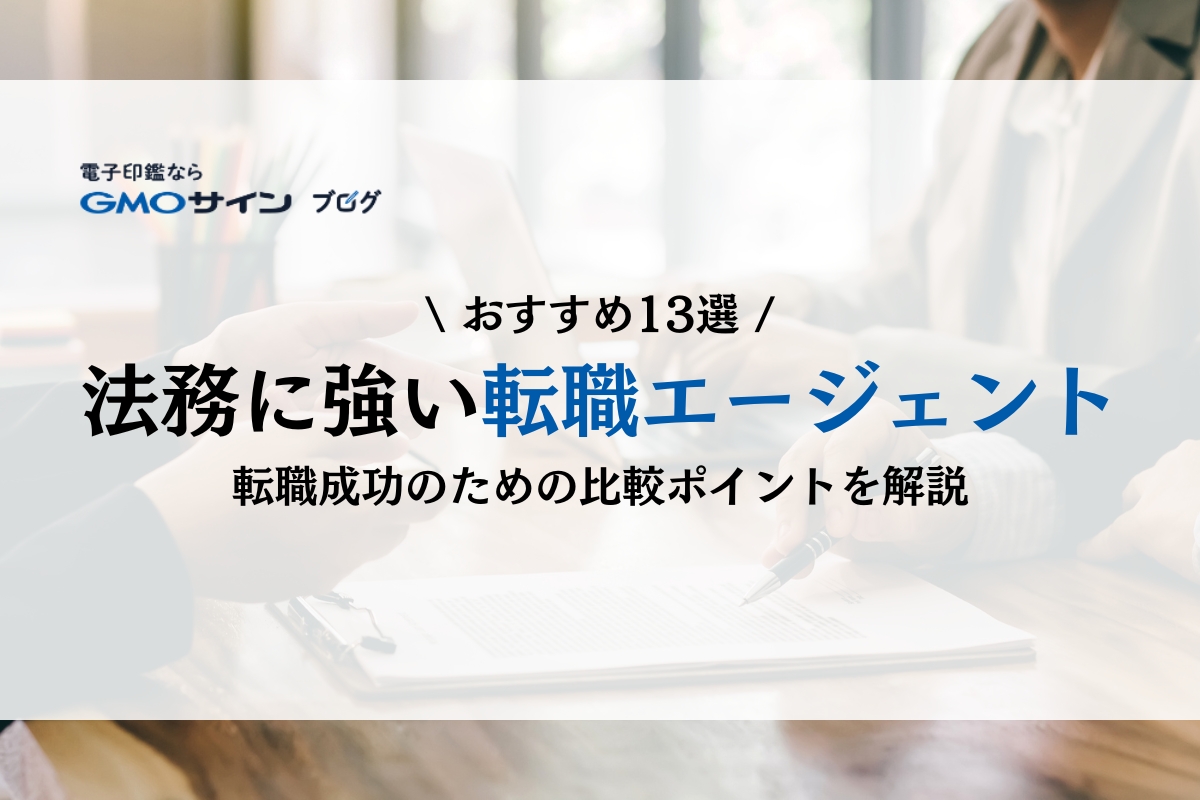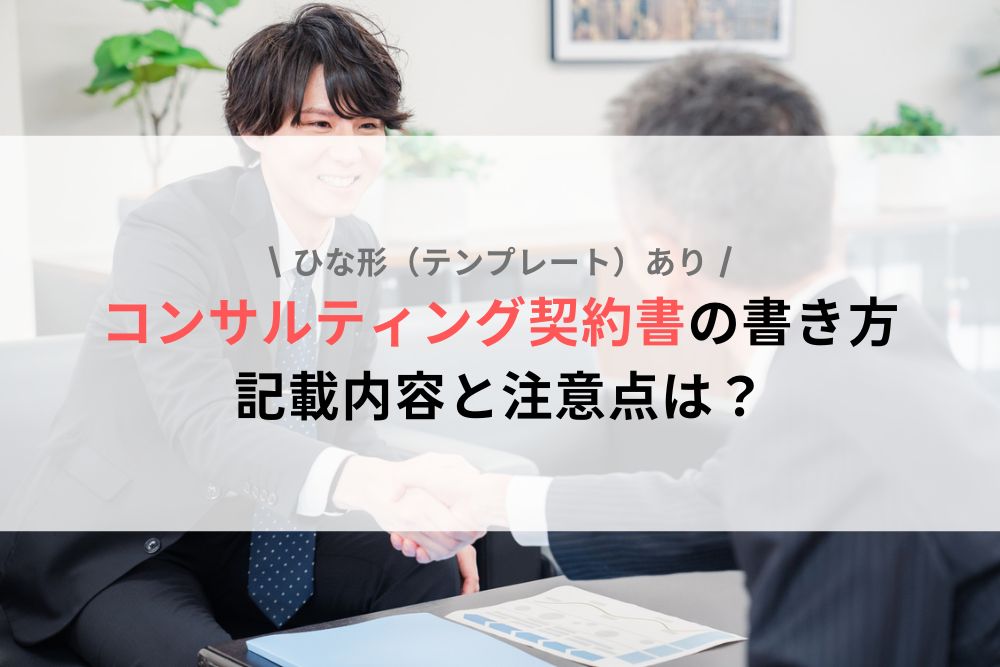「ハラスメントハラスメントとは具体的にどのような行為なのか、知っていますか?」パワハラやセクハラが社会問題となる一方、過敏な反応がハラスメントハラスメント(ハラハラ)という新たな問題を生んでいます。
本記事では、ハラハラの定義と具体例を解説します。ハラハラへの対策も解説しますから、職場内で発生するハラハラについて詳しく知りたい人は、参考にしてください。
ハラスメントハラスメントの定義
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは、正当な言動を過敏にハラスメントだと主張し、相手を萎縮させる嫌がらせ行為を指します。たとえば、上司の正当な業務指導や日常的なコミュニケーションを「パワハラ」や「セクハラ」と訴えるケースなどが該当します。
パワハラやセクハラなどに注目されがちですが、ハラハラについても理解を広げ、適切に対策をしていくのが重要です。
ハラスメントハラスメントが起きる背景
ハラスメントハラスメントが起きる背景には、社会全体でハラスメントに対する意識が高まった点が挙げられます。近年、パワハラやセクハラをはじめとした各種ハラスメントの深刻さが広まり、法改正や企業の対策が進みました。結果、被害者が声を上げやすくなり、保護される仕組みも整いつつあります。
一方で、正当な業務指導や日常的な会話に対して過敏に反応し「ハラスメントだ」と主張されるケースも増加しました。行き過ぎた訴えが、ハラスメント概念の濫用を生み出しています。
企業は正当な行為と不適切な行為を明確に区別する基準を設け、適切に対応しましょう。
ハラスメントハラスメントとパワハラの違い
ハラハラとパワハラは全く異なる概念です。ハラハラは、正当な注意や指導に対して「ハラスメントだ」と過剰に主張し、相手に心理的な負担を与える行為のことです。一方、パワハラは厚生労働省が定めた明確な定義が存在します。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
また、パワハラは法的にも対策が義務づけられており、労働施策総合推進法によって事業主に防止措置が求められています。ハラハラは法的な定めはないものの、ハラハラもパワハラと同様、職場に深刻な影響を与える問題です。
ハラハラとパワハラの違いを正しく理解し、状況に応じた適切な対応を心がけましょう。
ハラスメントハラスメントの具体例
職場では、正当な言動に対して過剰に「ハラスメントだ」と訴えるケースが増えています。しかし、どのような行為がハラハラに該当するのでしょうか。以下では、ハラハラの具体例を5つ紹介します。
正当な注意・指導を「パワハラだ」と主張する
正当な注意や指導に対して「パワハラだ」と訴えるケースは、ハラハラの代表例です。上司が部下に遅刻やミスを指摘するのは、組織の秩序を保ち、本人の成長を促すために不可欠です。たとえば、再発防止のためにミスの原因を分析し、改善点を伝えるのは正当な行為にあたります。
しかし、不快に感じたという感情のみでパワハラと主張される場面も少なくありません。正当な注意や指導をパワハラとされる状況が続くと、上司は萎縮して指導ができなくなり、職場の健全な成長を妨げます。正当な指導と不適切な言動の線引きが重要です。
プライベートな会話を「セクハラだ」と訴える
常識の範囲内でのプライベートな会話が、セクハラとして訴えられるハラハラも存在します。職場の雰囲気を和らげたり、信頼関係を築くために日常的な雑談を交わすことはよくあります。
趣味や休日の過ごし方などの話題は、自然なコミュニケーションの一部です。たとえば「最近どこか旅行に行きましたか?」という会話も、親しみのあるやりとりとして活用されます。
しかし、個人の価値観やプライバシーに対する意識が高まるなかで、質問が不快に感じられ、セクハラとして訴えられる場合も少なくありません。相手の反応を尊重し、会話の距離感を調整する意識が求められます。
業務外での付き合いや飲み会への誘いを「強要だ」と訴える
ハラハラには、業務外の飲み会やイベントへの誘いが「強要だ」と訴えられるケースも該当します。会社では組織としての一体感を育てるため、懇親の場を設けるのは珍しくありません。たとえば、新入従業員の歓迎会や繁忙期明けの慰労を目的とした飲み会などは、従業員同士の交流を深める良い機会です。
しかし「上司からの誘いだから断りづらい」と受け取られ「参加を強制された」と感じる従業員も存在します。ていねいな声かけだったとしても、受け手の主観によってハラスメントと捉えられるリスクがあるのです。誘う側は「参加は自由」と明確に伝え、無理のない関係性を意識しましょう。
スキルアップのためのノルマ設定が「過重だ」と訴える
スキルアップを目的としたノルマが「過重だ」と訴えられるのも、ハラハラになる場合があります。成長を促すために、少し高めの目標を設定するのは一般的な方法です。たとえば、前年より10%多い営業成果を求めるなど、現実的な範囲のノルマであれば本人の力を引き出す効果があります。
しかし、個人の感じ方や状況によっては「プレッシャーが強すぎる」と受け取られ、精神的な負担を理由にハラスメントとされるケースがあります。
ハラスメントハラスメントが職場に与える影響
ハラハラが職場で蔓延すると、管理職や従業員がコミュニケーションを取りづらくなり、職場に大きな悪影響を及ぼします。以下では、ハラハラが職場に与える影響を5つ解説します。
管理職や上司が部下への指導をためらうようになる
管理職や上司が部下への指導をためらうようになるのは、ハラハラによる深刻な影響の1つです。正当な注意やアドバイスは部下の成長を促し、組織の力を底上げするために重要です。たとえば、繰り返し遅刻をする従業員に対してルールを再認識させる指導は、企業活動の基本といえます。
しかし、最近では指導が「パワハラだ」と受け取られることを恐れ、何も言えなくなる上司が少なくありません。結果、従業員の成長機会が失われ、組織全体の生産性を低下させる可能性があります。
指導をためらわないためには、正当な指導とハラスメントの違いを全員で共通認識を持ち、記録をしたり伝え方を工夫したりするのが大切です。
業務に必要なコミュニケーションが減り連携が取りにくくなる
ハラハラは業務に必要なコミュニケーションを激減させ、連携が取りにくい環境を形成します。
言動が過剰に問題視されるのを恐れ、従業員同士が話すこと自体を避けるようになると、日々の業務連携に支障が出ます。たとえば注意や依頼、確認事項であっても「ハラスメントだ」と受け取られるかもしれないという不安から、発言を控える場面が増えるのです。
発言を控える状況が続くと、仕事の効率だけでなく、組織全体の信頼関係にも悪影響を及ぼします。
上司の業務負担が増える
上司の業務負担が増えるのも、ハラハラがもたらす影響の1つです。近年、正当な業務指示であっても「ハラスメント」と誤解される可能性があるため、指示自体を避ける傾向があります。部下に任せるべき仕事を上司が抱え込むため、過剰な業務量になりかねません。
ハラハラをする恐れがある従業員には、上司1人で対応せず、複数人で対応していく必要があるでしょう。
メンタル不調により貴重な人材が休職・離職に追い込まれる
ハラハラはメンタル不調により、貴重な人材が休職や離職に追い込まれる事態を引き起こします。ハラハラを恐れて上司が業務を抱え込み続けると、心身への負担が蓄積されやすくなります。
本来は部下に任せるべき仕事まで引き受けた結果、過労やストレスで健康を損なうケースが少なくありません。たとえば長時間労働が常態化すれば、労災や損害賠償、労働基準法違反に発展する可能性もあります。
働きやすい職場環境を維持するには、業務の見直しや支援体制の強化をおこない、上司と部下の双方が無理なく働ける環境を整えるのが重要です。
ハラスメントハラスメントの5つの対策法
ハラハラを防ぐには、組織全体での正しい知識の共有と、明確な対処体制の構築が不可欠です。以下では、ハラハラへの対策を5つ紹介します。
ハラスメントハラスメントの基準を記載したガイドラインを策定する
ハラハラの基準を記載したガイドラインの策定は、重要です。基準を記載したガイドラインがあると、従業員が「これはハラスメントに該当するのか」と迷ったときにすぐ確認できます。
パワハラやセクハラ、マタハラは厚生労働省の指針に沿って具体的に記載するとよいでしょう。また、トラブルが起きた際もガイドラインがあれば、企業側がどのような管理体制を整えていたのかが説明しやすくなります。
定期的にハラスメント研修を実施する
定期的にハラスメント研修を実施すると、従業員の正しい理解が深められます。ハラハラのリスクを軽減するには、正しい知識を持つのが重要です。
ハラスメント研修では「ハラスメントは許される行為ではないが、正当な指導を妨げるハラハラも問題である」というメッセージを明確にするのが重要です。一度きりで終わるのではなく定期的に実施すると、正しい知識が定着し、職場全体の意識改革につながります。
ハラスメント相談窓口を設置する
ハラスメント相談窓口を設置するのは、ハラハラ対策に有効です。ハラスメント相談窓口があると、問題の早期発見と適切な対応が可能になります。ハラスメントに関する正確な知識を持った担当者を配置し、内容の客観的判断と迅速な対応ができるようにしましょう。
たとえば判断が難しいケースも、社内の人事部と連携しながら冷静な対応が取れる体制を整えておくと安心です。ハラハラに関しても安心して声を上げられる環境があると、健全な職場を保てるでしょう。
過剰な訴えを繰り返す従業員への対応体制を整える
過剰な訴えを繰り返す従業員への対応体制を整えるのも、企業にとって必要な取り組みです。近年のハラスメント問題は複雑化しており、一見すると正当な訴えに見えても、実はハラハラであるケースがあります。
たとえば、正当な業務指導を何度も「ハラスメントだ」と訴えるような従業員に対しては、毅然とした態度が必要です。不当な訴えによって組織全体が萎縮しないよう、どのような手順で対応するか、対応フローや判断基準を社内で共有しましょう。
安易に謝罪しない
安易に謝罪しない姿勢を持つのも、ハラハラ対策で重要です。正当な指導を行ったにもかかわらず、相手の反応だけを理由にその場で謝罪してしまうと、相手に誤ったメッセージを与えかねません。たとえば、「自分の主張が通った」と感じた相手が主張をエスカレートさせる可能性があります。
指導内容が妥当であると確信できる場合には、客観的な証拠を整えたうえで、人事部やハラスメント相談窓口と連携して対応しましょう。
ハラスメントハラスメント発生時の対応フロー
ハラハラは事前に対応フローを知っていると、発生時に職場の信頼性や公正性を守ることにつながります。以下では、ハラハラ発生時の対応フローを解説します。
事実関係を調査する
ハラハラ発生時には、事実関係を調査しましょう。事実関係の調査では感情や主観に流されず、冷静に状況を把握する姿勢が求められます。
たとえば当事者双方の話だけでなく、同じ部署にいる第三者やその場に居合わせた従業員などからのヒアリングもおこない、状況を多角的に把握します。
情報が一方に偏ると判断を誤りかねません。調査では言動の背景やタイミング、関係性なども含めてていねいに確認しましょう。公平性と透明性を意識した調査姿勢が、後の対応の信頼性につながります。
調査報告書を作成する
調査報告書を作成するのは、判断の根拠を明確に示すために欠かせません。調査報告書には聞き取り内容や証拠資料をもとに、客観的かつ具体的な情報を整理して記載します。
たとえば、誰がどのような発言をし、どのような反応があったのかなどを時系列でまとめると、事実が見えやすくなります。調査報告書は、諮問委員会や経営層の判断材料となる重要な資料です。曖昧な記述や感情的な表現は避け、事実に即した内容を心がけましょう。
ハラスメントハラスメント認定がされた場合、厳正な処罰を下す
ハラハラと認定された場合は、加害者に対して厳正な処罰を下す必要があります。しかし、単に処罰を下すのではなく、ハラハラの何が問題だったのかを明確に伝え、本人に理解させましょう。
一方的な処罰ではなく、教育的なアプローチを取り入れると、同じ行動は繰り返さない意識を根づかせられます。
従業員のケアを行う
ハラハラ発生時は、従業員のケアを行うのが重要です。被害者は精神的に深いダメージを負っている場合が多く、適切なサポートが欠かせません。
たとえば、社内の面談制度を活用したり、必要に応じて外部のカウンセラーを紹介したりなど、安心して職場に戻れる環境づくりをしましょう。また、調査の結果や補償内容、加害者に対する処分の方針なども伝え、不安や疑念を残さない配慮が必要です。
ハラスメントハラスメントに関するよくある質問
ハラスメントとハラハラの違いは?
ハラスメントと、ハラスメントハラスメントの違いは以下のとおりです。
- ハラスメント
「嫌がらせ」や「いじめ」行為。職場においては、上司や同僚の言動が本人の意思とは関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を侵害したりする行為のこと。 - ハラスメントハラスメント
自分に向けられた行動や発言に対して過剰に反応し、「ハラスメントだ」と主張する行為。実際にはハラスメントに該当しない、または軽微な言動を過度にハラスメントとして扱う。
最大の違いは、ハラスメントが「実際に行われる嫌がらせ行為」であるのに対し、ハラハラは「ハラスメントの概念を過度に拡大する行為」である点です。
日本の三大ハラスメントは?
三大ハラスメントとは、法律で防止措置が義務付けられている以下の3つです。
- パワーハラスメント(パワハラ)
職場での優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの - セクシュアルハラスメント(セクハラ)
性的な言動や不快感を与える行為 - マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児を理由に不利益な扱いをすること。男性に対する「パタニティハラスメント」も含まれる
三大ハラスメントは、それぞれ労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で禁止されており、企業には防止措置を講じる法的義務があります。
言ってはいけない言葉のハラスメントは?
言葉によるハラスメントはおもに以下のようなものがあります。
| ハラスメントの種類 | 概要と具体例 |
|---|---|
| モラルハラスメント | 言葉や態度による精神的な虐待や人格否定 例)「お前には何もできない」「存在する価値がない」 |
| パワーハラスメント | 人格否定や長時間の厳しい叱責 例)「お前は新入社員以下だ」「給料泥棒」 |
| ジェンダーハラスメント | 性別に関する固定観念や差別的な言動 例)「女性らしくない」「男のくせに」 |
| レイシャルハラスメント | 人種・民族を理由とする差別的な発言 例)「ハーフなのに英語を話せないの?」「外国人は会議に出るな」 |
| リストラハラスメント | 解雇・退職をちらつかせて精神的圧力をかける発言 例)「無能だからリストラ対象になるんだよ」「このままだと、あなたを切るかも」 |
言葉によるハラスメントは受け手に精神的なダメージを与えるため、絶対に言わないようにしましょう。
ハラスメントハラスメントを正しく理解して毅然とした態度を取ろう
この記事では、ハラハラの定義や具体例、対策について解説しました。ハラスメントハラスメント(通称ハラハラ)とは、正当な言動を過敏にハラスメントだと主張し、相手を萎縮させる嫌がらせ行為を指します。
たとえば正当な注意や指導であっても、パワハラやセクハラなどと訴え、会社全体に悪影響を及ぼします。パワハラやセクハラなどに注目されがちですが、ハラハラについても理解を深め、適切な対策をしましょう。