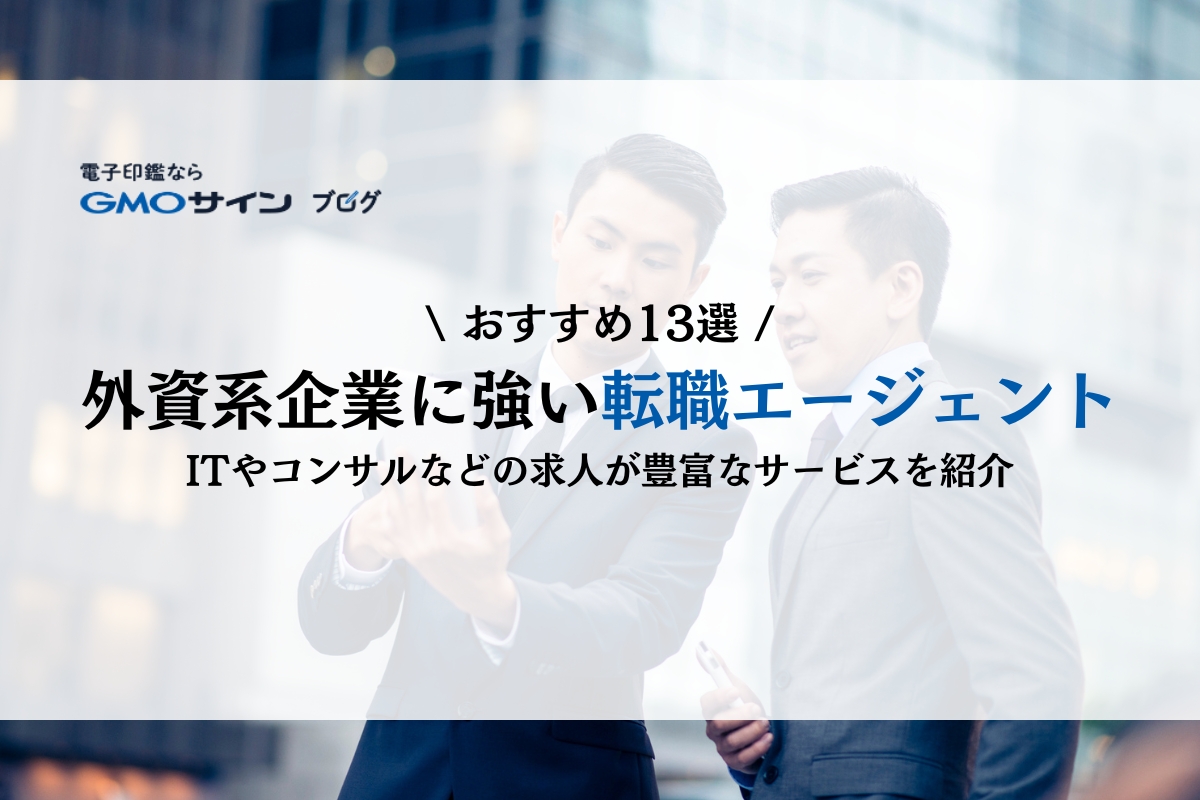\ 新プランリリース記念 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /
\ 新プランリリース記念 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー


企業買収(M&A)などを行うことで、企業価値を高めたり、自社にはない技術やノウハウを取得したりすることができます。
買収により生まれる企業に合弁会社というものがありますが、合弁会社という言葉を聞いたことがあっても、それが何を意味するのか、利用するメリットはあるのか、といったことについてあまりよく知らないという人は多いのではないでしょうか。ここでは、日本国内で適用される会社法にはない合弁会社について解説します。
合弁会社とは、複数の企業(2社以上)が一緒に事業を行うために、互いが出資をして新しく設立する会社、もしくはM&Aなどにより買収して共同で経営を行う会社を指します。
日本は長年にわたって護送船団方式と呼ばれる方法で、国内の企業活動を保護してきました。当時、外資系企業が日本で企業活動を行うためには日本企業と共同で出資を行い設立した会社で行うことが求められていました。
これがいわゆる合弁会社です。その後、経済のグローバル化に伴い、護送船団方式はなくなり、外資系企業も日本の市場に参画できるようになりました。
合弁会社を設立する場合、出資比率はどのようになるのでしょうか。合弁会社は双方が対等に出資し合うため、基本的には50%ずつの出資比率となります。もちろん、50%ずつでなければならないという規定はないため、話し合いにより出資比率を変えることはできます。
たとえば、A社が合弁会社の事業に多く関わる場合に、A社の出資比率を多くし、従属する側のB社の出資比率を少なくするというケースが考えられます。
出資比率に差を設けることで、意思決定をする際に出資比率の高い会社が決定権を行使しやすくなり、スムーズに物事を進めることができます。
会社法で定められている企業形態は4つあります。
合弁会社はこれらの企業形態には含まれておらず、あくまで2社以上の会社が共同で出資し経営を行う会社を指します。
合弁会社として事業活動を行うことにはどのような利点があるのでしょうか。合弁会社のメリットについてみていきましょう。
合弁会社を活用することで、たとえば現地法人を設立し、企業活動が進めやすくなります。
現地企業と合弁会社を設立することになるので、諸外国の法律に精通している地元企業をパートナーに迎えることにより商取引などのノウハウを学べますし、契約などにおいてはパートナー企業に依頼するといったことが可能です。
海外での企業活動を円滑に行う点で、合弁会社の活用に大きなメリットがあるといえます。
新たな事業を展開する場合、事業が円滑に行くかどうかは未知数です。失敗する可能性もあります。もし自社がすべてを手掛ける場合、万一事業が立ち行かなくなったとき、損害は全て自社が負うことになってしまいます。
このようなケースであっても、合弁会社を活用することで、損害のリスクを抑えることが可能です。出資を共同で行うことから、出資のための資金を抑えることができるというメリットもあります。
たとえば合弁会社の設立により、自社が有していない技術やサービスを手に入れられるというメリットがあります。
M&Aの目的の1つはまさにそれで、自社にはないサービスやノウハウを手に入れることで、企業価値を高めたり、新たな販路が拡大できたりするようになります。
メリットだけではなく、合弁会社のデメリットやリスクについても把握しておく必要があります。順に見ていきましょう。
合弁会社は共同経営の形態を取るため、物事を決定する際、基本的には出資している双方の会社に意思決定権があります。
決定する際の方向が同じであれば衝突が生じる可能性は少ないですが、双方の利害関係が絡んでくるときに、話し合いがまとまりにくくなることがあります。
一方はできるだけ速やかに意思決定を下したいのに、もう一方はなかなか同意してくれないため、物事が進まないということもあるでしょう。
別のデメリットとして、情報漏えいのリスクもあります。自社がどんなに機密情報を漏洩しないように注意したとしても、もう一方が情報管理に疎かったり、社員が情報を持ち逃げして売ってしまったりといったリスクがあります。
合弁会社でなくてもこのようなリスクは常に存在していますが、2社以上の企業が経営に参画することになるため、リスクが高くなるというデメリットも把握しておく必要があります。
合弁会社を設立するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
最初に求められるのが、合弁会社に参画する会社を選ぶことです。
候補となる会社の情報をしっかりと把握することにより、その後の経営で生じる可能性のあるリスクを抑えられます。具体的には、経営健全性、社風、風土、これまでの実績などを調査しておくことをおすすめします。
合弁会社の設立にあたって、基本合意の締結が必要になります。基本合意書を作成し、双方が合意する形で合意を結びます。
合意の締結にあたっては、出資比率や法人の形態、収益の分配といった事項を決定していくことになります。
基本合意の締結に続いて、合弁会社を設立するための契約書締結の段階を踏みます。基本合意でお互いに合意した事項以外に、役員の選出、遵守すべき事項、経費の負担といった事柄を決定します。
合弁会社の設立契約書を締結することで、合弁会社が立ち上がり、運営が始まります。
合弁会社を設立するおもなメリットは、一般的に以下の点が挙げられます。
ジョイントベンチャー(JV)と合弁会社は非常によく似た意味で使われ、密接に関連していますが、厳密には少しニュアンスが異なります。
複数の企業(または個人、団体など)が、特定の目的(例:新規事業の立ち上げ、共同での技術開発、大規模プロジェクトの遂行など)のために、互いの資源(資金、技術、ノウハウ、人材など)を持ち寄って行う共同事業そのものや、その事業を行うための「組織体を指す広い概念」です。
ジョイントベンチャーを遂行するための具体的な形態の1つで、参加する企業が共同で出資して新しく会社を設立するか、あるいは既存の会社を買収して共同で経営する場合の「会社」のことを指します。
合弁会社はいくつかの問題点やデメリットも抱えています。おもなものは以下のとおりです。
これらの問題点を事前に理解し、設立時の契約で明確なルールを定めたり、パートナー企業と十分なコミュニケーションを取ったりすることが、合弁会社を成功させるためには重要になります。
合弁会社にはメリットとデメリットがあるため、しっかりと把握した上で、自社にとって本当に必要かどうかを見定めてから踏み切るのが安全です。
合弁会社を設立することで、経営力を増強し、より収益を上げられるなどメリットがありますので、利点を強く感じる場合は、前向きに検討していくとよいでしょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。