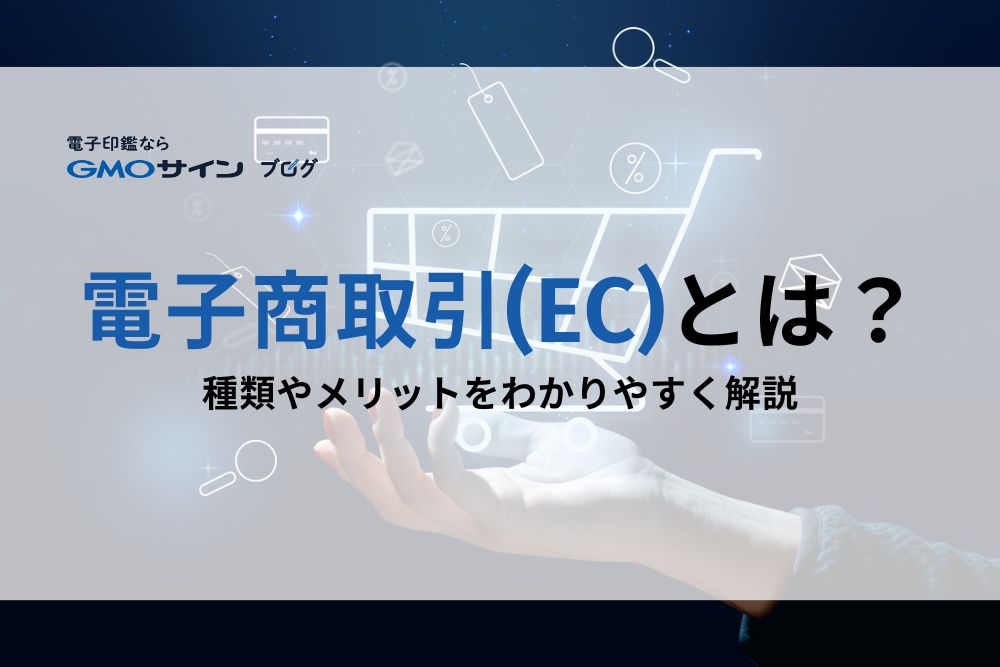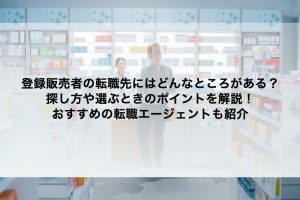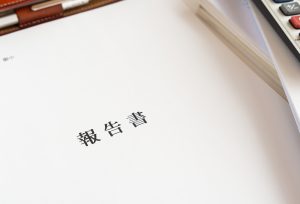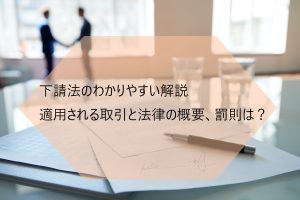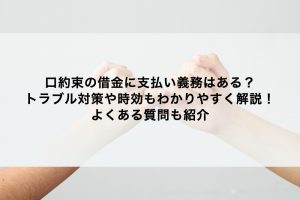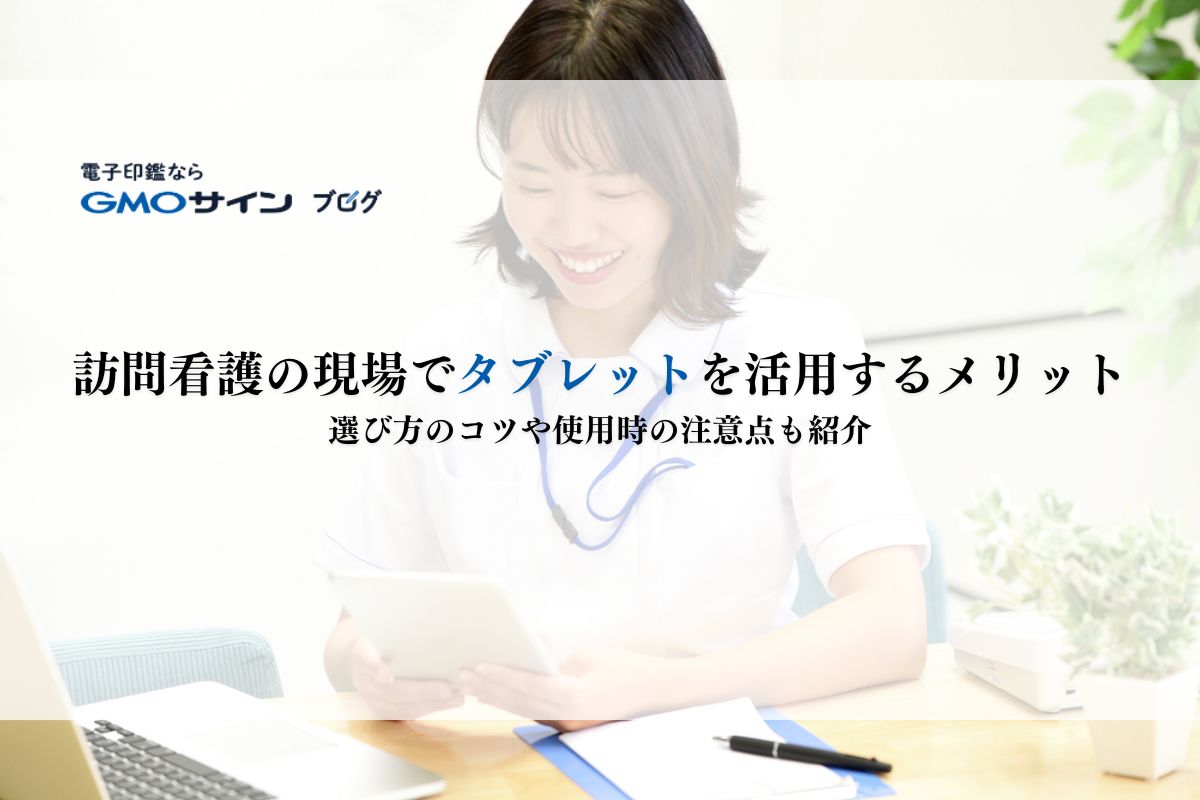ニュースなどで「コンプライアンス」という言葉を耳にしたことがあるという人は多いのではないでしょうか。コンプライアンスとは法令遵守という意味の言葉で、現在では企業倫理や社会道徳など法令にとどまらないところまでカバーするために用いられることが増えています。
コンプライアンスが具体的にどのようなことを意味するのか、その徹底のためにどのような対策を講じておくべきなのかについて理解しておくことは、企業活動を行ううえで欠かせません。その理解の助けとなるよう、この記事ではコンプライアンスの意義や事例について解説します。
コンプライアンスとは
コンプライアンスという言葉の辞書的な意味は法令遵守ですが、現代ではその意味は多様化しつつあります。
すなわち、社会規範や社会道徳といった意味合いも含まれることがあり、捉え方によっては株主をはじめステークホルダーの利益や要請に見合った活動といった意味まで含めることもあります。
コンプライアンスが重視される理由
コンプライアンスという言葉や考え方が注目を集めるようになったのは、1990年代または2000年代以降と考えられます。バブル崩壊やバブル崩壊以降の金融機関の破綻、企業の不祥事などが続出し、企業経営に対する問題意識の高まりが見られました。
また、インターネットの発展・普及もコンプライアンス重視に至った背景として挙げられます。企業に対する監視の目が厳しくなり、何か不祥事があればネットで情報発信される懸念が高まっています。
もし問題が広まれば、場合によっては風評被害で大きなダメージを受けかねません。そのようなこともあり、コンプライアンス重視の企業が増えているといえるでしょう。
コーポレートガバナンスとの違い
コンプライアンスと似た言葉に、コーポレートガバナンスという言葉があります。コンプライアンスが法令遵守を意味する一方、コーポレートガバナンスは法令遵守のための仕組みづくりを意味しており、後者は前者の手段のような位置づけと考えられます。
もちろん、たとえば不正行為を防止し効率的な経営を進めることでステークホルダーの利益を最大化するというゴールは同じであり、両者は強く関係しあっています。
内部統制との違い
また、内部統制もコンプライアンスに関連するものとして挙げられます。内部統制とは、適正な業務を担保するための体制を構築するシステムを指します。
コンプライアンスという、いわば「あるべき姿」を目指すための手段の一つが内部統制といえるでしょう。
コンプライアンスリスク事例について紹介
企業経営においては様々なリスクが存在しますが、コンプライアンスリスクには特に注意する必要があります。というのも、コンプライアンス違反により、非常に大きな悪影響を受けるおそれがあるためです。
ここでは、コンプライアンスリスクに関する事例をいくつか紹介します。
労務リスク
まず挙げられるのは、労働問題が発生するリスクである労務リスクです。近年の働き方改革の推進などにより、パワハラやセクハラ、長時間残業など労働基準法をはじめとした法令に抵触するような実態が広く認識されるようになっています。
法令に明らかに違反するものを防ぐべきなのはもちろんのこと、法令の趣旨を踏まえれば望ましくないということについてもきちんと対策をし、不適切事例が発生しないように努めることが会社にとっては結果的にプラスに働きます。
情報漏えいリスク
また、インターネットの普及でますます高まってきているリスクである情報漏えいリスクも挙げられるでしょう。
たとえば、顧客の個人情報や取引先に関する情報などが漏えいすることは重大なコンプライアンス違反となり、会社自体だけでなく社会に対しても大きな影響が及ぶことになるため、徹底的に対策を講じることが大切です。
直接的な経済的な損失だけでなく、信用を大きく損ねることになるため、十分な予防策が欠かせません。
契約違反リスク
契約違反に関するリスクも考えられます。事業を行う際、効率良く進めるために取引先と協力するケースは多くあると思いますが、取引にあたって締結する契約を遵守せず、契約違反を犯してしまうリスクも考慮する必要があります。
故意による違反はもってのほかですが、過失による違反についても避けることが会社にとっては大切です。そのためには、社内の法務部などが中心となって、契約違反リスクを最大限に抑える取り組みを進め、コンプライアンス違反が起こらないようにすることが欠かせません。
法令違反リスク
コンプライアンスという言葉が法令遵守を意味するように、法令違反リスクを考えることも欠かせません。
会社として活動を行ううえで直接関係する法令のほか、自社が事業を展開している業界と関連の強い法令についても十分に理解し、思わぬところで法令違反を犯さないように常に意識する必要があります。
不正会計リスク
会計・経理の点でも法令違反を犯さないようにすることが大切です。ご存じのように、業績不振時の粉飾決算など、不正会計に関する不祥事は少なくありません。企業の信用を失墜させることのないよう、常に適正な会計処理・報告が不可欠です。
コンプライアンスのために考えるべき対策とは?
コンプライアンスに反した行動をすれば、会社に大きな影響を与えかねませんし、場合によっては経営継続が難しくなることも考えられます。
そのため、コンプライアンス体制を社内でしっかりと構築することが大切です。最低限必要な方法をいくつか見ていきましょう。
最新情報をキャッチアップする
コンプライアンスに関連する法令は時代の移り変わりによって日々変わっていきます。そのため、関連法規の改正があった際にその情報をキャッチアップできる体制を構築しなければなりません。
たとえば、法務担当者をつけるなど人員を配置し、最新情報をチェックできるようにしておきましょう。資料を随時確認するだけでなく、関連するセミナーに参加することで積極的に情報を取りに行く姿勢も必要です。
社内規定・業務マニュアルを作成する
コンプライアンスの意識を従業員に徹底するためにも、社内規定や業務マニュアルを作成することも大事です。まだ規定やマニュアルなどを作っていないのであれば、法務担当者を軸にして早めに作成しましょう。
コンプライアンスに関する一般的な遵守規定を作り、そこから部門ごとの規定を作るなどマクロからミクロの順番で作成するのがおすすめです。また先ほども紹介したように、法令はその都度改正される可能性があります。
法令が改正されれば、その内容に即した規定やマニュアルも変更しアップデートすることを忘れないようにしましょう。さらに、社内規定やマニュアルが変更された場合には、社内で周知することも徹底しなければなりません。
窓口を設置する
もし社内で違法行為が横行した場合、早期発見・早期対策できればそのダメージも最小限に抑えられます。そこで、不正行為に関する情報を従業員が通報できる体制を築いておく必要があります。
内部通報窓口を設置すれば、早期に問題が発覚でき対処も可能です。もちろん、窓口を設置する際には、中立な立場で対応できる担当者を起用しなければなりません。
コンプライアンスに関するよくある質問
コンプライアンス違反の具体例は?
コンプライアンス違反は、企業活動における法令違反だけでなく、就業規則や社内規程、企業倫理や社会規範に反する行為全般を指します。
非常に多岐にわたりますが、具体的な例をいくつか挙げます。
| 領域 | 具体例 |
|---|---|
| 労務関連 | ・長時間労働、未払い残業 ・ハラスメント ・不当解雇、雇い止め ・労働安全衛生法違反 ・差別 |
| 情報管理関連 | ・個人情報漏洩 ・機密情報漏洩 ・不正アクセス ・目的外利用 |
| 会計・取引関連 | ・粉飾決算 ・不正経費の使用 ・インサイダー取引 ・談合、カルテル ・下請法違反 ・贈収賄 |
| 知的財産権関連 | ・著作権侵害 ・商標権侵害 ・特許権侵害 |
| 環境関連 | ・不法投棄 ・環境汚染 ・規制基準超過 |
これらの例は一部であり、業種や企業規模によっても直面するコンプライアンスリスクは異なります。
企業は自社の事業活動に関連する法令や社会規範を正しく理解し、従業員への教育や内部統制システムの構築を通じて、コンプライアンス違反の防止に努めることが重要です。
コンプライアンスの3原則は?
多くの企業や専門家がコンプライアンスを推進する上で、特に重要視する共通の考え方や要素があり、それらを「3つの柱」や「重要な要素」として説明することがあります。
これはコンプライアンスの最も基本的な意味であり、法律、政令、条例、業界規制などを守ることです。企業活動を行う上での最低限のルールといえます。
就業規則や社内規程、業務マニュアル、企業倫理綱領など、企業が独自に定めたルールを守ることです。これには、組織の価値観や行動規範を従業員一人ひとりが理解し、実践することも含まれます。内部統制の整備もこの一環といえます。
法令で明確に規定されていなくても、社会的な良識や道徳、倫理観に照らして適切に行動することです。ステークホルダー(顧客、従業員、株主、地域社会など)からの信頼を得て、企業が社会の一員として持続的に発展していくために不可欠な要素です。
コンプライアンスに反する行為とは?
コンプライアンスに反する行為とは、守るべきルールから逸脱する行為のことです。
コンプライアンスに反する行為は、企業にとっては信用の失墜、経済的な損失、法的な制裁、従業員にとっては懲戒処分や法的な責任を問われるなど、深刻な結果を招く可能性があります。
そのため、企業全体でコンプライアンス意識を高め、違反行為を未然に防ぐための体制づくりや教育が非常に重要です。
コンプライアンス体制の構築に取り組もう
コンプライアンスは、どの企業であっても意識することが大切です。コンプライアンス違反をすれば、ペナルティが課されるだけでなく、企業の信用問題にも発展するおそれがあります。
企業経営に対する悪影響を防ぐためにも、コンプライアンス体制をしっかりと構築することを徹底するようにしましょう。