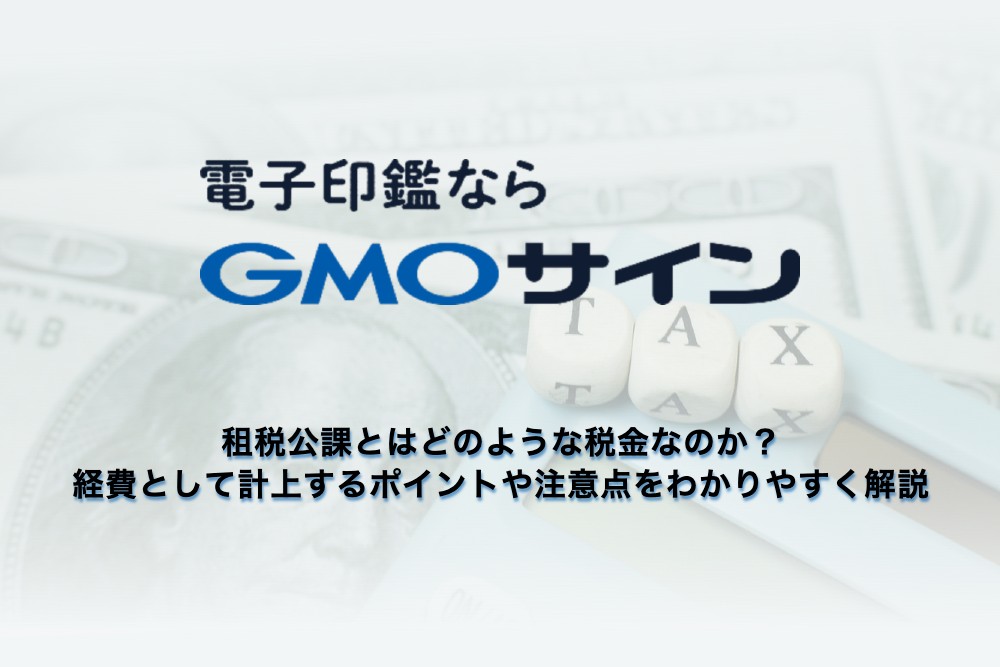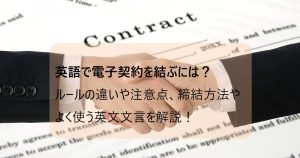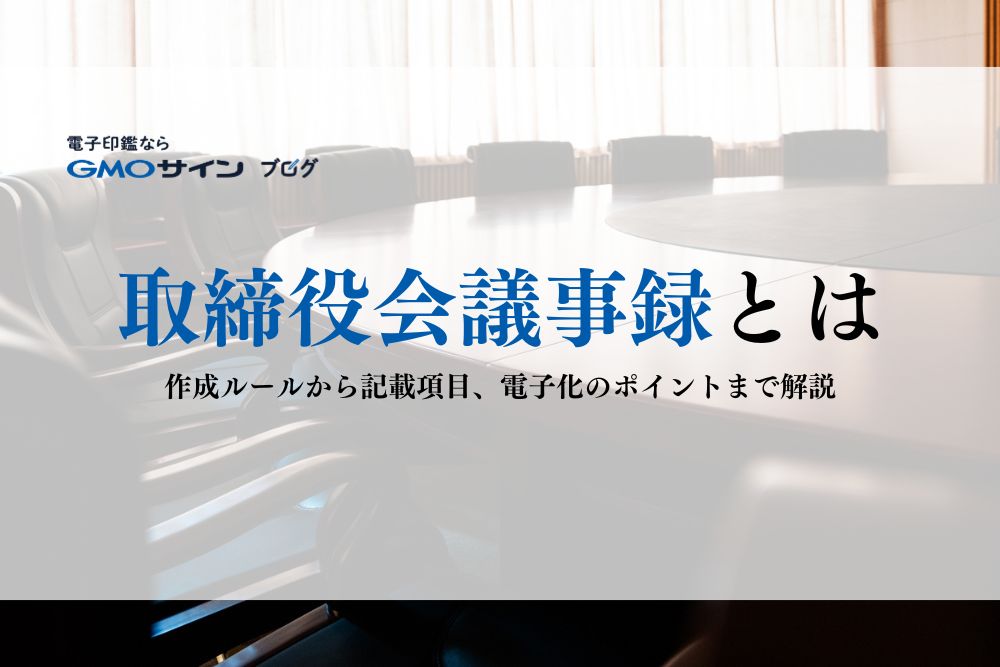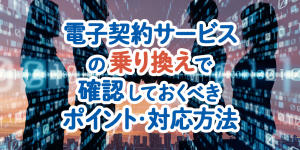署名代理は法的に有効?
代理署名を行う際に発生する法的リスクは?
実務で署名代理を安全に実行するための対策方法を知りたい!
署名代理には無権代理や私文書偽造といった重大な法的リスクが潜んでおり、対策を講じなければ企業の信頼失墜や損害賠償責任を負う可能性があります。この記事では、署名代理の法的な位置づけから実務での安全な運用方法までをわかりやすく解説します。
- 署名代理の基本概念と法的解釈
- 署名代理が有効となる要件と認められないケースの具体例
- 法人や個人でよくある署名代理のケースと注意点
- 電子契約における署名代理の可否と実施方法
- 無権代理や私文書偽造などのリスクと対策
安心して契約を結ぶためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。電子契約がおすすめできる理由として、PCやスマホから時間や場所を選ばず署名が可能であることが挙げられます。代理署名を依頼する機会自体を大幅に減らせるでしょう。
また、従来の紙ベースの契約と比較して本人確認の精度が高い点も特徴で、代理権の範囲や承認プロセスをシステム上で明確に管理することが可能です。電子署名の履歴は自動的に記録されるため、後々のトラブルを防止する効果も期待できます。
- 高度な本人認証機能(電話認証、SMS認証、身元確認書類アップロードなど)
- 柔軟な承認フロー設定により複数段階での確認が可能
- 電子署名法に準拠した法的証拠力の高い電子署名が可能
- 契約書の作成から署名、保管まで一元管理
- API連携による既存システムとのスムーズな統合
GMOサインではお試しフリープランも用意しており、月5件まで電子契約を無料で利用できます。無料プランでも基本的な電子署名機能や承認フロー、契約書の保管機能を利用できるため、まずは実際の使い勝手を確認してみてはいかがでしょうか。
署名代理とは?
まずは署名代理の基本的な定義をおさらいします。代理署名や記名代理との違いも解説しますので、参考にしてください。
署名代理の基本的な概念
署名代理とは、本人の代わりに別の人が契約書などに署名する行為のことです。単なる代筆ではなく、契約者本人が「この人に自分の代わりとして、署名してほしい」と意思表示をしたうえで、その権限を与えられた人が署名することを指します。
代理人に署名を任せる場合は、本人がきちんと「この人に署名を任せます」と権限を与える必要があります。そのためには、委任状を作成したり、社内で代理署名のルールを決めておくことが大切です。こうした手続きをきちんと行えば、代理人が署名した契約書も本人が署名したものと同じように有効になります。
署名代理と混同しやすい類似の概念(代理署名、記名代理との違い)
署名代理と混同しやすい言葉として、「代理署名」や「記名代理」などがあります。おもな違いは以下のとおりです。
| 署名代理 | ・本人の意思に基づき、代理人が本人の氏名を自筆で記入すること ・代理権が適切に与えられているかどうかで法的な有効性が変わる |
|---|---|
| 代理署名 | ・署名代理と同じ意味で使われることが多い ・代理人自身の名前の下に「〇〇(本人名)の代理人として」と追記する形式を指すこともある |
| 記名代理 | ・氏名を手書きで書く「署名」ではなく、ゴム印の使用や印刷などで氏名を記載すること ・法的な効力を補うために、あわせて押印が求められる |
契約における誤解を防ぐためにも、上記の違いを把握して、トラブルにつながらないようにしましょう。
署名代理は有効?法律での解釈を解説
署名代理が法的に有効かどうかは、場合によって異なります。ここからは、署名代理の有効性について、認められるケースと認められないケース、署名代理が法的に有効となるための要件を解説します。
署名代理が有効なケース・認められないケース
署名代理が認められるかどうかは、代理権の有無と範囲によって決まります。
署名代理が認められるケース
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 法に適した代理権が与えられている場合 | ・委任状などによって、本人から代理権を与えられている場合 ・代理人は本人の意思に基づいて署名を行うため、その効力は本人に帰属 |
| 本人が署名代理を追認した場合 | ・代理権がなくても、本人が後から署名代理を承認した場合は有効 |
署名代理が認められないケース
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 代理権がないにもかかわらず署名した場合 (無権代理) | ・本人から代理権を与えられていないにもかかわらず、勝手に署名を行った場合 ・本人の意思に基づかない署名のため、本人に効力を生じない |
| 代理権の範囲を超えて署名した場合 | ・特定の契約に関する代理権のみを与えられているにもかかわらず、別の契約に署名した場合など ・代理権の範囲を超えた部分は本人に効力を生じない |
| 署名代理が認められない契約の場合 | ・法律で本人の署名が義務付けられている特定の契約では署名代理が認められない ・公正証書遺言や婚姻届など本人性が重視される場合 |
署名代理を依頼する際や引き受ける際は代理権が付与された状態で行い、「署名代理が認められなかった」といった事態を防ぎましょう。
署名代理が法的に有効となるための要件
署名代理が法的に有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 本人から代理権が認められている | ・署名を行う代理人が本人から代理権を与えられている ・委任状などの書面で確認できる状態が望ましい ・委任状には、どのような契約に対して、どの程度の権限があるのか記載する |
| 代理権の範囲内の行為である | ・代理人は与えられた代理権の範囲内で署名を行う ・まったく関係のない契約に署名した場合、署名は無効になる |
| 代理の意思を示せる | ・代理人が署名を行う際、本人の代理として行われたことを示す ・署名欄に、本人の氏名・代理人の氏名・代理人である旨を明記する 【記載例】 〇〇株式会社 代表取締役 山田 太郎 上記代理人 営業部長 鈴木 一郎 |
| 署名内容が本人の意思に沿っている | ・代理人が本人の意思に反する内容で署名を行った場合、有効性が疑われる ※ ただし、相手方が善意無過失なら、契約が成立する場合がある |
上記の要件をすべて満たすと、署名代理が有効と認められます。企業では、社内規定で代理権を付与する手順や署名代理のルールを定め、遵守するようにしましょう。
署名代理が行われるおもなケースと注意点
署名代理が行われるケースとしては、以下が挙げられます。
法人における代表者署名(役員・従業員による代理)
法人が契約を締結する場合、代表者の署名が必要です。しかし、代表者がすべての契約書に自ら署名するのは現実的ではありません。そのため、役員や従業員が代理で署名するケースがあります。
代理署名を依頼するのであれば、社内規程や委任状で、誰がどの範囲で代理署名できるのかを明確にしましょう。代理人が権限を超えて署名する「無権代理」を防いで、契約の有効性を保てます。
病気やけが、身体的な理由で本人が署名できないケース
病気やけがなど身体的な理由で本人の署名が難しいときも、署名代理が使われる場合があります。
このとき鍵となるのは、本人の意思が尊重されている点です。代理人が署名する前に、本人の意思を確認し、その意思に基づいた署名が求められます。
たとえば、本人からの口頭の指示だけではなく、本人の意思を委任状などの書面で残すと「署名が本人の意思とは違う」といった争いを避けられます。
不動産取引における司法書士・弁護士による代理署名
専門的な知識や手続きが必要なため、不動産取引では、司法書士や弁護士が代理人として署名を行うケースがあります。司法書士や弁護士には、法律のプロとして業務を行う権限を与えますが、その範囲は別途、委任契約で定めます。
電子契約では署名代理が可能?
ここからは、電子署名を利用する場合でも署名代理ができるのかを解説します。電子契約ツールを使った署名代理の注意点もお伝えしますので、参考にしてください。
オンラインでの代理署名の可否と注意点
電子契約での代理署名は、紙の書面と同様に可能です。しかし、書面での署名代理と比べて、いくつか注意点があります。
まず、電子契約でも代理人が署名するときは「本人から正式に頼まれている(権限委譲)」という証拠が必要です。そのため、紙の契約と同じように、代理権を示す委任状をPDFファイルなどで用意しておきましょう。
また、電子契約では「署名したのが誰なのか」を明らかにすることが求められます。代理人が電子署名をする場合も、署名が代理人によるものという証明が必要です。
こうした要件を満たすためには電子契約ツールの利用がおすすめです。GMOサインのような電子契約サービスを使って代理署名を行い、署名の有効性が疑われないようにしましょう。
電子契約ツールを使った署名代理の方法
電子契約ツールを使って署名代理を行う場合、おもに2つの方法があります。
1つ目は、代理人が電子契約サービスに登録し、代理で署名する方法です。この場合、代理人は自身の電子証明書やIDを利用して署名を行います。契約書のファイルには「〇〇(本人名)の代理人 ××(代理人名)」といった形で、代理人である旨を明記しましょう。
2つ目は、代理人が本人に代わって、本人のアカウントで署名する方法です。本人が病気やけがなどで署名できない場合に実施される場合がありますが、セキュリティ上の危険が高いため、おすすめできません。
本人のIDとパスワードを代理人に共有するので、情報漏えいや不正利用のリスクがあります。より安全で法的に有効な署名代理をするには、代理人が自身の電子証明書やIDを使って署名する方法が適切です。
なお、電子契約サービスには、ワークフロー機能や承認機能が搭載されているものがあります。契約の締結前に本人の承認を得るプロセスを組み込めば、代理署名のリスクを減らせるので、あわせて以下の記事もご覧ください。
\\ こちらの記事もおすすめ //
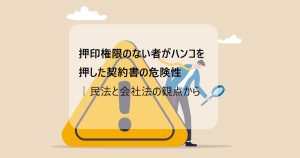
署名代理のリスク
署名代理には以下のようなリスクがあると考えられます。
それぞれのリスクを解説するので、順に見ていきましょう。
無権代理のリスク
署名代理で注意したいのが無権代理です。無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人と称して契約を締結することです。
一例として、従業員が会社の代表者として署名を無断で行い、契約を結んでしまったケースを考えてみましょう。従業員には代理権がないため、原則として会社は契約に拘束されません。しかし、相手方が正式な代理人によって契約が結ばれたと思っていた場合、混乱や損害が生じるおそれがあります。
このような事態を防ぐには、誰がどこまでの代理権を持っているのかを明確にし、社内で承認フローを定めることが不可欠です。
本人の意思と異なる契約締結
署名代理では、本人の意思と異なる契約が締結されてしまうケースも考えられます。代理人が本人の意図を正確に理解していなかったり、誤解したまま署名を進めてしまったりするケースが該当します。
たとえば、契約内容の一部が変更されたにもかかわらず、本人が変更を把握しないまま代理人が署名した場合、後からトラブルに発展しかねません。
本人の意思に反する契約をしないためには、代理人が契約内容を確認し、本人の承認を得たうえで署名を行う体制を作ることが大切です。重大な契約については、本人の最終チェックを通すなどのフローを設けましょう。
私文書偽造などの法的責任の発生
署名代理を正しい手続きを踏まずに行うと、「私文書偽造」として犯罪になることがあります。最悪の場合、刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
第百五十九条 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
引用:刑法第百五十九条
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
具体例を挙げると、以下のようなケースが当てはまります。
- 会社の代表者の署名欄に、代表者の承諾なしに別の人間が署名した場合
- 代理権の範囲を超えて署名した場合
- 虚偽に基づいて署名を行った場合
なお、私文書偽造罪ではなく詐欺罪や横領罪など、別の罪に該当する可能性も考えられます。罪に問われれば、個人だけではなく会社の信用も失いかねません。法に抵触しないためにも、署名代理を行う前に代理人が正式な代理権を有していることを確認し、その範囲内で署名をしましょう。
電子契約サービスのGMOサインでは、誰が・いつ・どの契約に署名したか記録が残せます。不正行為を防止するだけではなく、争いに発展した際の証拠としても利用可能です。オンラインで代理署名を行う機会が多い方はぜひ導入をご検討ください。
署名代理による法的リスクを避けるための対策
署名代理は法的なリスクをともなう場合もあるため、以下のような対策が求められます。
それぞれの対策について順に紹介します。
代理権の範囲を委任状・社内規程で明文化する
署名代理を安全に行うには、代理権の範囲を明らかにすることが大切です。代理権の範囲が不明確な場合、「代理権がないまま代理行為を行っている」と見なされ、契約が無効になるおそれがあります。そのため、代理権の範囲は委任状や社内規程で、以下のように定めておきましょう。
- 委任状:対象となる契約の種類や金額の上限などを含め、「誰が・何を・どこまで代理できるのか」を記載する
- 社内規程:署名代理の承認プロセスや責任の所在、代理権の付与条件などを定める
社内全体で代理権の範囲について認識をあわせ、運用を統一させることでリスクを回避できます。
電子契約ツールの承認フローと認証機能の活用
電子契約ツールの承認フローと認証機能を利用するのも、リスク対策の一つです。承認フローを設定すると、契約の締結前に本人の承認を得る仕組みの構築が可能です。
たとえば、代理人が署名を行った後、本人がシステム上で最終チェックや承認を行うフローを設けると、本人の意思と異なる契約を結ぶ可能性を減らせます。
また、電子証明書などの認証機能を利用すれば、署名を行ったのが誰であるかを証明できます。なりすましによる署名や、代理権の逸脱があった場合に証拠としての利用が可能です。
相手方への説明対応
署名代理を行う際には、場合によって契約相手への説明を行うことも大切です。
署名代理は、相手方にとって「本当に本人が同意しているのか」という疑問が生じる場合があります。そのため、代理権を相手方に示して不安を解消すると、信頼してもらったうえで契約を結べます。
具体的な対応としては、締結の前に相手方へ代理権の有無とその範囲を伝え、必要に応じて委任状の提示を行うとよいでしょう。
署名代理に関するよくある質問
代理で署名をするのは有効?違法?
代理で署名をすること自体は有効で違法性はありません。ただし、署名を依頼する本人が署名者に代理権を与える必要があります。代理権がなければ、その署名は無効とされるうえ、私文書偽造などの問題に発展するおそれがあるため、ご注意ください。
代理で署名をするときの書き方は?
代理で署名をする際は「A株式会社 代表取締役B 代理C」のように記載します。署名欄に代理人であることと、誰の代理であるかを明記しましょう。
ハンコを代理で押すことは有効ですか?
民法99条1項により、代理権の範囲内で代理人が顕名して押印すれば、その法律行為の効果は本人に帰属します。したがって契約自体は有効です。ただし、代理権の有無・範囲が争点化すると無権代理(民法117条)を問われるおそれがあるため、委任状や社内規程で権限を明確にしましょう。
なお、民事訴訟で契約書を証拠提出する場合は、民訴法228条4項により「本人または代理人の押印がある文書は真正に成立したものと推定」されます。つまり、代理権を裏付ける委任状が添付されていれば、相手方はその真正性を覆さない限り文書の成立を争えません(逆に委任状がないと推定が及ばず、真正性が問題化しやすくなります)。
手が不自由な人が署名するにはどうしたらいいですか?
手が不自由な人が署名をする場合、代理人による署名や電子契約の利用が考えられます。代理人に署名を依頼する際は、代理権を付与する書面を作成しましょう。
また、電子契約ツールでは、PCやスマートフォンからオンラインで署名できるため、手書きよりもスムーズに手続きを進められる場合があります。
自署できない場合は代筆者が署名できますか?
自署できない場合に代筆者が署名することは可能です。ただし、その署名が法的に有効であるためには、代理権を与えられている代筆者が、本人の意思に基づいて署名する必要があります。
署名代理のリスク回避にはGMOサインがおすすめ
署名代理とは、契約者本人に代わって代理人が署名をすることです。ただし、ただ代筆をするだけではなく、本人が代理権を与えたうえで代理人が署名する必要があります。また、認められた範囲を超えて契約に署名した場合は、無権代理になるおそれがあります。
電子契約サービスなら、署名の権限や承認の流れをシステム上でしっかり管理でき、誰がいつどの書類に署名したか自動的に記録されます。これにより、代理権の確認や証拠の保存がかんたんになり、不正やトラブルを未然に防ぎやすくなります。
また、電子契約ならPCやスマホからどこでも署名できるため、そもそも代理署名が必要な場面自体を減らすことも可能です。
GMOサインでは、改ざん防止や監査ログ機能も備えているので、安心して契約手続きを進められます。無料で月に5通までの電子署名・契約書の送信が可能なお試しフリープランもあるので、まずは使い勝手を試してみてはいかがでしょうか。
免責事項(本記事のご利用にあたって)
本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。