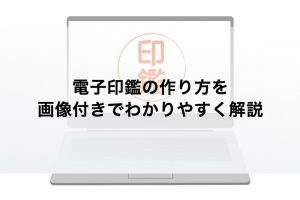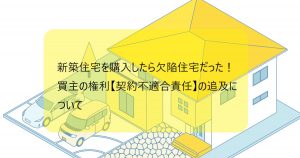\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

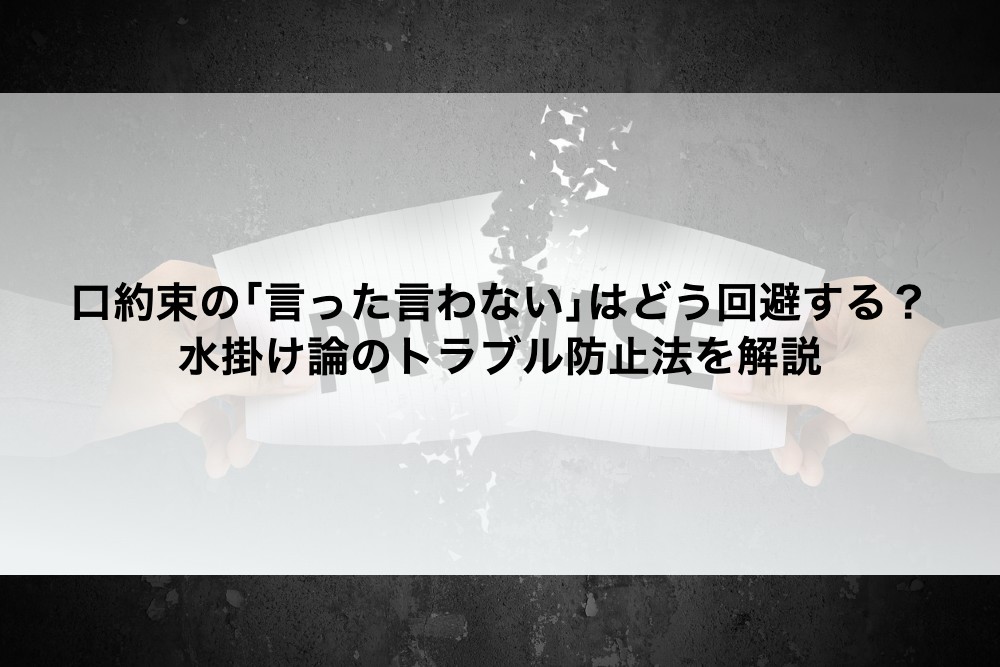
私生活や仕事上など、口約束を交わす機会は意外と多いですよね。ただ、口約束で困るのが「言った言わない」の水掛け論になってしまうことです。トラブルになると人間関係も気まずくなるので、できれば争うことは避けたいものです。
そこでこの記事では、口約束の「言った言わない」はどう回避すればいいのか、水掛け論のトラブル防止法などを解説していきます。「口約束での『言った言わない』のトラブルを避けたい」というときは、ぜひ参考にしてください。
まずは、大前提として理解してほしい「口約束の法的な効力」について解説します。
口約束であっても、原則として法的な効力を持ちます。これは口約束も契約の一つとされ、民法で契約の成立を次のように定めているためです。
民法第522条(契約の成立と方式)
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典:e-Gov法令検索
例えば「宅配ピザ」も口約束での契約です。電話をかけて「〇〇ピザのLサイズを1つお願いします」が申込みで、ピザ店が「かしこまりました」と承諾することで契約が成立します。
口約束ですが契約として成立するため、注文者がお金を払わなければ債務不履行です。
「口約束の法的な効力」については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
契約とは、法的には「一方当事者の申込みの意思表示(考えを表すこと)に対し、他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為」のことを言います。簡単にいうと「法的な責任が生じる約束」のことです。
当事者の一方からの「申込み」と、相手方の「承諾」という「意思表示の合致」があったときに、契約が成立します。
「契約」については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
ここからは、口約束での「言った言わない」といった水掛け論を避けるトラブル防止法を解説します。まずは契約書の作成です。
口約束に法的な効力があるとはいえ、トラブル防止の観点からは「契約書を作成して契約内容を証明する」ことがもっとも重要です。
契約書を作成することで、例えば次のような取り決めを証明できます。
特に小規模な企業では、「昔からの付き合いだから」と、契約書無しで取り引きすることも多いようですが、これでは「約束どおりに取り引きされない」ことがいつ発生してもおかしくありません。
以前からの慣習であっても、業務上重要なケースや金額が大きい取り引きでは、できるだけ契約書を締結しましょう。
契約書を作成するときのポイントは「口約束したすべての項目を、できるだけ詳細に記載する」です。
例えば、次のような項目を記載しましょう。
ちなみに、書面の名称に法律上の制限はありません。タイトルが「覚書」「合意書」であっても、契約内容がしっかり記載されていれば、契約書と効果は変わりません。
契約は原則として書面が不要です。しかし次のように、法律によって書面の作成などが必須となり、口約束だけではNGなケースもあります。
| ①保証契約 | 債務者が債務を履行しない場合に、代わっての弁済を約束する契約 (民法で「書面による契約」が義務付け) |
|---|---|
| ②定期建物賃貸借契約 | 定めた期間が満了することで、更新されずに確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約 (借地借家法で「書面による契約」が義務付け) |
| ③建設工事の請負契約 | 当事者の一方がある仕事を完成し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払う契約 (建設業法で「書面による契約」が義務付け) |
| ④警備業に係る契約 | 警備業者と依頼者との間で交わす契約 (警備業法で「契約締結前」と「契約締結時」の2回、依頼者に対して書面の交付が義務付け) |
| ⑤使用貸借契約 | 当事者の一方が、相手方から受け取った物について使用後に無償で返還する契約 |
| ⑥寄託契約 | 当事者の一方が、相手方のある物を保管する契約 |
上記①~④については法律で「書面の作成」が、⑤~⑥は「物の受け渡し」が必要(要物契約)と定められています。
特に専門的な契約を行うときには、先に「どういった書面や要件が必要なのか」を確認しておきましょう。
2つめの「言った言わない」を避けるトラブル防止法は、“口約束をしたやりとりの証拠を残す”です。
「借りる金額が少額だから、契約書を取り交わすほどではない」「昔からやっている取り引きなので、今更契約書とは言えない」など、状況によっては契約書を作らない(作れない)ケースもあるでしょう。
契約書を締結できないときは、できるだけ次のような「やりとりの証拠」を残しましょう。
後に「言った言わない」のトラブルになったときに、契約書ほどではなくとも、ある程度の証拠となってくれます。
“口約束をしたやりとりの証拠”としてのメールなどは、できるだけ「口約束の内容がわかる」ものを残しましょう。
証拠として特に有効なのは、「〇〇の件、以下の内容でお願いします。金額は…」など相手からの確認のメールです。口約束があったことを相手方が認めているので、内容まで記載されていれば、契約書に近い効力を持ちます。
一方で、あまり証拠にならないのが「先程の件、問題ないです。そのまま進めてください」のような、口約束の内容がわからないメールです。後にトラブルになったときに、「口約束を了承したわけではない」と言い逃れができてしまいます。
3つめの「言った言わない」を避けるトラブル防止法は、“不用意な口約束を行わない”です。
不要なトラブルを避けるために、特に業務上においては「不用意な口約束を行わない」ようにしましょう。
中には「口約束には効力がないだろう」と考え、取引先と不用意な口約束を交わしてトラブルになることも多いようです。さらに現代では、悪い評判はあっという間に拡散され、企業イメージの低下につながることもあります。
取引先の信頼を失うことがないよう、もともと遂行するもりがない事柄を、口頭であっても伝えるのはやめておくことをおすすめします。
不用意な口約束を行わないための第一歩は、口約束にも効力がある点をよく理解することです。
法律の知識がないと「契約書がないから、契約として成り立たないだろう」と考えがちですが、前述したとおり口約束でも契約は成立します。
社交辞令のつもりで言った「今度、仕事お願いするから」でも、相手にすれば“口約束による業務の受注”となるケースもあります。まずは「これを言ったら口約束に捉えるかな」と考え、下手に期待させることを言うのはやめましょう。
相手が口約束を守らず裁判となった場合でも、契約書などの証拠がないと敗訴することも有り得ます。
裁判においては、原則として権利を主張する側が証拠を提示する必要があるからです。いくら裁判所で「口約束したんです」と訴えても、裏付ける証拠がなければ、口約束があったことは認められません。
しかも裁判にまで発展すると、余計なお金と時間がかかってしまいます。業務上の取り引きでは、できるだけ契約書を作成して、トラブルを未然に防ぎましょう。
一般的な契約であれば、成立後は当事者の一方的な解約は認められません。しかし口頭での贈与契約の特徴として、贈与する前であれば当事者のどちらかが一方的に契約を解除できます。
民法第550条(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索
つまり、口約束ならではの「言った言わない」のほか、口頭の贈与契約では「やっぱり、あげるのやめた」が起こってしまうということです。トラブルに発展する可能性がより高くなるため、贈与契約では特に書面を残すことを心がけましょう。
この記事では、口約束の「言った言わない」はどう回避すればいいのか、水掛け論のトラブル防止法などを解説してきました。
気軽にできてしまう分、口約束ではトラブルが発生しやすくなります。ぜひ今回紹介した契約書などの証拠を残して、口約束の「言った言わない」を回避しましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。