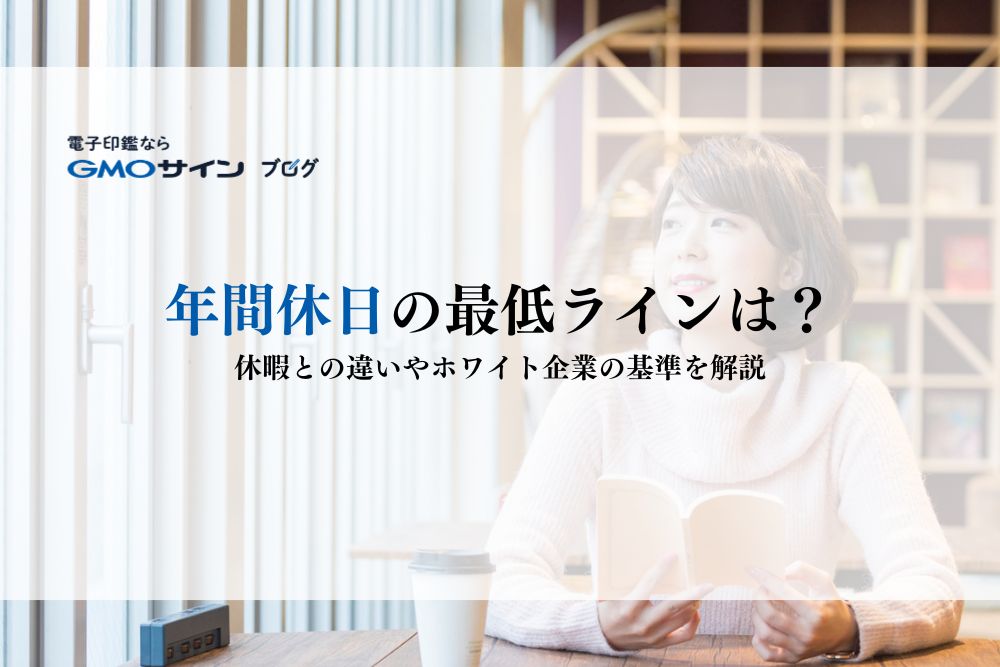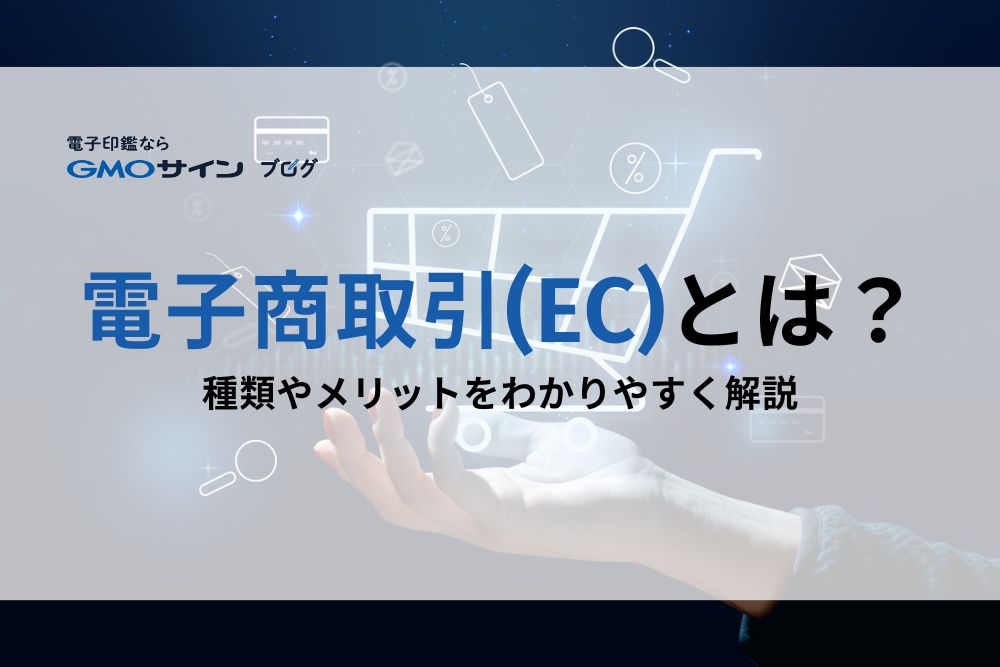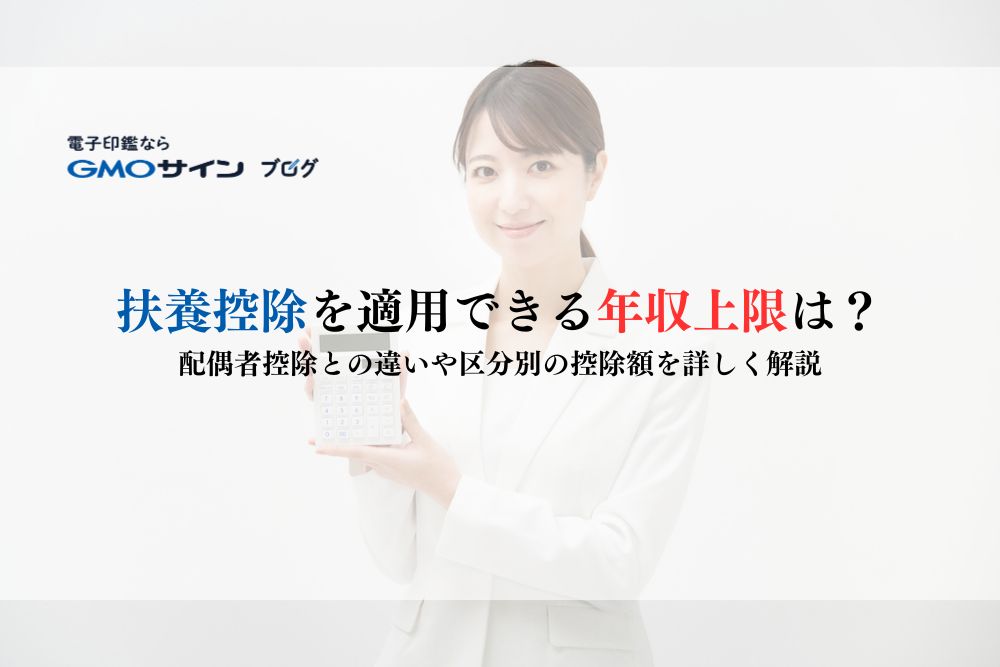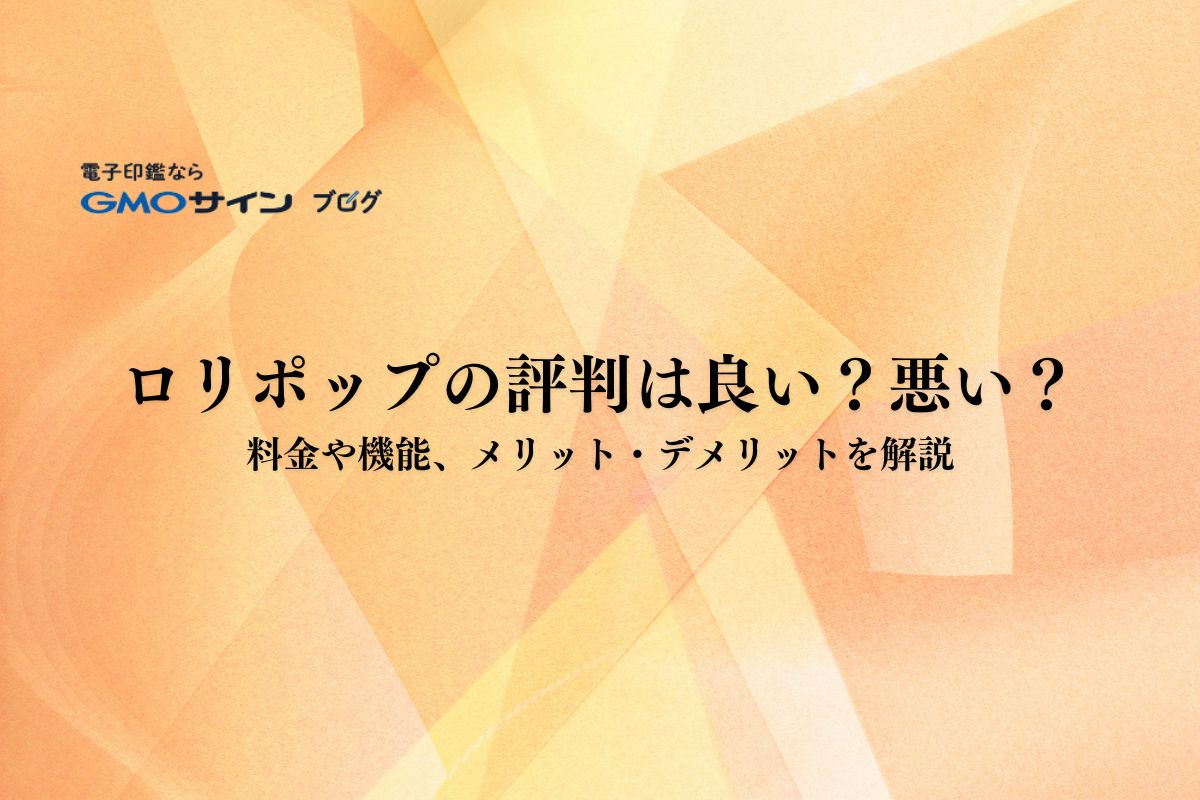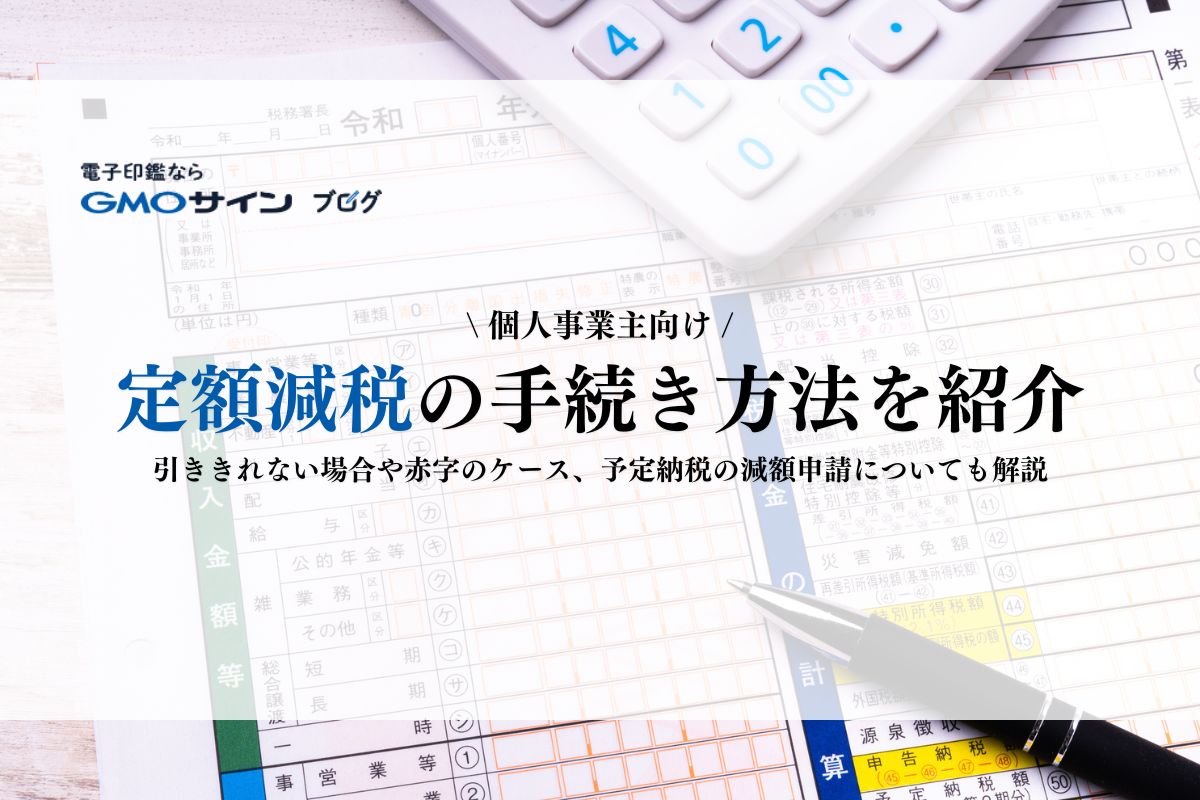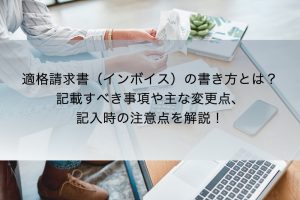\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /
\\ 期間限定キャンペーン実施中 //
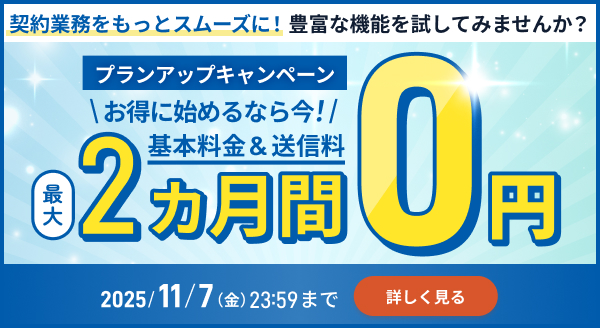
【予告】GMOサイン10周年特別セミナー


「和解契約にはどんな効力があるのか」
「示談との違いは何か」
「一度和解したら取り消せないのか」
和解契約は、当事者同士が話し合いによって争いを解決する法的手段として、多くの場面で活用されています。しかし、上記のような疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
和解契約は、裁判外で迅速かつ柔軟に解決できるだけでなく、費用と時間もかからずにできる有効な手段です。
本記事では、和解契約の基本的な仕組みから、成立要件、メリット・デメリット、法的効力まで詳しく解説します。さらに和解契約書の作成ポイントや確実な履行を確保する方法についても具体的に紹介します。
紛争解決の選択として検討している方は、参考にしてみてください。
和解契約とは民法第695条に基づき、当事者間で発生した紛争や争いごとに対して、お互いの譲歩により解決する契約です。裁判所を通さずに紛争を最終的に終結させます。
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
参考:民法第六百五条|e-Gov法令検索
時間や費用のかかる裁判を避けることが可能で、双方にとって納得のいく解決が期待できる重要な制度といえるでしょう。
和解契約とは、紛争の当事者が話し合いによって合意に達し、お互いに譲歩して争いを終結させる契約です。
単なる話し合いの結果ではなく、法的拘束力をもつ契約として成立するため、当事者には合意内容に従う義務があります。
和解契約には、双方の譲歩が必要な点が特徴です。たとえば、売買代金100万円の支払いの紛争で、債権者が80万円の減額を受け入れ、債務者が一括払いに応じるなど、お互いに妥協点を見出します。そうすることで裁判を経ずに紛争を解決できるというものです。
和解には大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの和解には異なる法的効力があるため、紛争の内容や当事者の希望に応じた適切な方法の選択が大切です。
和解と示談は混同されがちですが、基本的な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 和解 | 示談 |
| 適用範囲 | 民事上の争い | 不法行為による損害賠償請求 |
| 目的 | 紛争の円満な解決 | 損害賠償額の合意による解決 |
| 具体例 | ・離婚時の財産分与 ・売買契約のトラブル ・相続手続き | ・交通事故 ・傷害事件の損害賠償 |
和解は法的拘束力を持つ契約であり、示談は紛争を解決するための一般的な合意です。また、和解では必ず双方の譲歩が必要ですが、示談では必ずしも被害者側の譲歩を要しません。被害者が納得する条件を満たさない場合、応じる義務はないのです。

和解契約が法的に有和解契約を有効に成立させるには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
ここでは、それぞれの要件を解説します。
和解には、当事者間に何らかの法的な争いが存在している事実が必要です。争いとは法的関係の内容について当事者間で認識に相違がある状態を指します。
たとえば、契約の解釈をめぐる意見の対立や損害賠償額に対する見解の違いといったケースです。単なる感情的な対立や道義的な問題だけでは法的な争いとはいえず、和解の対象にはなりません。
和解成立には、当事者双方の譲歩が不可欠です。和解契約では一方的に相手の要求を受け入れるだけでは和解とはいえません。
譲歩の形態はさまざまで、金額の減額や支払い方法の変更、期限の延長などがあります。お互いが相手の立場を考慮した解決策が重要です。
和解は単なる勝敗の決着ではなく、当事者双方が受け入れあう解決といえるでしょう。
当事者が争いを終結させるために合意が欠かせません。単に条件面で折り合いがついただけでなく、合意内容が紛争を完全に解決し、今後は争わないという明確な意思の合致が必要です。
実務では、和解契約書に「本件に関し、本契約書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項の設定が一般的です。
この条項により、決定事項以外はお互いに請求できるものがないことを明確にします。また、将来的な紛争の再発を防ぎ、当事者間の法的関係を安定させられるでしょう。
和解には、
の2つがあります。それぞれ手続きや法的効力が大きく異なるため、紛争の内容や求める解決方法に応じて適切な選択が重要です。
ここでは、両者に加え、簡易裁判所で行う「即決和解」についても解説します。
訴訟外の和解は、当事者同士が裁判所を介さずに話し合いで解決する一般的な和解の形態です。民法第695条に基づいて、通常の契約と同様に法的拘束力をもちます。
手続きに特別な形式はなく、口頭でも成立します。しかし、後日の紛争を防ぐため書面化が一般的です。
費用が安く、迅速に解決できるメリットがあります。ただし、相手が和解内容を履行しない場合、ただちに強制執行を実施できません。強制執行するためには、改めて訴訟を提起して判決を得るか、公正証書を作成しておく必要があります。
訴訟上の和解は、裁判の進行中に裁判所で行われる和解です。裁判官の関与のもと、当事者が合意した内容が和解調書に記載されます。
和解調書は民事訴訟法第267条によると、裁判所による確定判決と同等の法的効力を備えるため、相手が履行しない場合は強制執行が可能です。
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
また、裁判官が公平な立場から和解案を提示し、当事者だけでは解決が困難な場合でも合意に至りやすい特徴があります。ただし、すでに訴訟が開始していることが前提となるため、訴訟提起の費用と時間がかかる点がデメリットです。
即決和解は、民事訴訟法第2754条で定められている簡易裁判所に申し立てて行う特別な和解制度です。訴訟を起こす前に、当事者双方が簡易裁判所に出頭し、裁判官の面前で和解したうえで和解調書が作成されます。
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
和解調書は確定判決と同一の効力をもち、強制執行が可能です。申立費用は2,000円程度と安価で、1回の期日で和解することが多いため、負担が少なく迅速な解決が期待できるでしょう。
ただし、相手方の同意と出頭が必要なため、相手が協力的でない場合は利用できません。
和解契約のメリットは、以下のとおりです。
それぞれの内容について詳しく解説します。
和解契約では、紛争を迅速に解決が可能です。訴訟では期日が月1回程度のペースで進行するため、控訴や上告まで進めば数年かかりかねません。一方、和解であれば、当事者間で合意に達すれば解決となります。
和解は当事者の都合にあわせて協議を進められ、数週間から数カ月での解決も可能です。ビジネス上の紛争など早期解決が求められる場面では、有効な手段でしょう。
和解契約は、訴訟と比べて大幅に費用を抑えることができます。訴訟を提起する場合に発生する費用は以下のとおりです。
具体的には訴訟額が1,000万円の場合、印紙代だけで5万円必要です。一方、和解であれば、印紙代は不要で弁護士費用も訴訟より低額に抑えられます。
経済的な負担を最小限にしながら紛争を解決できる点は、大きなメリットといえます。
参考:民事訴訟Q&A|最高裁判所
訴訟は原則として法廷で公開して行われるため、紛争の内容が第三者に知られる可能性があります。一方、和解契約なら当事者間の協議は完全に非公開です。
和解内容についても守秘義務条項を設ければ、外部への情報漏洩を防止することも可能です。企業の信用や個人の名誉を守りながら紛争を解決できるため、情報の取り扱いが難しい内容を含む紛争では和解が選ばれる傾向にあります。
和解契約は多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
和解を選択する前に理解しておくべきデメリットについて解説します。
和解契約の本質的なデメリットは、必ず双方が譲歩しなければならない点です。自分の主張が100%正しいと確信していても、和解では相手の要求をある程度受け入れる必要があります。
たとえば、100万円の正当な請求権があるにもかかわらず、80万円で妥協せざるを得ない状況も生じかねません。また、譲歩の程度について当事者間で認識が大きく異なると、和解交渉自体が成立しないケースもあります。
感情的な対立が激しい場合や原則論を重視する当事者の場合などでは譲歩の受け入れが心理的に困難な状況に陥りがちです。和解よりも裁判で決着を求める方が適している場合もあるでしょう。
訴訟外の和解契約では、相手が約束を守らない場合でも、迅速な強制執行ができません。強制執行するためには、改めて訴訟を起こして判決を得る必要があり、最終的に時間と費用がかかってしまいます。
公正証書を作成する方法もありますが、対象は金銭債務など一定の内容に限られます。また、相手方が公証役場への出頭を拒否すれば、公正証書は作成できません。
確実な履行を求める場合は、最初から訴訟を選択するか、あるいは即決和解などの裁判所を介した手続きが望ましいでしょう。
和解契約は「確定効」とよばれる効力により、後から争いを蒸し返すことができなくなるため、慎重な検討が必要です。ここでは、和解契約の確定効や履行確保の方法について詳しく解説します。
和解の確定効とは民法第696条に規定されている法的効力です。和解契約が成立した後に、和解と異なる事実が判明しても、原則として和解内容を覆せません。
(和解の効力)
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
たとえば和解で権利がないとされた後、権利が実際には存在すると判明しても、和解により消滅したものとして扱われます。
確定効によって、紛争の蒸し返しを防ぎ、当事者間の法的関係を安定して維持することが可能です。ただし、和解の前提となった事実に重大な錯誤があった場合や詐欺・強迫による場合は、例外的に和解の無効や取消しを主張できます。
和解契約を締結する際は、この強力な効力を理解したうえで、慎重に内容を検討しましょう。
通常の契約と同様に法的拘束力はありますが、訴訟外の和解契約には強制執行力はありません。相手方が和解内容を履行しない場合は、催告したうえで応じない場合に訴訟を提起する必要があります。
訴訟で勝訴判決を得て、はじめて強制執行が可能となりますから、和解契約書には履行期限を明確に定め、遅延損害金の条項を設定すると効果的です。また、連帯保証人を立ててもらって、履行の確実性を高める手段もあります。
ただし、対策を講じても、最終的には訴訟が必要となる可能性がある点を理解しておきましょう。
和解内容を確実に履行したい場合、複数の選択肢があります。
どの方法を選択するかは、紛争の内容や相手方の協力度合い、費用対効果などの総合的な判断による決定が大切です。
和解契約書は、当事者間の合意内容を明確にし、将来のトラブルを防ぐ重要な書面です。必要な条項を漏れなく記載するため、和解契約書作成の重要ポイントを解説します。
和解契約書に記載すべき主要な項目は、以下のとおりです。
和解条件はできるだけ明確に記載することが重要です。また、債務不履行の場合の措置を記載しておきましょう。
基本項目を網羅することで、法的に有効で実効性のある和解契約書となります。
和解契約書では、どのような紛争について和解するのかを明確に特定する必要があります。「令和○年○月○日付売買契約に関する紛争」など、対象となる取引や出来事を具体的に記載しましょう。
曖昧な記載では、和解の対象範囲が不明確となり、新たな紛争の原因となりかねません。
当事者の特定も重要であり、法人の場合は商号・本店所在地・代表者名を正確に記載します。代理人が関与する場合は、委任状の有無や代理権の範囲も確認が必要です。
清算条項は、和解契約書で重要な条項の1つです。清算条項により、和解で決めた内容以外には、お互いに請求できるものがないと明確にします。
一般的には「甲および乙は、本件に関し、本契約書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文言を用います。
ただし、清算条項の範囲には注意が必要です。たとえば、継続的な取引関係がある場合、すべての取引を対象とするのか、特定の取引のみを対象とするのか明確にする必要があります。
将来的な関係を見据えて内容を設定していくことが必要です。
和解契約では、一般的に紛争の内容や和解条件について守秘義務を設けます。
「当事者は、本和解の存在および内容について、正当な理由なく第三者に開示してはならない」といった条項です。
企業間の紛争では、取引内容や技術情報が含まれるケースもあるため、守秘義務は重要です。
守秘義務違反に対しては、違約金の定めが有効です。また、守秘義務の期間を定めるか、無期限とするかも検討事項になります。実効性のある守秘義務条項の作成が大切です。
和解契約について、よく寄せられる質問に回答します。
法律上、和解契約は諾成契約であり、当事者の合意があれば口約束でも成立します。電話や対面での話し合いで和解条件に合意した時点で成立です。
ただし、口約束では認識の相違が生じやすいため、和解契約書や合意書の作成をおすすめします。
和解契約がいったん成立すると、確定効により原則として和解内容は取り消せません。ただし、和解の前提となった重要な事実に誤りがあった場合は、例外的に取り消しが可能です。
和解契約の締結に、必ずしも弁護士は必要なく、当事者だけで締結することも可能です。ただし、専門的な判断も必要となるため、弁護士への相談をおすすめします。確実な解決を図るためには必要な費用と考えて良いでしょう。
和解契約は、当事者が互いに譲歩して紛争解決するための重要な法的手段です。訴訟と比較して、時間や費用を大きく節約でき、非公開で柔軟な解決が可能というメリットがあります。
一方で、必ず譲歩が必要であり、訴訟外の和解では強制執行力がないというデメリットも理解しておきましょう。
和解契約を成功させるためには、本記事で紹介した3つの要件の充足が欠かせません。また、和解契約書には必要な条項を漏れなく記載し、清算条項や守秘義務条項を適切に定めましょう。
和解契約には確定効という強力な効力があるため、いったん成立すると原則として取り消せません。適切で安全な和解契約により、双方が納得して紛争を終結させ、新たな一歩を踏み出しましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。