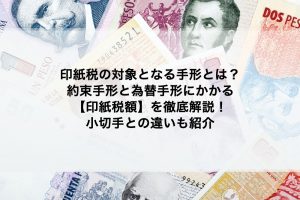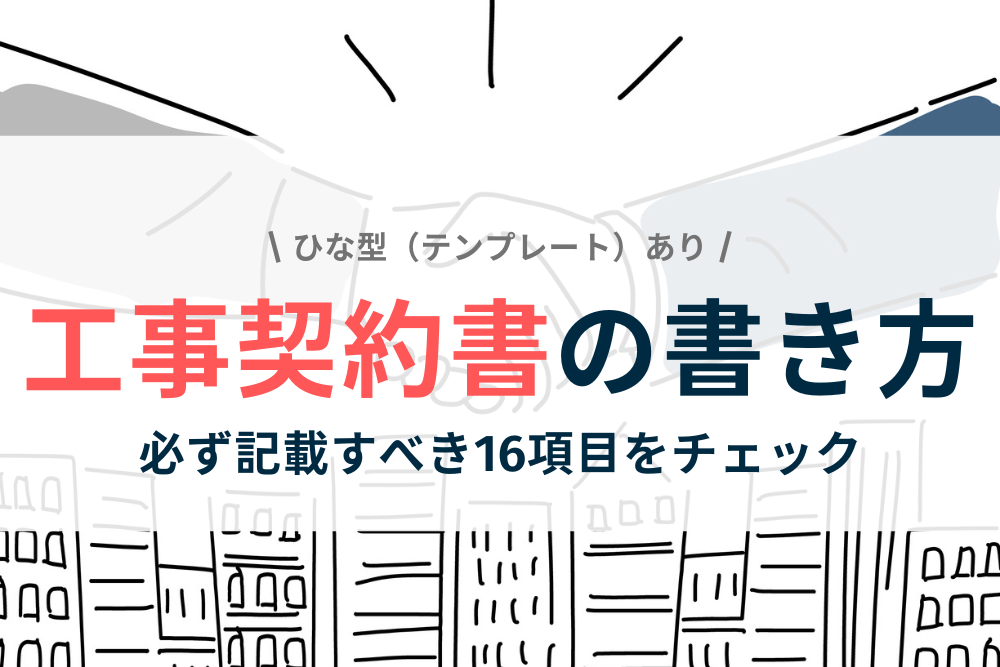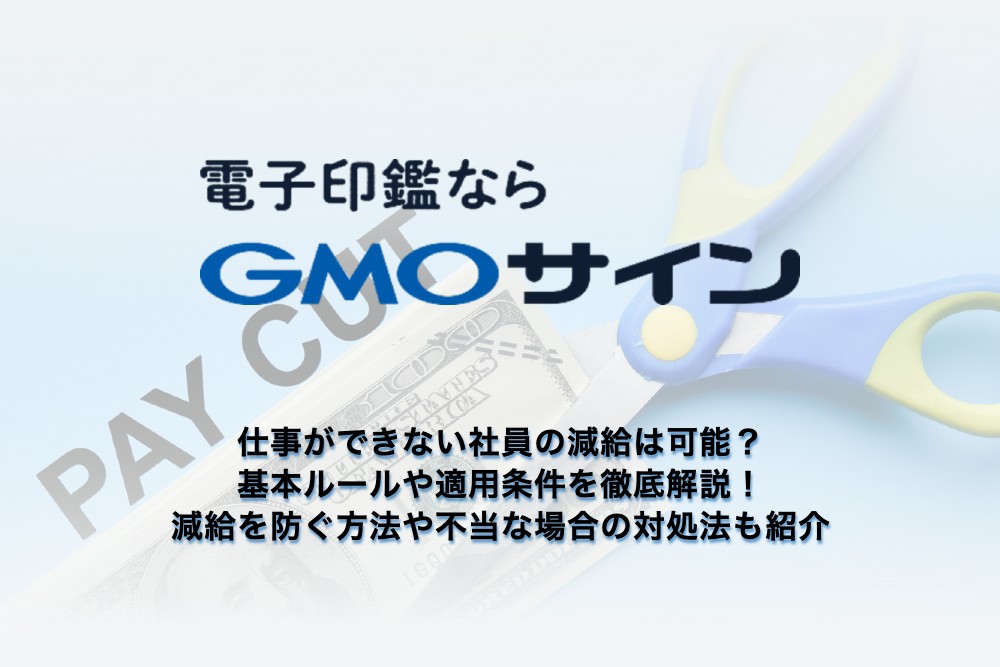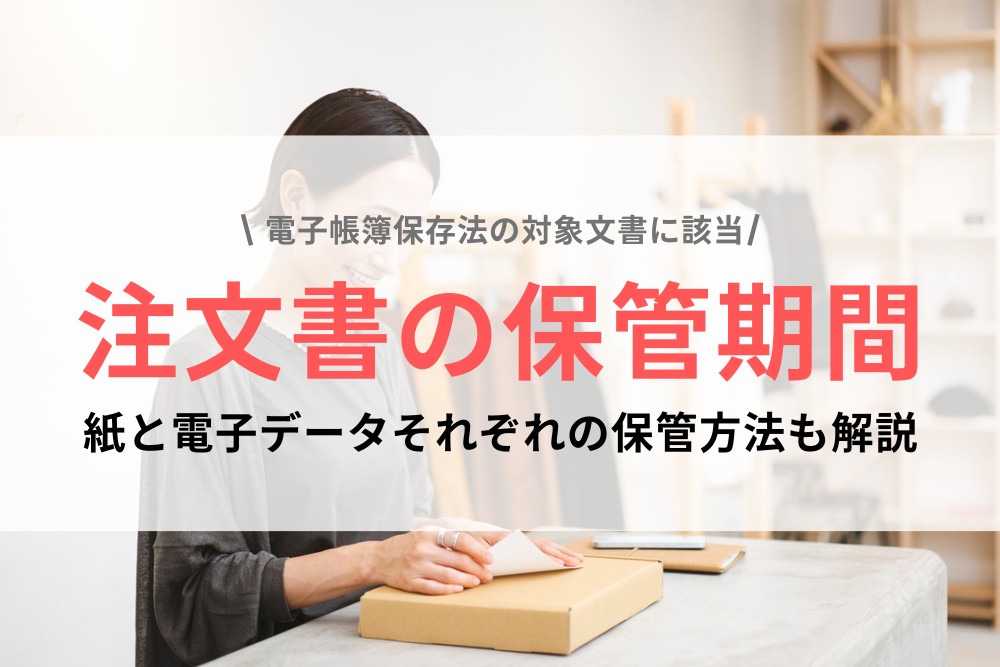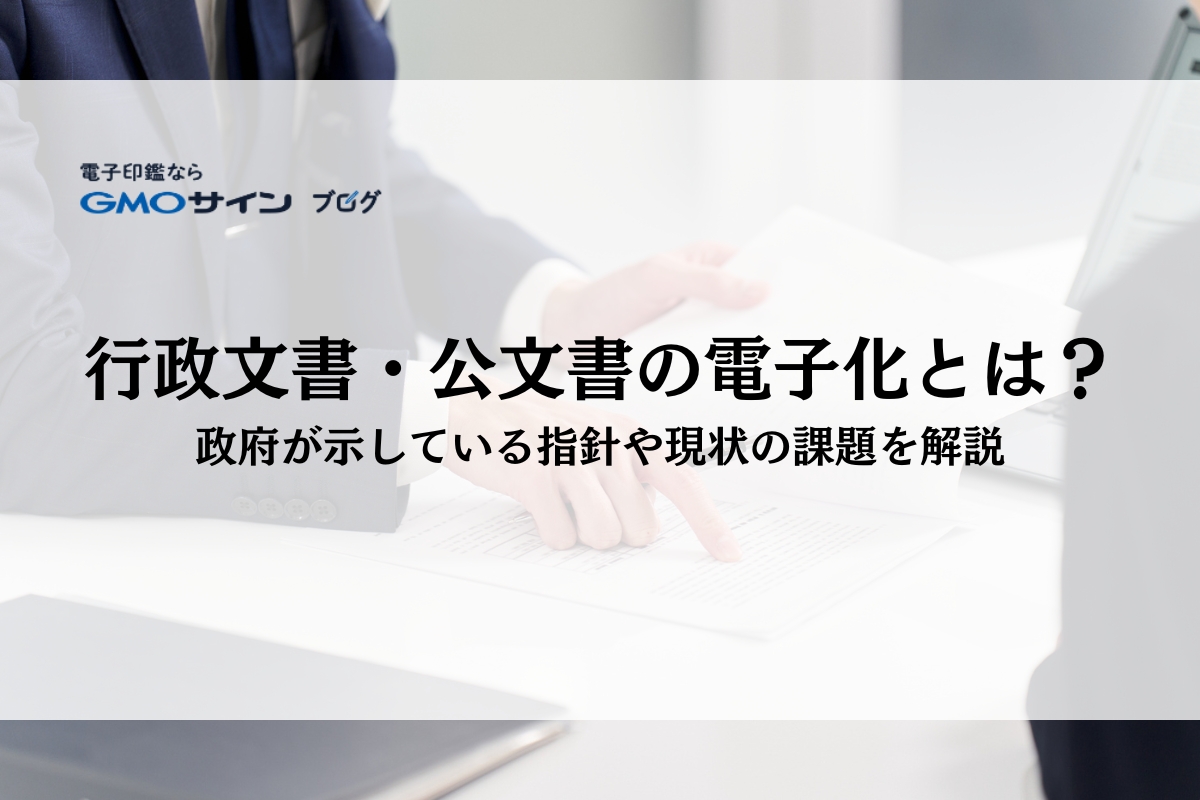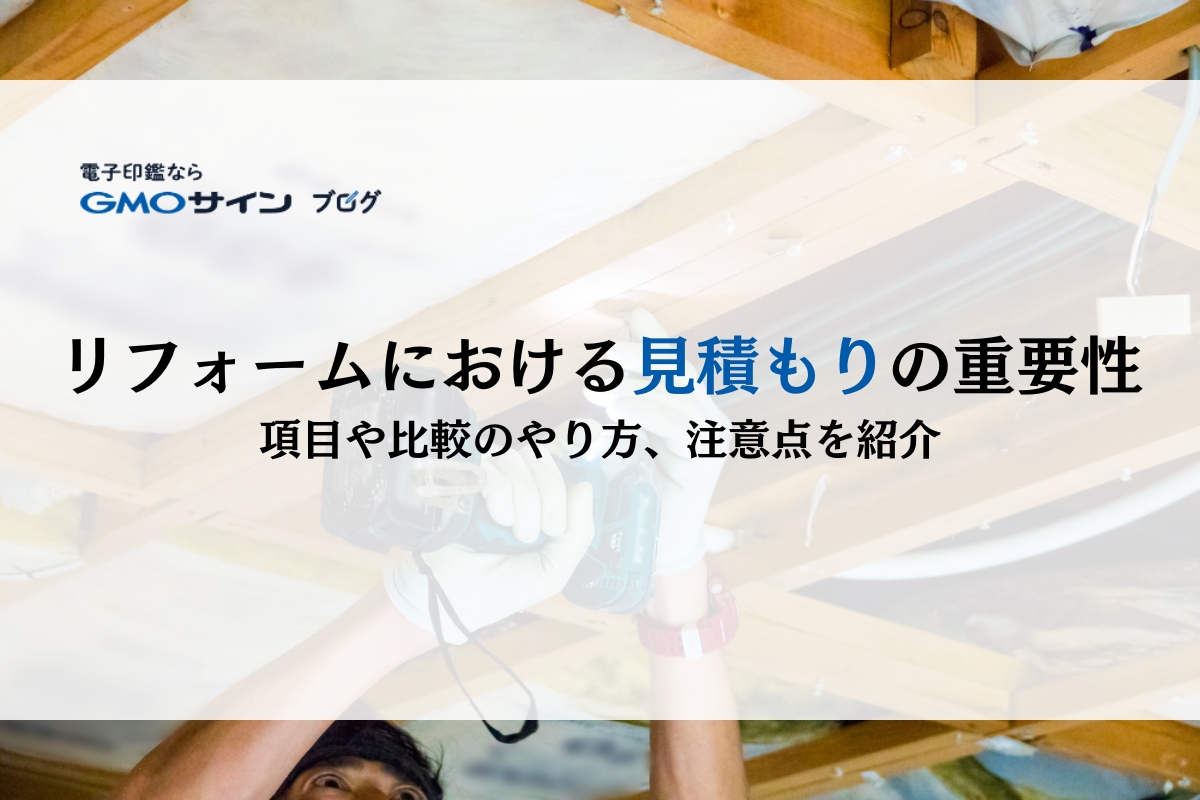ニュースなどで、懲役〇年・執行猶予〇年といった言葉を耳にしたことはないでしょうか。しかし、判決が下されたからといって、必ずしも刑務所に収監されるわけではありません。
懲役とは刑務所の中に一定期間収監されることです。このことは、多くの人が知っているかもしれません。しかし、具体的に懲役とはどのようなものなのか、よく知らない人も多いでしょう。そのほかにも禁錮という判決もあります。同じく刑務所に入りますが、懲役と禁錮には扱いに違いが見られます。
本記事では、懲役と執行猶予の基礎知識や違いなどをわかりやすく解説します。
懲役とは
懲役とは、決められた期間刑務所に入って特定の労役を強いられる刑罰です。では懲役刑を受けた場合、その人はどのようなかたちで罪を償わなければならないのでしょうか。
身体の自由が制限される
数ある刑罰の中でも懲役は、自由刑の一種です。自由刑とは体の自由が制限されることを意味します。懲役刑に処されると、その人は一定期間刑務所に入らなければなりません。
刑務所を出るなどの自由な行動はもちろんできません。罰金などの財産刑と比較すると、重い刑罰といえます。
刑務作業が課される
懲役刑と混同しやすい刑罰として、禁錮があります。しかし、懲役と禁錮の区別が付かない人もいるでしょう。両者の違いは、刑務作業を伴うかどうかです。
懲役では刑務作業が課されるのに対し、禁錮の判決が出た場合、刑務作業は免除されます。禁錮は懲役刑と比較すると、刑罰としてはやや軽めです。刑務作業はおもに以下の4種類があります。
生産作業
生産作業とは文字通り、物品を生産する作業のことです。木工や金属加工などが一般的です。作られた製品は、私たち一般人も購入できます。
社会貢献作業
社会貢献作業とは、社会に貢献できる作業のことです。具体的には除雪作業や除草作業が該当します。
職業訓練
職業訓練は、溶接やフォークリフト、自動車整備、介護など様々な職業訓練に対応しています。職業訓練によって、働くうえで必要な免許や資格を取得することが可能です。出所後の円滑な就職を支援する目的もあります。
自営作業
自営作業とは受刑者が生活するために欠かせない作業を担当することです。受刑者に提供する食事の調理、洗濯などが当てはまります。
懲役中の生活
懲役中は刑務所の中で生活しますが、自由に過ごせるわけではありません。まず起床は6時40分、就寝は21時と決まっており、日中は刑務作業を行います。起床時間などは刑務所によって異なる場合もありますが、おおまかな流れは変わりません。
ただし、ずっと刑務作業を続けるわけではなく、自由時間も夕食後には設けられています。時間は限定されるものの、テレビを見たり読書したりすることも可能です。食事は1日3食提供されます。ただし決められたメニューを食べることになり、食事内容も自由に選択できません。
有期刑と無期懲役
懲役期間ですが、有期と無期があります。有期刑の場合、期間があらかじめ決められています。期間は1カ月以上20年以下で、犯した罪の重さにあわせて期間が決められます。
一方、無期懲役の場合は文字通り、懲役の期間が決められていません。
法律上は10年以上刑に服すと仮釈放で外に出られる可能性がありますが、実際には30年以上かかる事例が多いようです。
執行猶予
判決の中で懲役〇年・執行猶予〇年とされ、執行猶予の付くケースも少なくありません。執行猶予が付くと、ただちに刑務所に入らずに済みます。
執行猶予の概要
執行猶予とは、判決の中で決められた刑罰を一定期間猶予するという意味です。
たとえば、懲役1年6カ月執行猶予2年の判決が出たと仮定しましょう。もし判決が出てから問題を起こさずに2年経過すれば、1年6カ月の懲役刑は免れます。
全部執行猶予と一部執行猶予の違い
執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予の2種類があります。
全部執行猶予
全部執行猶予とは、執行猶予の期間中再び問題を起こさなければ、刑罰のすべてが失効されてなくなることです。つまり、問題を起こすことなく猶予期間が経過すれば、すべての刑の執行が無効になり刑務所に入らずに済みます。
一部執行猶予
一部執行猶予とは、刑罰のうち一部の刑を執行するという意味です。
一部執行猶予の場合、「懲役1年6カ月、その刑の一部である6カ月の執行に関しては2年間猶予する」といった判決が出ます。この場合、まずは1年間懲役刑を受けます。そして執行猶予の2年間を問題なく過ごせば、残り6カ月の懲役刑は免除されるという意味です。
一部執行猶予をはじめて聞いたという方も多いかもしれません。施行されたのは2016年のため、比較的新しくできた制度といえます。
執行猶予を受けるには?
執行猶予付きの判決を受けるためには一定の条件があります。以下で紹介するように、刑法の中で明記されています。
(刑の全部の執行猶予)
(参考:e-Gov法令検索)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
殺人や放火のような重大犯罪の場合、3年以下の懲役になることはまず考えられません。つまり、一発で実刑になる可能性がかなり高いです。また、罰金と書かれていますが、罰金で執行猶予が付く事例はまずないと思ったほうがよいでしょう。
執行猶予の期間については、1〜5年と法律で定められています。明文化されているわけではありませんが、一般的に懲役や禁錮の年数の1.5〜2倍程度が執行猶予の期間になることが多いです。
執行猶予が付くメリット
執行猶予が付く最大のメリットは、刑務所に入る必要がない点です。執行猶予期間中は、特に行動の制約はありません。どこに出かけてもよいですし、仕事をしても問題ありません。社会復帰が早期に行え、更正も期待できます。
しかし、執行猶予とされても、前科が付くことに関しては違いがありません。今後の就職や転職活動でマイナスの影響を及ぼす可能性があることは頭に入れておきましょう。
執行猶予を得るための対策
執行猶予が付くのか、実刑になるのかは被告にとって大きな問題です。刑務所に入るか否かという点で、大きな違いがあるからです。
反省していることをアピールする
裁判官に今回犯した犯罪について真摯に向き合って反省している態度を示すことは基本です。反省していることが裁判官に伝われば、刑務所に収監しなくても更生の可能性があるという心証を持たせられるからです。
具体的には反省文を書いて提出する、法定の中で反省していることをアピールするなどの方法が考えられます。また慈善団体に贖罪寄付することで、反省している態度を示す方法も見られます。
示談交渉をする
もし被害者がいるのなら、被害者との示談交渉を進めることも執行猶予となるために必要なことです。刑の重さを決めるにあたっては、被害者感情が重視されるからです。
示談が成立すれば、被害者が加害者をある程度許していると推測できます。処罰感情がそこまで強くなければ、執行猶予が付くかもしれません。
身元引受人を確保する
身元引受人を用意すると、執行猶予が付く可能性が高まります。身元引受人は被告の生活を監督する役割を担います。再犯を犯さないようにチェックしてくれる第三者がいれば、裁判官としても執行猶予を付けやすくなるでしょう。
身元引受人の資格には、特に決まりはありません。一般的には家族などの親族にお願いすることが多いです。親族が身元引受人になってくれない場合には、職場の上司に頼む方法も検討できます。
犯罪を誘惑するものを断ち切る
再犯の可能性が高いと裁判官が判断すれば、実刑判決になる可能性も高くなります。逆にいえば、再犯しないように努力している姿を見せれば、執行猶予が付きやすくなるということです。犯罪に手を染める要因を排除するように努めましょう。
実刑判決を受けたら?
判決の結果、執行猶予とならないケースも出てきます。もし実刑判決を受けてしまったら、原則そのまま刑務所に収監される流れになります。しかし、納得いかなければ、控訴などの対応策もあるため検討してみましょう。
控訴する
実刑判決に納得いかない場合、控訴する権利があります。控訴すると上級の裁判所で審議され、場合によっては執行猶予付きの判決に変わったり、無罪判決が出たりする可能性もゼロではありません。
仮釈放のための努力をする
実刑が避けられそうになければ、仮釈放を取る努力をすることです。刑期が満了する前に仮釈放が認められれば、当初よりも早く刑務所から出られる可能性が出てきます。
仮釈放を勝ち取るためには、刑務所内での態度が重要です。懲役刑の目的のひとつに矯正があります。規律正しく労働に励む姿を見せることで、態度良好と判断され仮釈放が早めに可能となるかもしれません。
懲役に関するよくある質問
懲役と禁錮の違いは何?
懲役と禁錮の主な違いは「刑務作業の義務があるかないか」です。
懲役刑を受けた人は刑務所で暮らしながら、工場での作業など決められた仕事をしなければなりません。これに対して禁錮刑の場合は、同じく刑務所で過ごしますが、作業は義務ではありません。
また一般的に、懲役の方が禁錮よりも重い罰とされています。
懲役と罰金の違いは何?
懲役と罰金は刑罰の種類がまったく異なります。懲役は「自由刑」といって、自由に行動する権利を制限され、刑務所で生活しながら作業をする罰です。一方、罰金は「財産刑」で、決められたお金を国に支払う罰です。
罰金刑なら刑務所に入る必要はありませんが、支払えない場合は「労役場留置」となり、作業をさせられることもあります。どちらの刑罰も、判決が確定すれば「前科」として記録されます。
懲役と執行猶予の違いを正しく理解しよう
懲役刑は刑務所に収監され、一定の制約の中で刑務作業に励まなければなりません。しかし、罪の内容や加害者の態度次第では、執行猶予が付く可能性もあります。
執行猶予付き判決を得るためには、被害者との示談交渉や身元引受人の確保など、様々な方法が考えられます。
もし罪を犯してしまったのであれば、法律の専門家である弁護士に速やかに相談するのがおすすめです。また執行猶予が付かなくても、控訴することで判決が変わる可能性もあるため、対策を講じましょう。
住宅ローンの契約もオンラインの時代へ
住宅ローンの金利や保障内容を比較検討する中で、契約手続きの煩雑さに驚いている方も多いのではないでしょうか。大量の書類への署名・捺印、収入印紙の準備、金融機関への来店など、時間も手間もかかるのがこれまでの常識でした。
しかし近年、こうした住宅ローン契約の手続きに「電子契約」を活用する金融機関が急速に増えています。
電子契約を導入することで、利用者には以下のような大きなメリットがあります。
- 収入印紙が不要になる(コスト削減):紙の契約書で必須だった数万円の収入印紙が、電子契約では不要になります。
- 来店不要で手続きが完結する:スマートフォンやパソコンがあれば、場所や時間を選ばずに契約手続きを進められます。
- 書類の管理が簡単・安全になる:契約データはオンラインで安全に保管されるため、大量の契約書を自分で管理する手間や紛失のリスクがありません。
実は、こうした金融機関のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支えているのが、電子印鑑GMOサインをはじめとする電子契約サービスです。
住宅ローンのような重要な契約にも活用される高いセキュリティと信頼性を備えた「GMOサイン」は、不動産/金融業界はもちろん、さまざまな業界のビジネスシーンで導入が進んでいます。皆さまのお仕事における契約業務も、もっとスムーズで効率的に変えることができるかもしれません。
契約業務の改善にご興味のある方は、ぜひ「GMOサイン」の公式サイトもご覧ください。