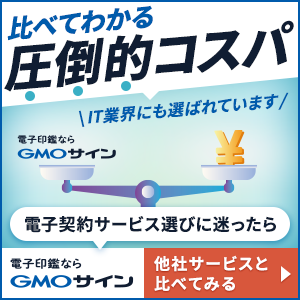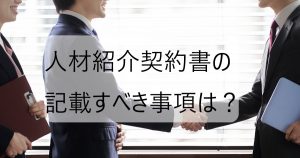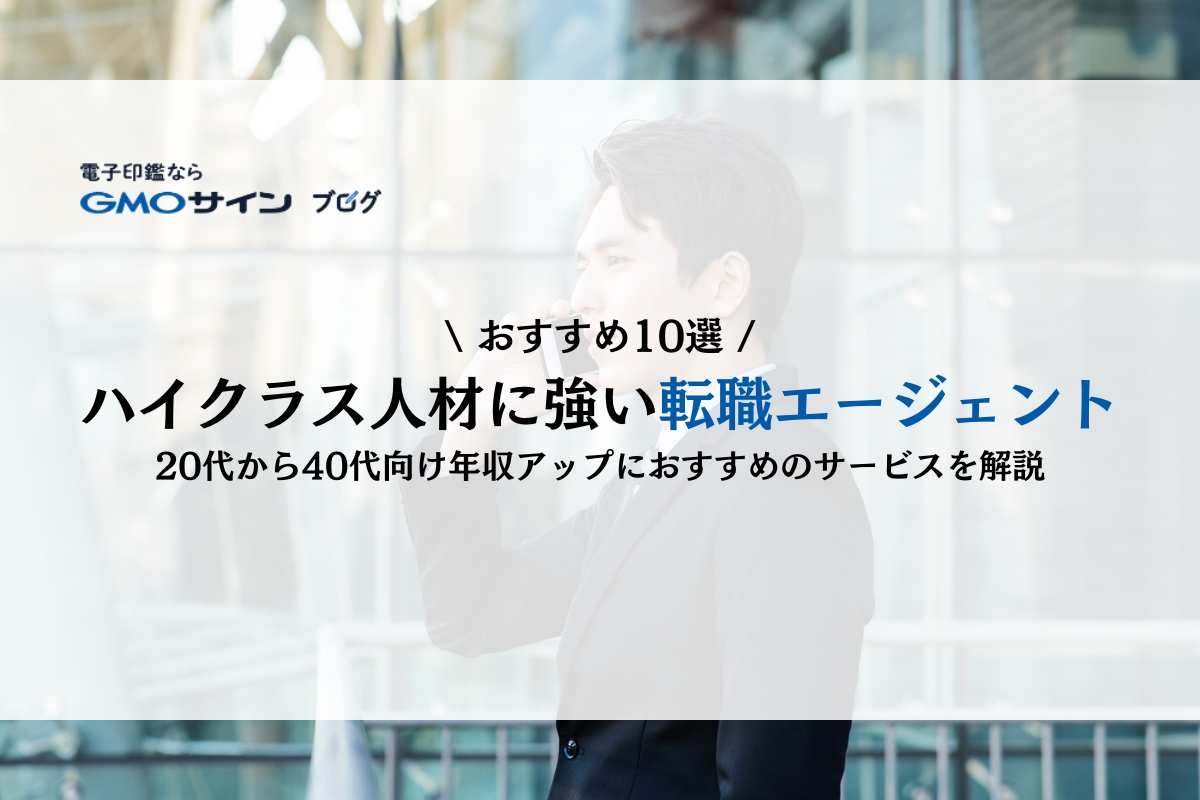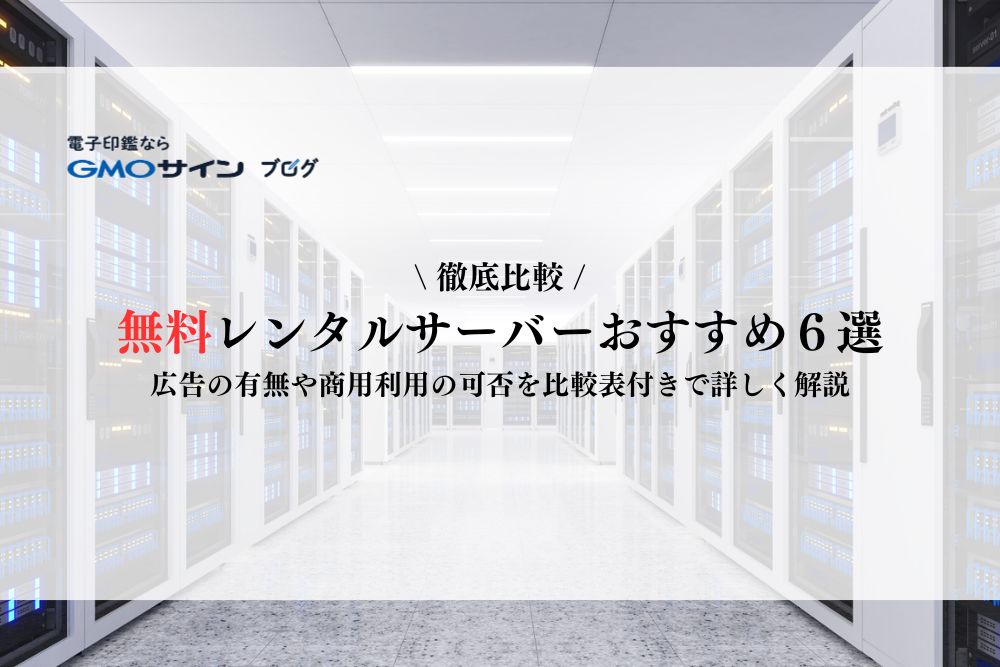長時間労働の削減や多様な働き方の実現を目指し、企業における働き方も多様化しています。これまで多くの企業では、社員やアルバイトなど自社で直接雇用した人材に出来る限り長く働いてもらえるよう教育を行ったり環境を整えたりするのが一般的でした。一方で最近は、事業を取り巻く環境変化の早さなどを理由に、請負や委託など外部の人材に業務をアウトソーシングすることも珍しくありません。
そこで今回は、業務のアウトソーシングを検討中の担当者様向けに、業務請負と業務委託の違いをわかりやすく解説します。混同しやすい委任契約や派遣契約との違いも整理し、それぞれのメリット・デメリット、契約書作成時の注意点、そして注意すべき下請法についても詳しくお伝えします。
業務請負、業務委託の概要と特徴
自社業務をアウトソーシングする際に必要な業務請負と業務委託、それぞれの概要や違い、特徴について解説します。
業務請負とは
業務請負とは、企業が何らかの仕事(業務)の完成を約束する契約方法の一つです。
業務請負の特徴は、業務の結果に対して報酬を支払う点いわゆる成果報酬である点にあります(民法632条)。つまり業務を請け負った側は、完成品を納品できないと契約を履行したことになりません。
(請負)
出典:民法 | e-Gov法令検索
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
具体的には、施工会社に自社商品の製造工場建築を依頼する、Webサイト製作会社に自社商品を販売するためのショッピングサイト制作を依頼するなどの契約です。
業務委託とは
業務委託とは、「業務請負契約」と「委任・準委任契約」の総称です。つまりさきほど紹介した業務請負は業務委託の一部といえます。
また、企業が受託者に対し業務請負契約を行う際の契約書は「業務委託契約書」が一般的ですが、これは委任・準委任契約の際にも利用できます。
委任契約・準委任契約とは
委任契約、準委任契約は、それぞれ次の民法による法律行為です。
- 委任契約(民法643条)
-
企業や依頼する側が受託者に対し法律行為を委託し、受託者の承諾により成立するものです。
(委任)
出典:民法 | e-Gov法令検索
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 - 準委任契約(民法656条)
-
委任契約とは異なり、法律行為ではない業務、事務などを委託するものです。
(準委任)
出典:民法 | e-Gov法令検索
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
委任契約における法律行為とは、具体的に弁護士に訴訟行為を依頼する、税理士に確定申告の手続きを依頼する、公認会計士に会計監査を依頼するなどを指します。業務請負契約のように何かしらの完成品を求めるものではありません。
一方、準委任契約とは、外部のシステムエンジニアのシステム設計を依頼する、経営コンサルタントに自社のコンサルティングを依頼するなどの行為を指します。これも業務請負契約のように具体的な完成品を求めるものではなく、業務遂行が契約の目的です。
派遣契約との違い
自社の社員以外に業務を委託するという意味では、人材派遣会社との契約も同様と思われるかもしれません。しかし、業務請負・委託契約と派遣契約では、次の2点が異なります。
自社が指揮命令権を持って指示ができる
業務委託契約(請負、委任、準委任)は、受託者に対し、基本的には指揮命令権を持って指示を与えることはできません。これに対し、派遣契約では、自社に派遣された人材に対し、指揮命令権を持って指示を与えられます。つまり派遣された人材は依頼した企業の管理下におかれますが、業務委託・請負契約では、依頼した企業と受託者の立場は対等です。
契約内容
派遣契約では、企業は派遣された人材が働いた時間に対して賃金(派遣料金)を支払います。しかし業務請負は完成品に対して、委任・準委任は委任契約の履行に対して報酬を支払う契約です。
\\ こちらの記事もおすすめ //
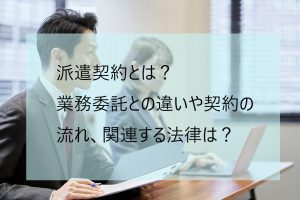
業務請負・業務委託を活用するメリット
企業が業務請負・業務委託を活用する際の主なメリットは次のとおりです。
自社社員の雇用・教育コストの削減
業務請負・委託契約を行うことで、企業は専門的な業務遂行に対し、新たな社員の雇用や既存社員に対する教育コストの削減が可能になります。
たとえば新規事業に必要なシステム開発やそれに伴う設備に投資するコスト削減も可能です。これらのコストを販売促進や店舗出店など他業務に使えるようになるのは大きなメリットといえるでしょう。
労務管理の手間やコストの削減
通常、新たに自社で人材を雇用する場合、必要になるのは雇用にかかわるコストだけではありません。
健康保険料や厚生年金保険料などの法定福利費、勤怠管理や安全衛生管理のような労務管理など、多くの手間とコストが発生します。しかし、外部に業務請負・委託を行えば、これらのコストを抑えることが可能です。
専門人材や即戦力人材のノウハウを活用できる
専門的な知識や技術を持つ即戦力人材のノウハウを存分に活用できるのも、業務請負・委託契約を利用するメリットといえます。
自社の人材に教育する時間が必要なくなるため、スピーディーに業務を進めることが可能です。競合に遅れを取ることなく、先行者優位の立場に立てる可能性も高まるでしょう。
長期の契約も可能
業務請負・委託は長期の契約も可能です。これにより自社のコストを抑えつつ、安定した業務を継続できる上、受託者が持つ専門知識やスキルを長期活用できるのは大きなメリットといえます。
企業が業務請負・業務委託によって生じるデメリット
企業が業務請負・業務委託によって生じる主なデメリットは次のとおりです。
委託した業務の進め方について指示を出せない
企業は、委託した業務の進め方や進捗状況について細かく管理、指示をすることはできません。そのため、スケジュール通りに進んでいれば問題ないものの、業務が滞りがちになった場合、細かい管理ができないと企業の損失につながるリスクが生じてしまうでしょう。
情報漏洩のリスクが高まる
委託する業務によっては、企業が持つ個人情報や機密情報を扱うケースもあり、外部への情報漏洩リスクが高まります。
専門的な業務のノウハウが社内に蓄積されない
業務請負・委託契約をした場合、基本的にすべての業務を受託者が行うため、自社内に委託した業務のノウハウや技術は蓄積されません。
その結果、たとえば、システム開発を依頼した場合、納品により契約が終了した後に、メンテナンスやトラブルが発生しても対応できず、業務が止まってしまうリスクがあります。
委託する業務内容によってはコスト高になる場合もある
業務請負・委託は長期契約できるのがメリットの一つです。しかし、多くの場合、自社では難しい専門知識が必要な業務のため、報酬は高額になるケースも少なくありません。
業務請負・業務委託を利用する際は下請法に注意
業務委託や業務請負は、多くの企業にとって重要な経営戦略の一つです。しかし、これらの取引を行う際には「下請法」に注意が必要です。知らずに違反してしまうと、罰則の対象となる可能性もあります。
本章では、企業の担当者が押さえておくべき下請法の基本を、適用対象から親事業者の義務・禁止事項までわかりやすく解説します。
下請法とは?
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、発注者である「親事業者」と受注者である「下請事業者」との間の取引を公正にし、立場の弱い下請事業者の利益を保護するための法律です。
下請法が適用される取引かどうかは、「取引の内容」と「両社の資本金規模」の2つの条件によって決まります。
下請法の適用対象
ご自身の会社(親事業者)と取引先(下請事業者)の資本金が以下の条件に当てはまる場合、下請法が適用されます。
①製造・修理・プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理などの委託
- 発注者の資本金が 3億1円超 → 受託者の資本金が 3億円以下 の場合に適用
- 発注者の資本金が 1,000万円超〜3億円以下 → 受託者の資本金が 1,000万円以下 の場合に適用
②デザイン・設計図面作成、ビルや機械のメンテナンス、コールセンターなどの役務提供
- 発注者の資本金が 5,000万円超 → 受託者の資本金が 5,000万円以下 の場合に適用
- 発注者の資本金が 1,000万円超〜5,000万円以下 → 受託者の資本金が 1,000万円以下 の場合に適用
親事業者の4つの義務
下請法が適用される取引では、親事業者には主に以下の4つの義務が課せられます。
- 書面の交付義務(第3条)
契約内容(給付内容、下請代金額、支払期日など)を明確に記載した書面を、発注後直ちに下請事業者に交付しなければなりません。 - 支払期日を定める義務(第2条の2)
下請代金の支払期日は、納品物やサービスを受領した日から60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。 - 書類の作成・保存義務(第5条)
取引の記録(給付内容、下請代金額など)を記載した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。 - 遅延利息の支払義務(第4条の2)
定められた支払期日までに代金を支払わなかった場合、納品物を受領した日から60日を経過した日から、実際に支払う日までの日数に応じて**年率14.6%**の遅延利息を支払わなければなりません。
親事業者の11の禁止事項
親事業者には、下請事業者に対して以下のような不当な行為をすることが禁止されています(下請法第4条)。
- 受領拒否
下請事業者に責任がないのに、発注した物品やサービスの受領を拒むこと。 - 下請代金の支払遅延
下請代金を定められた期日(受領後60日以内)までに支払わないこと。 - 下請代金の減額
下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた代金を減額すること。 - 返品
下請事業者に責任がないのに、受領した物品を返品すること。 - 買いたたき
市場価格などに比べて著しく低い代金を不当に定めること。 - 購入・利用強制
正当な理由なく、自社が指定する製品やサービスを強制的に購入・利用させること。 - 報復措置
下請事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引量を減らすなどの不利益な取り扱いをすること。 - 有償支給原材料等の対価の早期決済
有償で支給した原材料の代金を、下請代金の支払期日より早く支払わせたり、下請代金から差し引いたりすること。 - 割引困難な手形の交付
支払期日までに現金化することが難しい手形を交付し、下請事業者の利益を害すること。 - 不当な経済上の利益提供要請
自己のために金銭やサービスなどを不当に提供させること。 - 不当な給付内容の変更・やり直し
下請事業者に責任がないのに、費用を負担せずに内容の変更ややり直しをさせること。
罰則
親事業者が「書面の交付義務」や「書類の作成・保存義務」を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります(下請法第10条)。
また、禁止事項に違反した場合は、公正取引委員会から勧告や指導を受けることになり、企業名が公表されることもあります。コンプライアンス遵守の観点からも、下請法の正しい理解と運用が不可欠です。
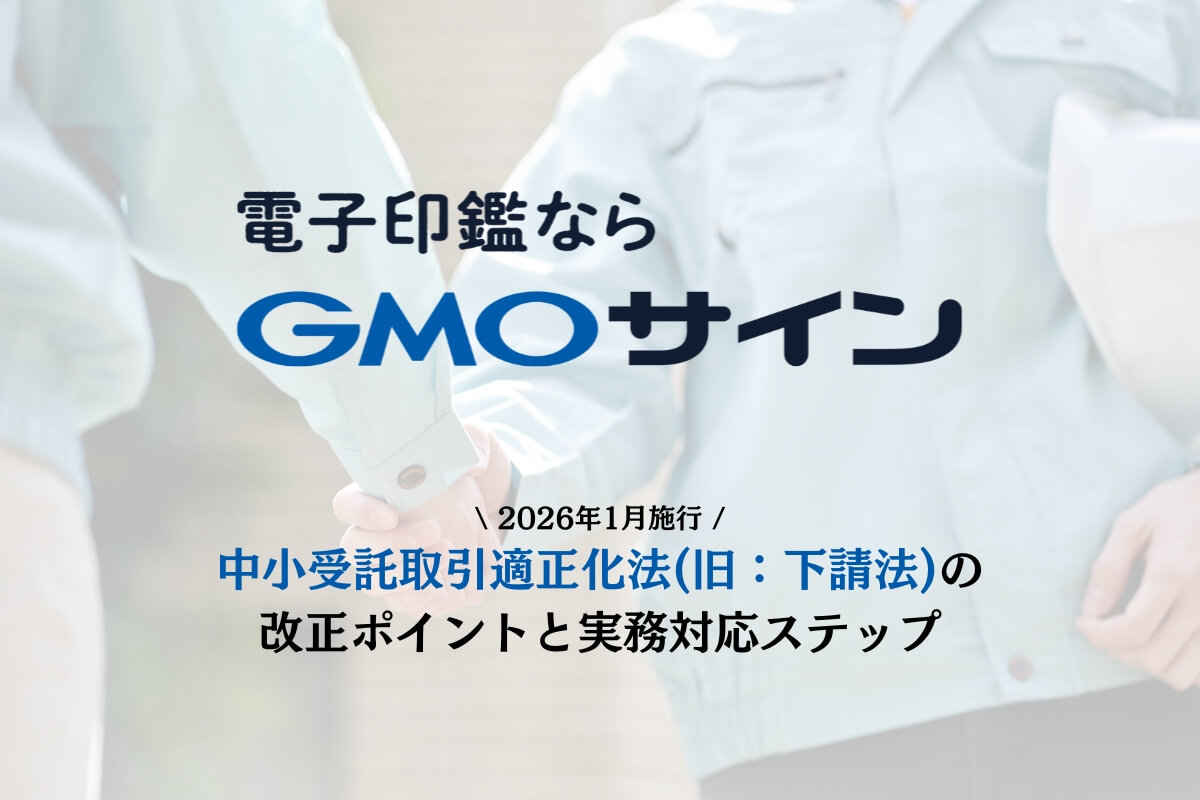
業務委託契約書に記載する内容
業務請負・委託を依頼する場合、必ずしも契約書を作成する必要はありません。実は民法上口頭での確認だけでも契約は成立します。ただし、前述した注意点については、明確に書面に記載しておかなければ、トラブルが起きた際の解決が困難です。
そこで、企業の人事担当者としては、業務委託契約書の作成が必須であり、記載方法を知っておく必要があります。ここでは、一般的な業務委託契約書の書き方、記載する内容を見ていきましょう。
必ず記載しておくべき項目
業務委託契約書に必ず記載しておくべき項目は次のとおりです。
依頼する業務の内容
依頼する業務の内容や範囲については具体的に記載しておく必要があります。特に業務範囲が明確でないと、企業側は当然やってもらうべき内容と思っていても、受託側に依頼されていないと言われれば何も言えません。
また、依頼側と受託者の特定も必須です。偽装請負などのリスクを防ぎ、お互いの義務と責任を明確にしておくことで、後々のトラブル防止にもつながります。
契約期間と報酬
業務請負契約の場合、いつまでに完成品を納品するのか、委任や準委任の場合についても、契約期間を明示しておくことで、契約終了や延長の手続きがスムーズになります。
そして、納品した場合の報酬額、支払い期日、方法、振込手数料の負担者まで明確にしておきましょう。また、業務を行う上で必要になる経費の支払いについても、依頼側がどこまで負担するかは明確にしておかなければなりません。
契約において、金銭に関わるものはトラブルにつながるリスクが高いため、事前に契約書に明示しておくことをおすすめします。
契約を解除する場合の理由
トラブル時も含め、どうなったら契約を解除するのかの理由も明示しておきましょう。たとえば、完成品を納品したら契約を解除する、そこから保守メンテナンス契約に切り替えるなど、契約形態を明確にすることで、トラブル防止が可能です。
そのほか、明示しておいた方がよい項目
必ず明示しておくべき項目のほかにも、次の項目については明示しておけばトラブル回避につながります。
損害賠償
当事者間でトラブルが発生した際の損害賠償についても明示する必要があります。どこまでを損害の範囲とするか、賠償金はどの時点から発生し、いくらを上限とするかを明確にしておきましょう。
民法641条では、受託者側が依頼した業務を終えない間、企業側はいつでも損害賠償をした上で契約を解除できるとしています。
一方で、請負契約において、受託者(請負人)の都合で契約を解除できるケースは法律上限定的です。例えば、注文者(企業側)が破産手続開始の決定を受けた場合などには解除が認められています(民法642条1項)。そのため、それ以外の理由で受託者側から解除できる可能性を残す場合は、契約書にその旨を明記しておく必要があります。
なお、委任・準委任は、当事者双方がいつでも解除可能です。ただし相手方に不利な時期の解除等では損害賠償が必要になることがあります(民法651条)。
知的財産権
たとえば、業務請負契約において、受託者が制作した完成品の所有権はどうするのかを明示しておくことも重要です。
通常、完成品を納品した時点で所有権は発注者側に譲渡されます。しかし、完成品を作成するなかで特殊な技術を使った場合、その部分に関しての知的財産権をどうするのかは互いに話し合っておく必要があるでしょう。
仮に納品したシステムを企業側が外部に販売する場合、受託者側とライセンス契約を締結し、利益の一部を支払う点についても明示しておかなくてはなりません。
秘密保持(NDA)契約
企業が受託者に要求するもので、業務を行う上で必要とする企業の機密情報に関して、情報流出を防ぐための契約です。
具体的には、業務に必要なシステムを作成する際、企業の個人情報を利用する場合、経営コンサルタント契約をする際、企業の財務状況を把握する必要がある場合などが挙げられます。
再委託
再委託とは、業務請負・委託契約を行った受託者が、自分以外の第三者に業務の委託をすることを指します。
委任・準委任契約は、委任者と受任者の信頼関係を基礎とするため、原則として受任者自身が業務を遂行すべきとされています。そのため、受任者が第三者に業務を再委託するには、原則として委任者の許諾が必要です(民法644条の2)。
一方、業務請負契約において再委託に関する定めは特にありませんが、依頼する企業側としては、第三者に業務を再委託されてしまうと、完成品の品質が落ちてしまうリスクがあります。そのため、再委託して欲しくない場合は、契約書に再委託の禁止について明示しなくてはなりません。
合意管轄
契約期間中、もしくは契約終了後でも何らかの取り決めがあった際、トラブルがあった場合に行う裁判についても明示しておく必要があります。
企業側、受託者側が所在する場所が離れている場合、どこの裁判所で裁判を行うかは交通費や滞在費も含め多くの費用を要するため、事前に確認して上で明示しましょう。
依頼者側である企業に近い裁判所を設定するのが一般的ではあるものの、公平性や実務上の便宜も考慮し、互いにとって不利益にならない設定が欠かせません。
\\ こちらの記事もおすすめ //

業務委託契約は電子契約でも締結可能
業務委託契約は、書面契約だけでなく電子契約でも締結が可能です。具体的な手順を見てきましょう。
契約書の準備
前章で紹介した内容やこちらの記事を参考に、業務委託契約書をWordやGoogleドキュメントで作成します。契約書の内容についてはメールやチャットで契約相手方に共有し、互いにレビューを行うことで、内容のすり合わせを実施します。
電子契約サービスへのアップロード
契約書の内容が固まったら、電子印鑑GMOサインなどの電子契約サービスにアップロードします。なお、事前に電子契約サービスへの利用申し込みが必要ですが、GMOサインのお試しフリープランであれば、すぐに申し込みが完了しその場で電子契約を実施できます(月に5件まで無料)。
アップロードする際のファイル形式はお使いの電子契約サービスにもよりますが、PDFやWord形式でのアップロードが一般的です。
電子署名の設定を行い送信
署名者や署名欄の位置設定など、契約書の最終準備を電子契約サービス上で行い、問題なければ、相手方に送信します。一般的にはメールアドレス宛に署名依頼を送る形になりますが、SMSでの送信が可能なサービスも存在します。
受取人側はメールアドレスに記載のリンクをクリックし、署名依頼に対応します。設定された署名者による電子署名がすべて完了したら、保存用の契約書データが契約当事者双方に送信されます。
お使いのサービスによって細かな部分は異なりますが、電子契約を締結する際の大まかな流れは以上です。いきなり取引先との契約に利用するのは躊躇するという方は、自身が持つサブメールアドレスを相手方に設定して、一通り流れを体験してみるなどもおすすめです。月5件まで電子署名(立会人型)を利用可能なGMOサインのお試しフリープランをぜひご活用ください。
\\ 最短③分でアカウント作成完了 //
業務委託をする際は法律を理解し、受託者と契約内容をしっかり話し合うことが重要
業務請負とは、業務委託の一部であり、依頼する側が受託者からの完成品の提供を持って完了とする契約を指します。業務委託は、業務請負契約のほか、委任契約と準委任契約があり、これらの総称です。
企業が業務委託をする際は、自社と受託者(企業)の資本金額により、下請法が適用される可能性がある点に注意する必要があります。下請法に反すると罰金を科される場合もあるため、しっかりと把握した上で契約を交わすようにしましょう。
また、情報漏洩や知的財産の保護など、受託者と明確にしておかなければならない点も多くあります。業務委託をする際は、法律の把握はもちろん、受託者としっかり話し合うことが重要といえるでしょう。