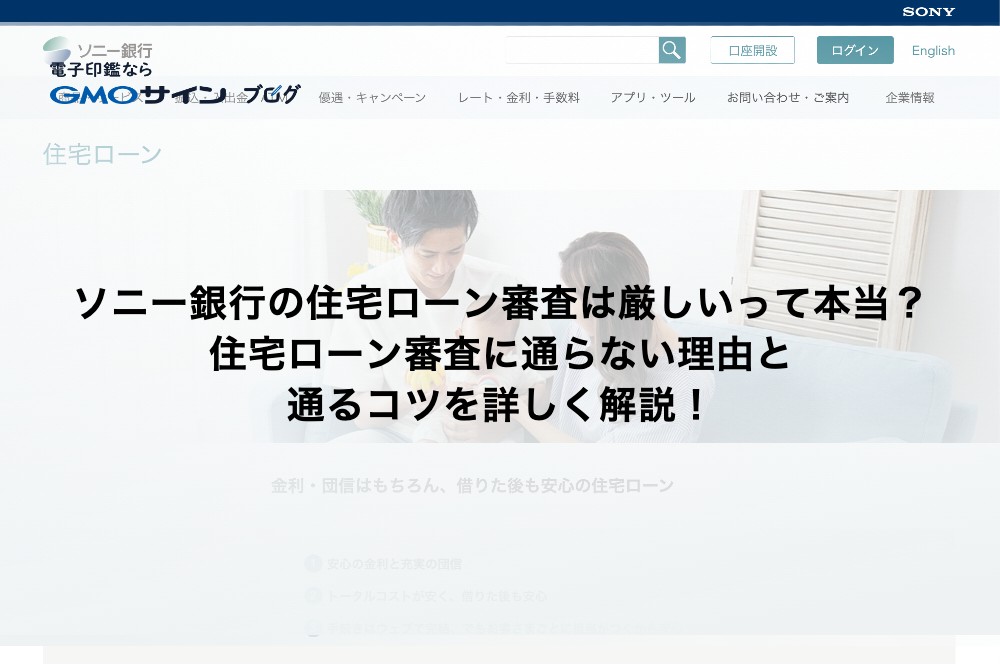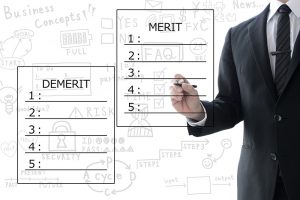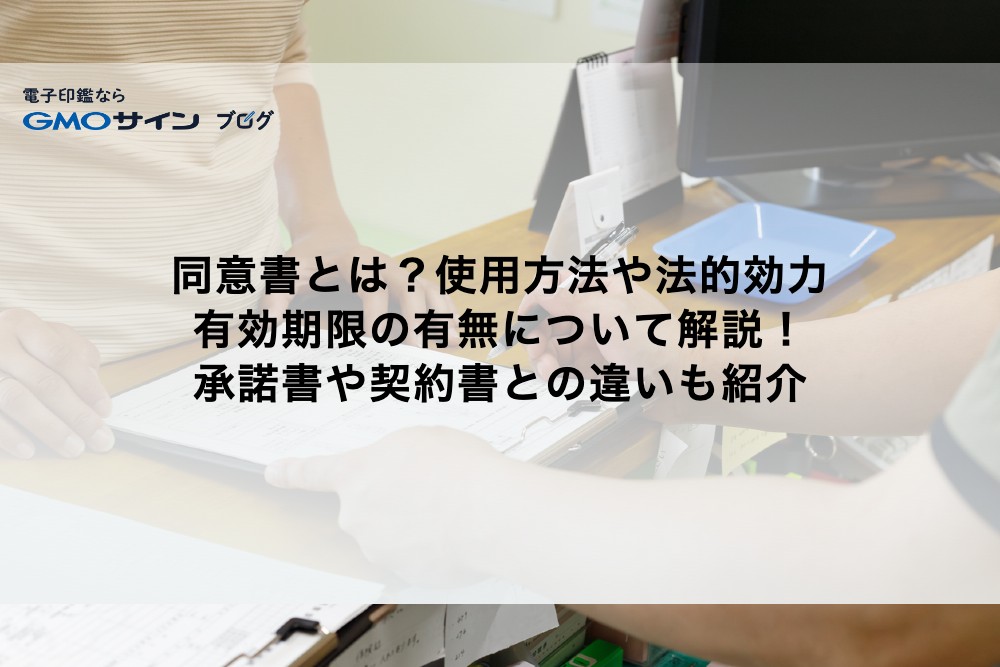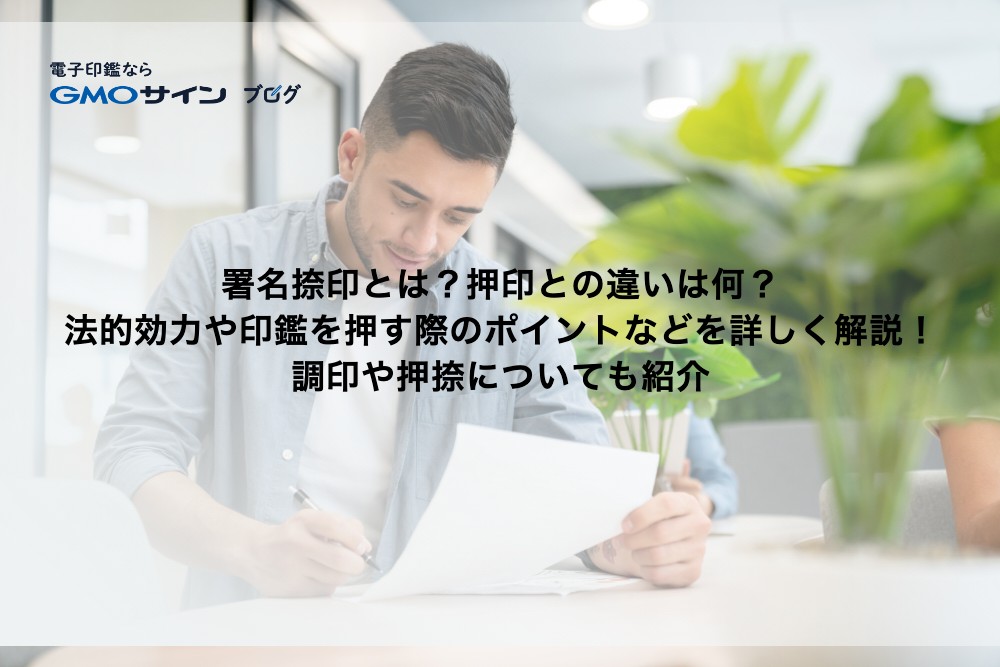所定労働時間は、企業が従業員に対して定める働く時間のことです。働き方の改革が求められている現代では、所定労働時間や法定労働時間の内容を把握して、適切な環境が設定されているのか確認することが大切です。
この記事では、所定労働時間や残業の定義、36協定の内容などをわかりやすく解説します。所定労働時間がどのようなものなのか、かんたんに理解が深まるのでぜひ参考にしてみてください。
所定労働時間とは?
会社で働くにあたっては、必ず労働時間が設定されています。その詳細は企業ごとの就業規則や個別の労働契約にて定められていますが、この設定されている労働時間が所定労働時間です。
所定労働時間とは、会社の始業時間から終業時間までの勤務時間から休憩時間を引いた時間が該当します。たとえば、始業時間が午前10時、終業時間が午後7時で休憩時間が1時間設けられている場合は、所定労働時間は8時間になります。
また、休憩時間については、労働基準法第34条で以下のように定められています。
(休憩)
引用:労働基準法第34条|e-Gov法令検索
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働の内容に関係なく、上記の時間を超える場合は、それぞれ定められた時間を従業員に取得させなければなりません。そして第34条に基づけば、6時間未満の場合は休憩時間を与えなくてもよいとされています。
所定労働時間は法定労働時間に基づいて設定
法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の上限を意味します。所定労働時間は、この法定労働時間に基づいて設定しなければならない勤務時間のことを指します。労働基準法第32条では、以下のように定められています。
(労働時間)
引用:労働基準法第34条|e-Gov法令検索
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
また、同じく労働基準法の第35条には休日設定について明確に定められています。
(休日)
引用:労働基準法第34条|e-Gov法令検索
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働時間かどうかの判断
残業を行う人々が増加している現代において、労働時間の定義がどこにあるのかが度々話題になります。会社が定めた勤務時間は所定労働時間です。しかし、始業前や終業後にちょっとした作業を頼まれた時などは労働時間に含まれないのかといった疑問が浮かんできます。
その行為が労働時間に該当するかどうかは、客観的に使用者の指揮命令下に置かれていると判断できるかで決まります。所定労働時間に含まれていない時間帯であっても、使用者の指揮命令下で作業をしているとみなされれば、それは労働時間となります。
時間外労働について
法定労働時間を超えた労働時間は、時間外労働(法定時間外労働)に該当します。本来、従業員に時間外労働をさせることは労働基準法で禁止されていますが、36協定を締結した場合には例外的に認められています。
たとえば、所定労働時間が1日7時間であった場合、8時間の勤務を行なっても超過した1時間は法定労働時間内の労働です。そのため、この1時間に対して残業代が発生するかどうかは、企業ごとに異なります。
時間外労働の仕組みについては、事業者側も従業員側も正しく把握しておかなければなりません。
36協定とは
従業員に時間外労働を課す場合に、必ず締結しなければならないのがこの36(さぶろく)協定です。36協定は、法定外の労働や休日労働について、使用者と労働者の間で交わした取り決めです。
36協定は、労使協定であり労働基準法第36条で定められていることから36協定と呼ばれています。36協定は、労働者の過半数で組織された労働組合、あるいは労働者の過半数代表と書面で締結することが必要です。また、締結だけでなく労働基準局監督署長への届出も必要です。
36協定を締結することで原則1カ月45時間、年間で360時間を上限とした時間外労働が認められます。36協定を結んだとしても、これを超える時間外労働は原則認められていません。
長時間の残業は、従業員の体調を崩してしまうリスクも考えられるため、事業者側は仕事の配分などを上手く調整することが求められます。また、18歳未満の年少者は、原則として時間外労働を行わせることができないため注意しましょう。また、育児介護休業法に基づいて、時間外労働が制限される場合もあります。
残業の定義
会社で働くにあたっては、突発的な業務発生などによって、残業を余儀なくされる場合が多々あります。状況次第では従業員も残業に応じざるを得ない場合もあるでしょう。
残業にはそれぞれの定義が存在します。残業は、法定内残業と法定外残業の2種類に大別されます。それぞれで残業代の扱いについて違いがあるため、仕組みについて理解しておきましょう。
法定内残業
労働基準法で定められている法定労働時間内で行う残業が、法定内残業です。会社で通常勤務する所定労働時間は超過していても、法定労働時間は超過していないものがこれに該当します。
36協定を締結しない限り1日の勤務は、8時間を超過してはいけません。たとえば、所定労働時間が6時間で2時間の残業を行った場合、その2時間は紛れもなく残業です。しかし、法定労働時間内であるため、法定内残業とみなされます。
法定内残業の場合、会社側は残業による割増賃金を払う義務は原則ありません。しかし、会社によっては就業規則などによって割増賃金を支払う取り決めとしているケースもあります。
法定外残業
法定労働時間を超過した残業は、原則として法定外残業に該当します。法外残業・法定時間外労働とも呼ばれる残業の形態です。
法定外残業では1時間あたりの賃金を25%以上の割増で支払わなければなりません。また、1カ月の法定外残業時間が60時間を超える場合は、50%以上の割増賃金を支払うことが労働基準法によって定められています。
60時間超の50%割増は大企業のみに適用されていました。しかし、2023年4月からは中小企業に対しても適用されるようになっています。
1日の労働時間が固定されないフレックスタイム制
1日の労働時間が固定されないフレックスタイム制を導入する企業が増加しています。
フレックスタイム制は、必ず出社すべきコアタイムの時間を除けばどのタイミングで出社してもよい制度です。従業員が仕事以外のプライベートな時間を十分に確保できるため、理想的なワークライフバランスを叶えるのに効果的とされています。
フレックスタイム制の導入によって、仕事の進捗に余裕を作ることも可能です。朝は家事やプライベートの時間を作ってゆっくりと出社する、夕方で早めに仕事を切り上げてプライベート時間を確保するという働き方も可能となるでしょう。
フレックスタイム制の場合、残業時間は総労働時間から実労働時間を引いたものが該当します。たとえば、1月の総労働時間が160時間で実労働時間が180時間だった場合、差分の20時間が残業時間とみなされます。逆に、実労働時間が総労働時間よりも短い場合は、不足分が賃金から控除されて翌月の総労働時間が増えるといった処理が行われます。
みなし労働の形態をとる裁量労働制
フレックスタイム制だけでなく、裁量労働制という形態も存在します。こちらも勤務における自由度を高められる制度として導入する企業が多くなっています。
裁量労働制は、実際の労働時間ではなく契約時に取り決めた労働時間分働いたとみなす労働の形態をとっています。つまり、契約における労働時間が6時間の場合、実働時間が4時間であっても6時間勤務の扱いとなり、賃金も6時間分発生します。
裁量労働制は、実働時間が少ない場合は多めに賃金が支払われてお得なイメージもありますが、実働時間が8時間の場合、差分の2時間の賃金は発生せず6時間勤務の扱いとなります。また、法定労働時間である1日8時間を超過した分については時間外労働とみなされることは覚えておきましょう。
裁量労働制の場合は、法定労働時間を超えているかを判断して残業代について計算する必要があります。裁量労働制は人件費の管理のしやすさ、仕事の繁忙などによっては双方のメリットになる場合もあります。
残業時間は勤怠管理ツールで効率的に管理
従業員の多い会社ほど、社員ごとの残業時間管理は難しくなります。労働時間の計上ミスや賃金の計算ミスを防ぐためにも、勤怠管理ツールを導入してデータ管理ができる環境を整えることがおすすめです。
所定労働時間に関するよくある質問
所定労働時間を下回るとどうなる?
企業側は、働いていない分の給与については支払い義務がありません。所定労働時間を下回った場合は、欠勤した日数や遅刻・早退した際の時間を差し引いて給与が算出されます。
1日10時間の所定労働時間は違法?
労働基準法で定められている労働時間の上限は1日8時間・1週間40時間であるため、10時間を指定することはできません。
ただし、従業員と企業間で36協定を締結している場合は時間外労働の上限が月に45時間になるので、10時間労働をすること自体は違法にはなりません。
所定労働時間が7時間45分なのはなぜ?
所定労働時間を7時間45分にすることが多いのは、休日数を減らせることが理由と考えられます。
8時間労働の場合、労働基準法の法定労働時間を遵守するためには月に9日の休日を与えないといけません。しかし、所定労働時間を7時間45分にすると、30日以下の月であれば休日を8日に調整できます。
所定労働時間や残業に応じて正しく賃金が支払われているか要チェック
所定労働時間とは契約時に必ず取り決めるものであり、その時間を超過するかどうかで残業とみなされるかも決まります。残業時間も法定労働時間内かどうかで割増賃金支払いの有無について変わります。
従業員側は自身の労働時間を正確に管理したうえで、正しく賃金が支払われているか確認しましょう。会社側も従業員ごとの働き方について管理を徹底して、正しく賃金を支払えるよう努めることが大切です。
なお、事業者と雇用者で契約書を締結する際は、電子契約を利用することがおすすめです。電子契約は印刷代やインク代などの費用を抑えられるだけでなく、封入などの細かい作業も削減できるため業務効率化を実現できます。
「電子印鑑GMOサイン」では、電子契約を導入する方に向けて、月に5件まで文書の送信が可能なフリープランも用意しています。
法律に準拠した電子署名やタイムスタンプの付与もできるため、はじめての方でも安心して電契約書を利用できることが特徴です。
操作がかんたんなことや豊富な補助機能も評価されており、導入企業数は350万社(※1)を突破しています。登録はわずか数分で完結するので、電子契約の利便性を確かめてから本格導入したい方はぜひ利用してみてください。
※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)