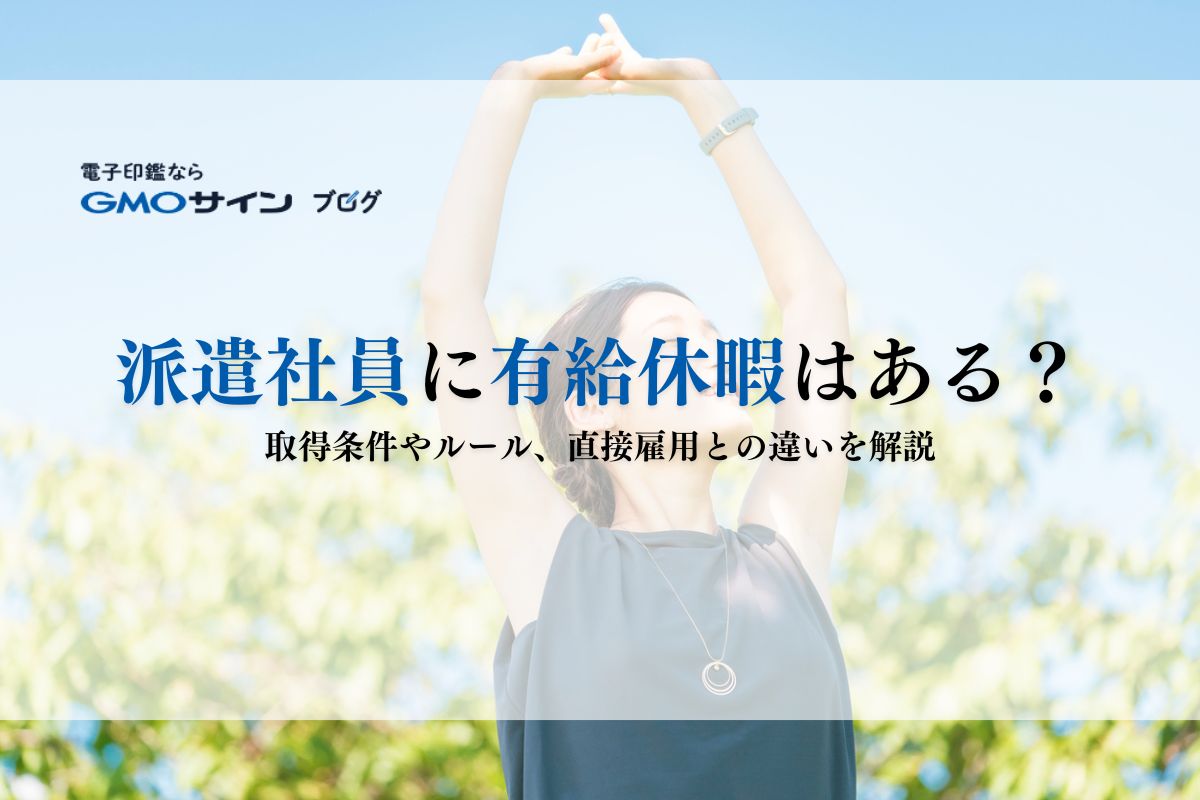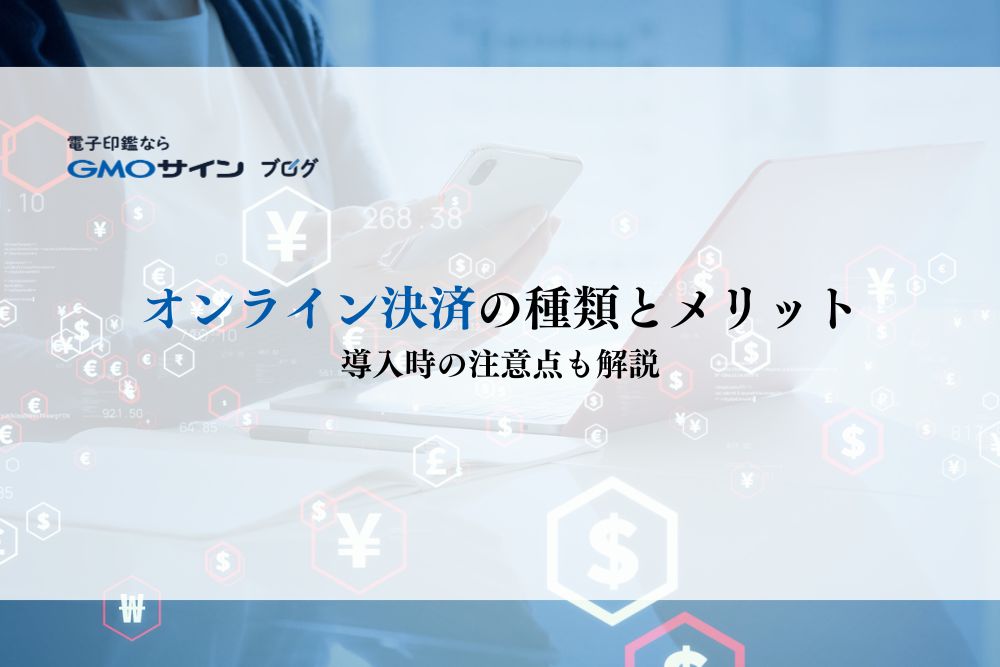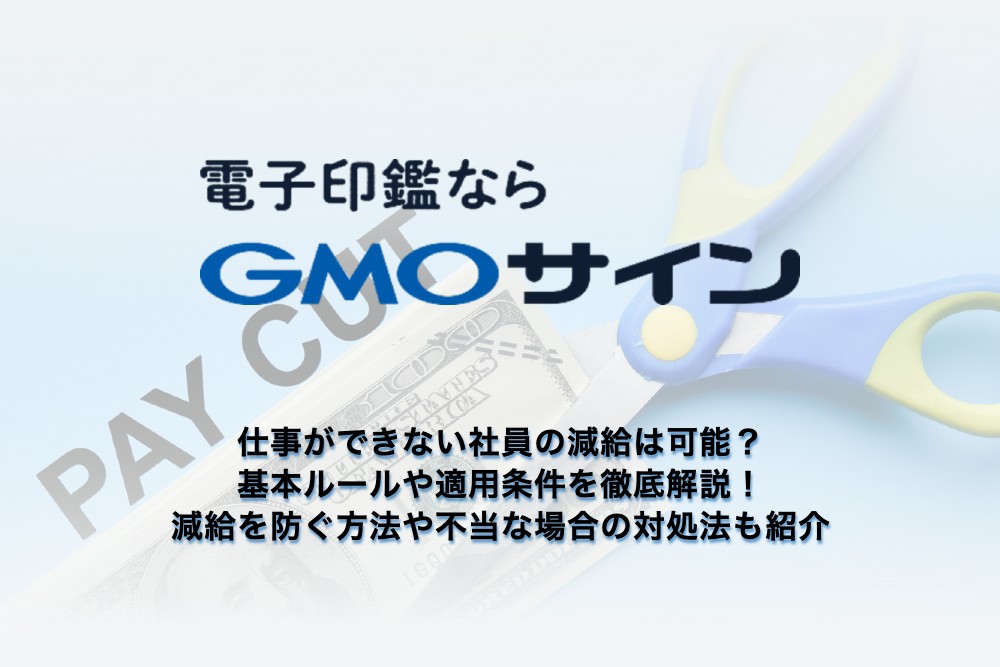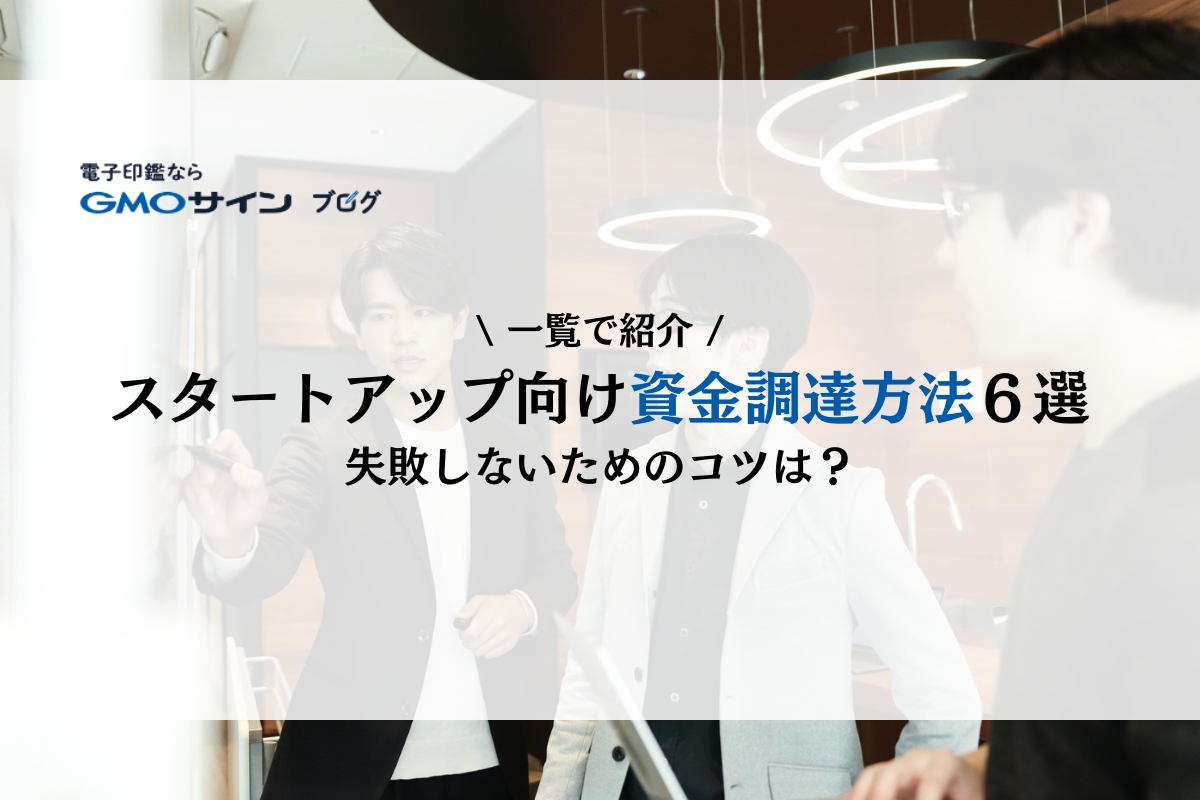日本では国民皆保険という世界的に珍しい制度が存在しており、日本国民は何らかの保険に加入することになっているのです。その中でも代表的な保険として、社会保険と国民健康保険が挙げられます。
一般的に会社員ならば社会保険、個人事業主や年金受給者は国民健康保険に加入します。しかし、会社を辞めて個人事業主になったり逆に入社したりする場合には、保険を切り替えないといけません。
そこで本記事では、社会保険と国民健康保険の違いや切り替えの手続きについて解説します。
社会保険と国民健康保険の違いとは
社会保険と国民健康保険の違いには、まず運営元が挙げられます。社会保険は健康保険協会や健康保険組合が運営していますが、国民健康保険では市区町村が運営を担っています。
また、加入条件や保険料の算出方法などさまざまな面で違いがあるので、詳しく解説します。
加入条件
社会保険と国民健康保険では、加入条件が異なります。社会保険は適用事業所で雇用されている正社員は、基本的に加入できます。また短時間労働者の場合でも、以下の5つの条件を満たせば加入可能です。
- 事業所の規模が常時500人を超えている
- 所定労働時間が週20時間以上
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 賃金が月額88,000円以上
- 学生ではない
これ以外の方は、国民健康保険に加入します。なお、生活保護受給者は国民健康保険に加入できません。なぜなら、生活保護には医療費補助制度が用意されているからです。
保険料の算出方法
社会保険では毎年4~6月の月額報酬をベースにして、標準報酬月額を算出します。健康保険料額は都道府県によって異なります。
一方国民健康保険では、世帯単位で算出する点が大きな違いです。また扶養に関する制度がない点も社会保険とは異なり、家族がいる場合には全員が被保険者という扱いになります。そのため保険料を計算する際には、被保険者である家族の人数や世帯収入、年齢を考慮に入れて個別に保険料を出します。
また同じ条件でも、自治体によって保険料が変動します。なぜなら、都道府県が運営元でも市区町村もあわせて運営を行っているからです。
扶養の有無
扶養に入れられるかどうかという点も、それぞれの違いの一つです。社会保険では配偶者や子どもを扶養に入れることが可能ですが、国民健康保険ではそもそも扶養という制度が設定されていません。
社会保険の場合、家族を自分の扶養の中に入れることができます。また被扶養者が何人いても被保険者分の費用だけで済むので、家族がたくさんいる方にとっては重宝する仕組みです。ただし配偶者が仕事をしていて、一定の収入を得ている場合には、被保険者とは別に社会保険料支払いが生じてしまう点には注意が必要です。
範囲
社会保険と国民健康保険の違いとして、保険の範囲も挙げられます。社会保険に含まれる保険は、広義の解釈では健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険が含まれます。なお、狭義の解釈では健康保険や厚生年金保険、介護保険とされています。
一方国民健康保険に含まれる保険は、健康保険と介護保険のみです。年金が含まれていませんので、国民健康保険の被保険者は別途で国民年金に加入するようになります。
切り替え手続きの流れ
就職を機に国民健康保険から社会保険に切り替えたり、離職することになって社会保険から国民健康保険に切り替えたりする場合には、手続きが必要になります。
社会保険への切り替えは雇用主と従業員がそれぞれ行わないといけない手続きがありますが、国民健康保険へ切り替える場合には従業員自身が自分だけで手続きをしなければならない点が大きな違いです。
国民健康保険から社会保険への切り替えの場合
国民健康保険から社会保険に切り替える際には、雇用主と従業員がそれぞれ手続きしなければなりません。まず雇用主は、新しく採用した従業員の社会保険加入の手続きを行います。この手続きには期限が決まっており、入社日から5日以内に済ませなければなりません。
具体的には、管轄する年金事務所に被保険者資格取得届を提出します。もし新規雇用した従業員に扶養する家族がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届もあわせて提出しなければなりません。
一方従業員は、雇用主が手続きを進められるように年金手帳とマイナンバーの記載されている書面の写しを提出しましょう。
社会保険から国民健康保険への切り替えの場合
会社を退職することになった場合、社会保険から国民健康保険に切り替えないといけません。また収入の問題で扶養から外れることになって、社会保険に加入できない場合にも国民健康保険への切り替えが必要です。
逆のケースでは従業員が手続きに必要な書類を用意し、実際に手続きをするのは雇用主でした。しかし、この場合では従業員が自分で切り替えの手続きをしなければなりません。
まず従業員が会社を辞めることになった場合には、被保険者資格喪失届を雇用主が日本年金機構に提出します。この手続きは、退職日の翌日から5日以内に進めないといけません。
また社会保険喪失証明書も入手しておくといいでしょう。社会保険喪失証明書は必ずしも必要ではありませんが、この書類があると従業員の切り替え手続きがスムーズに進むので作成しておくことをおすすめします。
協会けんぽに加入していた場合には年金事務所、健康保険組合に加入していた場合は当該健康保険組合から入手できます。 ただし、勤めていた会社が発行するケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
社会保険喪失証明書を入手したあとは、国民健康保険の加入手続きを自分で行います。手続きは、住んでいる市区町村の窓口で受け付けています。
いつ社会保険から脱退したのかが判明しないと保険料の計算ができないので、社会保険喪失証明書が必要となります。もし社会保険喪失証明書が入手できなかった場合には、離職票や退職証明書など退職した日のわかる資料を準備してください。
社会保険には任意継続制度がある
もし会社を辞める場合には、会社の社会保険から外れて国民健康保険に切り替える必要があります。しかし、例外的に引き続き社会保険に加入し続ける制度があり、この方法は社会保険の任意継続制度と呼ばれています。当該制度について詳しく解説します。
任意継続制度を利用するための条件
任意継続制度を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 社会保険の被保険者期間が資格喪失日までに継続して2カ月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する
加入期間は最長2年間です。また事業主による保険料負担がなくなりますので、全額自分で支払うようになります。期日までに納付しなければ、被保険者としての資格を喪失しますので注意しましょう。
任意継続のメリット
社会保険の任意継続制度を利用するメリットには、まず会社に在籍していた時とほぼ同じサービスが受けられる点が挙げられます。そのため、以前と同じ負担額で医療を受けられるようになります。
もし社会保険から国民健康保険に切り替えるのを失念していると、無保険状態になってしまいます。無保険状態で病気やけがなどによる治療を受けた場合、医療費は10割負担になりますので、かなりの費用が必要です。このような事態を避けられる点は、大きなメリットと言えるでしょう。
また国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる可能性がある点も、メリットの一つです。社会保険では標準報酬月額をベースにして保険料を算出しますが、この月額には上限があります。
任意継続のデメリット
任意継続制度のデメリットは、保険料が全額自己負担になる点です。本来社会保険は会社と折半で保険料を負担しますが、退職後は全額保険料を自分で支払わなければなりません。
ただし、国民健康保険も全額自己負担ですので、国民健康保険に切り替えた場合と比較すれば、保険料がそこまで大きな負担とは言えないでしょう。
(参考:資格の喪失について|全国健康保険協会)
二重加入には注意が必要
社会保険と国民健康保険は、必要に応じて切り替え手続きを速やかに行う必要があります。この手続きを行っていないと、社会保険と国民健康保険に二重加入してしまう可能性があります。どのようなパターンがあるのか解説します。
二重加入になるパターン
二重加入になるパターンは、おもに2つのケースがあります。まずもともと国民健康保険の被保険者で、転職などで社会保険に加入する場合が考えられます。
勤務先で社会保険の資格取得した場合には、その日から14日以内に国民健康保険資格喪失手続きを行わないといけません。
この手続きを適切に行わないと、社会保険に加入したあとで国民健康保険から保険料を支払うように請求が来てしまいます。なお、国民年金の場合には、社会保険に加入すれば手続きせずに自動で切り替えが行われます。
また被扶養者だった方が、働き始めて扶養から外れる場合があります。この場合には、扶養者の勤務先で健康保険被扶養者(異動)届の手続きを行い、被扶養者から外れないといけません。
二重加入期間中の返金について
国民健康保険と社会保険に二重加入していると、保険料を二重払いしていることになります。これは過払いになりますので、余計に支払った保険料は還付されます。過払いが発生していることがわかれば、還付通知書が自宅に届きます。
振込までには1カ月ほどかかる可能性があります。また振込後に通知が来るわけではないので、入金を確認しておきましょう。
国保と社保の違いに関するよくある質問
社保と国保の保険料はどちらが安いですか?
一般的に社会保険の方が国民健康保険より保険料負担が軽くなる傾向があります。これは社会保険の場合、保険料を事業主と被保険者で折半するシステムになっているためです。給与所得者の場合、保険料の約半分を会社が負担してくれるので、個人の実質負担は軽減されます。
一方、国民健康保険は加入者が保険料を全額負担する仕組みです。保険料は市区町村によって異なりますが、前年の所得や世帯人数などに基づいて算出されます。特に高所得者の場合、国保の保険料は社保より高額になることが多いでしょう。
ただし所得が低い場合は、国保の方が安くなるケースもあります。国保には所得に応じた軽減措置が設けられているからです。
国保と社保の負担額の違いは?
国保と社保では負担額の計算方法が根本的に異なります。
社会保険の場合、標準報酬月額(毎月の給与の平均額)に保険料率をかけて計算され、その半分を会社が負担します。たとえば月収30万円で保険料率が10%なら、月3万円の保険料のうち1.5万円が個人負担となるのです。
国民健康保険は所得割・均等割・平等割・資産割の4つの要素で計算されます。特に所得が高いと負担が増える仕組みになっており、前年の所得に応じて保険料が決まります。たとえば年収500万円の単身者と4人家族では、同じ所得でも4人家族の方が均等割の影響で保険料が高くなる傾向にあります。
まとめ
会社に勤めている場合は社会保険、それ以外の方は基本的に国民健康保険に加入します。しかし、会社に就職することになったり会社を辞めて独立したりする場合には、社会保険と国民健康保険の切り替え手続きを行わなければなりません。
会社に勤めていると、つい国民健康保険への切り替え手続きを忘れてしまう可能性もあるでしょう。無保険状態になってしまうと医療費が全額自己負担になってしまうので、切り替えを行う場合にはぜひ本記事を参考にしてください。