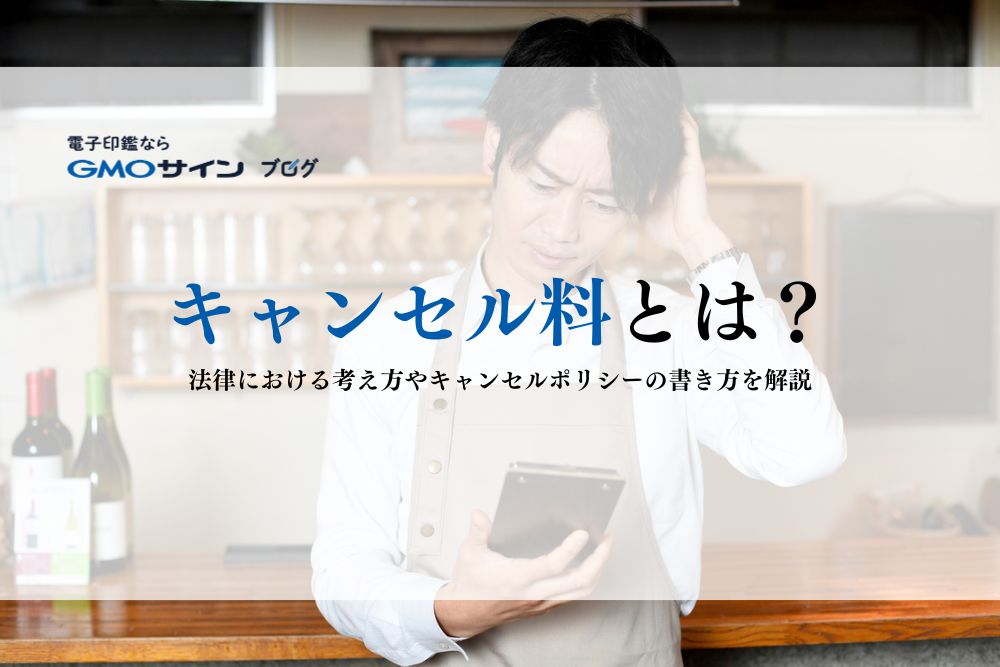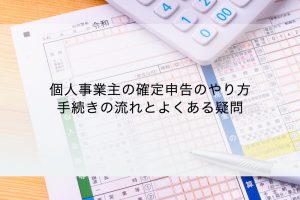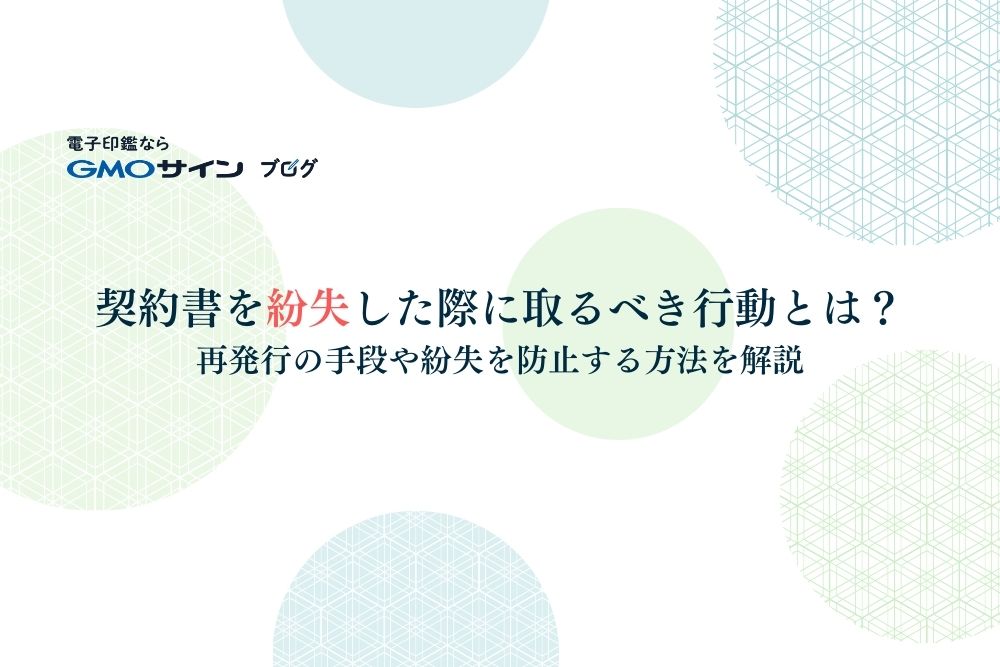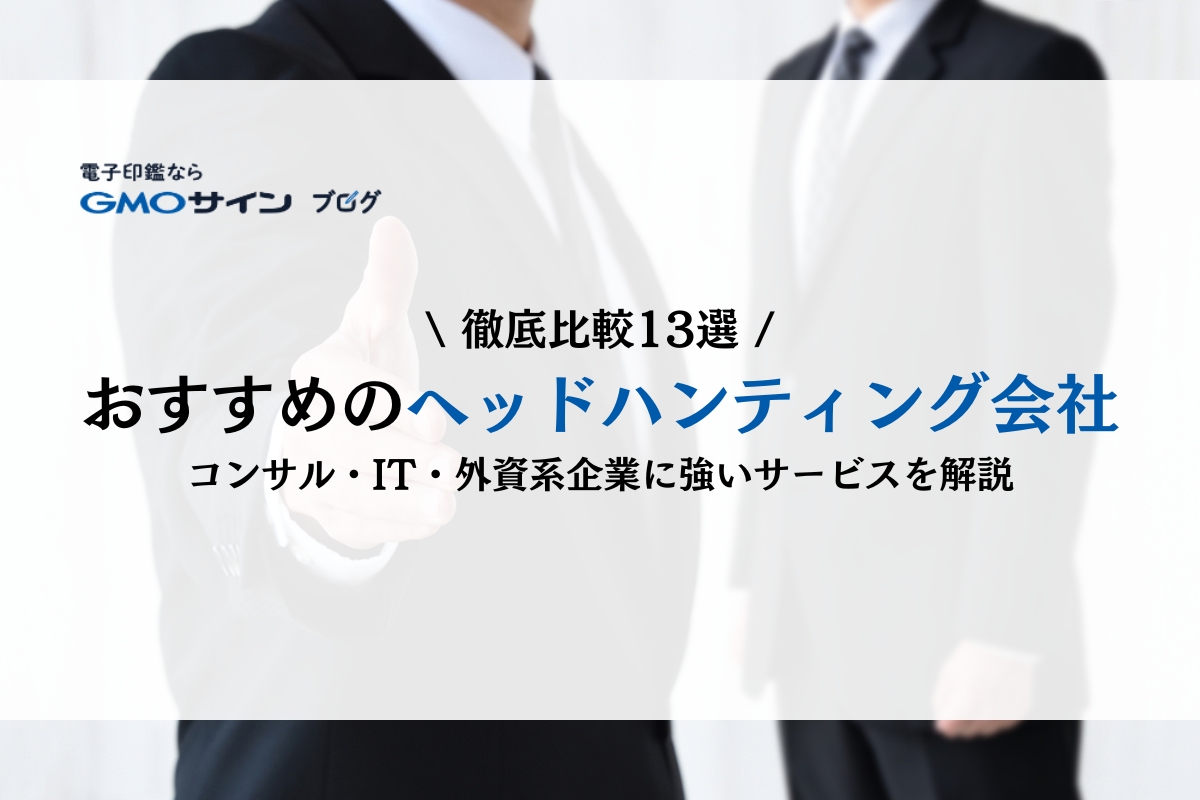育児・介護休業法による短時間勤務制度は、育児や介護などの家庭生活と、仕事をバランスよく両立させることを支援する重要な制度です。
当記事では、短時間勤務が適用される期間、制度採用時の注意点など、各種要点について解説を行っています。ぜひ参考にしてください。
時短勤務制度の概要
短時間勤務(時短勤務)制度は、育児・介護休業法によって定められています。従業員が子育てや家族の介護に専念することができるようにするための制度です。
この制度では、一日の勤務時間を通常より短くすることで、子育てや介護に関わる従業員の仕事と家庭生活の両立を支援しています。
育児における時短勤務
育児に関しては、3歳未満の子どもを養育する従業員が、この制度を利用できます。具体的には、原則として1日の所定労働時間を6時間とする時短勤務が可能です。
時短勤務がいつまで利用できるかは、子どもの誕生日を基準にします。以下に具体的な例を挙げて詳しく説明しましょう。
時短勤務を利用できる期間は、子どもの3歳の誕生日の前日までです。3歳の誕生日までと思われるかも知れませんが、法律上は誕生日の前日をもって年齢が変わるタイミングとしています。
子どもの誕生日が1月1日であった場合を考えてみましょう。この場合には、3歳の誕生日(1月1日)の前日である12月31日までが制度を利用できる期間となります。誕生日までではないことに注意が必要です。
(参考:育児休業、短時間勤務制度|厚生労働省)
介護で時短勤務を利用する場合
介護に関しては、介護を必要とする家族を持つ従業員がその家族を介護する場合に、この制度を利用できます。
育児の場合と同様、一日の勤務時間を短縮することで介護の負担を軽減し、従業員が仕事と介護の両方を両立できるようにすることが目的です。介護を行う従業員の状況に応じて、短縮する時間を定めましょう。
介護を理由とする時短勤務制度の取得期間には明確な制限は設けられていません。しかし、取得可能な回数については制限規定があります。
介護が必要な家族ひとりあたり、利用開始から連続して3年以上にわたる期間に2回以上利用可能という規定です。このように、介護の時短勤務についての上限は厳密に決められていません。具体的な期間は、労使間で話し合って決めることになります。
(参考:介護休業|厚生労働省)
時短勤務と就業規則
育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を取り入れる際には、その詳細を就業規則に明記することが必要です。
就業規則への記載
以下のように、短時間勤務制度の対象者を規定します。
「育児や介護を理由に短時間勤務制度を適用できる。対象者は、育児中の従業員(3歳未満の子を養育する場合に限る)、および、介護中の従業員(要介護認定を受けた家族がいる場合)とする。」
また、短時間勤務制度の適用期間に関しては次のように記載します。
「育児短時間勤務制度は、1日6時間までの勤務とする。介護短時間勤務制度は、1日の勤務時間を6時間以下に短縮することができる。」
制度の申請手続きについても明記しておきましょう。
「時短勤務制度を利用するためには、必要な書類を提出し、事前に管理者と協議することが必要である。育児を理由に時短勤務を申請する場合、子の出生証明書を、介護を理由に申請する場合、家族の要介護認定証を提出すること」
このように記載します。そのほかに以下の項目も、入れておくとなおよいでしょう。
「労働者の申出があった場合には、特別の事情がない限りこれを拒まないものとする。なお、時短勤務期間中の労働条件については、別途協議のうえ、決定する」
ただし、これらの規定は一例であり、組織や業種によって異なる場合があります。適用範囲や条件、申請手続きなどについては、適宜調整が必要です。
(参考:就業規則の作成のポイント|厚生労働省)
労働基準監督署長への届け出
時短勤務制度を導入する際には、就業規則への記載が必要です。また、変更した就業規則は、労働基準監督署長への届け出が必要です。
短時間勤務制度を取り入れることになった場合、変更後の就業規則を、所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
短時間勤務制度のデメリットと対処法
短時間勤務制度には数多くの利点がある反面、注意すべきデメリットも存在します。従業員がデメリットに対して不安を感じてしまうと、短時間勤務制度が利用しにくくなってしまいます。
従業員にとって時短勤務制度を利用しやすい職場環境とするためには、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。検討すべきデメリットとその対処法を考えてみましょう。
従業員にとってのデメリットと対処法
時短勤務は、従業員の給与を減らす可能性があります。給与が減ると、家計にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。従業員の給与減少に対する不安を軽減するためには、時短勤務中の給与補助などを検討することが重要です。
また、時短勤務を利用した従業員は、フルタイム勤務の同僚と比べてキャリアアップが遅れる可能性があります。これを防ぐためには、事業主は時短勤務を利用した従業員にもフルタイムの従業員と同じキャリアアップの機会を提供することが重要です。
短時間勤務に切り替えても、業務量が変わらない場合には、負荷が大きくなってしまいます。業務の負荷を軽減するためには、事業主は適切な業務分担やサポート体制を確立することが重要です。
事業主にとってのデメリットと対処法
時短勤務制度を導入すると、特定の時間帯に人員が不足する可能性があります。特に、一部の従業員が全員同じ時間帯に時短勤務を希望する場合などが問題となります。
問題に対応するためには、柔軟なスケジューリングと予測による人員不足の回避が必要です。また、必要に応じて一部業務のアウトソーシングも検討する必要があります。短時間勤務制度を導入すると、給与計算、業務スケジューリング、パフォーマンス評価などの管理作業が複雑化します。
これらの課題を軽減するには、給与計算や業務スケジューリングを自動化するソフトウエアの導入なども検討するべきでしょう。
短時間勤務者とフルタイム勤務者との間で情報共有が不十分になる可能性があります。時短勤務者が会議や研修などに参加できない時間帯があるケースです。
短時間勤務者とフルタイム勤務者とのコミュニケーションを確保するためには、異なる勤務時間帯でも情報が共有できるような環境を作ることが大切でしょう。たとえば、デジタルツールを用いて会議の録音・録画を行いあとで視聴可能とする、社内のコミュニケーションツールを活用するなどが考えられます。
時短勤務に関するよくある質問
時短社員制度は2025年から増える?
時短社員制度の導入時期は企業によって異なりますが、多くの企業では2025年の4月または10月から本格導入を予定しています。この背景には、2024年度の両立支援法拡充が影響しています。
2025年4月からは、3歳になるまでの子を養育する社員に対する「短時間勤務制度」などの導入が義務化されます。また、2025年10月からは、3歳以上小学校就学前の子を養育する社員に対し、「柔軟な働き方を実現するための措置」(例:始業時刻変更、テレワーク、短時間勤務制度、新たな休暇等)を2つ以上講じることが義務化されます。
こうした義務化に伴い、多くの企業では制度導入に向けた試験的な運用やモデルケースの検証を行っているケースが見られます。
時短勤務は小学校3年生まで?
時短勤務の適用期間については、法律上は3歳未満の子を養育する労働者が対象です。しかし、多くの企業では独自の拡充を行っており、小学校3年生までという設定が一般的になっています。
この背景には、小学校低学年の子どもの下校時間が早いことや、放課後の過ごし方に親の関与が必要な場合が多いという実情があります。なかには小学校卒業まで延長している企業も増えてきました。
育児時短勤務は3歳以上でも可能?
育児のための時短勤務は、法律上は3歳未満の子どもを持つ親に限定されていますが、実際には3歳以上でも利用できるケースが多くなっています。多くの企業では独自の福利厚生として、小学校入学前や小学校低学年までといった形で期間を延長しているのです。
特に、共働き世帯の増加に伴い、就学後も下校時間や長期休暇の対応が必要なため、こうした拡充が求められています。
時短勤務はいつまで延長される?
時短勤務の延長可能期間は、企業独自の制度によって大きく異なります。最近の傾向としては、小学校就学前までという企業が多いものの、小学3年生終了時まで、あるいは小学校卒業までと幅広く設定するケースも増えています。
時短勤務の義務化はいつから?
時短勤務制度の義務化は、2009年の育児・介護休業法改正により2010年6月30日から実施されています。この法改正によって、3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合、事業主は原則として1日6時間の勤務時間とする短時間勤務制度を設けることが義務付けられました。
現在では企業規模を問わず、ほとんどの職場でこの制度が整備されています。
時短社員が導入された理由は何?
時短社員制度が導入された主な理由は、働く人々のライフステージにあわせた多様な働き方を可能にするためです。特に少子高齢化が進む日本社会では、育児や介護と仕事の両立を支援することが急務となっていました。
くわえて、質の高い人材の確保や離職防止という企業側のメリットも大きな推進力となっています。優秀な社員が家庭の事情で退職せざるを得ない状況を回避し、長期的に活躍してもらうための施策としても機能しているのです。
SDGsへの取り組みやダイバーシティ経営の一環として、多様な働き方を認める企業文化の醸成という側面もあります。結果として、企業と従業員の双方にとって価値ある選択肢となっているといえます。
導入には制度理解と周知が必要
時短勤務制度を上手に利用することで、従業員はよりよいワークライフバランスを実現することが可能です。また、事業主にとっては、従業員の生産性を維持しつつ、その幸福度を向上させるための強力な手段となります。
制度を採用するにあたっては、事前に従業員との間で適切な協議と合意が必要です。従業員にとって安心して働ける職場であるためにも、制度の詳細を理解するとともに従業員にも積極的に周知していきましょう。
(参考:短時間勤務等の措置とは|厚生労働省)