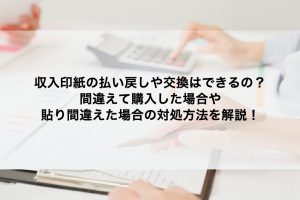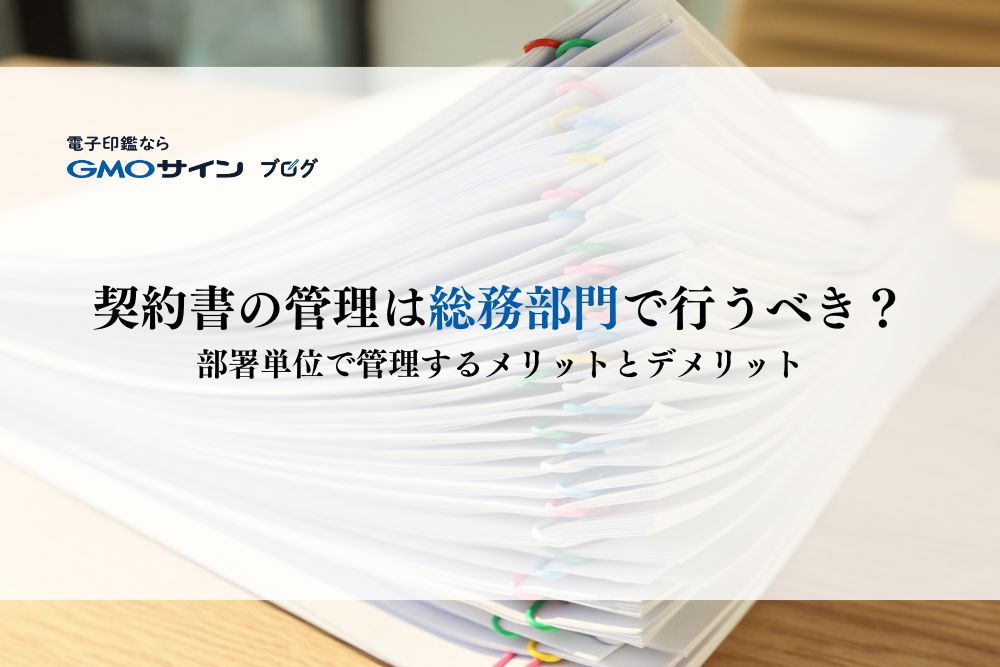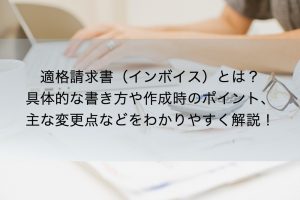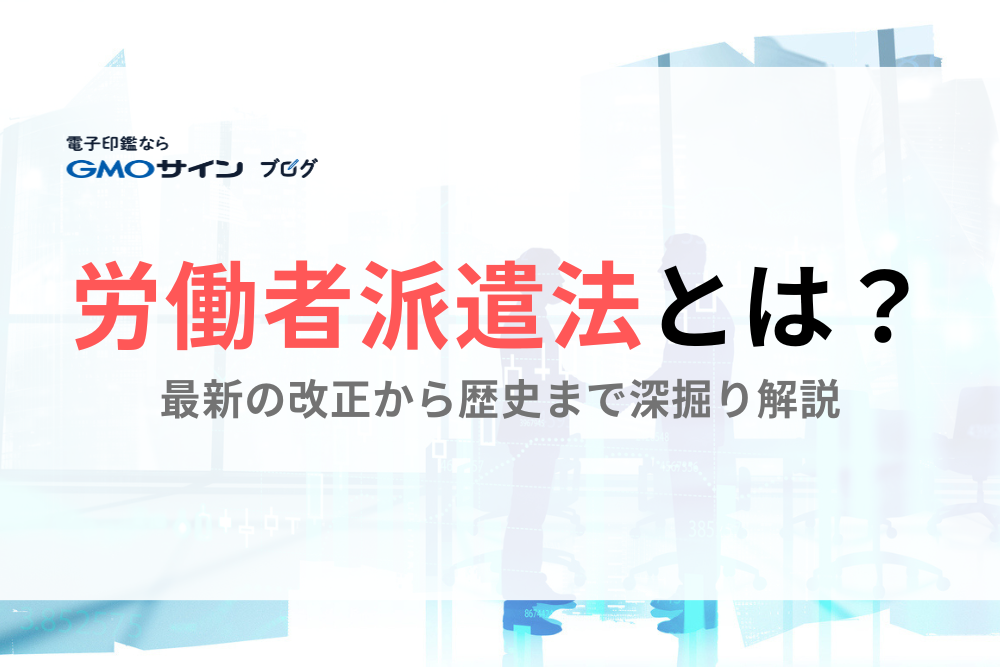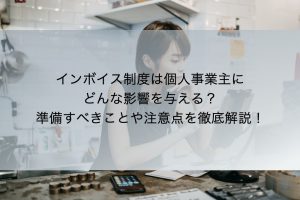事業活動を行う中で避けて通れない廃棄物の処理。これを正しく行わなければ環境汚染や健康被害を引き起こし、企業の社会的責任が問われる深刻な問題となりかねません。
そこで本記事では、廃棄物処理法の基本的な内容から処理責任の在り方、違反時の罰則まで、事業者が知っておくべきポイントについて詳しく解説します。
廃棄物処理法とは?
廃棄物処理法とは、廃棄物の保管や運搬、処分に関するルールを定めた法律です。廃棄物処理法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が正式名称であり、「廃掃法」という略称で呼ばれる場合もあります。
廃棄物処理法の目的と制定された背景
廃棄物処理法は、廃棄物の正しい処理を通じて生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る法律です。この法律がなぜ制定され、どのような目的を持つのかを詳しく見ていきましょう。
廃棄物処理法の目的
廃棄物処理法の目的は、廃棄物を正しく処理することで、人々の生活環境保全や公衆衛生向上を図ることです。また、廃棄物の排出を抑えてリサイクルや埋め立てといった安全な処理を促すことも大切な目的となっています。
違反すると罰則の対象となるため、法律にもとづいた正しい処分が求められます。
制定された背景
このような厳格な法律が制定された背景には、高度経済成長期の深刻な環境問題があります。高度経済成長期に家庭ごみや産業廃棄物が急増し、不法投棄や野積みによる環境汚染・悪臭・健康被害が深刻化したことがきっかけで制定されました。
これまでの「清掃法」では、産業廃棄物(例:工場の汚泥や廃油、プラスチックくずなど)への対応が不十分で、社会問題に発展したため、1970年に廃棄物処理法が新たに作られました。
この法律は、廃棄物の正しい処理と生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的として制定され、現在の廃棄物管理の基本ルールとなっています。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
ひとくちに廃棄物といっても、大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物の2種類があります。ここでは2種類の廃棄物について解説します。
産業廃棄物
産業廃棄物は、企業による事業活動によって生じる廃棄物のことを指します。量的、そして質的にも環境汚染につながる可能性のあるもので、工場での生産によって生じた焼却炉の残灰や廃油、木くずや廃プラスチック類などが当てはまります。
世間一般における廃棄物のイメージは、この産業廃棄物のほうが強いでしょう。品目にもよりますが産業廃棄物は、正しく処理できなければ有毒物質が発生する恐れもあるため、その取り扱いは法によって厳格に定められています。
一般廃棄物
一方の一般廃棄物とは、人々の日常生活において排出される廃棄物のことを指し、市町村が有する処理能力で十分に処理が可能なものが該当します。たとえば、日常生活で発生する程度の紙やプラスチックごみ、飲食店からの生ごみなどは一般廃棄物として扱われます。
廃棄物の処理責任
廃棄物の処理責任は、状況によって異なります。ここでは、産業廃棄物と一般廃棄物の処理責任を詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物で違いがある
廃棄物を処理する場合、その責任がどこにあるのかは産業廃棄物と一般廃棄物で違います。
廃棄物処理法に基づくと、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。排出事業者とは廃棄物を直接的に発生させる事業者のことを指し、事務所や工場から事業活動によって廃棄物を排出している場合などが該当します。
産業廃棄物の処理責任も状況により異なる
産業廃棄物はそれぞれの排出事業者が独自に処理することもありますが、許可を持つ産廃処理業者へと委託するケースも多いです。廃棄物の処理責任について、誰が排出事業者なのかを問われることもありますが、基本的に事業を行う元請業者が排出事業者に該当します。
しかし、事業を下請業者が管理している場合は下請業者が排出事業者となり、元請が下請に指示を出していた場合は元請が排出業者となります。誰が排出事業者であるかの定義は少し複雑ですが、明確にしておかなければ問題発生時の責任の所在が不明確になるため重要な確認項目です。
産業廃棄物の取り扱い方法
廃棄物の中でも処理が複雑な産業廃棄物については、その処理や保管の方法について細かい基準が定められています。誤った取り扱いによって、地域の住民や環境に悪影響を及ぼさないように注意しましょう。
処理基準
処理基準は大きく分けて収集運搬と処分の2つに分類されます。それぞれ収集運搬時に廃棄物が流出・飛散しないこと、騒音や悪臭によって生活環境に支障が出ないよう措置を取ることなどが定められています。
さらに、爆発性や毒性、感染性などがあり、周囲の人に被害を与える恐れのある特別管理産業廃棄物については、ほかの廃棄物と混ざらないように区分して、専用の運搬容器にいれて収集運搬する決まりがあります。
保管基準
保管基準では、保管期間や保管場所、保管によって生じる汚水の処理方法や害虫発生防止についての規定があります。
廃棄物処理法違反時の罰則例
廃棄物処理法に違反した場合は、排出事業者や処理事業者に対して罰則が科せられます。いずれも軽い罰則ではないため、廃棄物の処理は慎重に実施しなければなりません。
無許可の営業
都道府県知事などから排出事業者・処理事業者としての許可を得ずに、廃棄物の運搬や処理といった事業を行った場合は罰せられます。
しかし、専用施設が必要であったり、コストや手間がかかったりするため、外部へ委託するケースがほとんどです。許可は不要であるものの、産業廃棄物の取り扱いについては基準に従わなければなりません。
処理施設の無許可設置
廃棄物の処理施設を設置またはすでに設置されているものを変更する場合、事前の許可が必要です。無許可でこれらの行為に及んだ場合は罰則が適用されます。廃棄物処理施設の許可については15条許可と呼ばれるものがあり、廃棄物処理法の第15条に記載があります。
(産業廃棄物処理施設)
第十五条
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
(参考:e-Gov法令検索)
委託基準違反
排出事業者が、廃棄物処理に関わる作業について、委託基準を満たしていない業者に委託した場合は罰則の対象になります。委託基準にはいくつかのルールがあり、適切な業者へ委託しなければなりません。
たとえば、紙くずの廃棄を委託する場合は、紙くずの廃棄物処理の許可を有している業者でなければ罰則が科せられます。誠実な委託業者であればこのルールについて当然知っているため、まず委託を断られるでしょう。廃棄物は全部で20品目に分けられるため、処理を委託する品目に対応する許可を持つ委託先を探しましょう。
無許可での輸出入
廃棄物の輸出入は、廃棄物処理法にもとづく環境大臣の許可を得たうえで、外国為替及び外国貿易法(外為法)にもとづく経済産業大臣の承認を受ける必要があります。無許可で廃棄物を輸出入することは禁じられているため、必ず事前に許可を取りましょう。
記載義務違反
産業廃棄物を処理業者に委託した場合、契約の内容通りに適正な処理が行われたかを確認するための管理伝票が存在します。これをマニフェストと呼びますが、マニフェストに記載すべき事項が記載されていない状態で交付すると記載義務違反となります。
専門の業者へ委託する場合は、マニフェスト交付の義務がありますが、市町村や都道府県へ委託する場合には交付不要とされています。また、事業者は交付したマニフェストの写しを5年間保管しなければならないため注意しましょう。
排出事業者となる側の注意点
生産系の企業の場合、事業を進める過程で何かしらの産業廃棄物を排出するケースは多いです。その時にルールを守った適切な行動が取れるよう、事前に注意点を把握しておきましょう。
特別管理産業廃棄物と通常の産業廃棄物の違いを理解する
人々の健康や生活環境に被害を及ぼしかねない特別管理産業廃棄物は、排出事業者側が守るべきルールや基準も通常の産業廃棄物とは異なります。それぞれの違いについて明確に理解したうえで、適切に区別して取り扱うことが大切です。
特別管理産業廃棄物の中でも、特に有害性が高いものとされる特定有害産業廃棄物は、細心の注意を払って取り扱わなければなりません。どの廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するかは環境省のWebサイトで公開されているため、自社で排出される廃棄物が該当していないかを入念に確認しましょう。
委託先は品目や許可の有無を考慮して適切に選定する
基本的に産業廃棄物の処理は専門業者へ委託するため、その委託先が適切であるかを確認する必要があります。委託する品目についての許可を持っているのか、無許可の業者ではないかを慎重に調べて選定することが必要です。
廃棄物処理法はSDGsとも深い関係
近年、世界中の環境問題や人権問題といった課題を解決するための計画・目標として持続可能な開発目標(SDGs)が注目されています。このSDGsには17個の目標が定められており、特に12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」は廃棄物処理と深い関係にあります。
廃棄物処理法には、リサイクルなどの廃棄物再生についてのルールも含まれており、このルールを遵守したうえでの廃棄物の排出量削減と再生利用の推進を実施することが重要になるでしょう。
ルールを守り環境保護に貢献しよう
廃棄物処理法は、廃棄物を適切に処理するために必要なルールが多数定められています。廃棄物を処理する立場に立った場合は、委託先の選定や廃棄物の分別など、違反にならないように行動しましょう。
ルールを守ることは、SDGsの達成目標としても掲げられている廃棄物排出量の削減やリサイクル推進に大きく貢献できます。ごみだらけで不衛生な街、人々が廃棄物の処理による公害で苦しめられるような街を作らないよう、自分達ができる取り組みを少しずつ進めていきましょう。