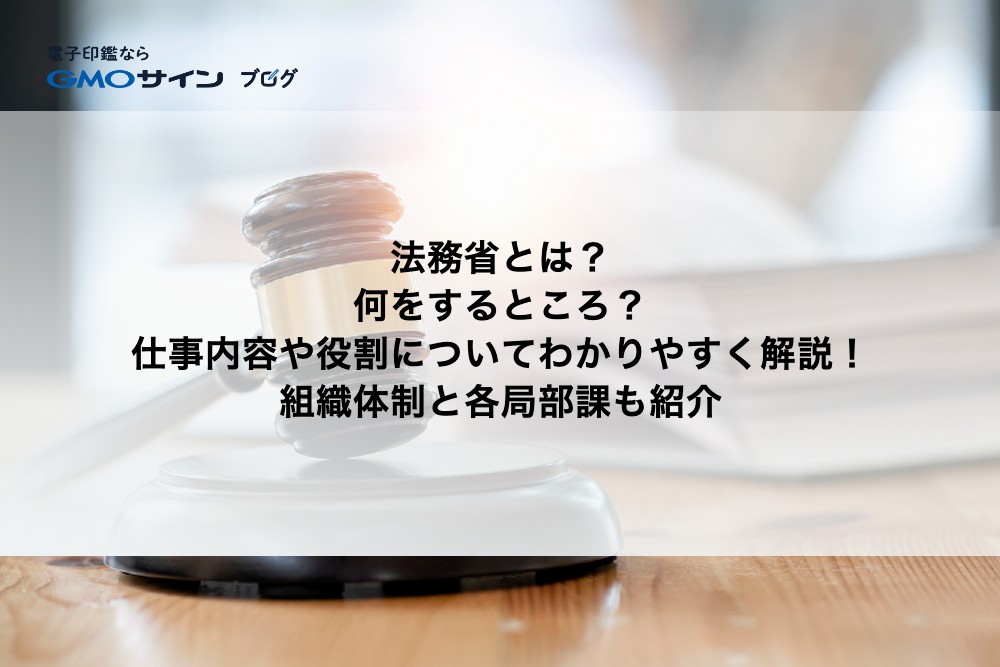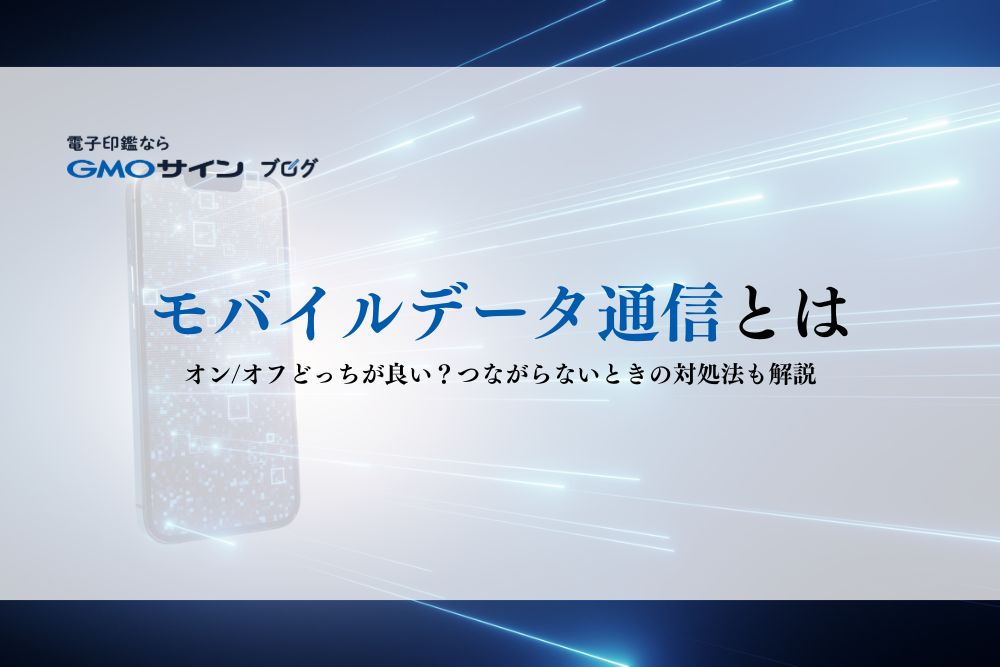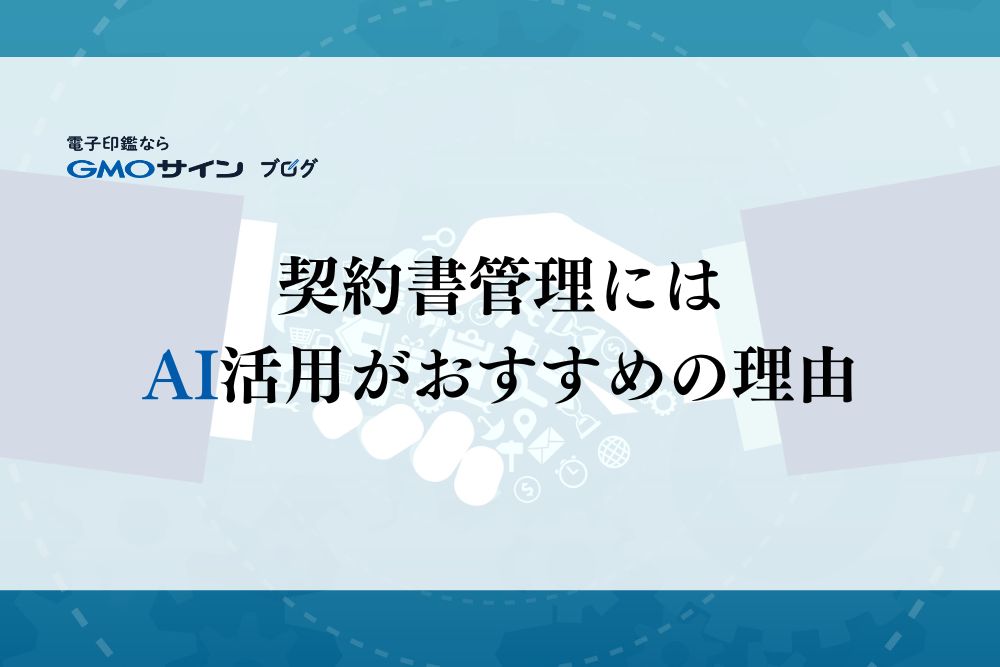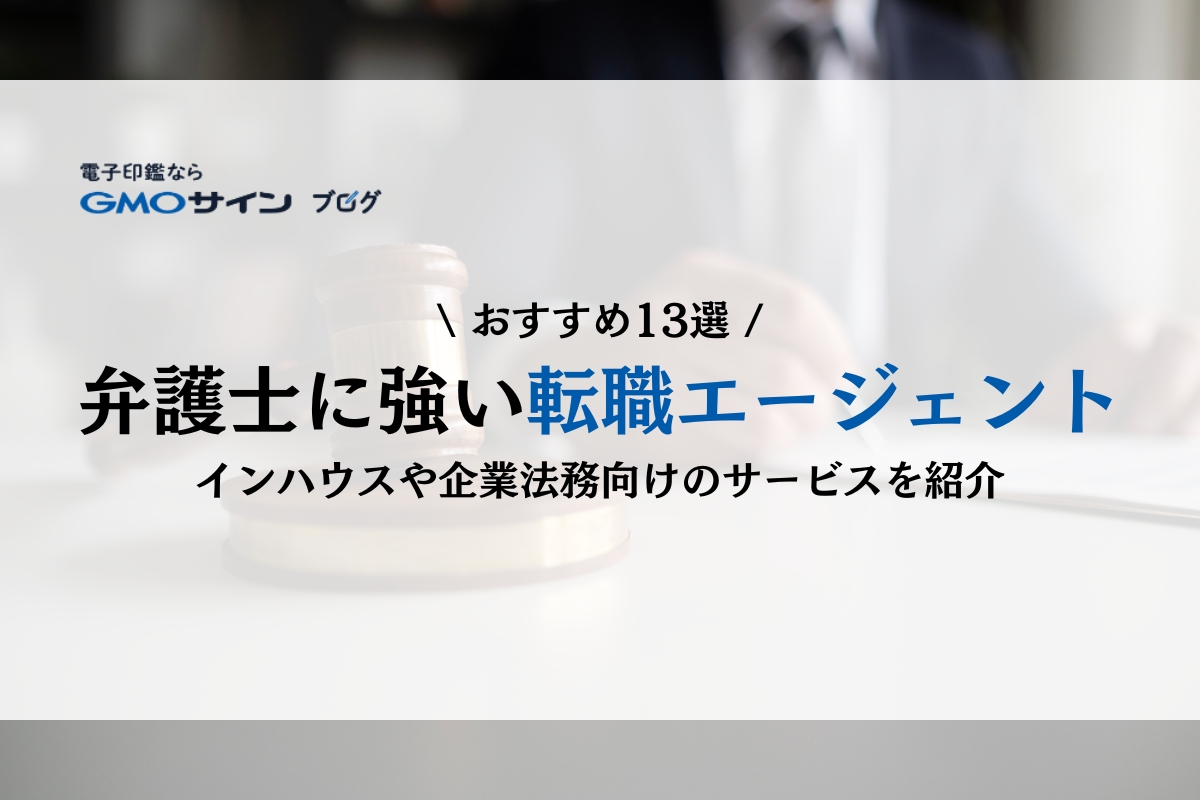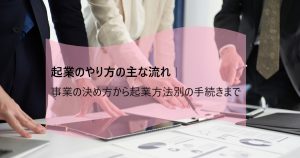「セキュリティ・クリアランスって何だろう」
「セキュリティ・クリアランス制度がわかりにくい」
「セキュリティ・クリアランス制度による影響を受けるのだろうか」
2025年5月から施行されるセキュリティ・クリアランス制度について上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
海外で導入されていたセキュリティ・クリアランス制度が、いよいよ日本でも導入となります。近年、安全保障環境の変化や経済と安全保障の関連度合いが密接になっていることに鑑み、さまざまな機密情報を適切に保護する目的でこのタイミングの導入となりました。
セキュリティ・クリアランス制度導入後は国や国民の安全に重要な機密情報を取り扱う企業や個人は、事前に必要な調査を受けることが求められるようになります。認定を受けられない場合は、情報にアクセスできない仕組みです。
本記事では、セキュリティ・クリアランス制度の基本的な概要や仕組み、対象者、企業の対応ポイントについてわかりやすく解説します。同制度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
セキュリティ・クリアランス制度とは?
セキュリティ・クリアランス制度は、国の安全や防衛に関わる重要な情報について、あらかじめ国が信頼性を調査したうえで、認められた者だけが扱えるようにする仕組みです。ここでは、本制度の概要と海外での運用例を含めて説明します。
セキュリティ・クリアランスの定義と目的
セキュリティ・クリアランスとは、政府が保有する安全保障上における重要な情報へのアクセス権限を、信頼性が確認できた者へ付与するものです。セキュリティ・クリアランス制度は、国家安全保障上における機密情報漏えいの防止をおもな目的としています。
まず、個人の経歴や素行、信頼性などの厳密な調査を実施。機密情報を取り扱う人物として適正かどうかを判断します。
セキュリティ・クリアランスは単なる形式ではなく、国の安全と企業の機密を守る重要な防波堤です。近年ではサイバー攻撃や産業スパイの脅威が高まり、重要性はさらに増している傾向にあります。
海外のセキュリティ・クリアランス制度との比較
アメリカではセキュリティ・クリアランスは長い歴史を持ち、厳格な運用がされています。機密情報は3段階に分類され、定期的な再審査も行われる点が特徴です。
他国では、すでに導入されています。以下の表は主要国のセキュリティ・クリアランス制度の比較です。
| 国名 | 範囲 | おもな分類レベル |
|---|---|---|
| アメリカ | 政府や諜報、防衛、関連部門で働く個人 | ・トップシークレット(機密) ・シークレット(極秘) ・コンフィデンシャル(秘密) |
| イギリス | 情報機関や防衛機関 | ・CTC(テロ対策チェック) ・SC(セキュリティ・チェック) ・DV(発展型審査) |
| オーストラリア | 国家安全保障業務に従事する個人 | ・ベースライン ・ネガティブ審査レベル1(NV1) ・ネガティブ審査レベル2(NV2) ・ポジティブ審査(PV) |
| 日本 | 政府機関や経済安全保障に関連する個人 | 現時点では不明 |
日本では、2025年4月時点で海外のような具体的な分類レベルを公開しておらず、議論の中で重要度に応じたレベルへの分類が提案されています。
セキュリティ・クリアランス制度の導入背景
世界の安全保障環境や経済の立ち位置が急速に変化する中、機密情報や重要技術の保護は国家の重要な課題です。ここでは、セキュリティ・クリアランス制度が導入されることとなった背景を解説します。
世界的な安全保障環境の変化
近年、世界の安全保障環境は急速かつ複雑に変化し、従来の軍事的な脅威だけに留まらない状況になりました。たとえば、以下の点が挙げられます。
- サイバー空間における脅威の深刻化
- 技術派遣を巡る競争の激化
国家や重要インフラ、企業などを標的とした高度なサイバー攻撃が頻発している状況です。そのため、機密情報の漏えいや不正取得のリスクが高まっています。
また、国家間の技術競争も激化している状況もあり、特に重要技術は経済成長に不可欠な要素です。産業スパイなどによる不正な情報窃取も活発化しています。
このような脅威から国家の安全を守るため、機密情報へのアクセス管理強化が不可欠になりました。日本も例外ではなく、セキュリティ・クリアランス制度導入の必要性が高まっています。
経済安全保障の重要性の高まり
安全保障と経済は密接に結びつき、「経済安全保障」の重要性が高まってきました。経済の発展が国の安全につながると認識されるようになるほど、関連性が深くなったためです。
たとえば、AIやバイオテクノロジーなどの先端技術は国の技術発展だけでなく、軍事的な優位性につながるケースがあります。
重要な経済基盤の保護や機密性が高い情報の管理が求められており、セキュリティ・クリアランス制度は重要な役割を担います。
セキュリティ・クリアランス制度の仕組み
セキュリティ・クリアランス制度は機密情報を適切に保護するための重要な枠組みです。個人の信頼性を多角的に審査し、合格者のみに機密情報へのアクセス権を付与します。
ここでは、具体的な仕組みから審査基準やプロセス、個人情報の扱いまで詳しく見ていきましょう。
重要経済安保情報保護活用法との関係
重要経済安保情報保護活用法はセキュリティ・クリアランス制度の法的基盤であり、同法における適格性評価制度として位置づけられています。重要経済安保情報保護活用法が成立したことで、経済安全保障に関わる重要情報の保護と適切な活用の枠組みが明確化されました。
行政機関が保有する安全保障上で重要な情報などを「重要経済安保情報」として指定します。この情報をセキュリティ・クリアランス制度で認められた者が取り扱い可能となるのです。本制度は事業者と個人それぞれが認められて初めて、重要経済安保情報の提供を受けられるようになります。
(参考:内閣官房|いわゆる「セキュリティ・クリアランス」制度の概要)
審査基準
セキュリティ・クリアランス制度の審査は、多岐にわたる厳格な基準で実施されます。政府が保有する安全保障上で重要な情報として、指定された情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認するために必要な審査です。
「適正評価」と呼ばれる審査では、以下の項目について審査します。
- 重要経済基盤毀損活動(※)に関する事項
- 犯罪や懲戒の経歴
- 情報の取り扱いに係るトラブル
- 薬物使用や処方薬などの濫用の経歴
- 精神疾患に関する受診歴
- 飲酒トラブル
- 信用状態や経済的な状況
(※重要経済基盤毀損活動は、他国の利益を図る目的で、国や国民の安全を損なう政治活動などのこと。情報を取り扱う本人だけでなく家族や同居人の個人情報も調査対象となる。)
また、外国との関わりについても、他国への流出リスクの懸念から調査されます。
審査プロセス
セキュリティ・クリアランス制度における審査の手続きは、以下のとおりです。
- 民間事業者が対象範囲から評価対象者を選定
- 評価対象者への同意
- 民間事業者が行政機関へ伝達
- 行政機関から評価対象者へ告知と同意確認
- 行政機関から内閣府へ調査依頼
- 内閣府が調査実施
- 調査結果の回答
- 調査結果に基づいて評価
- 評価結果を伝達
適正評価の有効期間は定められていませんが、信頼性に疑義が生じたと判断された際には再審査が必要となります。
審査における個人情報の扱い
セキュリティ・クリアランス制度の審査では膨大な個人に関する情報が収集されるため、個人情報の保護は欠かせません。調査で得た情報は勤務先へは提供されず、適正評価への対応や結果などを理由とした不利益となる取り扱いも防止するべきとされています。
対象者には、情報の使用目的や保管期間について明確な説明が行われます。また、自分の情報がどのように扱われるかを理解した上で、同意を示すことが求められるでしょう。
セキュリティ・クリアランス制度の対象者
セキュリティ・クリアランス制度の対象者は、政府が指定する重要経済安保情報にアクセスする必要がある適合事業者と従業者です。ここでは、対象となる事業者の具体例や直接の対象でなくても影響があるかどうかを解説します。
対象となる業界や職種の具体例
セキュリティ・クリアランス制度の対象となる業界や職種は、政府が保有する以下の情報へアクセスする必要があるかどうかがポイントです。
- 安全保障上の重要な情報
- 経済安全保障に関する情報
具体的に考えられる事業者は以下の表になります。
| 事業者 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| インフラ事業者 | 国民生活や経済活動の基盤 | ・電気 ・ガス ・水道 ・通信 ・鉄道 ・航空 |
| 重要物資のサプライチェーンに関連する事業者 | 国民生活や経済活動に不可欠 | ・半導体 ・機械 ・産業用ロボット ・重要鉱物 |
| 先端技術の開発事業者 | 経済安全保障で重要 | ・AI ・バイオ技術 ・量子コンピューター ・宇宙・サイバー分野 |
| サイバーセキュリティに関連する事業者 | サイバー脅威への対応 | ・情報分析 ・対策技術の開発 ・セキュリティシステムの運用 |
| 国際共同研究開発に関連する事業者 | 外国政府や企業との共同研究開発プロジェクトに参加 | 国際共同研究プロジェクトの関係者 |
企業は、まず自社が制度対象となる可能性があるかどうかを検討する必要があるでしょう。必要に応じて情報管理体制の整備や社員の適性評価への対応を準備する必要があります。
対象外でも影響を受ける可能性
直接的な対象者でなくても、セキュリティ・クリアランス制度の影響は広範囲に及びます。たとえば、対象企業の協力会社や下請け業者も間接的に影響を受けるケースもあるでしょう。また、海外の取引先がセキュリティ・クリアランスの保有を前提条件とする場合もありえます。
現時点では対象外であっても、今後の運用基準や関連した法令などにより影響を受ける可能性はあるということです。本制度の動向を把握しておくことが大切になります。
セキュリティ・クリアランス制度に対する反対意見と懸念点
セキュリティ・クリアランス制度においては、反対意見と懸念点が挙げられています。
- プライバシーの侵害
- 雇用や労働条件との関係
- 企業活動への影響
- 本制度の必要性
それぞれの内容を見ていきましょう。
プライバシーの侵害
セキュリティ・クリアランス制度に対する懸念の一つは、プライバシーの侵害です。審査過程では個人の詳細な情報が収集されます。対象者の犯罪歴や精神疾患、経済状況など一般的に調査されない内容であるため、個人の私生活に対する過度な干渉とも受け取られかねません。
現在特に問題視されているのは、家族構成や交友関係まで調査対象である点です。対象者だけではない詳細な身辺調査が、プライバシー侵害への懸念となるのではと疑問視され、制度に対する反対意見になっています。
雇用や労働条件との関係
セキュリティ・クリアランス制度は雇用や労働条件に大きな影響を与える可能性があります。おもな懸念点を以下の表にまとめました。
- 望まない配置転換や解雇などの不当な取り扱い
評価への不同意や評価の結果としてセキュリティ・クリアランスを認められなかった場合の対応 - 採用活動への影響
セキュリティ・クリアランスの認定を前提として採用した者が審査に落ちた場合や内定段階で評価実施の可否などの対応
セキュリティ・クリアランスへの認定次第で、労働環境が変化しうる点が現在問題になっています。
企業活動への影響
セキュリティ・クリアランス制度は、企業活動にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。適合事業者認定に伴う負担の増大が大きな懸念です。具体的には、施設設備の特別な整備や厳格な情報管理体制の構築が求められるため、多くの投資が必要になります。
また、社員の適性評価に関わる手続きも企業の大きな負担となるでしょう。調査への協力や書類準備、面接設定などといった人事部門の業務量が著しく増加する恐れがあります。さらに、調査費用の負担も企業経営を圧迫する要因となるでしょう。
セキュリティ・クリアランス制度の必要性
セキュリティ・クリアランス制度の必要性への疑問は少なくありません。安全保障上の情報保全は重要ですが、制度範囲や対象が広すぎるためです。
さらに、既存の特定秘密保護法にて機密情報保護の法的枠組みが存在する状況において、新たな制度が重複する箇所も多いという意見があります。企業や個人に過度な負担を強いることにもなりかねません。
セキュリティ・クリアランス制度に対する企業の対応ポイント
セキュリティ・クリアランス制度への対応に向けた企業の動きとして必要になるポイントは、以下のとおりです。
- 準備すべき基本内容
- 社員への情報共有と教育
- 情報管理体制の整備
それぞれの内容について解説していきます。
準備すべき基本内容
セキュリティ・クリアランス制度への適切な対応は、企業の信頼性を高めます。まず自社が制度対象となるかどうか確認が必要です。重要インフラ事業者やサイバーセキュリティ関連企業は経済安全保障の観点から対象となる可能性があります。
対策としては社内で基本方針を策定する必要があるため、本制度の正確な理解が重要です。制度対応への役割分担を行い、会社全体で取り組む姿勢が重要となります。
また、個人情報の厳格な管理が必要となるため、現状の内部規程を見直す必要があります。情報取得から廃棄までの流れや情報漏えいや不正利用に対する防止策を盛り込むと、情報提供する評価対象者に対して効果的です。
社員への情報共有と教育
セキュリティ・クリアランス制度の円滑な運用には、事業者だけでなく個人単位での認定が必要であるため、全社員の理解と協力が欠かせません。
本制度の目的や重要性をていねいに説明し、評価認定されない場合のリスクも伝えると理解を得やすくなります。また、本制度と密接な関係がある重要経済安保情報保護活用法について、社員に理解させることも重要です。
なお、適性評価への協力を促すための説明会もおすすめです。一般的な個人情報以上に聞き取りが発生する審査項目やプロセスについて、個人情報保護への取り組みとあわせて説明すると効果的でしょう。
情報管理体制の整備
セキュリティ・クリアランス制度では「重要経済安保情報」を守る体制づくりが必須です。政府から情報提供を受けるためには、適合事業者として認定される必要があり、情報管理体制の整備は欠かせません。自社の情報管理体制が国の安全保障に直結するため、企業の責任は重大になります。
情報保全措置の強化として、取扱部署での入退室管理や情報保管場所での暗号化や管理システムといったセキュリティ対策の強化が必要です。ただし本制度への対応は重要ですが、一方でコスト負担を伴うため計画的かつ適切な準備対応が必要になるでしょう。
セキュリティ・クリアランス制度の理解を深め、できる準備から始めよう
セキュリティ・クリアランス制度は2025年5月から施行される日本の安全保障を強化する重要な取り組みです。施行前の現段階より、理解を深めておくことが企業の競争力維持につながります。
本制度は事業者単位と個人単位それぞれで認定が必要です。適合事業者としての認定には、情報管理体制の整備が重要になります。また、個人では行政機関を通して内閣府からの調査を受けなければなりません。
また、社員への情報共有も計画的に進めるべきです。本制度の目的や重要性を伝え、情報管理の意識向上に努めます。なお、個人情報を提供することになる調査に関してていねいに説明すると、社員の不安を取り除く効果があります。
施行が近づくにつれ、具体化する情報もでてきます。今できる準備から着手し、将来的な変更にも柔軟な対応ができる体制づくりを心がけましょう。