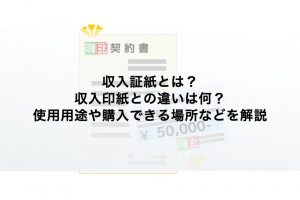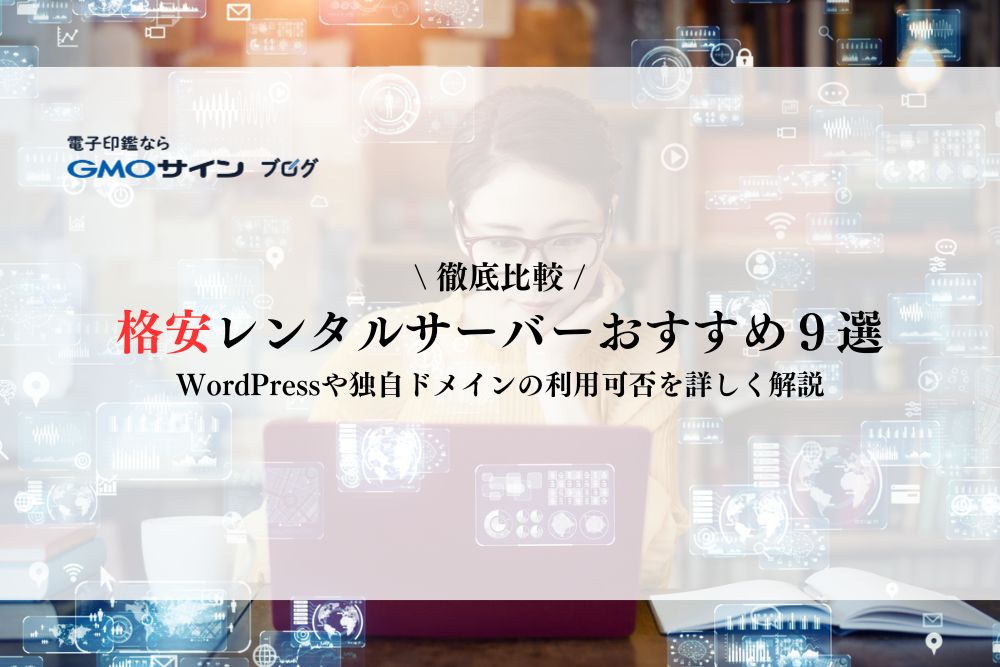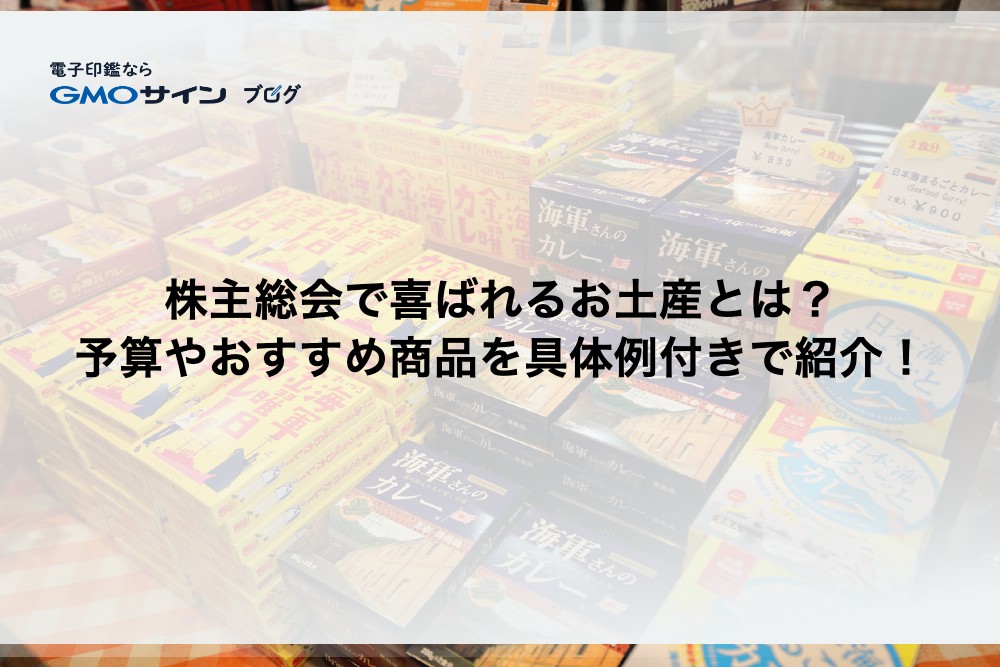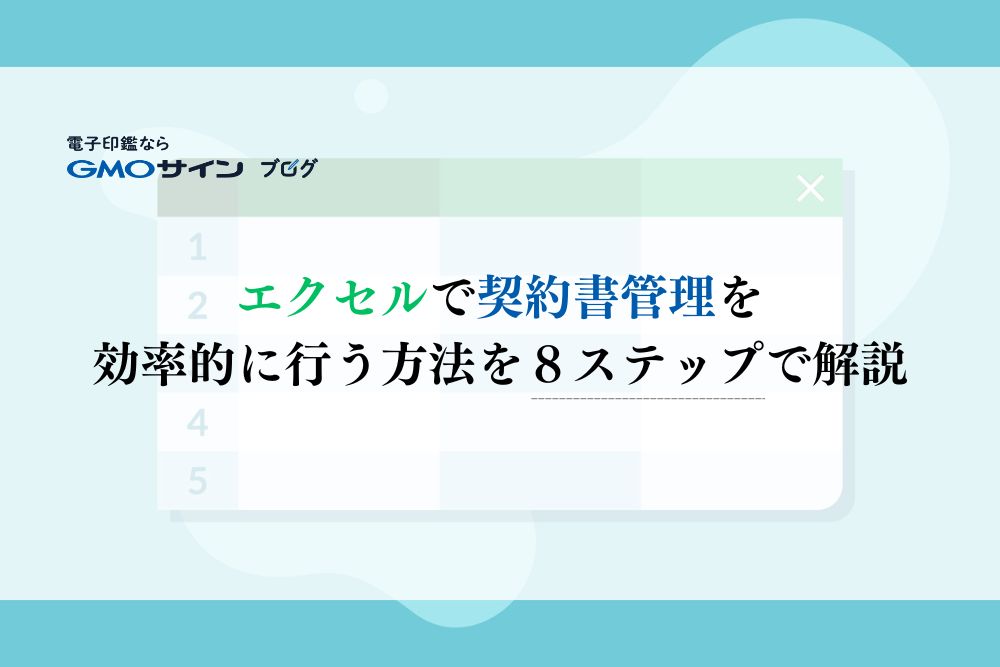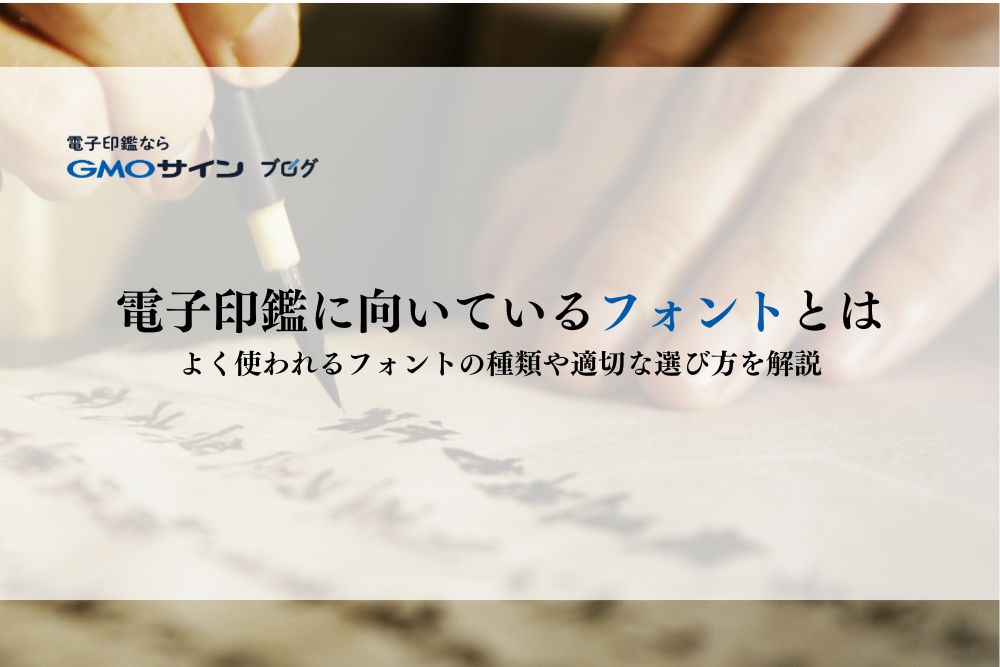\ 新プランリリース記念 /

\ 新プランリリース記念 /


ワークライフバランスを重視する現代において、長時間労働は依然として深刻な問題です。「1日8時間勤務は非推奨」と謳う企業もあります。一体、どれだけの労働時間を過ぎると一般的な長時間労働とみなされるのでしょうか?
本記事では、長時間労働の定義となる基準、そしてその危険性について詳しく解説します。
長時間労働の基準は、明確に法律で定められているわけではありません。
労働条件の最低基準を定めている労働基準法によれば、原則として1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間以内とされています。この基準を超える労働は、長時間労働とみなされる可能性が高いでしょう。
実際は、労働時間によって業務状況も大きく異なりますよね。たとえば、繁忙期や緊急時は1日の労働時間が8時間を超えてしまうケースも少なくありません。おおよそ、長時間労働と判断されてしまう基準は次の3つです。
これらの基準もあくまでも目安であり、個々の状況によって判断も異なるため注意が必要です。
1カ月45時間以内とは、会社が従業員に依頼できる残業時間の目安です。時間外労働・休日労働は最小限にとどめることを前提に、会社と労働組合(または従業員代表)は、残業時間に関する決まりごとを明記した「36協定」を締結します。
36協定とは、労働基準法第36条で定められている「時間外・休日労働に関する協定」で、締結後労働基準監督署への届け出を行う必要があります。
従業員の健康を守るためには1カ月あたりの残業時間の上限は45時間以内とされています。しかし繁忙期など、どうしても残業が必要な場合は、この上限を超えることもあるでしょう。
重要なのは会社が36協定の内容を守り、従業員の労働時間を適切に管理することです。 45時間を超える残業をさせる場合は、法律違反になる可能性があります。
1カ月80時間以上という労働時間は、過労死のリスクが非常に高まる目安とされています。 これは法律で決められたものではありませんが、労働時間管理において重要な指標です。
厚生労働省は、2〜6カ月間の平均残業時間が80時間以内であれば問題ないと、この基準を参考にしています。つまり、ある月は80時間を超えても、他の月で調整できれば良いということ。
会社と労働組合が結ぶ「36協定」では、1カ月間の残業と休日出勤の合計を100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内にすることが一般的です。36協定を結んだ場合は1カ月100時間を超える残業は違法となるため、注意が必要です。
一方で、36協定を結んでいない会社の場合は、この基準はあくまでも目安として扱われます。ただし、厚生労働省では時間外労働の上限規制として、年間720時間以内という基準も設けているため、この労働時間を超える場合は、長時間労働と判断できるでしょう。
1カ月160時間以上の残業は、精神疾患のリスクを高めるとされ、長時間労働の目安としてよく挙げられています。これは厚生労働省が定めた精神障害の労災認定基準に基づくものです。
具体的には、以下の状態が当てはまった場合は、労災認定の対象となる可能性があります。
ただし、精神疾患の発症には労働時間の他に、職場環境や人間関係、個人の性格や体質などのさまざまな要因もあります。たとえば、1カ月160時間未満であっても精神疾患を発症する可能性は十分にあり、逆に160時間を超えていても発症しない方もいるでしょう。
重要な指標は、会社が従業員のメンタルヘルスに配慮し、長時間労働をさせないように努めているかどうかです。従業員自身も自分の心身に異変を感じたら早めの相談が必要です。
長時間労働は労働者の心身や企業、社会に深刻な影響を与えます。ここからは、どのようなリスクがあるのか詳しく解説しましょう。
長時間労働は、健康に深刻な悪影響を及ぼします。心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクが高まるだけでなく、ある研究では、長時間労働者はそうでない人に比べて心筋梗塞のリスクが 1.63倍高いという結果も報告されているのです。
さらに、睡眠不足や不規則な生活、運動不足などが重なり、代謝異常、免疫力低下、消化器疾患、睡眠障害といったさまざまな身体的な問題を引き起こす可能性もあります。
身体面だけでなく、精神面への影響も無視できません。長時間労働によるストレスや疲労は、うつ病、不安障害、パニック障害、燃え尽き症候群などの精神疾患の発症リスクを高めます。不安や緊張状態が慢性化し、心身に深刻な負担がかかるのです。
長時間労働は、労働者の集中力や創造性を阻害し、結果として個人の生産性、ひいては組織全体の生産性の低下につながるでしょう。
(参照:労働時間と急性心筋梗塞・脳卒中発症リスクとの関連|国立がん研究センター)
長時間労働は、企業にとってもさまざまな悪影響を及ぼします。従業員の健康だけでなく、企業の業績や社会全体にも負の影響を与えかねません。考えられる影響は、おもに以下の2つです。
長時間労働による企業への影響とは、人材問題、企業イメージの悪化、そして労務トラブル増加という三重苦を指します。
常に従業員が疲労困憊しているとモチベーションが低下し、離職率の上昇につながり、優秀な人材の流出を招きかねません。 長時間労働が常態化している企業は、働き方改革への意識が低く、従業員の健康を軽視しているという負のイメージを抱かれやすく、優秀な人材の確保が困難になります。
さらに、労働基準法違反や労災事故などのリスクも高まり、経済的損失や社会的信用失墜という深刻な事態を招く可能性もあるでしょう。
一方で社会への影響として考えられることは、生産性の低下や社会福祉費の増加、労働意欲の低下などが挙げられます。
長時間労働は、個人の生産性低下から社会全体の経済停滞、社会福祉費の増大、そして国民全体の活力低下という深刻な社会問題を引き起こします。
疲労とストレスは労働者の集中力と創造性を奪い、生産性を低下させ、ひいては経済成長を阻害することになるのです。くわえて、健康問題や労働災害の増加により、社会福祉費の増大につながり、国民全体の負担も増加します。ここまで来ると、もはや個人の健康面に限らず、企業の業績や社会全体に悪影響を及ぼす深刻な問題です。
働き方改革を推進し、長時間労働を解消することは個人の幸福、企業の成長、社会全体の活性化にとって不可欠といえるでしょう。
ここからは実際のニュースも踏まえて事例を紹介します。
日本はヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヶ国の先進国が加盟する国際機関OECD諸国(経済協力開発機構)のなかでも労働生産性が低い国の一つとされています。
OECD.Statデータベースなどをもとに2023年公益財団法人日本生産性本部が実施した調査によると、38か国中30位と他の国と比べると低い水準にあるのです。
大きな理由として、長時間労働が常態化していることが挙げられるでしょう。長時間労働常態化により労働者の集中力や創造性を低下させていることが問題視されています。
長時間労働を減らし、労働者のワークライフバランスを改善することが日本の労働生産性向上に不可欠といわれています。
長時間労働は、従業員のモチベーション、活力、そして仕事への満足度を著しく低下させます。
優秀な人材ほど、能力を活かせる環境とワークライフバランスを重視し、長時間労働の企業を離れる傾向にあるのですが、2024年では建設業界における時間外労働の上限規制が、人材獲得競争の激化と人件費の高騰を招き、企業経営を圧迫する大きな問題となりました。
建設業界は長年、長時間労働が当然といった環境でした。人材不足も深刻な課題でしたが、2024年に行われた時間外労働の上限規制により、既存の問題をさらに悪化させてしまったのです。
企業は規制に対応するため、人材確保や業務効率化に努力せざるを得ません。しかし人材不足と採用難は容易に解決できるものではなく、人件費の高騰も避けられません。
結果として、時間外労働の上限規制は建設業界に大きな打撃を与えており、人材不足の解消と真の働き方改革が喫緊の課題となっているのです。
1991年と2015年の広告代理店における新入社員の過労自殺のニュースは、知っている方も多いのではないでしょうか。この事件は日本社会に大きな衝撃を与え、長時間労働の危険性を改めて認識させ、働き方改革の必要性を強く訴える契機となりました。
1991年の事件では、若手社員の過労自殺を受け、遺族が会社を訴えを起こしました。その結果、裁判で長時間労働と自殺の因果関係、会社の安全配慮義務違反が認められたのです。
この事件は「過労自殺」という言葉を広く知らしめることとなりました。また2015年の事件でも、新入社員の過労自殺が労災認定され、月100時間を超える長時間労働やパワハラの実態が明らかになっています。
これらの事件を受け、日本の企業は労働時間管理の徹底、労働環境の改善、メンタルヘルス対策に力を入れるように変化しようとしています。政府も働き方改革関連法を制定するなど、社会全体で長時間労働問題への取り組みが進んでいます。
今後も、従業員の安全と健康を守るための継続的な努力が日本社会においては必要不可欠といえるでしょう。
長時間労働は、従業員の心身の健康を損ない、労働生産性を低下させるなど多くの問題を引き起こします。だからこそ長時間労働を解消し、働き方改革を進めることは企業、従業員の両者にとって重要な課題でしょう。
ここからは長時間労働にならないために今からできる対策方法を紹介します。
企業側における長時間労働の要因は、おもに次のとおりです。
新規事業の立ち上げや市場競争の激化により業務量が増加し、残業が必要になることがあります。また、効率的でない業務プロセスや無駄な会議が時間を浪費し、従業員の負担を増加させるケースもあるでしょう。
さらに、人手不足も問題であり、業務をこなすために残業が避けられない状況が生まれがちです。これは、従業員の長時間労働を助長する要因にもなり得ます。こうした課題を総合的に改善することが、長時間労働の解消に向けた第一歩となります。
こうした対策は、従業員が時間内に業務をこなせるようサポートし、働き方改革を促進することで、従業員の心身の健康を守り、生産性向上にもつながるでしょう。
一方で、従業員自身にも、長時間労働の原因となる要因があります。
こうしてみると、 時間管理能力の不足による計画性の欠如なども要因として挙げられることがわかります。企業側の問題とは別に、個々の従業員が長時間労働に陥るリスクを高めているのです。
これらの意識を持つことが重要でしょう。自己啓発と意識改革によって個々の働き方を改善し、長時間労働リスクの軽減が期待できます。
一般的に、1日12時間勤務は法定労働時間を超えているため行うことはできませんが、36協定を締結していれば違法ではありません。
ただし、時間外労働の上限が1カ月45時間・1年360時間と定められているので、慢性化してしまうと違法になる可能性があります。
36協定を結んでいる場合でも、上限の1カ月45時間を超えると原則として違法になります。
しかし、特別条項が適用されている場合は、1年間で6カ月以内であれば月100時間未満の残業を行えるので問題ありません。
長時間労働は、おもに法定労働時間を超えた場合に適用されます。一方で、過重労働は過度な残業や高頻度の休日出勤など、身体と精神に悪影響を与える働き方のことです。
長時間労働はあくまでも長い時間働くことを指しているため、身体や精神にダメージを与える重大なケースだけとは限りません。
長時間労働は、従業員だけでなく企業にとっても大きな損失をもたらします。長時間労働を解消し、働き方改革を推進するためにも、企業と従業員の双方で意識改革を行い、具体的な対策に取り組む必要があるでしょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。