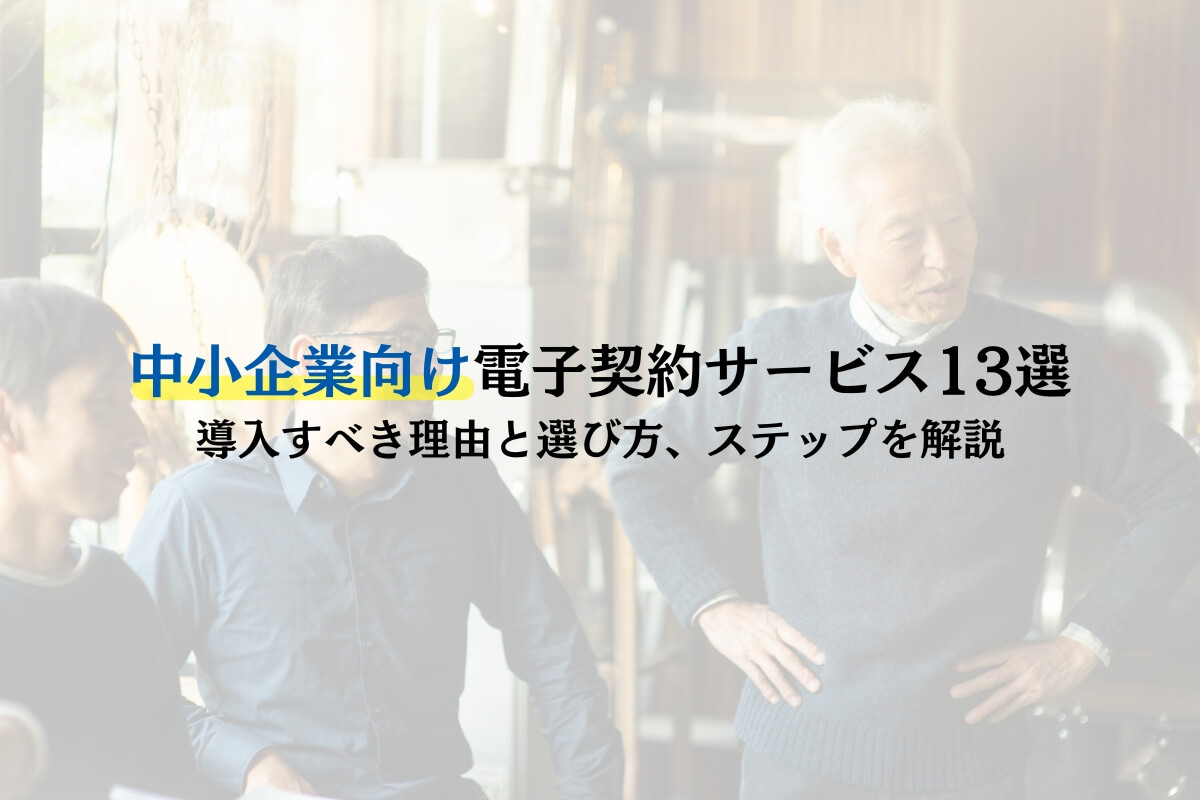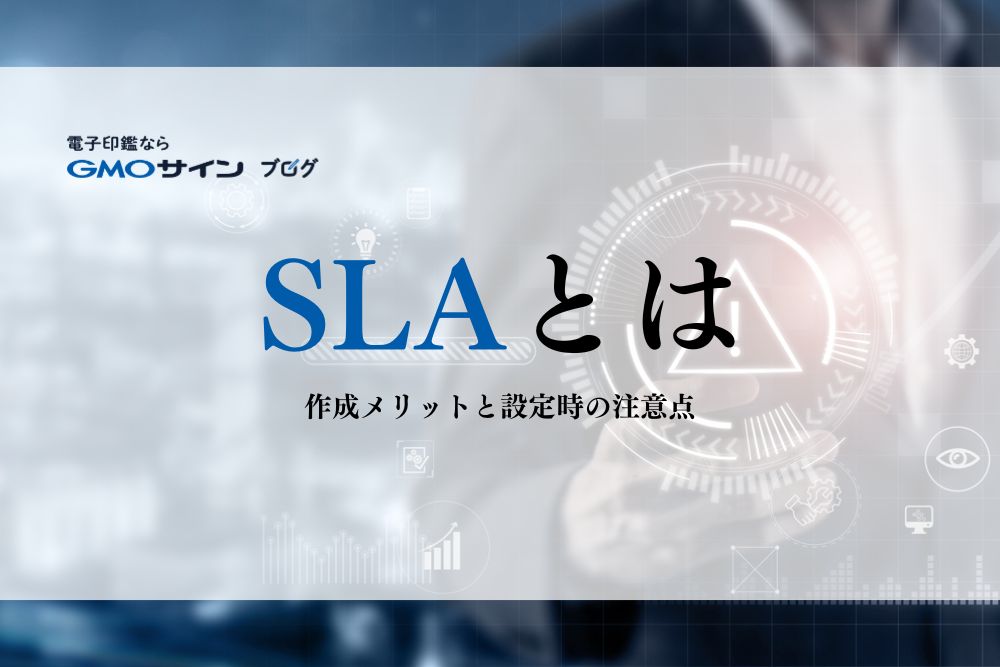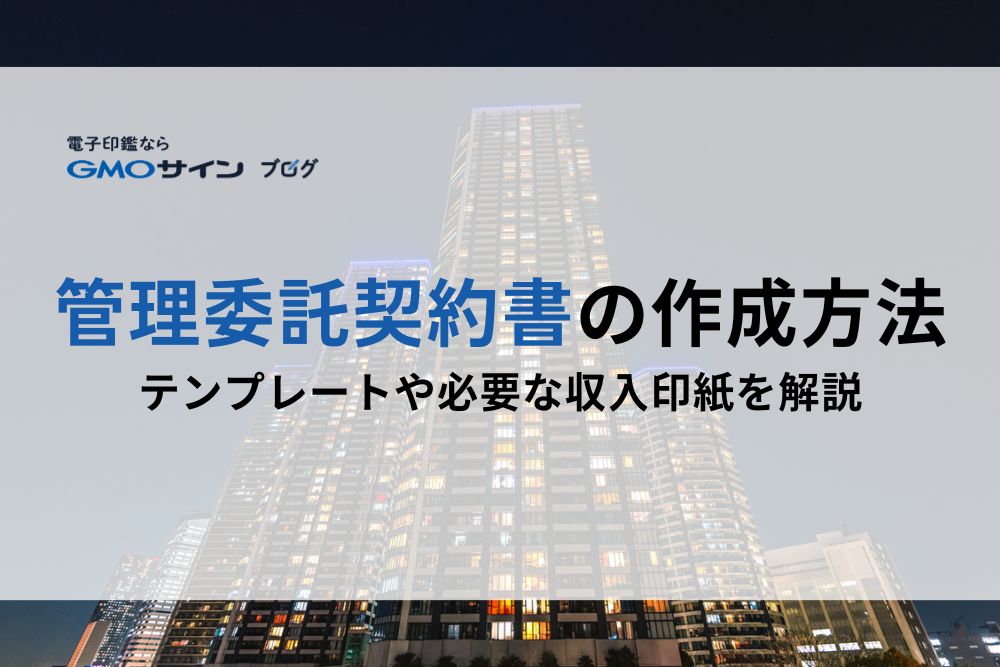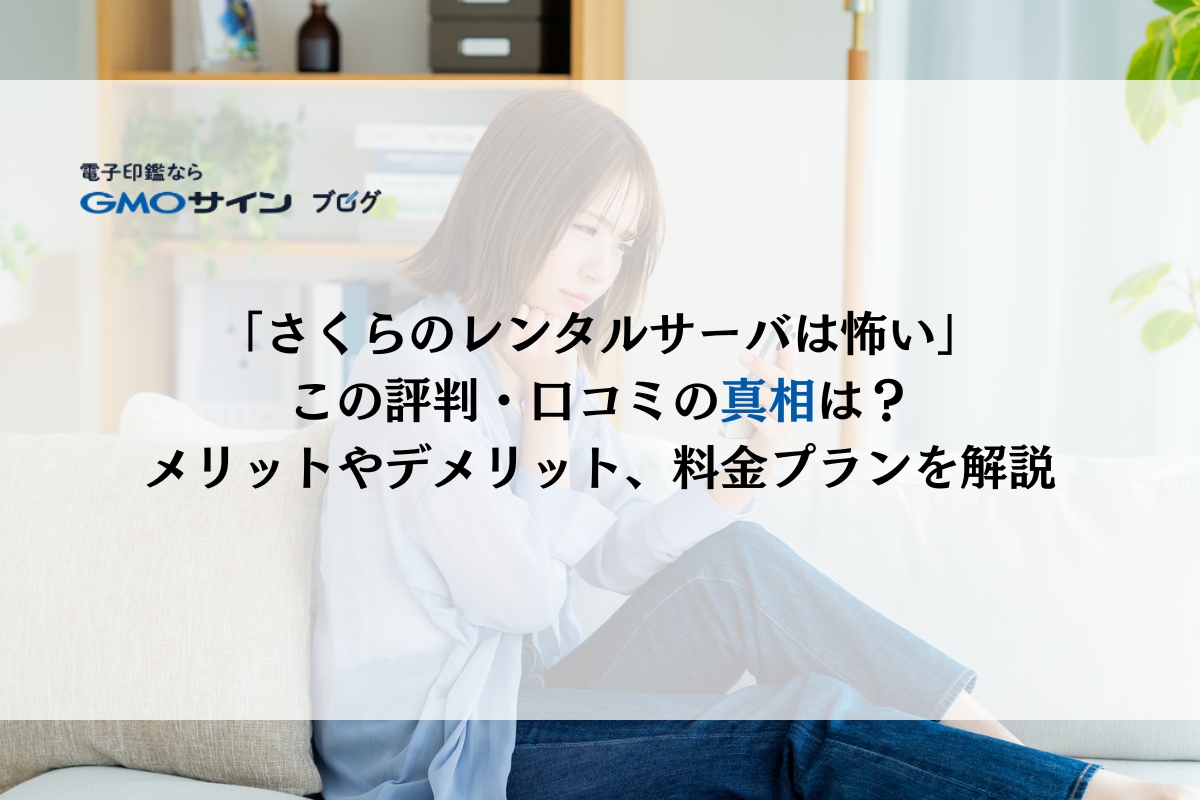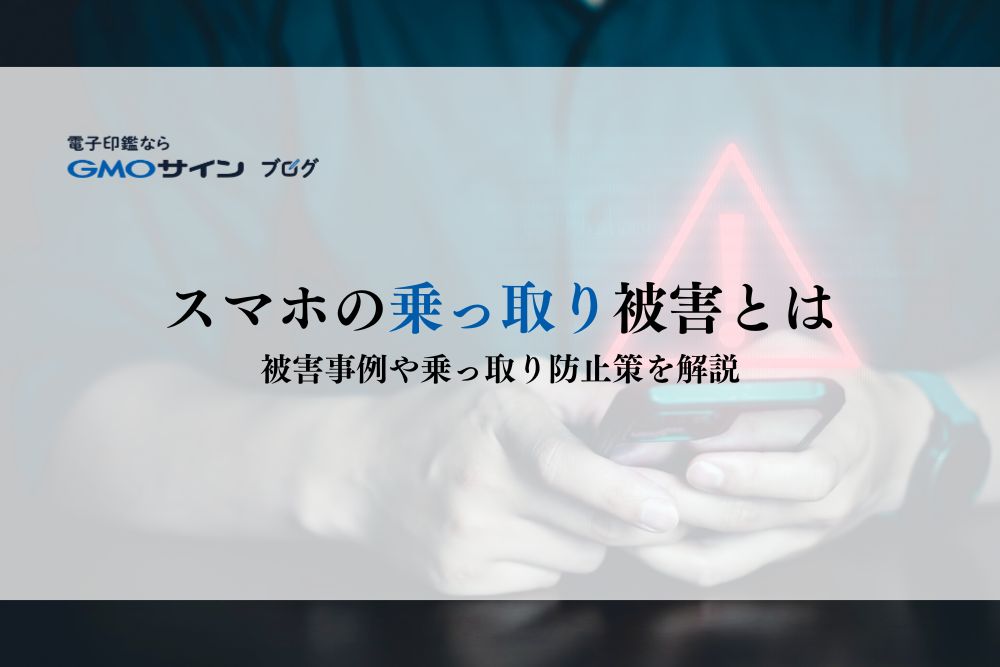背任とはおもに会社での不正行為に該当する犯罪行為であり、見過ごしてしまうと大きな損害を出してしまうリスクがあります。そのため、問題なくビジネスを行うためには、背任について詳しく知り、対策も把握することが重要です。
そこで本記事では背任の概要や見つかった場合の対処法、防止策についても紹介しますので、ぜひご覧ください。
背任とは
背任とは刑法247条に規定されている犯罪行為であり、事務を処理する者が自己または第三者の利益を図るか本人に損害を加える目的から任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を与える行為を指します。背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
背任罪の構成要件について
背任罪が成立する構成要件は、以下のとおりです。
- 他人から事務処理を委託された
- 任務に背く行為があった
- 図利加害目的があった
- 本人に財産上の損害を与えた
それぞれ詳しく解説します。
他人から事務処理を委託された
背任罪が成立するケースは、他人から事務処理を委託された場合に限られます。そのため、行為者自身の意思で事務処理を行った場合には背任罪は成立しないと考えられます。
任務に背く行為があった
他人のために行う事務処理について、その任務に背く行為が認められることも必要です。本来委託された事務に関して行為者は誠実に対応する義務がありますが、その期待に反して背任的行為を行ったことも要件となります。
図利加害目的があった
図利加害目的とは、行為者が自己または第三者の利益を図るか、本人に財産上の損害を加える目的を指します。また、本人の利益を図る目的がないことも要件として考えられますが、判例ではケースバイケースで判断されています。
本人に財産上の損害を与えた
背任罪は、本人に財産上の損害を与えた時点で行ったものと見なされます。そのため、実際に損害が生じていない場合には、背任未遂罪にとどまります。
特別背任罪との違い
背任罪に類似している犯罪行為として、特別背任罪が挙げられます。特別背任罪とは、会社の役員など権限を持つ人間が背任行為をした場合に成立する犯罪です。
特別背任罪は会社法960条で規定されており、法定刑は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されることが定められています。
権限のある人間が行う犯罪行為であることから、背任罪と比べて刑罰が重くなっている点が特別背任罪の特徴といえます。構成要件は背任罪とほぼ同じですが、行為者が役員など権限ある人間に限られている点が異なります。
背任罪で逮捕された後の処遇について
背任罪が発覚して逮捕された場合には、管轄の警察署で取り調べを受けることになります。取り調べで嘘をついたり誤魔化したりした場合には、刑罰が重くなる可能性が考えられるでしょう。ただし、黙秘権がありますので、自身に不利になる内容は発言しなくてもいいことが認められています。
また、逮捕から48時間以内に身柄が検察庁に送られ、再度取り調べを受けます。この時点で身柄を拘束する必要があると判断された場合には、裁判官に勾留されることが要求されます。そして勾留決定した場合には10日間、延長があった場合にはさらに10日間勾留されてしまうのです。
勾留期間中に検察官は取り調べの内容を精査して、証拠もチェックして起訴すべきか不起訴にすべきか判断します。不起訴の場合はこの時点で刑事手続きは終わりますが、起訴された場合には刑罰を受けることになるでしょう。また、略式起訴ならば数日で完了しますが、裁判になった場合には手続きが長期にわたりますので、かなりの心的疲労を受ける事態が予想されます。
背任罪が発覚した場合の影響
背任罪が発覚した場合は、さまざまな影響が考えられます。勤務先と自身への影響について、それぞれ解説します。
勤務先への影響
刑事事件における有罪率はほぼ100%ですので、背任罪などの犯罪で逮捕された場合には、勤務先に影響を及ぼす事態は避けられないでしょう。特に特別背任罪の場合は役職を利用した犯罪となりますので、大きな影響を与える事態が懸念されます。
自身への影響
背任罪が成立した場合には、ほぼ勤務先を離職することになるでしょう。また、損害賠償を請求される事態も考えられます。背任罪で懲役刑が科せられた場合には、執行猶予がつく場合を除いて5年以下の期間刑務所に入所しなければならなくなってしまいます。
背任が見つかった場合の対処法
社員や役員など会社の関係者による背任行為が見つかった場合には、以下の対処法を行うことをおすすめします。
- 背任行為に関する調査
- 背任行為を中止させる
- 裁判を検討する
背任行為に関する調査
まずは背任行為が認められるかどうか調査することが必要です。社内における周辺の関係者における聞き取りや当該社員に委託している事務処理に関するデータの保存などを行いましょう。
また、法務部など専門の部門と協力して、適切な対策を講じることも求められます。弁護士など外部の専門家とも連携して、早急な対応を考えましょう。
背任行為を中止させる
背任行為を認められるに足る証拠がそろい、対策も決まったらすぐに当該行為をやめさせましょう。
背任と疑わしい行為が見つかった場合にはその場で中止させたくなりますが、証拠不十分のままだとその後の裁判で不利になったり適切な懲戒処分が行えなくなったりする恐れがありますので、まずは調査を十分行うことが必要です。
裁判を検討する
背任罪は成立すると思われる場合には、裁判を検討しましょう。背任罪は会社が主体となって、対象の行為者を刑事告訴できます(刑事訴訟法230条)。ただし、損害賠償を求める場合には民事訴訟も必要となる点に注意してください。
背任罪を防止するには
背任罪を防止するには、以下の対策を実施するとよいでしょう。
- 会社のコンプライアンス徹底
- 法務部門や弁護士などとの連携の確認
- 業務内容の確認体制や監査など内部統制の徹底
- AIツールの活用
会社のコンプライアンス徹底
自社が社員や役員の不正行為に対して、コンプライアンスを徹底していることを社内外にアピールできます。法務や監査などの役割をきちんと果たしていることをアピールできますので、健全性を取引先や関連会社などに伝えられます。
法務部門や弁護士などとの連携の確認
問題解決によって、社内における法務部門や社外の弁護士などが連携して不正行為に対処するノウハウを獲得できます。そのため、再発防止や他の不正行為におけるスムーズな対応といった効果が期待できるでしょう。
業務内容の確認体制や監査など内部統制の徹底
背任罪を防ぐには、業務内容の確認体制や監査など内部統制を徹底することが重要です。具体的には社員が相互的に業務を確認したり、業務の属人化を避けたりする方法などが有効です。できれば監査を社内だけでなく、外部からチェックする機能を整備しておけば、確実に不正行為を防げるようになるでしょう。
AIツールの活用
AIツールを導入して、財務プロセスや資産を管理する方法もおすすめです。不自然な取引や資産の流れなどを迅速に検出できますので、不正行為の防止や効率的な発見に役立つでしょう。
背任に関するよくある質問
背任行為の具体例はどういうもの?
背任行為とは、信頼された立場の人が、その信頼を裏切って損害を与える行為です。たとえば、会社員が取引先から裏でお金をもらう、取締役などの会社役員が会社のお金を私的に使うなどが該当します。
背任と背信はどう違う?
どちらも信頼を裏切る行為ですが、使い方が違います。
背任は「任された仕事に反して、相手に損害を与える行為」で、特に法律では会社などから任された人が損害を与える場合に使います。
背信は「約束を破る行為」という広い意味で、必ずしも損害が生じなくても使えます。
横領と背任はどう違う?
両方とも他人の財産に関する犯罪ですが、内容が違います。
横領は「自分が管理している他人の物を勝手に自分のものにする行為」で、会社の物を無断で持ち帰るなどの行為です。
背任は「任された仕事に反して損害を与える行為」で、物を取るだけでなく、情報漏えいなども含みます。
背任罪には厳格に対応して、コンプライアンスを遵守しましょう
背任罪はおもに会社に財産上の損害を与える犯罪ですので、厳格な対応が必要です。また、背任罪に対して的確に対処することで、コンプライアンスを遵守していることを社内外にアピールできます。
不正行為の再発防止や法務および弁護士との連携確認などの効果もありますので、自社の健全性をアピールするために本記事で紹介した対処法や防止策をぜひ参考にしてください。