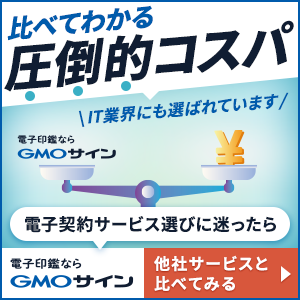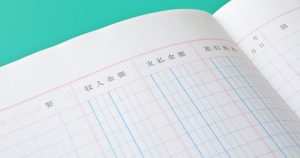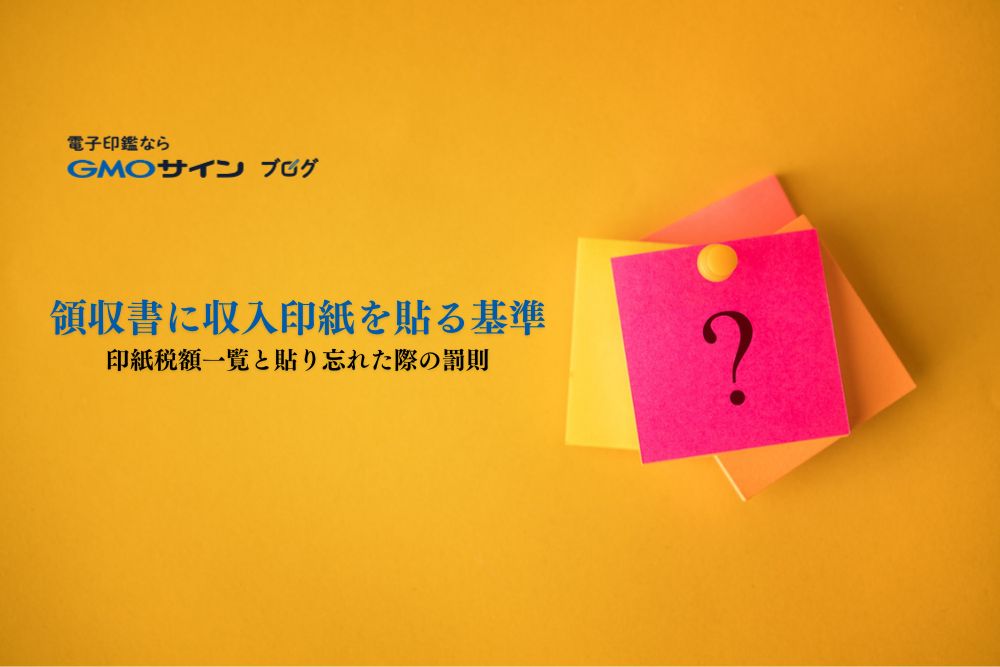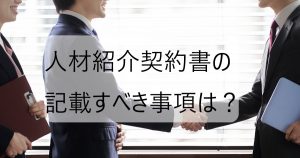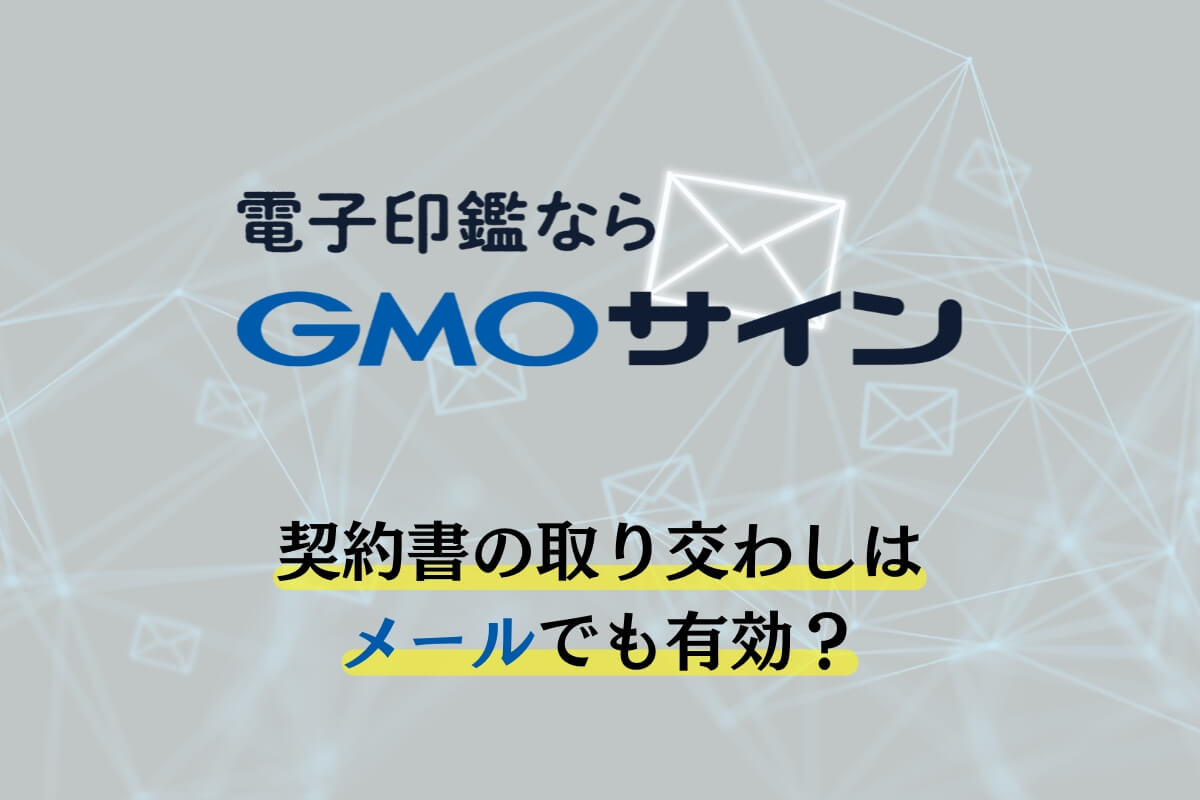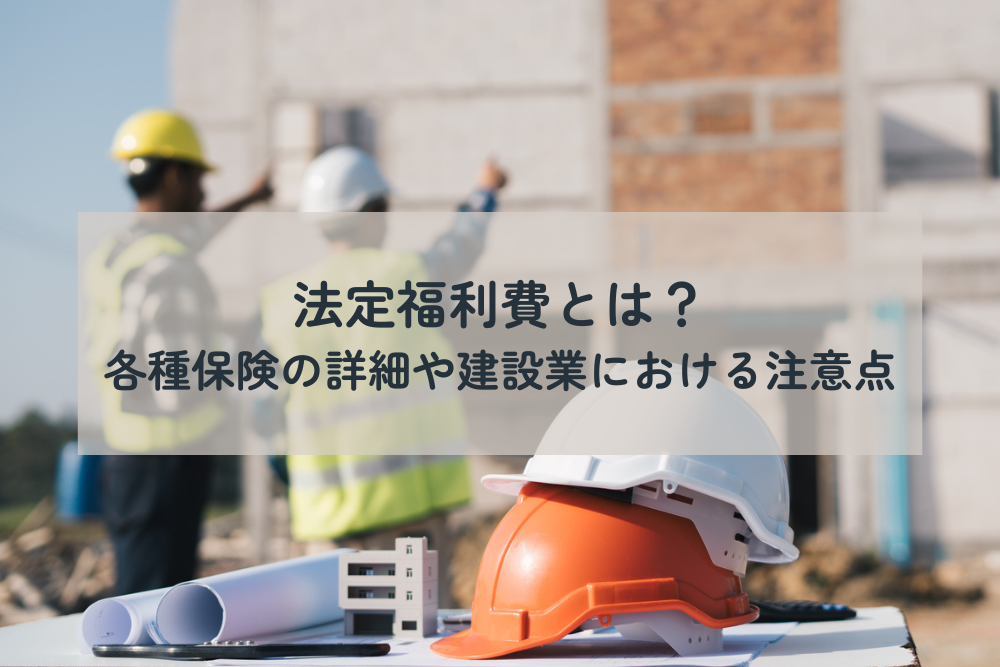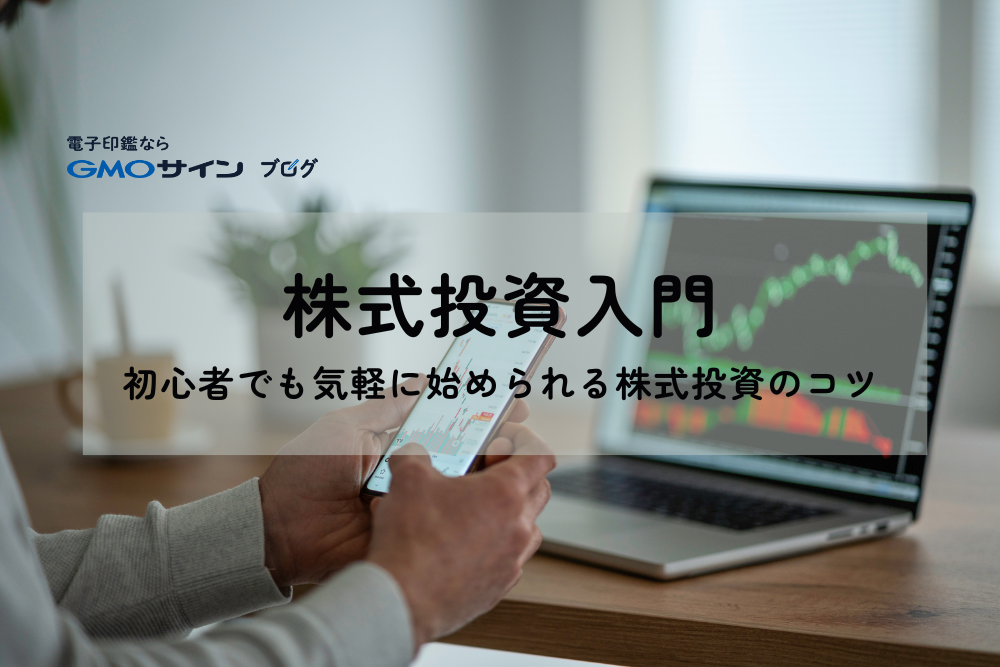世帯を構成する全員の住民税が非課税となる住民税非課税世帯となれば、住民税がかからなくなるのはもちろん、他にもさまざまな優遇措置が受けられます。
本記事では、住民税非課税世帯の概要を解説したうえで、年収やそれ以外の要件、住民税非課税世帯となった際の優遇措置などについてお伝えします。住民税非課税世帯に該当しているかどうかを知りたい方はぜひ、参考にしてください。
※なお、記事内の数字はすべて2024年11月5日現在のものです。
住民税の仕組み
住民税非課税世帯を理解するには、まず住民税の仕組みを知る必要があります。ここでは住民税の概要について解説します。
住民税の概要
住民税は、道府県民税(都道府県民税)と市区町村税の2つから構成されている地方税です。子育てや生活保護のほか、道路、公園、住宅の建設管理などに使われる一般財源として徴収されます。
住民税には法人が支払う法人住民税と個人が支払う個人住民税があります。会社員の場合、毎月の給与から天引きされ、会社(法人)が代わりに自治体に支払うのが一般的です。自営業や個人事業主の場合、個人が収入に応じて自身で支払います。
均等割と所得割
所得税の課税方法は均等割と所得割の2つあり、それぞれの税額(率)は次のとおりです。
均等割
均等割とは、所得に関わらず課税されるもので、税額は次のように決まっています。
| 総額 | 内訳 | |
|---|---|---|
| 令和5(2023年)年まで | 5,000円 | 市民税均等割 3,500円 都道府県民税均等割 1,500円 |
| 令和6年(2024年)以降 | 5,000円 | 市民税均等割 3,000円 都道府県民税均等割 1,000円 森林環境税 1,000円 |
令和5年(2023年)までは市民税均等割と都道府県民税均等割の2つで5,000円でした。令和6年(2024年)からは森林環境税が加わるものの、市民税と都道府県民税が500円づつ下がるため、合計金額は代わりません。
所得割
所得割とは、年間所得に応じて課税されるものです。扶養控除や社会保険料控除などを鑑みたうえで算出されますが、通常は道府県民税4%、市町村民税6%の10%となります。
(参照:総務省 個人住民税)
住民税非課税世帯とは
住民税非課税世帯とは、現在居住している自治体に住民税が課税されない世帯を指します。
ただし、先述したように住民税は世帯で支払うものではなく、個人で支払うものです。そのため、世帯のなかに1人でも住民税非課税世帯の要件に該当しなければ非課税世帯になることはできません。
住民税非課税世帯になるには、世帯年収や個別の要件に該当していることが必要条件となります。ここからは、住民税非課税世帯になるための年収の目安や要件のほか、住民税非課税世帯に適用される優遇措置について解説します。
住民税非課税世帯になる年収の目安
先述したように住民税の税額を決めるのは、均等割と所得割です。そして住民税非課税世帯というのは、均等割と所得割の両方が非課税になる世帯を指します。
一般的に住民税非課税世帯になる収入目安は次のとおりです。
| 給与収入(高齢者世帯は年金収入) | 均等割 | 所得割 | |
| 生活保護級地区分 | |||
| 1級地 | 3級地 | ||
| 単身 | 100万円 | 93万円 | 100万円(※1) |
| 夫婦のみ | 156万円 | 137.8万円 | 170万円 |
| 夫婦+子ども1人 | 205.7万円 | 168万円 | 221.4万円 |
| 夫婦+子ども2人 | 255.7万円 | 209.7万円 | 271.4万円 |
| 高齢者単身(65歳以上) | 155万円 | 148万円 | 155万円(※2) |
| 高齢者夫婦(65歳以上) | 211万円 | 192.8万円 | 222万円 |
※1:単身世帯での所得割は、所得控除などにより、課税最低限の108.8万円までは課税されません
※2:高齢者単身世帯での所得割は、所得控除などにより課税最低限の157.1万円までは課税されません
状況別の年収目安についても具体的に見ていきましょう。
単身世帯の年収目安
単身世帯で住民税が非課税となる年収の目安は、おおむね100万円前後です。年齢や障がいの有無によっても基準が異なりますが、多くの場合、給与収入ベースで100万円以下であれば住民税はかかりません。
ひとり親家庭の年収目安
ひとり親の場合、子供の数で住民税非課税となる年収の目安が変わります。児童扶養手当の有無や自治体ごとの控除の差によって多少変動しますが、基本的にはこの水準が判断基準になります。
| 子供の数 | 年収目安 |
|---|---|
| 1人 | 204万円 |
| 2人 | 205万円 |
| 3人 | 225万円 |
子供の数が増えるほど所得控除が増加し、対象範囲が広がります。学費や生活費がかさむ中、住民税の負担が減ることは非常に大きな助けとなるため、要件に当てはまるか早めに確認しましょう。
夫婦世帯の年収目安
夫婦2人だけの世帯では、収入が一方に集中している場合、年収がおおよそ155万円以下で非課税となるケースが多いです。配偶者控除などが適用されるため、世帯としての年収が少なくても条件を満たしやすくなります。
子供2人を持つ世帯の年収目安
共働きで子供が2人いる家庭の場合、住民税非課税となる世帯年収の目安は約255万円です。ただし、夫婦の収入配分や控除の適用状況により多少前後します。
児童手当や学費の負担が大きい時期には、非課税判定を受けることで手当の増額や補助の対象となる可能性もあります。
子供3人を持つ世帯の年収目安
子供が3人いる場合、非課税となる世帯年収はおおよそ280万円以下が目安です。人数が多いぶん扶養控除も大きくなり、条件を満たす幅が広がります。食費や教育費が重なるこの時期に、住民税の支払いが免除されることで、家計に余裕を生みやすくなります。
子供4人を持つ世帯の年収目安
子供が4人いる家庭では、非課税の目安となる年収は300万円前後です。扶養控除に加えて、自治体独自の手当制度が適用される場合もあり、実質的な支援額が大きくなります。
条件を満たせば、学費補助や保育料の減免といった制度の対象になるため、自治体への確認も忘れずに行いましょう。
子供5人を持つ世帯の年収目安
子供が5人いる世帯の年収目安は約320万円とされています。控除額が最大級になるため、他の世帯よりも非課税となる可能性が高まります。
支出の多さから金銭面に不安を感じている家庭も、こうした支援を上手に活用することで、教育費や医療費の負担を軽減することが可能です。
自営業の年収目安
自営業の場合、収入ではなく「所得」で判断されるため、必要経費を差し引いた金額が重要になります。目安としては、所得が45万円以下であれば住民税は非課税です。
帳簿管理や確定申告を正確に行うことで、控除の恩恵を最大限に受けることができるため、経費処理を怠らないようにしましょう。
年金受給者の年収目安
年金を受け取っている方は、年金額が年間約80万円以下であれば非課税となるケースが多いです。
非課税となることで、介護保険料や医療費の自己負担割合が軽減されるなど、日々の生活にも好影響が期待できます。
均等割と所得割の両方が非課税になる要件
均等割と所得割の両方が非課税になるための要件は次の3点のうち、1つでも満たしている必要があります。なお、数字はすべて東京23区の場合です。
1. 生活保護法による生活扶助を受けている
生活扶助とは、生活保護法第12条におき、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して行われるものです。具体的には衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な金銭の給付、更生施設への移送などが行われます。
なお、生活扶助を受けるための要件は地域によっても異なります。東京で単身世帯の場合、月の世帯収入が13万円以下です。
(生活扶助)
出典:生活保護法 | e-Gov法令検索
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
2. 障害者・未成年者・寡婦もしくは1人親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
給与所得者の場合は年収204万4千円未満。
3. 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下
たとえば東京23区内に住んでいる場合の額は次のようになります。
| 同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下 |
| 同一生計配偶者もしくは扶養親族がいない場合 | 45万円以下 |
なお、扶養家族は、16歳未満および地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養家族限定となります。また、23区以外に住んでいる場合は、均等割が非課税になる合計所得金額が異なる場合があるため、必ずそれぞれの居住する自治体に確認してください。
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
出典:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)|e-Gov法令検索
所得割のみ非課税になる要件
所得割のみが非課税になるための要件は、前年中の総所得金額などが次の金額以下の場合です。
| 同一の生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合 | 36万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下 |
| 同一生計配偶者もしくは扶養親族がいない場合 | 45万円以下 |
なお、扶養親族の定義に関しては、均等割と所得割の両方が非課税になる要件同様、16歳未満および地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養家族限定となります。
住民税非課税世帯に適用される優遇措置
住民税非課税世帯となった場合、住民税が非課税になるだけではなく、次のような優遇措置も適用されます。
国民健康保険料の減免
住民税非課税世帯になると国民健康保険料が軽減されます。軽減額は前年の所得に応じて7割、5割もしくは2割の減額です。対象者の要件は次のようになります。
| 減額割合 | 対象者の要件(令和5年度) (例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合) |
|---|---|
| 7割 | 43万円(※1)以下(給与収入98万円以下) |
| 5割 | 43万円(※1)+(被保険者数)×29万円以下(給与収入197万円以下) |
| 2割 | 43万円(※1)+(被保険者数)×53.5万円以下(給与収入302万円以下) |
(参照:国民健康保険の保険料・保険税について)
さらに、令和4年(2022年)4月より子育て世帯の経済的負担を軽減する観点から、国や地方の取組として未就学児の均等割保険料(税)を軽減する制度が開始されました。軽減率は、未就学児に係る均等割保険料の5割が公費によって軽減されます。
国民年金保険料の免除もしくは納付猶予
住民税非課税世帯で、前年所得(※1)が一定額に届かなかった、失業したといったなどの事情により国民年金保険料の支払いができない場合、免除もしくは納付猶予が与えられます。
免除を希望する場合は、居住する地域の自治体に対し申請書を提出します。承認された場合の免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかです。
免除や納付猶予となる所得の基準を算出する際は、前年の所得(※1)が次の金額以下となった場合です。
- 全額免除:(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
- 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
- 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
ただし、住民税非課税世帯の場合、免除申請をした場合、基本的に全額免除となります。
また、20~50歳未満の方で前年の所得(※1)が一定額に届かなかった場合、納付猶予の申請が可能です。免除申請同様、居住する地域の自治体に対し申請書を提出し、承認されれば、納付が猶予されます。
なお、免除や納付猶予は遡っての申請も可能で、具体的な期間は次のとおりです。
- 過去期間:申請書が受理された月から、すでに保険料が納付済の月を除く2年1カ月前まで
- 将来期間:翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの12カ月です。それを超える期間で申請する場合は、必要に応じて年度ごとに申請書を提出しなくてはなりません。
また、全額免除になった場合、老齢基礎年金の受給資格期間には合算され、老齢基礎年金の年金額への反映もあります。具体的には全額免除期間について、支給額は保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1となります。
納付猶予が承認された方の場合、老齢基礎年金の受給資格期間への参入はありますが、老齢基礎年金の年金額への反映はありません。後から追納しないと老齢基礎年金額は増えないままとなります。
※1:1月から6月までに申請する場合は前々年の所得
参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
医療費負担の軽減
住民税非課税世帯は高額療養制度の自己負担上限額が通常よりも低く設定されます。高額療養制度とは、1カ月にかかった医療費が高額になった場合、自己負担上限額を超えた分に関して後から支給される制度です。
住民税非課税世帯の自己負担上限額は次のように定められています。
| 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯II(70歳以上) | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯I (年金収入80万円以下など)(70歳以上) | 15,000円 | |
| 住民税非課税世帯(69歳以下) | 35,400円(24,600円※1) | |
(参照:高額療養費制度の見直しについて)
通常、年収156~約370万円でひと月の上限額が57,600円のため、住民税非課税世帯は、大幅に減額されています。
保育料の無償化
通常、幼稚園や保育園、認定保育園の利用料が無料になるのは3~5歳までです。しかし、住民税非課税世帯の場合、0~2歳までの子どもが保育園や認定保育園に行った場合の利用料も無料になります。
大学や専門学校の入学金・授業料の無償化
住民税非課税世帯で次の要件を満たしている場合、大学や専門学校の入学金・授業料が無償化もしくは給付を受けられます。
| 要件 | 年収の目安 |
|---|---|
| 両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合 | ~270万円 |
| 両親・本人(19~22歳)・高校生の家族4人世帯の場合 | ~300万円 |
支援・給付額は次のとおりです。
【支援額】
| 国公立 | 私立 | ||||
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | ||
| 大学 | 昼間制 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
| 夜間制 | 約14万円 | 約27万円 | 約14万円 | 約36万円 | |
| 通信課程 | – | 約3万円 | 約13万円 | ||
| 短期大学 | 昼間制 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |
| 夜間制 | 約8万円 | 約20万円 | 約17万円 | 約36万円 | |
| 通信課程 | – | 約3万円 | 約13万円 | ||
| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 | |
| 専門学校 | 昼間制 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |
| 夜間制 | 約4万円 | 約8万円 | 約14万円 | 約39万円 | |
| 通信課程 | – | 約3万円 | 約13万円 | ||
【給付額(月額)】
| 国公立 | 私立 | ||||
| 自宅生 | 自宅外 | 自宅生 | 自宅外 | ||
| 大学 | 昼間・夜間 | 33,300円 | 66,700円 | 42,500円 | 75,800円 |
| 通信課程 | – | 51,000円 | |||
| 短期大学 | 昼間・夜間 | 33,300円 | 66,700円 | 42,500円 | 75,800円 |
| 通信課程 | – | 51,000円 | |||
| 高等専門学校 | 25,800円 | 34,200円 | 35,000円 | 43,300円 | |
| 専門学校 | 昼間・夜間 | 33,300円 | 66,700円 | 42,500円 | 75,800円 |
| 通信課程 | – | 51,000円 | |||
住民税非課税世帯かどうかは必ず自治体で確認を
さまざまな事情で収入が減少したり、少ない方にとって住民税が非課税になれば大きな負担軽減となります。
ただ、収入が少ないだけで住民税非課税世帯が適用されるわけではありません。住民税の概要を理解し、年収の目安を把握したうえでそれ以外の要件も理解する必要があります。
ただし、年収の目安や優遇措置については、自治体により異なる場合もあります。また、時期により税制改正があれば、制度自体が変更になる場合もあるため、必ずそれぞれが居住する自治体のWebサイトで確認をしてください。
そのうえで自身が住民税非課税世帯に該当する場合は、適切な準備を行い、申請しましょう。