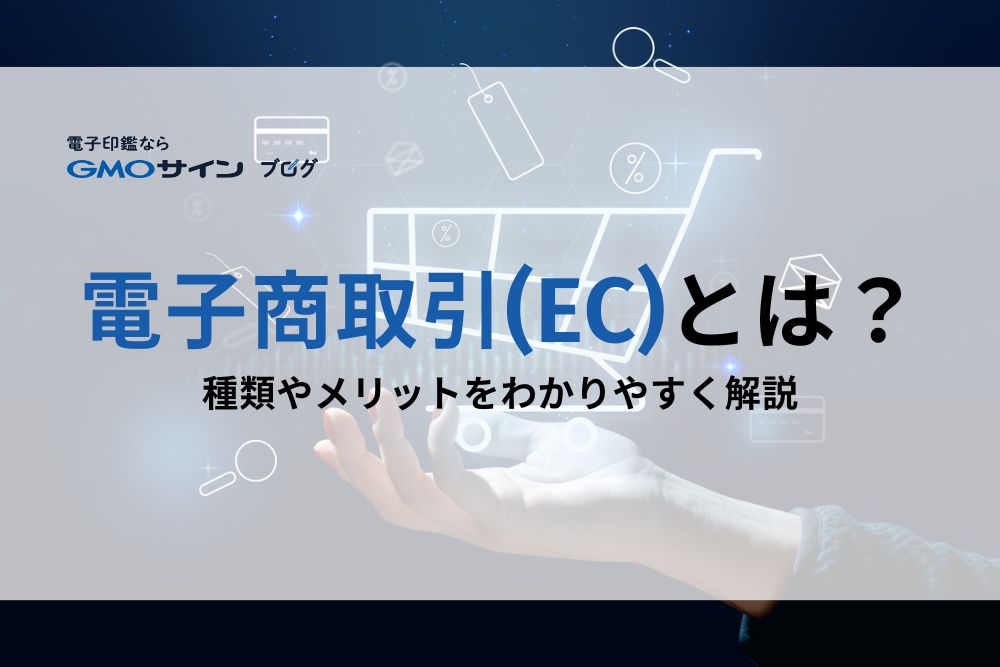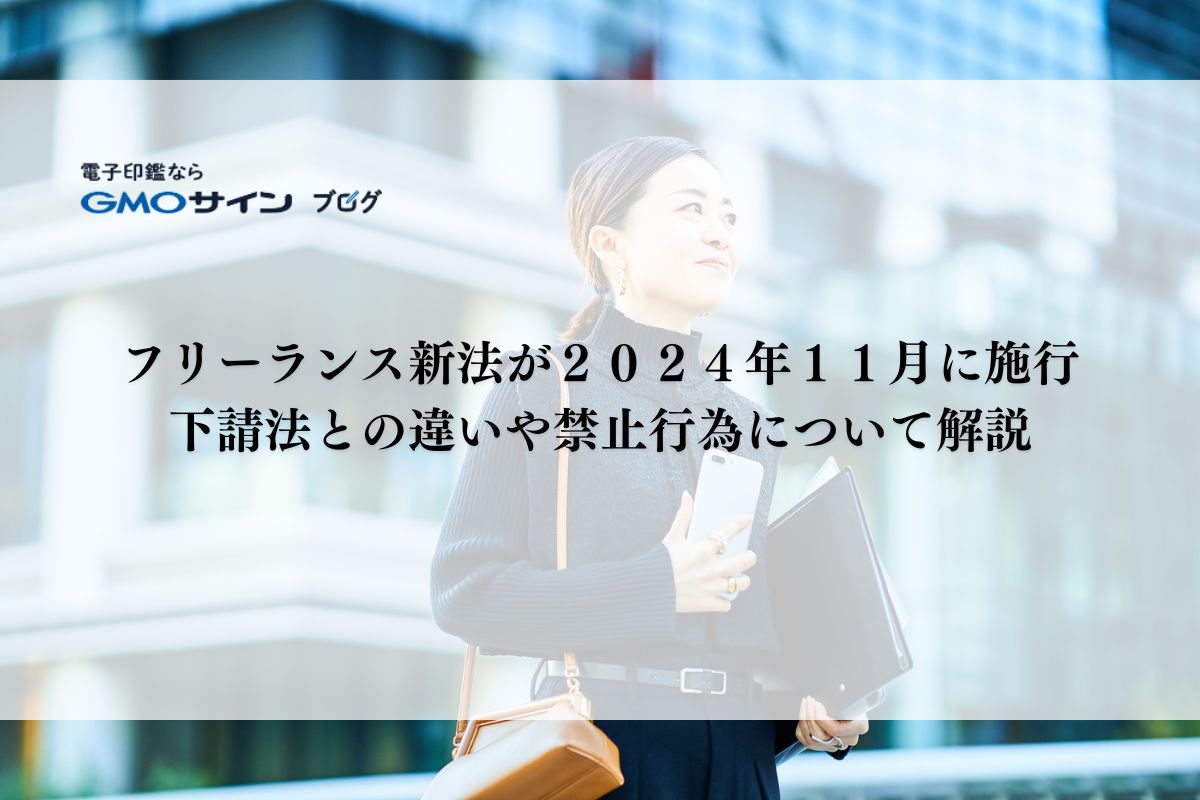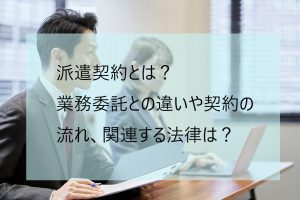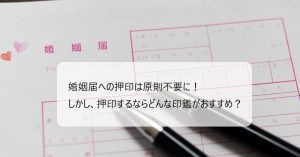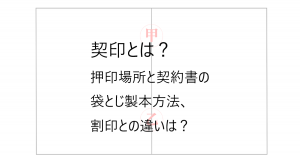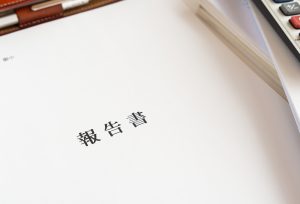戸建てに引っ越す予定だけれど、地震保険はいらないって本当?
と気になっていませんか。
万が一への備えになる一方で、戸建てには不要という声もあります。
この記事では、戸建てに地震保険は必要なのかを解説します。いらないといわれる理由や地震保険への加入がおすすめの人の特徴も紹介するので、保険への加入で迷っている方は参考にしてください。
地震保険とは?
地震保険とは、地震による家屋の損害を補償するものです。以下のようなケースで適用されます。
・地震によって家が壊れた
・地震で火事になり、家が焼失した
・地震の影響で最寄りの山が噴火し、家が壊れた
・地震の影響による土砂崩れで家が埋没した
・地震の影響による津波で家が流された
地震の影響による火事・山の噴火・土砂崩れ・津波による家の損害も補償されるので、幅広い自然災害に備えられるでしょう。
一点注意したいのが、地震保険は単独で加入できない点です。火災保険とセットで加入する必要があるので、申し込む際は2つ同時に手続きをしなければなりません。なお、火災保険契約途中に、地震保険を追加することも可能です。
戸建てに地震保険がいらないといわれる理由は?
地震保険はさまざまなシーンに適用されるものの、戸建てにはいらないといわれています。なぜ戸建てには不要なのか、その理由を見てみましょう。
地震保険を使えるシーンが限られている
地震保険は使えるシーンが限定されているので、加入しても使いにくい点がデメリットとして挙げられます。前述したように、保険は地震や関連する災害によって家が壊れた際に適用可能です。それに対し、火災保険は以下のようなシーンで適用されます。
・火災
・落雷
・ガス漏れによる破裂
・ガス漏れによる爆発
・台風による被害
・雹(ひょう)や雪による被害
・水災
・外部からの物体の衝突
・水濡れ
・盗難
火災保険は火事だけでなく、落雷や何らかの理由による爆発事故、台風、雹や雪による被害も補償してくれます。盗難被害にも対応しているので、幅広いシーンで補償を受けられるでしょう。
この点から、火災保険には加入するけれど、地震保険は必要ないと判断する人が多い傾向にあります。
地震に強い家を建築している
現在の家は地震に強い構造で作られていることから、保険への加入は不要と考える人も一定数います。家を建築する際は、耐震基準を満たさなければなりません。1950~1981年までに適用されていた旧耐震基準では震度5程度の地震に耐えられることを定めていましたが、1981年に内容が改正されています。
1981年から施工された新耐震基準では、震度6~7程度に耐えられることを定めています。旧耐震基準よりも厳しい内容にすることで、強い地震が起こっても損壊しにくい家が増えるため、地域全体の損害を抑えることが可能です。
地震で全損しても再建築費用全額をもらえるわけではない
地震保険加入時、適用される保険金額を設定できます。設定できるのは火災保険の金額の30~50%なので、再建築にかかる費用の一部しか補償されないと考えておきましょう。
地震保険は、家の建て直しではなく、損害後の生活を立て直すために適用される保険です。たとえ家が全壊したとしても、再建築費用の一部しか受け取れないことから不要だと判断する人も多くいます。
地震があまり起きない地域に住んでいる
地震があまり起きない地域に住んでいる方は、地震保険への加入に消極的です。日本は各地で地震が起こっているものの、頻繁に揺れを感じる地域は比較的限定されたエリアとえいえるでしょう。
保険料が高額で支払いが難しい
地震保険料の支払いが難しく、加入を断念する人もいます。保険料は以下の要素で決定します。
・家のある場所
・家の構造
・耐震や免震など、構造への割引
・加入者が希望する支払い方法や保険の適用期間
前述したように、日本は地域によって地震の頻度が異なります。発生頻度に応じて保険料が変わるため、住んでいる場所によっては高額になる恐れもあるでしょう。また、建物の構造によっても保険料は左右されます。
建物の造りによっては、地震が起こった際に大きな損害を受けます。構造によって損害リスクが異なるため、この点も保険料に反映されると考えておきましょう。耐震や免震施行をしている場合は割引が適用されるので、料金を抑えられます。
保険料は、長期契約で一括払いを選択したほうが安くなります。しかし、まとめて支払うことが難しい場合は分割で払っていくので、一括よりも高い金額を納めなければなりません。
地震保険への加入を検討したほうがいい人の特徴
地震保険は不要だと判断する人が多い一方で、加入を検討したほうがいいケースもあります。ここでは、保険への加入を検討したほうがいい人の特徴を解説しましょう。
地震が起きやすいエリアに住んでいる
日頃から頻繁に揺れが生じている、または規模の大きい地震を体験している方は、保険への加入を検討しましょう。過去に起きた大規模な地震は、発生から長期間、余震が続いています。
1923年9月1日に起きた関東大震災は、本震から約4カ月後の1924年1月にもマグニチュード7.3の大きな地震が起こっています。2011年に起きた東北大震災は本震から今もなお余震が続いており、なかには規模の大きい地震もあるため、予断を許さない状況です。
過去に大きな地震が起きているところや日頃から頻繁に揺れが生じている地域は、万が一への備えを確保することが大切です。
海の近くに住んでいる
地震によって津波が起こると、海沿いの地域に被害が生じます。津波によって浸水したり、最悪の場合は流されたりするので、地震保険に加入することがおすすめです。
海から少し離れているから危険かどうかがわからないという方は、地域別のハザードマップを確認しましょう。ハザードマップには、大雨による洪水や津波が起きた際に危険とされる地域や避難所が記載されています。
万が一の事態が起こったときにどこに逃げればいいのか、住んでいる場所は水害の危険があるのかを事前に把握できるでしょう。
住宅ローンの残債が多い
現時点で住宅ローンの残債が多い方にも地震保険への加入がおすすめです。
被災後も返済を続けていかなければなりませんが、損害が生じた状態で返済するのは困難でしょう。
地震保険に加入しておけば、損害の程度に応じてある程度の額が補償されます。保険金を元に返済しつつ、生活を立て直すことも可能ですから、加入を検討してみてください。
地震によって収入がゼロになる恐れがある
地震によって収入がゼロになる恐れがある方は、万が一の事態に備えて保険に加入しておきましょう。地域で農業を営んでいる、または会社に勤めている方は、地震によって仕事を失う可能性があります。会社が地震によって被害を受け、経営できない状態に陥れば、収入はゼロになってしまうでしょう。
収入がゼロになれば、住宅ローンの返済はもちろん、日々の生活費ですら工面できなくなります。生活が困窮する可能性があるので、被災後のリスクを抑えるためにも、地震保険への加入を検討しましょう。
地震保険に加入する必要のない人の特徴
地震保険への加入を検討しているけれど、自分に必要なのかがわからないとお困りの方も多いでしょう。ここでは、保険に加入する必要のない人の特徴を紹介します。
免震・耐震などの施工を実施している
新耐震基準で建築していることに加え、免震や耐震などの施工を実施している場合は無理に保険に加入する必要はありません。地震対策につながる構造には3つの種類があります。
・制震:住宅内に設置された制震装置が揺れを吸収する
・耐震:建物の構造を補強することで揺れに耐える
・免震:建物と地盤を切り離すことで揺れにくくする
いずれも地震への対策として有効ですが、なかでも免震は地震による揺れが少なく、建物内部への損傷をできるだけ抑えられるなどのメリットがあります。これらの対策を実施して建てた家は地震に強いといえるため、被災する可能性も低くなるでしょう。
預貯金が十分にあり、住宅ローンの残債も残りわずか
現時点での住宅ローンの残債を大幅に上回る預貯金がある場合も、地震保険に加入する必要はありません。万が一災害によって家が倒壊したとしても、被災後の生活費は預貯金で賄えます。住宅ローンの残債もまとめて支払えるため、ローンの返済に苦しむことはないでしょう。
ただし、預貯金がさほどなく、地震による損害を被る可能性がある方は保険への加入を検討しましょう。被災した際に家が倒壊すると、預貯金はその後の生活費に充てなければなりません。返済に回すお金を用意できなくなるので、保険で賄うことがおすすめです。
地震が起きるリスクが少ない
地震が起きるリスクが少ない地域に住んでいる方も、保険は不要でしょう。保険は地震への備えとして用意するものなので、リスクが少ない地域であれば使う可能性は極めて低いといえます。そのため、高額の保険料を支払って無理に加入する必要はありません。
ただし、今後起こることが予測される南海トラフの被害地域に住む方は保険への加入を検討しましょう。南海トラフは関東から九州まで、太平洋側の地域に被害が発生する可能性があります。場所によっては震度7の地震が起こると予測されているので、万が一の備えとして、保険を検討することも重要です。
地震保険が必要・不要な人の特徴から加入を検討しよう
戸建てに住む際、地震保険はいらないといわれた経験がある方も多いでしょう。万が一の事態に備えられる保険ではあるものの、地震リスクが少ない地域や免震構造の家に住んでいる方は、無理に加入する必要はありません。
しかし、日頃から地震が頻繁に起こる地域に住んでいる、または被災後に生活が困窮する恐れがある方は保険を検討することがおすすめです。いつ起こるかわからない地震への備えを万全にすることで、災害によるリスクを最小限に抑えられるでしょう。