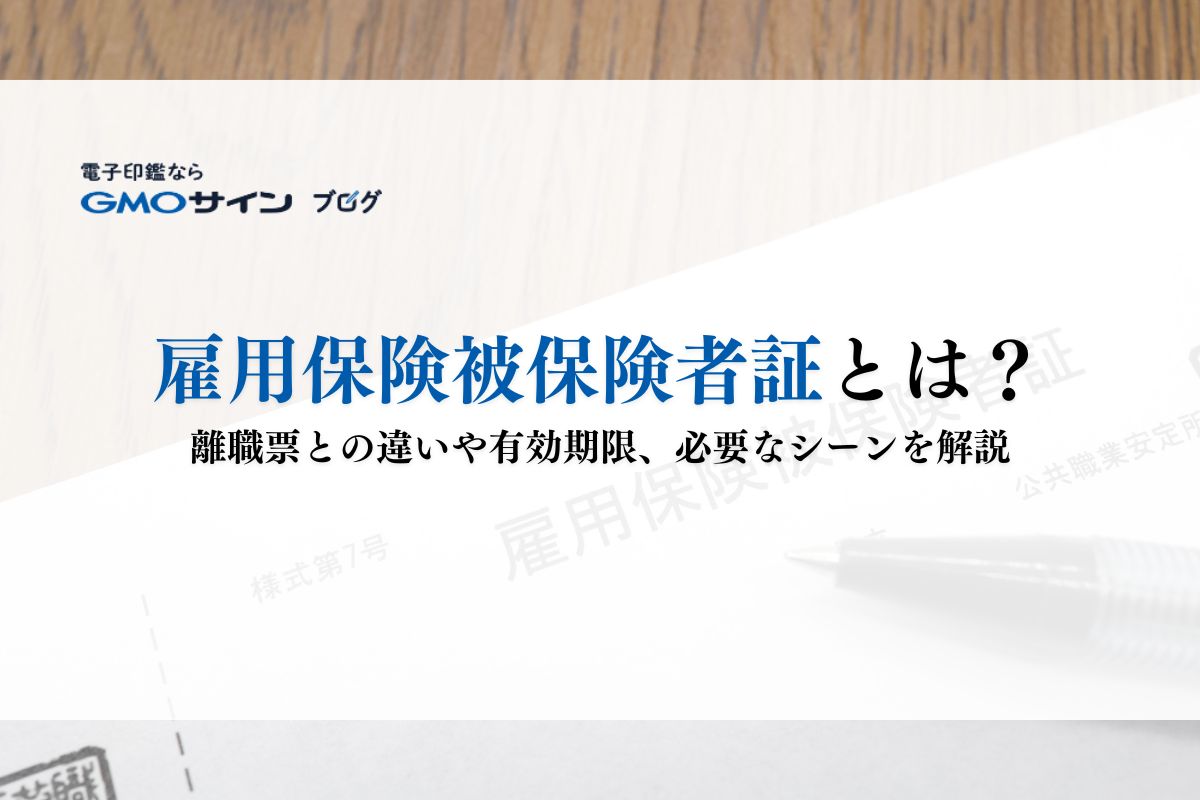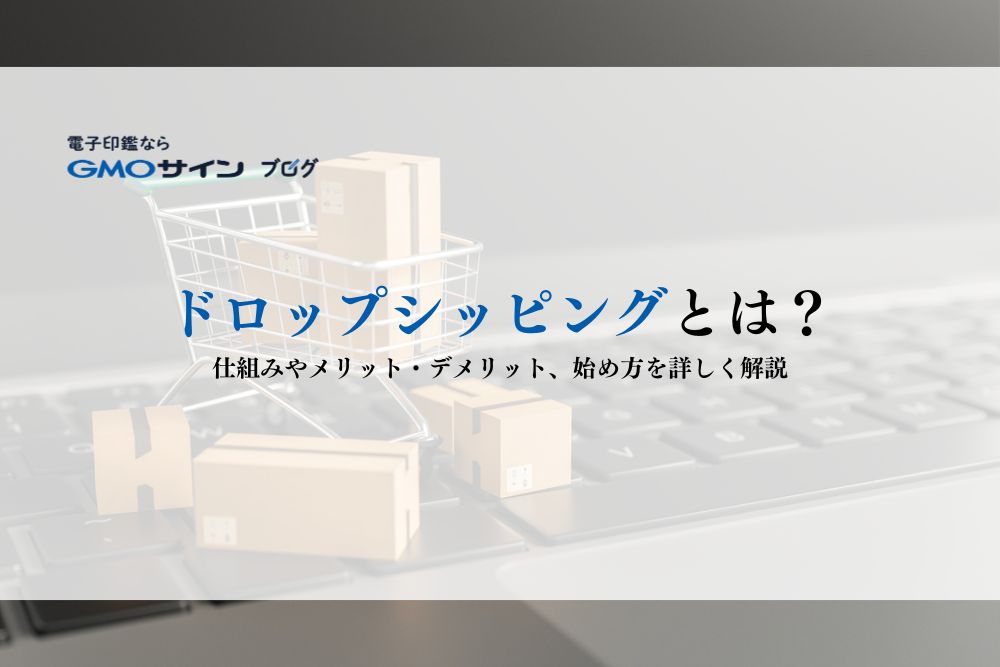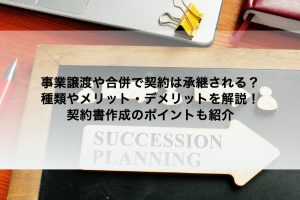法定労働時間とは法律で決められている労働時間の上限で、1日あたりの時間と1週間あたりの時間が決められています。この法定労働時間を超えて労働させる場合には、割増賃金を支払うことが必要です。
似た言葉に所定労働時間というものがありますが、それぞれ意味するものは異なります。ここでは、両者の違いや36協定、残業代の計算方法について解説します。
法定労働時間の基本を理解しよう
法定労働時間とは、労働基準法によって規定されている、労働時間の上限を指します。基本的に1日8時間・週40時間が上限と定められています。
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
法定労働時間は労働者保護の観点から制定されています。長時間労働などの過酷な労働を強いられることで、労働者の心身の健康が損なわれるのを防ぐのが一つの目的です。
所定労働時間との違い
法定労働時間以外にも、労働時間に関する言葉として、所定労働時間というものがあります。
所定労働時間とは
法定労働時間が労働基準法を根拠としているのに対し、所定労働時間とは会社自身で定める勤務時間のことです。所定労働時間は、基本的に法定労働時間の定める上限のもとで定めなければなりません。
月平均所定労働時間とは
残業代を計算するにあたっては所定労働時間をベースにしますが、該当する月の実日数を合計したものを用いるのは一般的ではないため、月平均所定労働時間を用いて計算することになります。具体的には、月平均所定労働時間は以下のように計算します
(1年365日 – 年間の休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月
月平均所定労働時間が残業代の計算に使われるのは、月によって1カ月の日数が異なるからです。もし実日数を用いると1時間あたりの基礎賃金が変わってしまい、実態を適切に反映した残業代を計算することができなくなってしまいます。そこで、月ごとのずれをならすために月平均所定労働時間が用いられるわけです。
休日や休憩時間のルール
労働基準法には、休日や休憩時間に関するルールが制定されています。これも過重な労働環境で労働者の健康を損ねないようにするためのものです。
休日に関する規定
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
このように、労働基準法では週1日以上もしくは4週間で4日以上の休日を与える決まりになっています。これは法定休日と呼ばれます。
実際のところ、週休2日制を導入している企業は多いと思います。この週休2日制の場合、週休1日は法定休日、残りの1日は法定外休日という取り扱いになります。もし休日出勤を求める場合、両者で扱いが変わってきます。
まず休日に労働者を働かせるためには、労使間で36協定を結ぶ必要があります。そして法定休日に労働者に働いてもらうためには、36協定で休日労働に関する取り決めの中に盛り込んでおくことが前提です。この部分は労働基準法でも規定されていて、休日労働を求める際には、通常よりも35%以上の割増賃金が発生することになります。
一方、法定外休日に働く場合、これは休日労働には該当せず、時間外労働の扱いになります。ただし、時間外労働を求める際にも、前もって36協定を交わしておく必要があります。ちなみに法定外休日労働を求めた結果、週40時間の法定労働時間を超えた場合には割増賃金として通常の25%以上の割増賃金を支払わないといけません。
休憩に関する規定
(労働時間)
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
休憩に関する規定も労働基準法で定められています。上で紹介したように、労働時間が6時間を超える場合で45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を付与することが必要です。
また、休憩時間はすべての労働者に一斉に与える必要がありますが、労使間で合意すればばらばらに休憩時間を与えることも可能となります。
36協定とは
(休憩)
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
法定労働時間を超えて労働者に働いてもらうためには、上で紹介したような協定を労使間で締結しなければなりません。労働基準法第36条で規定されていることなので、36協定といわれています。
36協定とは、かんたんに言えば時間外労働に関する取り決めをした労使協定のことです。36協定を締結する場合、労働者側は次のいずれかが主体となって行うことになります。一つは労働者の過半数で組織された労働組合、もう一つは労働者の過半数を代表する者です。後者は、前者の労働組合が存在していない場合に認められます。
36協定を締結することで、過剰な長時間労働を防止しながら、法定労働時間を超えて働いてもらうということが可能となります。
36協定の時間外労働の規定
労使双方が納得したとしても、時間外労働が青天井で自由に認められるわけではありません。労働者の健康管理の観点から、法律上時間外労働の上限が決められており、1カ月につき45時間・1年間で360時間が上限となります。
ただ、事業所で当初想定していなかった業務量の大幅な増加で、一時的に労働時間を増やさないといけない事態も出てくるでしょう。そのような場合は、先ほどの上限を超えて、臨時的に上限の幅を増やすことが可能です。しかし臨時的でも時間外労働の上限は設けられていて、それを順守する必要があります。
臨時的なケースにおける時間外労働の上限は少し複雑です。条文に基づくと以下のようになります。
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
② 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
まず基本となるのは年間720時間以内です。そのほかにも、休日労働との兼ね合いの条件があります。両者の合計が月間100時間を切らなければならず、さらに数カ月に及ぶ場合は2〜6カ月の1カ月あたりの平均時間が80時間以内でなければなりません。そして、時間外労働が月に45時間を超えるのを1年あたり6カ月以内に抑える必要があります。
残業代の計算方法
時間外労働をした労働者に対しては、その時間外労働に合わせた残業代を支給しなければなりません。残業代は所定労働時間と法定労働時間の関係を踏まえて計算することになります。このことは労働基準法で定められており、規定に沿って計算する必要があるので注意しましょう。
法定労働時間内の場合
残業代は所定労働時間を超えた労働をした場合にはじめて発生します。会社によっては所定労働時間と法定労働時間が異なることもあるでしょう。
この場合、所定労働時間は超えているけれども、法定労働時間は超えていないといったケースが起こりえます。このようなケースは法定内残業といわれます。
法定内残業は会社からみれば残業ですが、労働基準法上の時間外労働には相当しません。このため、通常の賃金をベースに残業代を支払うことになります。
法定労働時間を超える場合
法定労働時間を超えて残業をした場合、これは法定外残業もしくは時間外労働に相当します。時間外労働をした労働者に対しては、割増賃金として残業代を計算し支払わないといけません。
割増賃金は以下で紹介するように労働基準法で定められているので、その規定に従って計算する必要があります。
⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
かんたんに言えば、60時間以内であれば25%以上の割増率になり、60時間を超える部分については50%以上の割増率となります。なお、2023年4月以降、中小企業の月60時間超の部分も25%以上ではなく50%以上の割増率になりました。
法定労働時間の例外
法定労働時間は原則として1日8時間・週40時間です。しかしすべてのケースがこれに当てはまるわけではありません。労働基準法では、いくつか例外規定が設けられています。
特例措置対象事業場の場合
特例措置対象事業場に該当する場合、1日8時間・週44時間が法定労働時間になります。特例措置対象事業場は、商業や映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業が該当し、なおかつ常時使用している労働者が10人未満であることが条件となります。
変形労働時間制を導入している場合
最近では変形労働時間制を導入している企業も少なくありません。変形労働時間制による場合、特定の1週間における平均労働時間が法定労働時間を超えているかどうかで判断されるのが特徴です。
単位は1カ月と1年間のいずれかです。週や月によって労働時間の変動があっても、平均労働時間が法定労働時間を超えていなければ問題ないという考え方です。
フレックスタイム制を導入している場合
フレックスタイム制とは、基本的にいつでも仕事をはじめ、終えても構わないという働き方です。会社によっては、コアタイムといって絶対に勤務しないといけない時間帯を設けているところも多いです。しかしこのコアタイムは必ず設定しないといけないものではありません。
フレックスタイム制の場合、一定期間の総労働時間の範囲内であれば法定労働時間内であると判断されます。総労働時間は、労使協定によって決められます。総労働時間のカウント対象の期間も労使協定で決めますが、いくらでもよいというわけではなく、3カ月以内の期間で決めなければなりません。この期間を清算期間といいます。
繁閑の差が激しい場合
繁閑の差の激しい業種、具体的には小売業や旅館、料理店、飲食店で常時働いている労働者数が30人未満の場合、1日10時間を法定労働時間の上限とすることも可能です。ただし、労使協定を締結していることが前提となります。
裁量労働制を導入している場合
裁量労働制を導入している場合、法定労働時間の規定に関し例外的な取り扱いが行われます。裁量労働制は、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の二つに大きく分かれます。具体的な扱いとして、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」という効果が発生することになります。
(時間外及び休日の労働)
(引用:労働基準法|e-Gov法令検索)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
農林業・畜産業・養蚕業・水産業の場合
以上の事業に携わる人たちは、いわゆるサラリーマンとは異なる労働スタイルを取ります。このため、統一した労働時間でマネジメントするのは難しく、法定労働時間の適用は受けないこととされています。
まとめ
労働者の労務管理を行う場合、ここで紹介した法定労働時間や所定労働時間に関する知識を正しく把握しておかないといけません。というのも、法定労働時間を超えて不適切に従業員に労働を強いることにつながりかねないからです。
もし法定労働時間を超えた勤務をお願いする必要が出てくる場合は、労働者側の承諾を得る必要があります。具体的には、ここで紹介した36協定の締結、および労働基準監督署への届け出です。このようなルールを把握したうえで、適切な労務管理に努めるようにしましょう。
なお、企業と労働者で契約を締結する際には、電子契約を利用することがおすすめです。電子契約は紙の契約書にかかっていたインク代や印紙代などの費用を削減できます。文書の封入や投函も必要ないので、業務効率化につながることがメリットです。
月に5件まで文書の送信ができるフリープランも用意しているので、これから電子契約を利用する方は試しに導入してみてください。