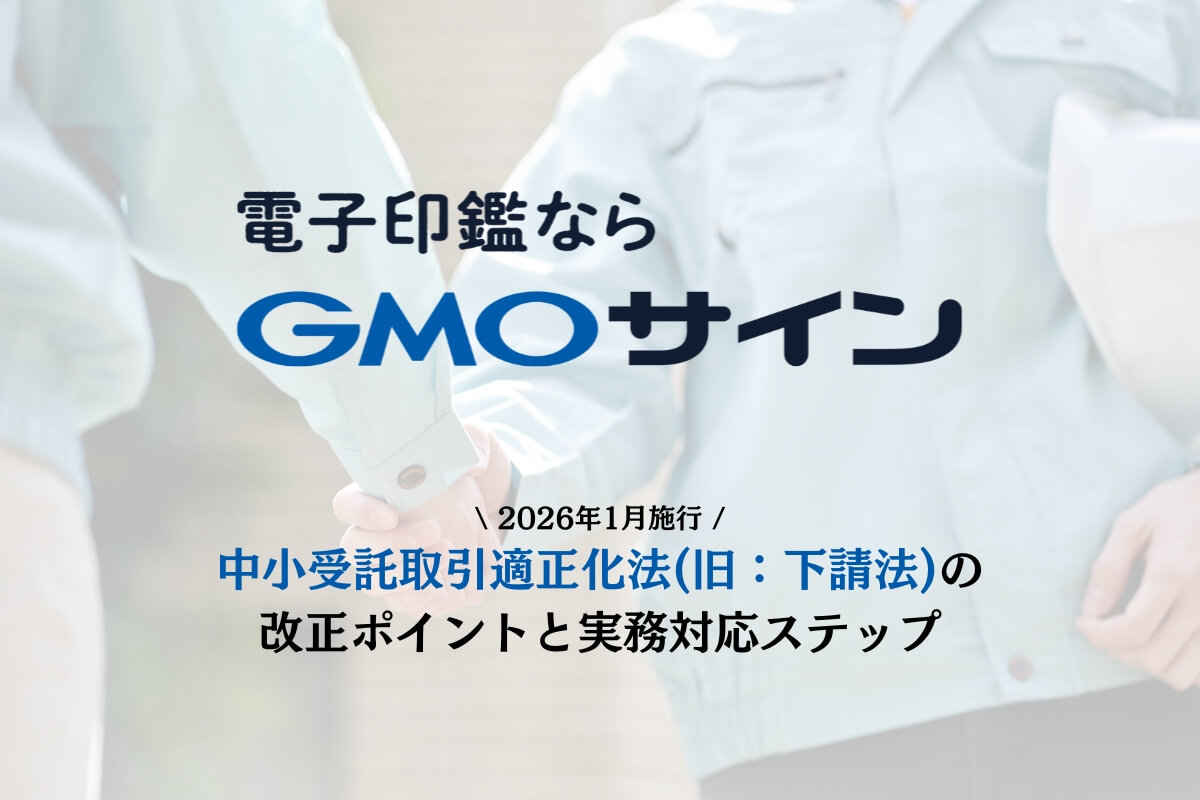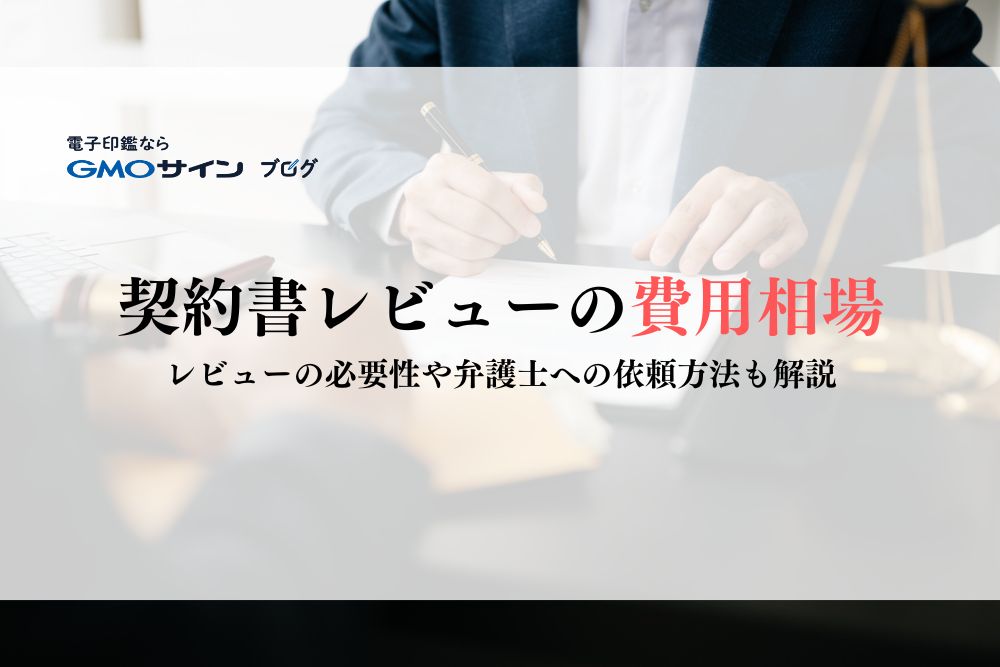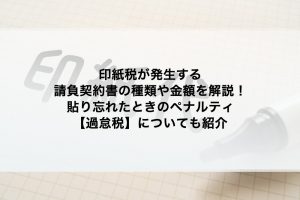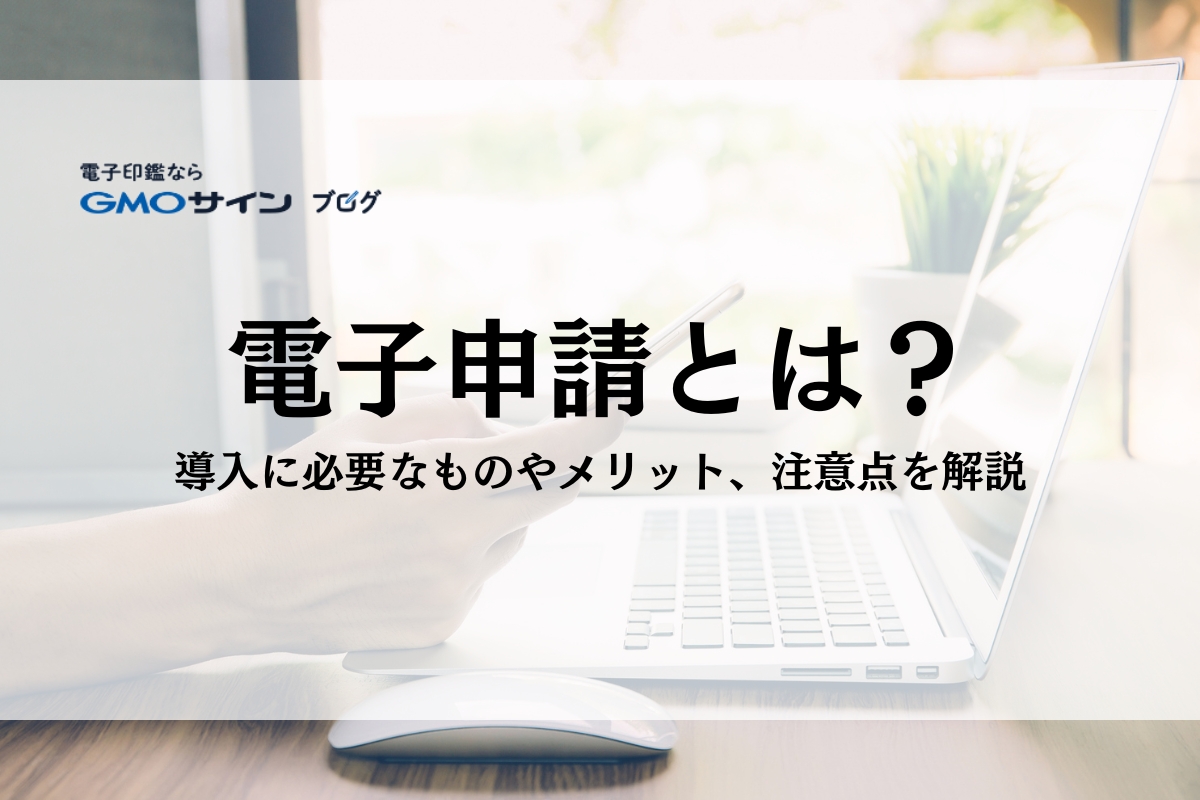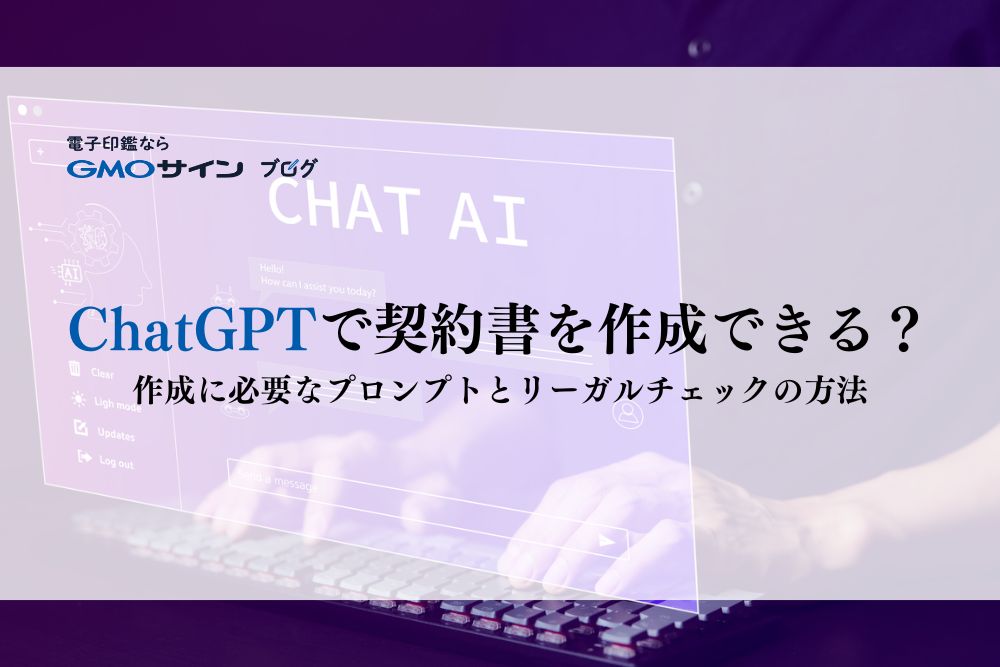大半の企業では就業規則を定めているのが一般的です。
就業規則があることで、その職場の労働条件やルールなどが明確になり、トラブルの防止などにも役に立ちます。
ただ、現時点で就業規則を作成していない職場もあるでしょう。今後、就業規則を作成しようと検討している経営者の方もいるかもしれません。
その際に気になるのが、就業規則の記載事項や作成手続きの手順です。就業規則の内容に不備があると、逆にトラブルの原因になる可能性もあるため、不備がないように作成しましょう。
本記事では就業規則に関して、記載事項や作成手続きなどを中心に全般的な解説をしていきます。
就業規則の基本
就業規則の他にも、労働契約や労働協約で労働条件や待遇などに関して規定されることがあるでしょう。労働基準法などの法令にも、労働条件に関する規定が設定されていますから、就業規則との関係をよく理解しておくことが重要です。
では、就業規則の役割や他の規律との関係について、基本的なポイントを見ていきましょう。
就業規則の役割
就業規則は、労働者が仕事をする際に守るべきルールや待遇などについて規定した文書です。
労働時間や休日、給与、退職などに関することも就業規則に明文化されています。就業規則に規定されている内容は、基本的にその事業所の労働者全員に適用されますが、パートタイム労働者などにのみ適用される規定を設けることも可能です。
しかし、その場合にはルールの内容があいまいになりがちです。就業規則は労働者の権利や義務を明確にする役割を果たしています。
就業規則と労働契約労働協約、法令との関係
労働者はその職場で雇用される際に、事業主と労働契約を締結しています。職場によっては、労働組合との間で労働協約が締結されているケースもあります。労働基準法などの法律にも労働条件に関する規定があり、それぞれの規定で矛盾する内容もあるかもしれません。
就業規則と労働契約の違いは適用範囲です。
就業規則は、事業所内の労働者全員に一律に適用されますが、労働契約は各労働者に対して個別に適用されます。
そして、労働条件に関して、労働契約の内容が就業規則の内容に達しない場合にはその部分が無効になる仕組みです。無効になった部分は就業規則の内容が適用されます。このことが労働契約法11条と12条に規定されています。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。引用元:労働契約法|e-Gov 法令検索
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
また、達しないというのは内容が異なるという意味ではなく、労働者にとって不利な条件という意味です。労働契約で就業規則よりも労働者にとって有利な条件を定めている場合には、労働契約の規定が適用されます。
これに対して、労働協約と法令に関しては扱いが異なる点に注意が必要です。
就業規則の内容が労働協約または法令に反する部分は適用されません。さらに、労働協約と法令に反してはならないことが労働基準法92条に規定されています。また、反するというのは、内容が有利か不利かを問わず内容が矛盾するという意味です。
(法令及び労働協約との関係)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
労働基準法92条の規定により、就業規則の内容が法令と労働協約に反する場合には、行政官庁から変更を命じられる可能性もあります。
就業規則の作成は義務?
就業規則の作成は、すべての事業所に作成が義務づけられているわけではありません。
また、就業規則の作成が義務づけられているにもかかわらず、作成していない場合には罰則も設けられているため注意が必要です。
では、就業規則の作成義務がある事業者の基準や罰則の内容について見ていきましょう。
就業規則の作成が義務づけられている事業所の規模
就業規則の作成が義務づけられているかどうかは、常時使用する労働者の人数で基準が設けられているため、そこで決まります。具体的には常時10人以上の労働者を使用する事業所です。
常時と規定されているため、一部の労働者が退職して一時的に9人以下になっても、対象から外れるわけではありません。また、一時的に10人以上になる場合も同様です。
たとえば、繁忙期に臨時のアルバイトを雇ってそのときだけ10人になっても、普段は9人以下なら常時10人以上には該当しません。
あくまで常態としての人数で判断されます。
労働者の人数に含めるのは直接雇用している労働者すべてです。正社員だけでなく契約社員やパート、アルバイトなども含みます。
派遣元では労働者にカウントされます。
また、経営者は労働者ではないため人数に含めません。
このあたりの細かなルールは、きちんと理解しておく必要があります。
労働者への周知が必要
具体的には作業場の見やすい場所に掲示しておく方法と備え付けておく方法、書面で交付する方法などで周知しましょう。労働基準法106条に就業規則の周知に関する規定が置かれています。
(法令等の周知義務)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
② 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
作成しただけで周知していない場合には効力が発生しないため、注意が必要です。
また、作成直後だけでなくいつても、いつでも労働者が内容を確認できる状態にしておく必要があります。
労働基準監督署長への届出も必要
就業規則を作成し、周知も行ったら、労働基準監督署長への届出も済ませておかなければなりません。このことが労働基準法89条には、就業規則の作成に関することとして規定されていますが、「行政官庁に届け出なければならない」という文言が含まれています。
この場合の行政官庁というのが労働基準監督署です。
(作成及び届出の義務)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
また、届出の期限については明確には規定されていませんが、早めに済ませておくことが望ましいでしょう。
罰則もあり
就業規則の作成義務に関しては、労働基準法120条に罰則が設けられているため注意しましょう。複数の違反行為に関してまとめて規定されていますが、就業規則の作成義務に関わる箇所が含まれています。
罰則の内容は30万円以下の罰金です。
就業規則の作成義務があるにもかかわらず、作成しなかった場合や届出をしなかった場合に適用される可能性があります。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
就業規則は事業場単位
就業規則の作成義務は会社単位ではなく事業場単位で判断されます。
ただ、規模が小さく事業所としての独立性がない場合には、本社や他の拠点の一部として扱われることもあります。
作成義務がない事業所ではどうするべきか
もし今後10人以上になった場合には、その時点から作成すれば済みます。
しかし、現時点で就業規則の作成義務がなくても、余裕があれば作成しておく方が望ましいです。トラブルの防止につながり、求職者からの印象も良くなる効果も期待できるでしょう。
就業規則の記載事項
就業規則に記載する内容は、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項の3種類に分かれます。では、それぞれどのような内容を指すのか見ていきましょう。
絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項というのは、就業規則を作成する際に必ず記載しなければならない内容です。労働基準法89条には、就業規則の作成と届出を義務づける規定と併せて、規定が必要な事項について列挙されています。この列挙されている事項が絶対的必要記載事項です。
(作成及び届出の義務)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
主に労働時間に関することと、賃金に関すること、退職に関することが絶対的必要記載事項として扱われています。労働条件にもさまざまものがありますが、労働時間と賃金はとりわけ重要度が高いです。退職に関することは、労働者としての地位の安定に関わります。労働者が安心して働くためには、必ず確認が必要です。そのため、就業規則への記載が義務づけられています。
具体的には次の事項を記載しなければなりません。
- 始業と終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 交代制の場合の就業転換に関する事項
休暇というのは通常の休日とは別に設ける休みのことです。年次有給休暇や育児・介護休業など法律上の制度を含みます。独自の休暇制度を設ける場合にも記載しておきましょう。
- 賃金の決定方法
- 賃金の昇給方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払い方法
- 賃金の締め切り時期
- 賃金の支払い時期
- 昇給に関する事項
賃金の決定方法というのは、もともと第三十条の基本給の項にも記載されていた学歴や勤続年数、年齢、職階、出来高制が該当し、それに準じています。ちなみに、第三十条は現在、働き方の多様性などを尊重するために削除された項目です。賃金の計算方法というのは、時給制や日給制、日給月給制、月給制などに関して記載します。
- 退職の手続き
- 退職の事由
- 解雇の事由
定年を設ける場合には、退職の事由に関して記載しておきましょう。
解雇の事由に関しては、懲戒解雇と普通解雇についての基準などを明記しておきます。
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項というのは、特定の項目に関して制度として導入している場合に記載しなければならない内容です。労働基準法八十九条に該当し、具体的には次の項目が該当します。
- 退職手当関係
- 臨時の賃金
- 費用負担関係
- 安全衛生関係
- 職業訓練関係
- 災害補償、業務外疾病扶助関係
- 表彰または制裁関係
- 上記または絶対的必要記載事項以外で事業場の労働者すべてに適用されるルール
(作成及び届出の義務)
引用元:労働基準法|e-Gov 法令検索
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
臨時の賃金というのは、いわゆるボーナスのことです。支給時期や計算方法などを記載します。
費用負担関係というのは、食費や作業用品などにかかる費用を労働者に負担させる場合のことです。
すべて事業主が負担し労働者の負担がない場合には、記載する必要はありません。
また、減給や停職、戒告などの懲戒処分の制度を導入する場合には、表彰または制裁関係として記載します。
相対的必要記載事項として挙げられていることに関して、制度として導入するかどうかは各企業の任意です。制度として導入していない場合には、就業規則への記載も必要ありません。
任意的記載事項
任意的記載事項は、その名の通り、記載が法律上義務づけられていません。各事業所で就業規則に記載しておきたい場合に記載できる項目です。
たとえば、企業理念や服務規程、個人情報保護に関する事項などを任意的記載事項として記載できます。
就業規則の作成手順
就業規則を作成する際にどのような手順で行うのか見ていきましょう。
現状の確認
自社で現在どのような労働条件のもとで業務が行われているのか、労務管理の方法はどうなのか確認してみましょう。
相対的必要記載事項に該当する事項に関しても、自社で実施しているのかどうかの洗い出しが必要です。
原案の作成
原案はできるだけわかりやすい表現で作成するのが望ましいです。また、法令との整合性も加味しなければなりません。現状の労働条件を労働基準法などの法令と照らしあわせて、適合しない部分がないかどうかを確認しましょう。問題なく適合している部分に関しては、現状の実態通りに記載します。もし、法令に適合しない部分があれば、適合する内容に修正して記載しましょう。
ただ、就業規則の原案を一から作成するのは非常に手間がかかります。そのため、厚生労働省の公式ホームページで公開されているモデル就業規則を活用するのがいいでしょう。自社にあわせてカスタマイズすれば、就業規則作成の手間を大幅に削減できます。
また、社会保険労務士や弁護士などの専門家に就業規則の作成を依頼するのも一法です。ただし、費用がかかる点に留意しておきましょう。
過半数代表者への意見聴取
就業規則を作成する際には、労働者の過半数で組織されている労働組合から意見を聴取しなければなりません。事業所に労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者から意見聴取をする必要があります。
意見聴取の際には単に意見を聞くだけでは足りません。就業規則へ記載するかどうかを検討したり議論したりする必要があります。その上で、原案に調整を加えましょう。
できる限り労働者の意見に耳を傾け、就業規則の内容に取り入れていく姿勢が望ましいです。
そして、労働者の意見は意見書として、過半数代表者から書面でまとめてもらい残しておきます。
労働基準監督署長への届出
就業規則を作成して、周知も行ったら、労働基準監督署長へ提出します。
紙媒体で作成して提出する場合には、提出用の他に控えも用意しておきましょう。
窓口に持参して提出する場合には、その場で控えにも受付印を押印してもらえます。郵送の場合には、控えと切手を貼付した返信用封筒を同封しましょう。そうすると、控えに受付印を押印したものを返信してもらえます。
控えは就業規則の届出を行ったことを証明する手段になるため重要です。
支店や営業所など複数の事業所がある場合には、事業所ごとに届出をする必要があります。ただし、就業規則の内容が同じであれば、本社一括で届出をすることも可能です。
また、就業規則の届出は電子申請で行うこともできます。
電子申請の場合には、封筒代や切手代などのコストがかからず、手間もかかりません。
就業規則の変更手順
すでに作成し届出済みの就業規則を変更する必要がある場合の手順について見ていきましょう。
どのようなときに変更が必要なのか
就業規則の変更が必要になるのは、主に労働関係の法律が改正されたときです。
これまで問題なかった内容でも、法改正により法律に適合しなくなる部分が出てくる場合があります。
そのようなときに、法律改正後の内容に適合するように就業規則も変更しなければなりません。
また法律の改正とは別に、企業内部の事情や社会情勢の変化などにより就業規則を変更することも可能です。
基本的には作成と同じ手順
就業規則の変更手続きは、基本的には新規で作成するときと大きく変わることはありません。変更が必要な部分に関してのみ新しい内容を考えます。既存の記載を変更する他に、新たな項目を追加したり、逆に削除したりすることも可能です。
就業規則変更の際にも作成の場合と同様に、過半数代表者への意見聴取を行わなければなりません。その上で意見書を作成し届出のときに添付する点も同様です。
また、届出の際には変更後の新しい就業規則と併せて、就業規則変更届も提出する必要があります。
就業規則変更届というのは、変更する箇所と変更前後の内容を記載するための書類です。
新しい就業規則には、変更のない箇所も含めて、最初から最後まですべて記載します。
就業規則を作成する際に、社会保険労務士や弁護士に依頼した場合には、変更の際にも同じところに依頼するのが無難です。
不利益変更の扱い
就業規則の変更内容が労働者にとって不利益な内容の場合には、過半数代表者の合意なしで変更することは基本的にはできません。
たとえば、賃金を引き下げたり労働時間を長くしたりすることなどが不利益変更に該当します。
経営状況が悪化して、これまで通りの条件が続けられない場合などには合理的な理由として扱われます。
不利益変更に合理的な理由があっても、労働者側が強く反対していると、意見書の作成を拒まれることもあるかもしれません。そのような場合には、意見書の代わりに報告書を提出することで対応可能です。報告書には、意見聴取を実施した旨や合意が得られていない経緯、合理性があることなどについて記載します。
就業規則に関するよくある質問と回答
就業規則に関して、よくある質問とその回答を見ていきましょう。
- 就業規則はどこで閲覧できますか?
-
職場にもよりますが、入社時に就業規則を小冊子などの書面で交付しているところが多いです。職場内の設置されているところもあれば、オンラインで閲覧できるようにしているところもあります。
- 就業規則を渡さない会社は違法ですか?
-
事業主は就業規則を周知する義務がありますが、必ずしも書面を渡す方法による必要はありません。いつでもかんたんに確認できる状態にされていれば、周知しているものとして扱われます。
たとえば、職場内のわかりやすい場所に備え付けておく方法やデータでいつでも確認できるようにしておく方法なども可能です。
- 従業員が10人未満の会社は就業規則は必要ですか?
-
就業規則の作成義務は、常時使用する労働者の人数を基準に事業所単位で判断されます。
常時使用する労働者が10人未満の事業所なら法律上は、就業規則を作成する必要はありません。しかし、トラブル防止などの観点から、できれば作成しておくのが望ましいです。
まとめ:就業規則を正しく作成して届出を済ませておこう
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業所に作成と届出の義務があります。労働者にとっては職場のルールや労働条件に関わる重要なものです。届出をしない場合には罰則も設けられているため、作成と届出の義務がある場合には、必ず済ませておきましょう。
就業規則の作成義務がない事業所でも、できるだけ作成しておくのが望ましいです。
そして、就業規則を作成して届出をした後は、記載内容の通りにきちんと運用していくことが大切です。