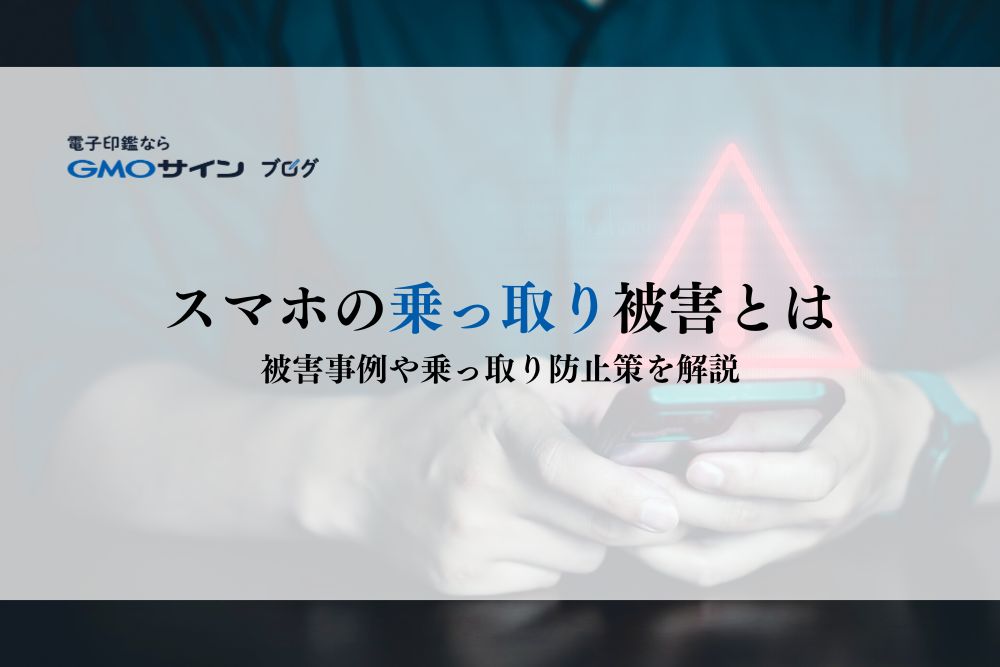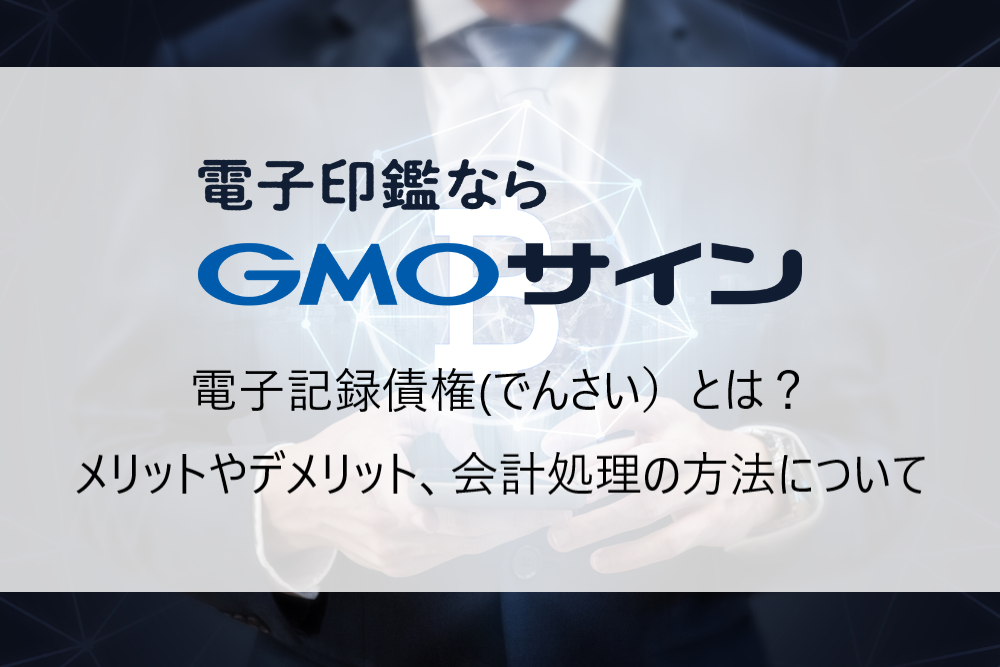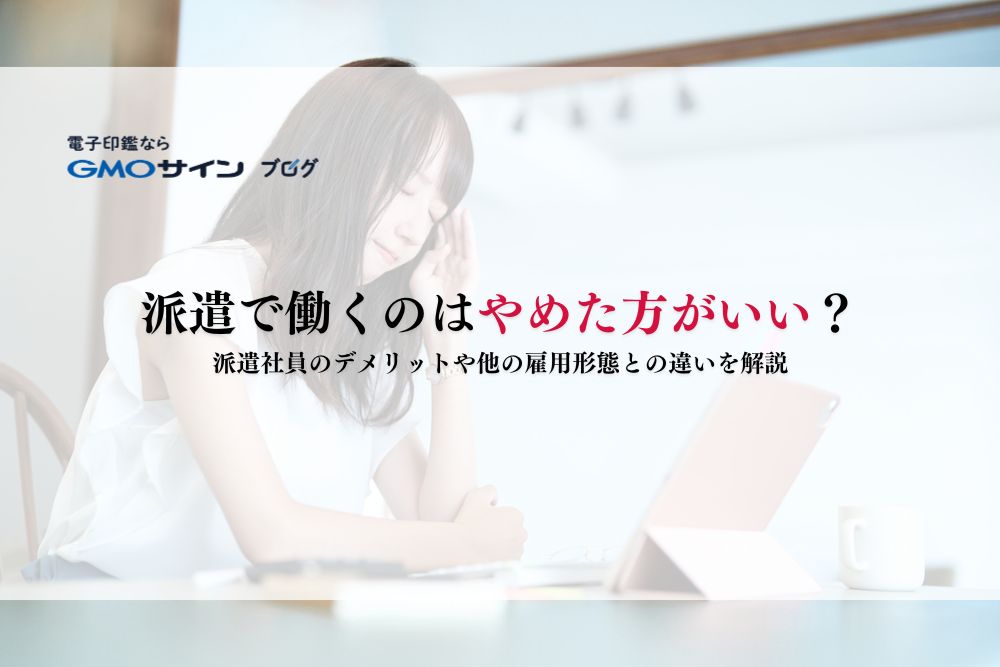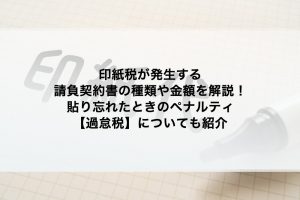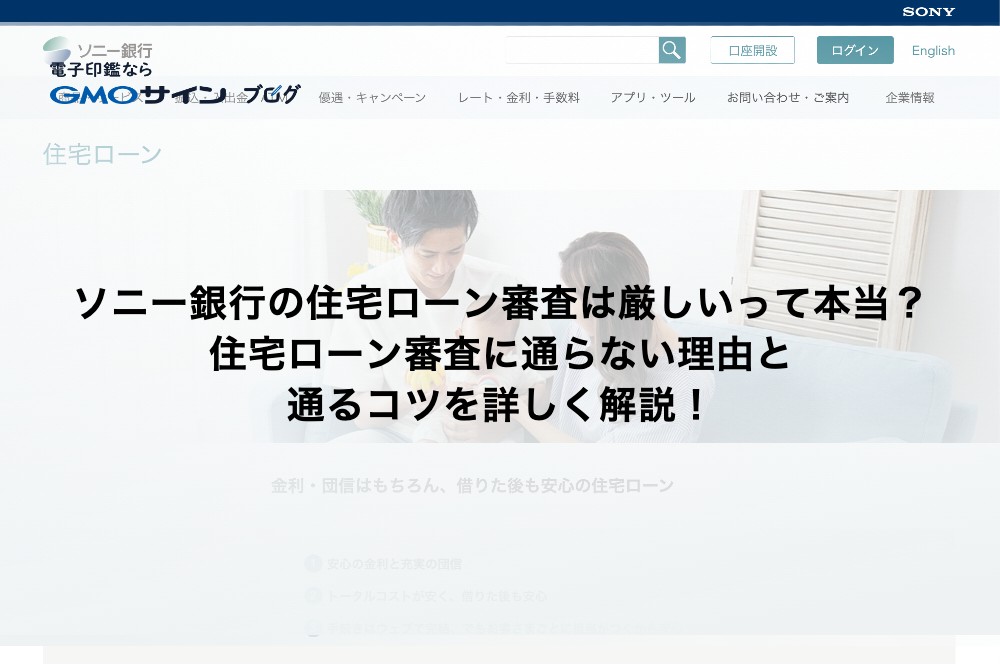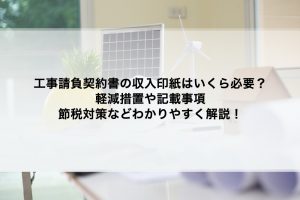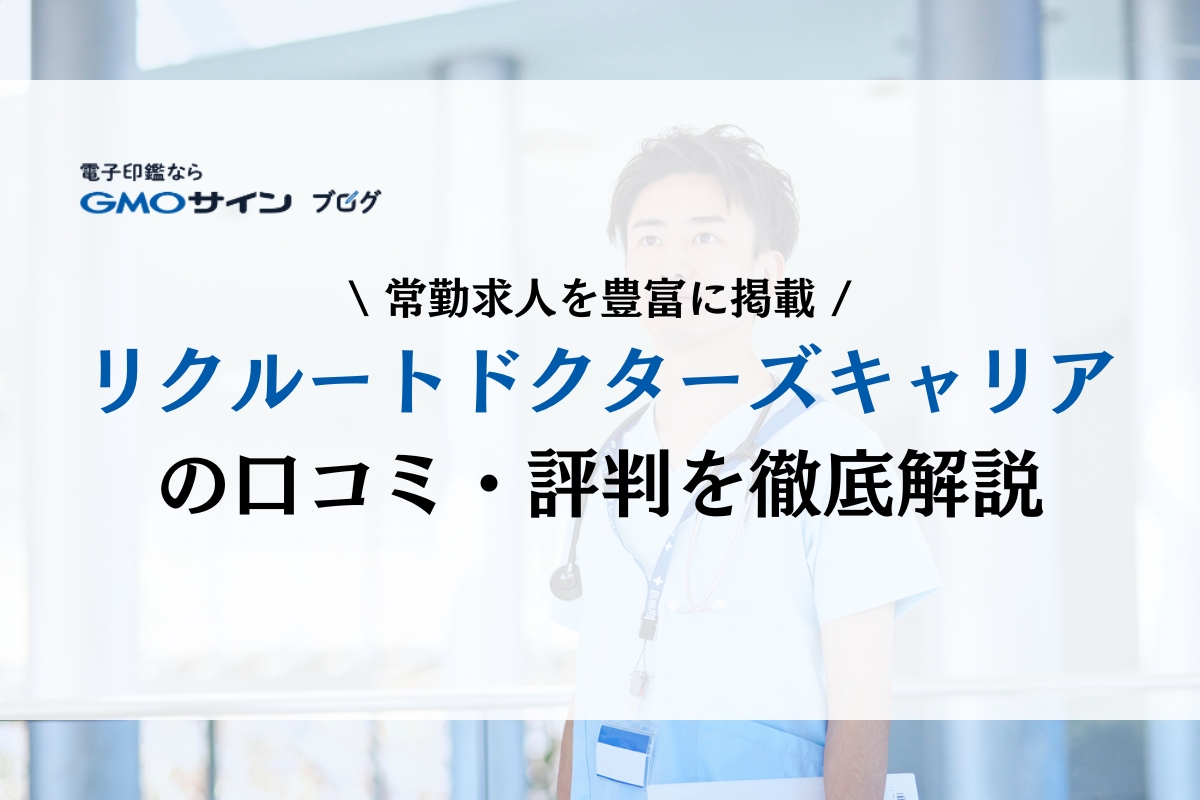カルテルは、消費者の利益や商品の価値を損なう不当な企業連合のことです。国内では独占禁止法によって禁止されていますが、その問題点や種類などについて理解しきれていない方もいるでしょう。この記事では、カルテルについて以下の内容を解説していきます。
- カルテルの意味
- カルテルが禁止されている理由
- カルテルと談合の違い
- カルテルの種類
- カルテルを行った場合のペナルティ
- カルテルに関するよくある質問
カルテルの定義やリスクなどを正確に把握したい方は、ぜひ参考にしてください。
カルテルとは
カルテルとは企業連合を指す言葉で、複数の事業者が集まり、価格や販売地域、そして生産計画などの協定を結ぶことを示しています。こうした協定を結ぶ理由は、事業者同士が互いに競争し合うのを避けるためです。
事業者間の利益を不当に守るために結ばれるカルテルは、サービスを購入する消費者の利益や商品自体の価値を損なうものとして、独占禁止法によって禁止されています。
カルテルが禁止されている理由
カルテルが行われる目的は、本来競合するはずの事業者同士が競合を避け、不当な利益を得ることです。互いに競争を避けてサービスや商品の価格を高い水準で維持しようとしているわけです。
正しい市場のあり方は、各事業者が互いに競争しあい、企業努力によってサービスや商品の質を向上させ、それを適正な価格で提供するものです。消費者は安くて質の良いサービスや商品に惹かれる傾向があります。その要望を実現できない企業は自然と淘汰されていく仕組みが作られているわけです。
このような決定が成されてしまうと、事業者は互いに競争をする必要がなくなるため、サービスや商品の質の低下を招いたり、サービスや商品が適正価格以上で提供されたりする結果となります。消費者が損をして、事業者がもうかる仕組みが構築されてしまうわけです。
たとえば、A社とB社、C社というテレビを扱う企業があるとします。テレビの適正価格が10万円だった場合、正しい市場のあり方に則った競争が行われていたら、この3社は自社のテレビの性能を向上させる努力が必要となるでしょう。また、少しでも売れるように価格を下げるなどの企業努力も必要となります。競争が行われることで私たち消費者は、手頃な価格で良い性能のテレビを購入することができるわけです。
しかし、この3者が互いにカルテルを行った場合、3社のテレビの価格が20万円から動かず、消費社はどの企業のテレビを購入しても同じ価格を支払うことになります。企業間の競争回避は、テレビの性能を向上させるなどの企業努力が行われないことを意味します。正しい市場のあり方で販売されるテレビよりも、高額で質の悪いテレビしか市場で販売されないことになってしまうのです。
消費者の利益を損ない、正しい競争を阻害するといった理由から、カルテルは、不当な取引制限であるとして禁止されています。
カルテルと談合の違い
カルテルと同様に、談合も不当な取引制限として独占禁止法で禁止されています。談合とは、公共入札を対象とした参加者間の取り決めのことです。
国や地方公共団体が行う入札に参加する者が複数名集まり、事前に受注業者や受注価格を決定してしまうことを指します。談合もカルテルと同様に、事業者同士の競争をなくし不当に利益を得ることを目的としているため、禁止されているわけです。
カルテルの種類
カルテルにはさまざまな種類がありますが、大きく2つの種類に分類可能です。
- ハードコア・カルテル
- 非ハードコア・カルテル
それぞれ解説します。
ハードコア・カルテル
ハードコア・カルテルとは、実質的な競争の制限に限って結ばれたカルテルのことです。ハードコア・カルテルもいくつかの種類に細分化されているため、以下の代表的な5つを紹介します。
- 価格カルテル
- 市場分割カルテル
- 数量制限カルテル
- 技術制限カルテル
- 設備制限カルテル
価格カルテル
価格カルテルとは、サービスや商品につける価格やその価格の上限値・下限値に関して合意を行うものです。これによって事業者間の価格競争を避け、サービスや商品の価格を不当に高い水準で保つことができるようになります。
前述したテレビの例がこの価格カルテルに該当します。
市場分割カルテル
市場分割カルテルとは、複数の事業者がサービスや商品を販売する地域を互いに分割し、自社に割り当てられた担当地域で市場を独占するカルテルのことです。このカルテルは、同じ地域における事業者同士の対立をなくすために行われます。
たとえば、テレビの部品を取り扱う企業の中で、巨大なシェアを獲得しているA社とB社がいたとします。この2者がカルテルを行い、A者は西日本のみ、B社は東日本というように地域を分割して市場を独占する行為などがこれに該当します。
数量制限カルテル
数量制限カルテルとは、いくつかの事業者が互いに相談しあい、商品の販売量や生産量を減らしてしまうことです。市場への商品の供給量自体を低く設定することで価格の引き上げを容易にし、商品の価格を不当に高い水準で維持するために行われます。
たとえば、テレビの部品に関して巨大なシェアを獲得しているA社とB社が、部品の生産量を年に100個というように限定してしまうことが該当します。大量に生産できる環境があるにもかかわらず、あえてそれをしないという点が不当な取引制限に該当するわけです。
技術制限カルテル
技術制限カルテルとは、商品をつくる際に使用する技術の開発利用を制限する協定を結ぶことです。協定を結んだ企業同士が互いに開発努力を行わなくなるため、消費者側にとっては商品の質の向上が望めない状況に陥ります。
その分、事業者側は開発コストの削減などが可能となるため、サービスや商品の価格を不当に高い水準で維持することができるようになります。
設備制限カルテル
設備制限カルテルとは、サービスや商品の供給に使用される設備の機能を制限する協定を結ぶことです。設備の機能を低下させることは、自ずと供給量の低下につながります。
その結果、価格が下がりにくく、サービスや商品が高値で流通することになります。事業者側は、大量生産による価格の下落を防ぐことができるため、その分の利益を手に入れることができるわけです。
非ハードコア・カルテル
非ハードコア・カルテルとは、競争の制限だけではなく、それ以外の目的も含めて結ばれるカルテルのことです。たとえば、複数の事業者が集まって、互いの技術やノウハウを提供し合いながら共同研究・開発を行った商品を販売することなどがこれに該当します。
そのため、実質的に市場の競争が制限されているかどうかなどを総合的に判断したうえで、不当な取引制限とみなされなかった場合は独占禁止法違反とはなりません。
不当な取引制限とは
不当な取引制限とは、独占禁止法で禁止されている事項で、協定や協約といった名義に関わらず、以下の要件を満たす行為を指します。
⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
引用:昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)|e-Gov法令検索
カルテルを行った場合のペナルティ
独占禁止法違反に該当するカルテルを行ったことが発覚した場合は、以下に示す4つのペナルティが科される可能性があります。
- 排除措置命令
- 課徴金納付命令
- 課徴金納付命令
- 被害者に対する損害賠償
排除措置命令
独占禁止法の運用を行う公正取引委員会は、カルテルを行った事業者に対して、不当な取引制限にあたる行為の差し止めや違反行為を取り除くための措置を命令できます。これが排除措置命令です。
課徴金納付命令
公正取引委員会は、当事者である事業者に対して、課徴金の納付を命じることが可能です。課徴金額は、以下の式によって算出されます。
課徴金額 =(違反行為に係る期間中の対象商品又は役務の売上額又は購入額+密接関連業務の対価の額)× 課徴金算定率 + 違反行為に係る期間中の財産上の利益に相当する額(談合金等)
(参照:課徴金制度 公正取引委員会)
ただし、違反した事業者やそのグループ企業などがすべて中小企業であった場合は、課徴金の算定率は4%に固定されます。その他にも、課徴金額が1.5倍や2倍となる場合もあるため注意が必要です。
また、独占禁止法では、こうしたカルテル行為の自主的な報告を促進させるために、リーニエンシーと呼ばれる課徴金減免制度を採用しています。つまり、公正取引委員会に自らカルテルを行ったと申告した事業者は、課徴金の減免を受けることができるわけです。
被害者に対する損害賠償
カルテルの締結によって消費者や他企業に損害を与えた場合、該当する事業者はその被害者に対する損害賠償が命じられることがあります。
刑事罰
カルテルによる不当な取引を行った事業者や排除措置命令が確定したにもかかわらずその命令に従わない事業者は、刑事罰の対象となることがあります。
不当な取引制限を行った事業者に対しては、5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金が、そして排除措置命令に従わない事業者に対しては、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。
こうしたカルテルに対するペナルティの事例は、公正取引委員会の公式ホームページにて詳しく公開されています。カルテルに関する処分について、より具体的な例を知りたい方は、ぜひ公正取引委員会の公式ホームページをチェックしてみてください。
カルテルに関するよくある質問
カルテルのリスクは?
カルテルを行ったことが発覚すると、排除措置命令や課徴金納付命令、被害者への損害賠償、刑事罰などが科される可能性があります。近年では、コンプライアンスに対して厳しい目を向けられることが多いため、独占禁止法に違反した事実が世間に広がってしまうと、ブランディングにも悪影響が生じるでしょう。
カルテルの身近な事例は?
公正取引委員会のホームページでは、カルテルの身近な事例が掲載されています。
たとえば、旅行業者によるカルテルの事例では、旅行業者5社がある年に実施される市立中学校の修学旅行に向けて、貸切りバス代金や宿泊費、企画料金の料率などの基準を設けました。その結果、市立中学校側はどの旅行代理店を選んだとしても、基準以上の費用を支払わなければいけなくなってしまいます。
公正取引委員会によって調査が行われた結果、旅行業務市場の競争を実質的に制限したカルテルとして認定され、排除措置命令が下されました。
トラストやコンツェルンとの違いは?
トラストは、複数の企業が合併や買収などを行うことで経営統合し、実質的に一社として運営する形態のことを指します。カルテルはそれぞれ独立した事業者間で行われますが、トラストは法的・経営的に一体化した状態です。
コンツェルンは、資本的な結合によって異なる業種の企業が1つのグループになることです。国内では、旧財閥系企業が該当します。
アメリカや欧州ではどのような対策が行われている?
アメリカでは、シャーマン法第1条にて「各州間の又は外国との取引又は通商を制限するすべての契約、トラストその他の形態による結合又は共謀」が禁止されています。
また、欧州においてもEU機能条約第101条で以下のような記載がされており、カルテルが規制されています。
加盟国間の取引に影響を与えるおそれがあり、かつ、域内市場の競争の機能を妨害し、制限し、若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結果をもたらす事業者間の全ての協定、事業者団体の全ての決定及び全ての共同行為であって、特に次の各号の一に該当する事項を内容とするものは、域内市場と両立しないものとし、禁止する。
引用:EU(European Union)|公正取引委員会
まとめ
カルテルとは、カルテルを行った事業者のみが利益を得ることができる不当な取引制限です。これを行うことによって正しい市場のあり方が損なわれることになり、消費者や正当な方法で事業を行っている事業者に対して大きな被害をもたらすこともあります。
こうした被害をなくすためにも、独占禁止法のもとで公正取引委員会が監視を行っています。しかし、完全に根絶するためには事業者自身のモラルが問われるところが大きいのも事実です。
一時の利益に目がくらみ、自身の企業の社会的信用度を下げてしまうことがないように、公正な判断が事業者側には求められるのです。