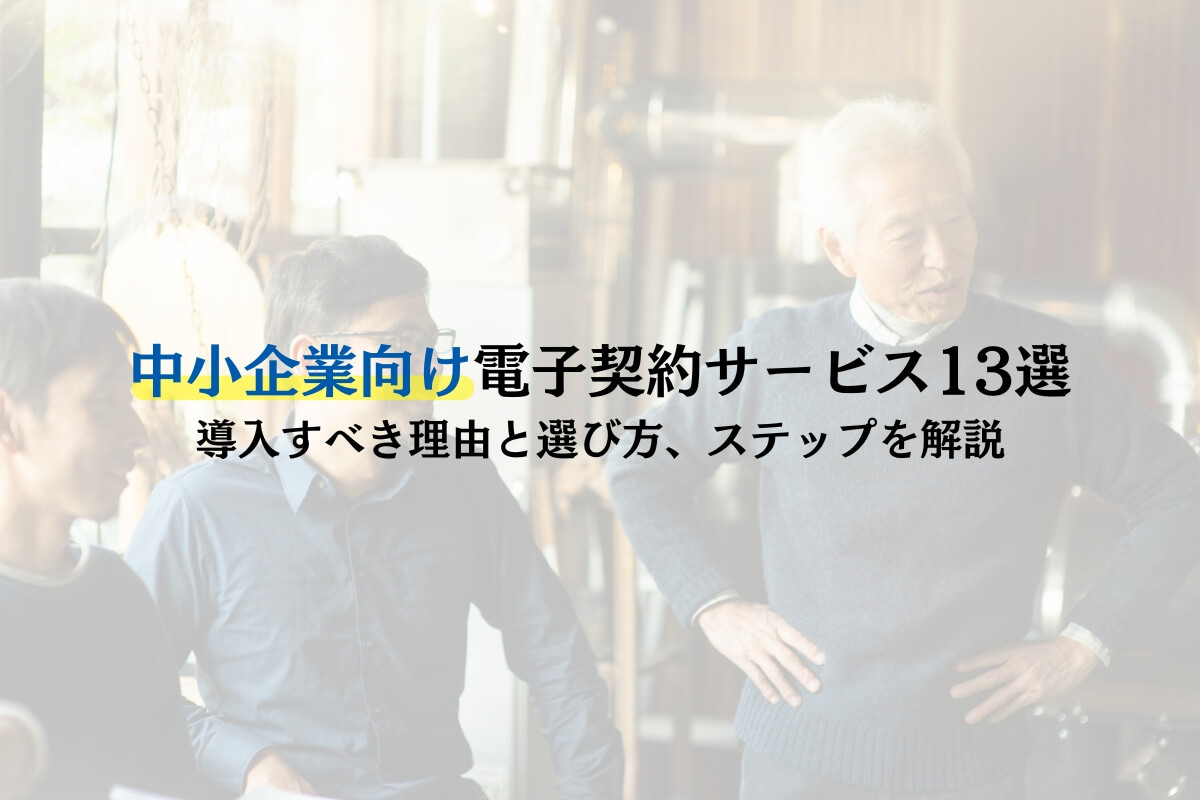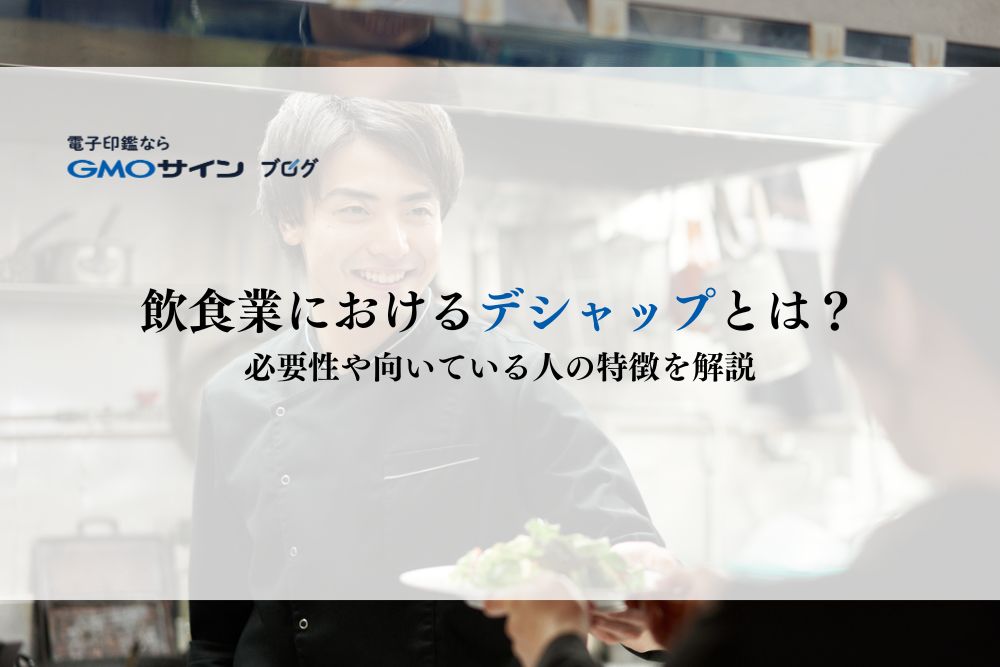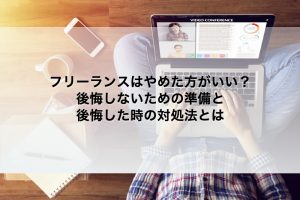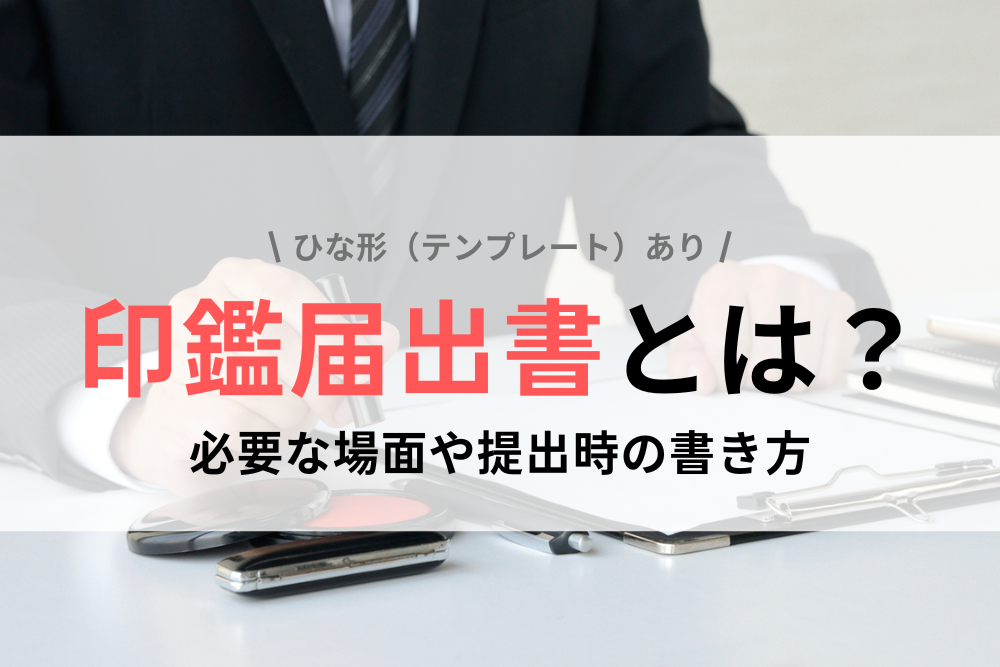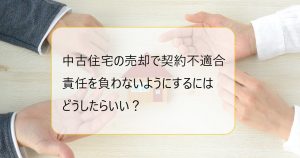政令や省令という言葉について、なんとなく聞いたことはあるものの、意味や違いについてわからないという方は多いのではないでしょうか。両者は日本の法令の一種で生活に深く関わっているものですが、さまざまな違いがあります。本記事では、政令と省令の基本から両者の違いを解説します。
政令とは
まず政令について見ていきましょう。政令と省令の違いを理解する前に、それぞれの基本的なことから確認していきます。
政令は内閣が定める命令
政令を簡単にいうと、法律に関連して内閣が定める命令です。法律自体はどちらかといえば抽象的で広範な原則を規定するものですが、政令は法律を具体的に運用するために機能します。政令は、通常、内閣の閣議で決定されたのち、国務大臣と内閣総理大臣が署名し、天皇による公布を経て、官報に掲載されるという制定プロセスをとります。
一部の重要な政令については、国会の承認を必要とすることもあります。政令は、行政の執行において重要な役割を果たし、法律の具体的な実施や行政の円滑な運営を支えるために欠かせません。そのため、政令の制定では、プロセスの透明性が確保されることが大切です。
政令の例
政令は、日常生活やビジネスに多くの影響を与える法令です。たとえば、道路交通法にもとづく施行令があります。交通信号機に関するルールや速度制限など、道路交通法についての具体的な規制や規則を政令によって定めることになります。
ほかにも、「政令指定都市」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、その名のとおり「政令」が関わっています。政令指定都市は、日本の地方自治体の中で、人口が50万人以上の都市に対して、一定の自治権と行政機能を委譲し、効率的な行政を行うための制度です。
自治権の強化と効率的な行政運営を通じて、都市の魅力向上や住民生活の質の向上を実現し、国内外で競争力のある都市を育てる役割を果たすことを可能としており、政令の重要性を感じることのできる一例といえるでしょう。
省令とは
続いて、政令と似た言葉である省令について見ていきましょう。
省令は各省大臣が発する命令
省令は、各省の大臣が法律や政令の委任にもとづいて発する命令です。政令と同じように、法律や政令を具体的に実践したり、具体化するために発せられます。省令は、「法律や政令の委任にもとづく」とあるように、それらの範囲内で効力を有します。
省令の制定においては、関連する各省の担当大臣が個別に制定・公布します。政令と同様に法律ではないため、国会による改正手続きの必要はなく、法律と比べて迅速な制定が可能です。
省令の例
省令の具体例について見ていきましょう。まず、食品衛生法にもとづく施行規則があります。この省令は、食品の製造・販売に関する規制や品質・安全性の基準を設けています。食品や添加物、器具および容器包装の使用基準などが具体的に定められ、食品の品質の保持や消費者の健康が守られることになります。
政令と省令の違い
政令と省令は、日本の法体系において似ている点もあります。たとえば、法律は立法機関である国会がつくるものですが、政令や省令は行政機関がつくるもので、行政立法と呼ばれます。双方とも、憲法や法律に反する内容のものを定めることはできず、委任がないかぎり罰則を設けることもできません。
ただし、政令と省令は発令主体が異なります。政令は内閣が、省令は各省が発するという点が大きな違いです。先にも触れたとおり、制定プロセスも異なります。政令は閣議決定が必要となりますが、省令は各省の大臣が個別に制定します。
また、両者で優先順位がはっきりしているという特徴もあります。政令が法律の委任にもとづくものであるのに対し、省令は法律・政令の委任にもとづくものであるため、省令よりも政令のほうが優先されます。このように、序列がはっきりしています。
形式的な点では、両者は制定されたときの名称が異なります。違いとしては、一般的に政令が「○○施行令」と記載されるのに対し、省令は「○○施行規則」と記載される点です。冒頭に「○○政令」、「○○省令」とも記載されますので、ある規定が政令と省令のどちらかなのかはそれをみて確認できます。
政令に関するよくある質問
政令を簡単に説明すると何ですか?
政令とは、内閣が制定する命令で、憲法や法律を実際に動かすために必要な具体的なルールを定めるものです。法律だけでは決めきれない細かな手続きや運用方法などを補う役割があります。政令は国会の議決を経ずに制定でき、法律の範囲内で効力を持ちます。
政令と法律の違いは何ですか?
法律は国会で議決して制定する国の基本的なルールで、国民の権利や義務に直接関わる内容を定めます。一方、政令は内閣が法律を実施するために補助的に作る命令で、法律の具体的な運用方法や細部を定めます。政令は法律に反する内容を定めることはできません。
政令と条例の違いは何ですか?
政令は国の内閣が制定し、全国に適用される命令です。これに対して、条例は地方自治体(都道府県や市区町村)の議会が制定し、その地域内だけで効力を持つルールです。条例も憲法や法律、政令に反してはならず、地域の実情にあわせて定められます。
政令や省令は日常生活に深く関わっている
政令と省令はいずれも法令の一種であり、生活に深く関わっています。両者は名称が似ているものの、それぞれの目的や発令主体、制定プロセス、優先順位の違いといった明確な相違点が存在します。
普段の生活で法律を意識・理解することは大切ですが、具体的な規定である政令・省令もしっかり理解しておくことが欠かせません。まずは自身の生活や仕事にどの政令・省令が関係しているのかを確認してみるとよいのではないでしょうか。